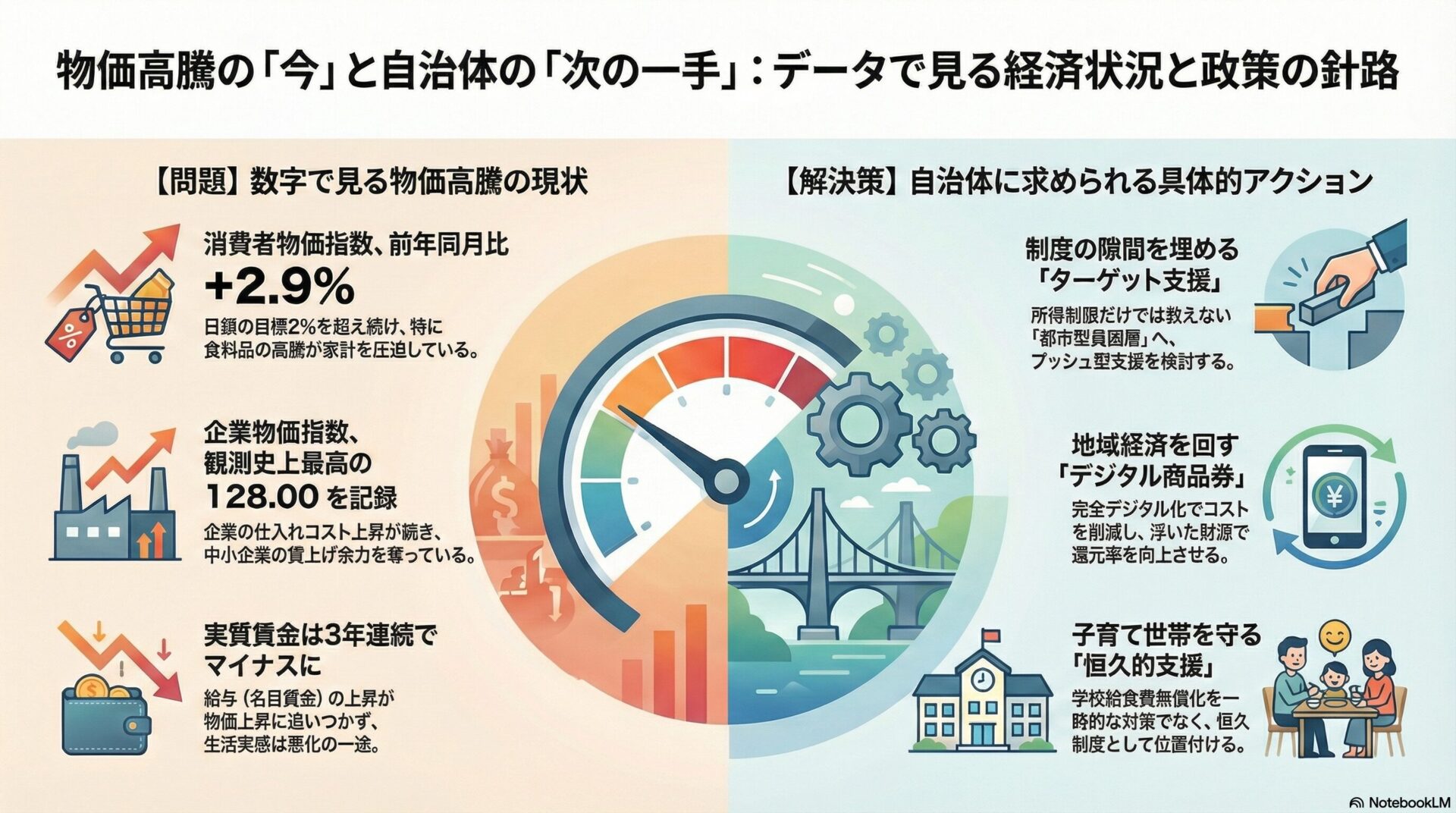【特別区長会】令和8年度 国の施策及び予算に関する要望について

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
令和7年8月に公表された特別区長会の「令和8年度国の施策及び予算に関する要望書」について、各カテゴリーごとに分類するとともに、「前年度(令和7年度)からの変化(新規・拡充など)」「政策立案への示唆」を試行的に追加しました。
(出典)特別区長会「令和8年度 国の施策及び予算に関する要望について」令和7年度
令和7年8月に公表された特別区長会による「令和8年度国の施策及び予算に関する要望書」の全文(省庁別)は、以下の通りである。
自治体経営
1. 地方分権改革の推進・地方税財源の充実強化
「地方分権改革」は、地方分権一括法や国と地方の協議の場に関する法律の成立により、一部の事務で権限移譲が行われるなど、その理念を具体化しつつある。しかし、真の分権型社会を実現するためには、改革の歩みを止めることなく、国と地方の役割分担を明確にし、地方がその責任と権限に応じた役割を果たせるよう、必要な財源を国が責任を持って保障することが重要である。このため、次の方策を講じること。
(1) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の確実な実現
真の「地方分権改革」を早期に実現するため、基礎自治体が実質的に地域の総合的な行政主体として役割を果たせるよう、事務移譲や義務付け等の関与の見直しを行うこと。用途地域等の都市計画決定権限をはじめ、特別区を権限移譲の対象外とすることなく、今後、一定の規模・能力を有する基礎自治体を対象に権限移譲を行う場合には、特別区も対象に加えること。
(2) 地方税財源の充実強化
① 地域間の税収格差の是正は、国の責任において地方交付税制度で行われるべきものであり、地方税の原則を歪め、地方分権に逆行する法人住民税の一部国税化を早期に見直し、自治体間に不要な対立を生む新たな税源偏在是正措置を行わないこと。また、法人実効税率の引下げ等、地方財政に影響を与える税制改正を行う場合、国の責任において、確実な代替財源を確保すること。
② 自治体が担う事務と責任に見合った税源配分とし、税源移譲により国と地方が公平な税源配分となるよう、適切かつ確実な財政措置を講じること。
③ 地方税財源の充実確保に向けて、偏在性が小さく、税収が安定的な地方消費税等の税源を移譲するなど、地方税中心の税体系に向け抜本的な再構築を図ること。
④ 国から地方への税源移譲にあたっては、地方交付税の不交付団体が抱える財政需要に十分配慮すること。
⑤ 国庫補助負担金制度については、国と地方の役割分担を明確にし、国の責任において措置すべきものについては地方に負担転嫁せず、地方に超過負担が生じないようにすること。
(3) 国の施策変更に伴う地方への十分な配慮
社会保障と税の一体改革等、地方に関わる国の施策の変更等に伴い地方における費用負担が急激に増加する事務については、地方の意見を聞き、意見を十分尊重するとともに、実質的な地方負担増が生じないよう、国において十分な財政措置を講じること。
(4) ふるさと納税制度の廃止を含めた抜本的な見直し
現在のふるさと納税制度は、自らが居住する自治体の行政サービスを提供するために必要な住民税を実質的に移転させるもので、受益と負担という税制本来の趣旨を逸脱しており、地方自治の根幹を破壊するものである。また、寄附の対価ではない別途の行為であるはずの返礼品が、寄附を集める主な手段となっており、返礼品やポータルサイトに依存する歪んだ制度となっているほか、所得に応じて控除額の上限も高くなる仕組みとなっており、高所得者ほど多額の寄附金控除を受けられるなど、公平性の観点から問題がある。その上、ポータルサイトなどの経費負担により、寄附金の5割程度が実質的に減少する仕組みは、本来、住民のために使われるべき税金の在り方としても問題がある。さらに、減収額については地方交付税により一部補填されているが、このことは、地方交付税の財源を圧迫し、実質的に将来世代へ負担を先送りにしており、非常に大きな問題である。加えて、ワンストップ特例制度により「手続きの簡素化」という名目で一方的に所得税控除分を自治体に肩代わりさせているなど、制度を巡る様々な問題は未だに解消されていない。このため、制度の廃止を含めた抜本的な見直しと、当面の緊急対応として、次の事項について直ちに見直すことを強く求める。
① 住民税控除額のうち、特例分の上限を所得割の「2割」以前の「1割」に戻すとともに、控除額に上限を設けること。また、寄附金控除の対象額から返礼品相当分を除外し、他の寄附金税制との整合性を図ること。
② ふるさと納税による減収額については、地方交付税の不交付団体に対し、地方特例交付金等で補填することにより、交付団体と不交付団体の格差を調整すること。
③ ふるさと納税受領額を地方交付税の基準財政収入額に算入することにより、寄附受入額による自治体間の格差を調整すること。
④ ワンストップ特例制度は、既にマイナポータル連携による確定申告が開始されている現状を踏まえ、速やかに見直すとともに、見直しまでの間は、自治体が負担している所得税控除分を、国が地方特例交付金等で補填すること。
⑤ 募集に要する費用の上限を寄附金の額の合計額の「100分の50」から縮小を図ること。特に返礼品経費の上限については、「100分の30」から更なる縮小を図ることで返礼品の規制を強化すること。
(5) 地方消費税清算基準の制度本来の趣旨に即した見直し
地方消費税交付金清算基準の見直しにより、特別区全体で令和7年度は約337億円の減収が見込まれている。税収を最終消費地に帰属させるという制度本来の趣旨に沿った内容とすること。
(6) 法人住民税及び法人事業税交付金の減収補填債の発行に向けた制度改正
特別区では、年度途中に大幅な減収が生じた際、法人住民税及び法人事業税交付金に係る減収補填債が発行できないため、一般の市町村と同様、法的根拠を明確にしたうえで、発行可能となるよう制度改正すること。
(7) 区立小中学校教職員の人事権の移譲
各区がそれぞれの教育方針に基づき、長期的視点に立った学校教育を責任を持って推進できるよう、区立小中学校教職員の人事権を、都から特別区へ移譲すること。これに併せて、給与負担に係る財源の移譲を行うこと。
前年度(令和7年度)からの変化
- 拡充: ふるさと納税制度について、前年度よりも問題点の指摘が詳細かつ具体的になり、制度廃止を含めた抜本的な見直しをより強く求める内容となっている。「公平性の問題」「経費負担による実質的な税金の減少」「地方交付税財源の圧迫」といった新たな論点が追加された。
- 新規: ふるさと納税の緊急対応策として、「寄附金控除の対象額から返礼品相当分を除外」「ふるさと納税受領額を基準財政収入額に算入」という2つの具体的な見直し案が新たに追加された。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 地方分権を推進し、基礎自治体が地域の実情に応じた行政サービスを責任もって提供するためには、その裏付けとなる安定した税財源の確保が不可欠である。法人住民税の一部国税化やふるさと納税制度による税収流出は、受益と負担の原則を歪め、大都市の安定的な行財政運営を脅かすものであり、地方自治の根幹に関わる問題である。
- 具体的なアクション
- 法人住民税の一部国税化の見直し、ふるさと納税制度の廃止を含めた抜本改革、地方消費税清算基準の是正など、国の税制・財政制度の構造的な問題について、国に対して強く是正を求める。また、特別区が一般市と同様の権限を持てるよう、権限移譲を要請する。
- 行政側の意図
- 「税源の偏在是正」の名のもとに行われる大都市を狙い撃ちにした税制改正の流れを食い止め、地方税財源の安定化と充実強化を図りたい。特にふるさと納税制度については、多くの問題点を具体的に指摘することで、制度そのものの持続可能性に疑問を投げかけ、世論を喚起し、国に抜本的な見直しを迫る強い意図がある。
- 期待される効果
- 不合理な税制改正による減収が是正され、特別区の財政基盤が安定・強化される。これにより、住民サービスの維持・向上が図られる。
- 課題・次のステップ
- 税制改正は、全国の自治体間の利害が複雑に絡むため、合意形成が極めて困難である。特にふるさと納税制度は、多くの自治体や関連産業にとって重要な財源となっているため、その見直しには強い抵抗が予想される。国や他の自治体に対し、論理的かつ粘り強い働きかけを継続することが不可欠である。
- 特別区への示唆
- 国への要望活動を継続するとともに、ふるさと納税による税収流出の影響額や、それが区民サービスに与える具体的な影響をシミュレーションし、区民に対して分かりやすく情報提供することで、問題意識の共有を図ることが重要である。また、移譲を求める権限について、受け皿となる組織体制の準備を進めておく必要がある。
DX政策
2. 行政のデジタル化の推進
デジタル・トランスフォーメーションの推進による住民の利便性向上や効率的な行政運営のため、行政のデジタル化について次の方策を講じること。
(1) 情報システムの標準化に係る財政措置
情報システムの標準化に係る経費については、移行に伴うシステム運用経費の増加分及びガバメントクラウド利用料・回線使用料について、地方交付税措置ではなく、全額国庫負担とすること。また、「デジタル基盤改革支援補助金」の上限額を撤廃すること。
(2) マイナンバーカード及び電子証明書の更新等諸手続の簡素化
行政サービスの向上に寄与するオンライン手続の整備、セキュリティ対策のための環境整備について、十分な財政措置を行うこと。特にマイナンバーカードの電子証明書の更新については、地方の負担が過大となることから、オンラインによる手続ができるよう、早期に対応すること。
(3) 戸籍における氏名の振り仮名記載事項化に対する財政措置
戸籍における氏名の振り仮名記載事項化に係る戸籍法の改正に伴い、戸籍システムの改修や人員の確保が必要となるため、システムの安定稼働に向け責任を持って対応するとともに、事業詳細を早急に示し、それに係る費用を全額国庫負担とすること。
前年度(令和7年度)からの変化
- 拡充: 情報システムの標準化に係る財政措置について、前年度の「システム改修やハードウェア整備」等に加え、「移行に伴うシステム運用経費の増加分」も国庫負担とするよう、要望がより具体化・拡充された。
- 整理: 前年度にあった「情報システムの標準化の推進」に関する要望(スケジュールや仕様書に関する内容)が削除され、財政措置に関する要望に集約された。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 行政のデジタル化は、住民の利便性向上(24時間365日手続き可能など)と、行政内部の業務効率化に不可欠である。特に、国が主導する情報システムの標準化やマイナンバーカードの普及は、全国どこでも質の高い行政サービスを提供するための基盤となるものであり、基礎自治体として着実に対応する必要がある。
- 具体的なアクション
- 国の政策誘導によって発生するシステム改修や運用経費(標準化、戸籍法改正対応等)について、地方に財政負担を求めるのではなく、全額国庫で負担するよう国に求める。また、住民の利便性を損なっているマイナンバーカードの電子証明書更新手続きのオンライン化を要請する。
- 行政側の意図
- 行政デジタル化の必要性は認識しているものの、その推進が地方の新たな財政負担増につながることを強く懸念している。特に、国の号令一下で進められる全国一律の制度改正(標準化、戸籍法改正)については、原因者である国が責任をもって費用を負担すべきであるという考えが根底にある。自治体のデジタル化を加速させるためにも、財政的な障壁を取り除く必要がある。
- 期待される効果
- 自治体の財政負担が軽減され、円滑に行政のデジタル化が進展する。住民は、窓口に行かなくても様々な手続きをオンラインで完結できるようになり、利便性が大幅に向上する。
- 課題・次のステップ
- 国の「デジタル臨時行政調査会」などの場で、地方の財政負担の実態を具体的に示し、国庫負担の必要性を訴え続けることが重要である。また、システムの標準化については、都市部特有の行政需要に対応できる柔軟な仕様となるよう、国に対して継続的に働きかけていく必要がある。
- 特別区への示唆
- 国の動向を注視し、システムの標準化や法改正に計画的に対応できるよう、庁内の体制を整備しておく必要がある。マイナンバーカードの普及については、カードを活用した独自の住民サービス(施設利用料の割引など)を展開することで、住民の取得メリットを高め、普及を促進することができる。
子育て、子ども政策
1. 子育て支援策の充実
都市部においては、女性の社会進出や様々な雇用形態に対応するための長時間保育や病児・病後児保育、学童保育等の多様な保育サービスの需要が増大化しており、待機児童の解消を含む保育サービスの十分な供給は、依然として困難な状況にある。こうしたなか、地価や賃料の高い特別区では、保育所や学童クラブ等の施設の整備に係る財政負担が大きく、民間事業者にとっても参入が困難な状態にある。地域の実情に合った子育て支援策をより一層充実させる必要があるため、次の方策を講じること。
(1) 保育環境の充実に向けた支援の拡充
① 子ども・子育て支援法に基づく「子どものための教育・保育給付交付金」による処遇改善等加算や配置改善加算等を継続すること。また、物価・賃金の上昇下においても、安心・安全で質の高い教育・保育サービスの提供を継続できるよう、公定価格の適切な単価の引上げ等を行うこと。
② 保育所における保育の質の向上や安全性の確保、保育所機能や専門性を地域の子育て支援の活用に資する人材の安定的確保・定着のために、「保育対策総合支援事業費補助金」を活用した「保育士宿舎借り上げ支援事業」を継続し、施設の所在地に住む場合は補助を加算するなど、制度の充実を図ること。また、幼稚園職員も補助対象に加えること。
③ 「こども誰でも通園制度」の実施が、保育士不足の深刻化を招かないよう、国の責任において、保育士の処遇改善、保育士確保等の支援措置を行うこと。
(2) 学童クラブ等への整備の促進及び財政支援
学童クラブの需要増を踏まえ、学童クラブ事業への参入促進及び継続的な運営支援のため、施設整備費及び運営費の助成を大幅に拡充すること。また、放課後子ども教室についても、学童クラブ運営における補助と同等の実現実行性の確保に向けて、必要とされる単価の増額や処遇改善を行うこと。
(3) 医療的ケア児保育支援事業への補助の拡充
保育園等において医療的ケア児を受け入れるにあたり、特に、医療的ケアを実施する看護師等の確保が困難である状況を踏まえ、看護師等の配置に係る経費の補助について大幅な見直しを行うとともに、安全な保育の確保と負担軽減のため、施設に対する補助の充実や支援策の拡充を行うこと。
前年度(令和7年度)からの変化
- 新規: 「医療的ケア児保育支援事業への補助の拡充」が、独立した項目として新たに追加された。前年度は要望がなかったわけではないが、より重要性を強調する形で構成が変更された。
- 整理: 前年度にあった「保育所等における給食費の無償化」に関する要望は、「学校教育の推進(国土交通省への要望)」に集約・整理された。
- 拡充: 「保育士宿舎借り上げ支援事業」について、「幼稚園職員も補助対象に加える」という具体的な拡充内容が明記された。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 少子化対策は国の最重要課題であり、その根幹をなすのが、子育て世帯が安心して子どもを預け、働き続けることができる環境の整備である。特に、待機児童問題が深刻な都市部において、保育の受け皿確保と質の向上を図ることは、女性の活躍推進や経済成長にも資するものであり、国が責任をもって取り組むべき課題である。
- 具体的なアクション
- 保育士の処遇改善や配置基準の改善につながる公定価格の引き上げ、「保育士宿舎借り上げ支援事業」の継続・拡充など、保育人材の確保・定着に向けた支援を強化する。また、学童クラブの整備・運営への財政支援を拡充する。
- 行政側の意図
- 保育所の整備(ハード)と保育士の確保(ソフト)を両輪で進めることで、待機児童問題の根本的な解決を目指したい。また、「こども誰でも通園制度」のような新たな制度導入が、現場の負担増だけに終わらないよう、国の責任による財政支援を強く求めている。医療的ケア児のような特別な配慮が必要な子どもたちの受け入れ体制整備も急務と捉えている。
- 期待される効果
- 待機児童の解消と、保育の質の向上が図られる。保護者の就労継続と子育ての両立が支援され、子育て世帯の経済的・精神的負担が軽減される。
- 課題・次のステップ
- 保育士・看護師等の専門人材の絶対数が不足しており、処遇改善だけでなく、魅力ある職場環境づくりや養成課程の充実など、中長期的な視点での人材確保・育成策が不可欠である。公定価格の引き上げに必要な恒久的な財源の確保も大きな課題である。
- 特別区への示唆
- 国の補助制度を最大限活用し、地域のニーズに応じた保育所の整備や多様な保育サービスの提供を計画的に進める必要がある。特に、地価・賃料の高い区の実情に合わせた宿舎借り上げ支援の上乗せ補助など、人材確保に向けた独自のインセンティブ策を講じることが、保育の質を確保する上で効果的である。
2. 児童相談所設置の促進
平成28年6月に公布された、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行により、特別区も、政令による指定を受けて児童相談所の設置が可能となり、令和7年4月時点で10区が児童相談所を開設したところである。今後も、準備が整った特別区から順次、児童相談所の開設を予定していることから、国は、特別区における児童相談所の設置・運営が円滑に行えるよう、次の方策を講じること。
(1) 児童相談所設置・運営に係る財政措置
特別区が迅速に児童相談所を設置し、円滑に運営していくためには、国による財政支援の充実・強化が必要不可欠である。その多くが地方交付税措置とされている、児童相談所の整備・運営費等について、国庫補助の対象とすること。
(2) 児童福祉司や児童心理司等の確保・育成に係る支援及び財政措置
多種多様な相談対応や、措置等の権限行使を含む相談援助活動の実施など、児童虐待に係る対応は高度に専門的対応が求められるため、職員の確保・育成は重要な課題である。このため、児童福祉司等の処遇改善に係る経費や、法定の人員配置基準を超えた児童福祉司及び児童心理司の配置に係る経費を国庫補助の対象にするなど、国として、十分な職員体制を確保するための必要な支援を行うこと。
前年度(令和7年度)からの変化
- 継続要望: 要望の骨子は前年度と同様であるが、児童相談所を開設した区の数が「8区」から「10区」へと現状が更新されている。
- 整理: 前年度にあった「社会的養育の基盤整備」に関する要望は削除され、児童相談所の設置・運営に関する財政措置と人材確保に要望が重点化・集約された。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 深刻化・複雑化する児童虐待問題に迅速かつ的確に対応するためには、住民に最も身近な基礎自治体が、相談から調査、一時保護、その後の支援までを一貫して担う体制を構築することが最も効果的である。特別区による児童相談所の設置は、子どもの命と権利を守るためのセーフティネットを強化する上で極めて重要である。
- 具体的なアクション
- 児童相談所の設置・運営にかかる経費について、現行の地方交付税措置から、より確実で手厚い国庫補助制度に転換する。また、専門職である児童福祉司・児童心理司の処遇改善や、法定基準を超える手厚い人員配置を可能とするための財政支援を行う。
- 行政側の意図
- 児童相談所の設置は、本来国が推進すべきナショナルミニマムに関わる重要な施策であるとの認識がある。そのため、設置に伴う財政負担を地方に押し付けるのではなく、国の責任において安定的な財源を保障すべきであると考えている。特に、専門職の人材確保は全国的な課題であり、国の主導による処遇改善が不可欠であるという強い意図がある。
- 期待される効果
- 特別区による児童相談所の設置が促進され、地域に根差した、きめ細かで迅速な児童虐待対応が可能となる。専門職の確保・定着が進み、相談支援体制の質の向上が図られる。
- 課題・次のステップ
- 経験豊富な児童福祉司・児童心理司は全国的に不足しており、人材の確保・育成が最大の課題である。国による処遇改善と併せて、自治体独自のキャリアパスの提示や研修体制の充実が求められる。財源についても、国庫補助への転換に向けた国との粘り強い協議が必要となる。
- 特別区への示唆
- これから児童相談所を設置する区は、先行する区の事例を参考にしつつ、自区の地域特性や児童・家庭の状況を踏まえた、特色ある相談所のビジョンを策定する必要がある。既に設置した区は、運営実績を評価・検証し、課題を国や都にフィードバックしていく役割が期待される。区の間での情報共有や連携も重要となる。
福祉政策
3. 障害者施策の充実
障害者施策の充実のため、地域の実情に応じた財政措置等が行われるよう、次の方策を講じること。
(1) 障害福祉サービス事業(自立支援給付や地域生活支援事業等)の充実と地域の実情に即した財政支援の拡充
障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業」等の障害者支援に対する国の財源を確保し、基準額を上回る場合や包括補助のため生じている特別区の超過負担が増加しないよう、特別区の事業執行額に見合った負担や補助等を行うこと。
(2) 福祉基盤整備に対する財政支援の拡充
重度障害者向けグループホーム等の用地取得費について、都市部の実情を十分踏まえ、補助対象とすること。また、施設整備(新規及び拡張整備) については「社会福祉施設整備費補助金」等の財源確保及び基準額の拡大を行うこと。加えて、国有地を活用した施設整備を行う際は、介護施設と同様に賃料を10年間5割減額される措置を講じること。
(3) 福祉人材の確保、育成及び処遇改善のための財源の確保
障害福祉サービス事業所等が安定的に事業を運営し、利用者ニーズに即したサービスを提供できるよう、報酬を引上げること。また、障害福祉サービス等職員の処遇改善に資する、基本報酬の引上げをすること。障害福祉サービスの利用に係る相談支援事業の推進を図るため、相談支援専門員が専従職員としてサービス等利用計画の作成業務に従事できるよう、報酬額を増額するなど、福祉人材の処遇に係る財源を確保すること。
(4) トワイライト事業等の制度見直し及び支援の拡充
① 放課後等デイサービスが、障害児の家族が働き続けるための夕方支援に積極的に取り組み、学童クラブと同様の機能を果たせるよう、各種加算の増額等サービス報酬を見直すなど制度の拡充を行うこと。
② 高校卒業後の障害者の家族が、仕事と介護を両立していけるよう、既存の障害福祉サービス事業所等が、障害者を対象とした夕方の居場所事業を実施可能とする制度を構築すること。その際、事業所家賃や利用者数に応じた職員配置、強度行動障害や医療的ケアを含む重度障害への対応なども考慮すること。
前年度(令和7年度)からの変化
- 継続要望: 令和7年度の要望書(厚生労働省宛)に含まれていた内容が、こども家庭庁への要望として継続されている。内容はほぼ同様。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 障害の有無にかかわらず、誰もが地域で安心して暮らせる共生社会の実現は、国の責務である。障害者の自立と社会参加を支えるためには、グループホーム等の生活の場や、日中の活動の場を質・量ともに確保し、ライフステージに応じた切れ目のない支援を提供する必要がある。
- 具体的なアクション
- 地域生活支援事業に対する財源を確保し、自治体の超過負担を解消する。地価の高い都市部の実情を踏まえ、グループホーム等の用地取得費を国庫補助の対象とする。障害福祉サービス報酬を引き上げ、福祉人材の処遇を改善する。
- 行政側の意図
- 障害福祉サービスの提供基盤が、自治体の財政力によって格差が生じることがないよう、国の責任においてナショナルミニマムを保障すべきであるという考えがある。特に、施設整備の最大の障壁である用地費や、人材不足の根本原因である低賃金構造に対し、国の財政措置によって直接的に改善を図りたいという強い意図がある。
- 期待される効果
- 障害者が地域で生活するための社会資源(施設、人材)が安定的に確保される。障害者の自立と社会参加が促進され、その家族の負担も軽減される。
- 課題・次のステップ
- 社会保障費全体の抑制という国の大きな方針の中で、障害福祉分野の予算をいかに確保していくかが最大の課題である。福祉人材の確保については、処遇改善だけでなく、専門性の向上やキャリアアップの仕組みづくりなど、総合的な魅力向上策が求められる。
- 特別区への示唆
- 国の制度改正を待つだけでなく、区の障害者福祉計画に基づき、地域に必要な社会資源の整備を計画的に進める必要がある。国の補助制度と東京都の補助制度を効果的に組み合わせ、社会福祉法人やNPO等の多様な事業者と連携して、地域の実情に応じたサービスを創出していく主体的な姿勢が期待される。
まちづくり、インフラ整備政策
1. 交通システムの整備促進
(1) 交通政策審議会答申に位置付けられた路線(東京8号線・11号線・12号線・都心部・臨海地域地下鉄・新空港線・区部周辺部環状公共交通)の早期実現
特別区における交通システムの整備は、沿線地域のみならず東京圏全体の公共交通環境の向上に寄与し、人口増加やまちづくりの進捗に伴う交通需要の増加へ対応していく上でも、極めて重要な課題である。このため、交通政策審議会が平成28年度に答申した、「東京圏の都市鉄道が目指すべき姿」を実現するうえで意義のあるプロジェクトと位置付けられた以下の路線について、早期の実現に向けた方策を講じること。加えて、鉄道が社会的な便益を安定的・継続的にもたらすことを踏まえ、収益採算性の判断基準の長期化など鉄道事業者への支援や、鉄道整備及び沿線まちづくりに対する財政支援を拡充すること。
① 東京8号線 (有楽町線)の延伸 (豊洲~住吉)
② 東京8号線の延伸 (押上~野田市)
③ 東京11号線の延伸 (押上~四ツ木~松戸)
④ 東京12号線(大江戸線)の延伸 (光が丘~大泉学園町~東所沢)
⑤ 新空港線の新設 (矢口渡~蒲田~京急蒲田~大鳥居)
⑥ 都心部・臨海地域地下鉄構想の新設(臨海部~銀座~東京)
⑦ 区部周辺部環状公共交通の新設(葛西臨海公園~赤羽~田園調布)
(2) ご当地ナンバーの導入に伴う地方版図柄入りナンバープレートの台数要件の緩和
特別区において、ご当地ナンバーの導入を伴う地方版図柄入りナンバープレートの導入は、地域の風景や観光資源を図柄とすることにより、各区の魅力を全国に発信し、地域振興、観光振興につながる非常に重要な施策である。令和7年8月現在、23区中6区がご当地ナンバーの導入を伴う地方版図柄入りナンバープレートを導入している。なお、現在、区市町村における地方版図柄入りプレートの導入台数要件は登録自動車数が10万台以上となっており、台数要件に満たないがゆえに導入検討ができない区も存在している。そのため、希望する全ての区がご当地ナンバーの導入を伴う地方版図柄入りナンバープレートを導入できるよう、台数要件を緩和すること。
前年度(令和7年度)からの変化
- 継続要望: 鉄道整備に関する要望は、前年度の内容をほぼ踏襲している。
- 拡充: ご当地ナンバー導入区の数が「5区+申請1区」から「6区」へと現状が更新されている。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 鉄道網の整備は、首都圏の国際競争力強化、交通渋滞の緩和、環境負荷の低減に資する広域的な課題であり、国が主導して推進すべきプロジェクトである。また、ご当地ナンバーは、費用対効果の高いシティプロモーション手法であり、地域の活性化を促すツールとして、希望する自治体が導入しやすい環境を整える必要がある。
- 具体的なアクション
- 交通政策審議会答申に盛り込まれた鉄道新線の事業化に向けて、国が財政支援を拡充し、関係者間の調整を主導する。また、ご当地ナンバー導入の際の登録自動車数の台数要件を、現在の10万台から大幅に引き下げる、あるいは撤廃する。
- 行政側の意図
- 鉄道整備のような巨額の投資を要するプロジェクトは、民間事業者や一自治体だけではリスクが大きく、事業化が進みにくい。国が財政面・制度面で強力にバックアップすることで、計画の実現性を高めたい。ご当地ナンバーについては、自治体の創意工夫による地域振興を後押しするため、画一的な基準を見直し、より多くの自治体が活用できるようにしたいという意図がある。
- 期待される効果
- 鉄道新線の整備により、通勤時間の短縮や経済活動の活性化が期待される。ご当地ナンバーの普及により、各区の認知度が向上し、観光振興や地域への愛着(シビックプライド)の醸成につながる。
- 課題・次のステップ
- 鉄道整備については、事業の採算性評価と、国・都・区・鉄道事業者間の費用負担割合の調整が最大の課題である。ご当地ナンバーの要件緩和については、ナンバープレートの種類が増えることによる視認性や管理上の問題について、警察庁など関係機関との調整が必要となる。
- 特別区への示唆
- 鉄道新線計画のある区は、沿線のまちづくりビジョンを具体化し、整備による便益(B/C)を高める努力をすることで、事業化を後押しすることができる。ご当地ナンバーを導入したい区は、デザイン案の選定プロセスに住民参加を促すなど、導入に向けた機運を醸成していくことが重要である。
2. 都市計画道路等の整備促進
特別区では、主要な幹線道路網の未整備区間が散在しており、首都東京の都市計画道路ネットワークが十分機能していない状況にある。これらは、事故の危険性や道路交通円滑化の大きな妨げとなっている。このため、首都東京の地域特性を考慮し、緊急輸送路としての機能を確保するためにも、都市の基幹的施設である都市計画道路の整備が計画的かつ確実に促進されるよう、次の方策を講じること。
(1) 都市計画道路の整備促進
都市計画道路の整備を促進するため、安定的かつ十分な財源を確保し、特別区の防災機能向上等、都市再生の観点からも早期に整備するために必要な財政措置を講じること。
(2) 連続立体交差事業の整備促進
「開かずの踏切」を早期に解消するため、都内に残存する踏切は、道路交通円滑化や、鉄道で分断された地域の再生等の妨げとなるため、その解消に効果的である連続立体交差事業の整備促進に向け必要な財政措置を講じること。
前年度(令和7年度)からの変化
- 整理: 前年度あった「東京外かく環状道路等の整備促進」の項目が削除され、より基礎自治体に関わりの深い都市計画道路と連続立体交差事業に要望が重点化された。
- 拡充: 連続立体交差事業について、前年度の「予算の拡大」から「整備促進」へと表現が変わり、財政措置を求める趣旨がより明確になった。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 都市計画道路や連続立体交差事業は、交通の円滑化だけでなく、災害時の延焼遮断帯や緊急車両の通行路として、都市の防災性を飛躍的に向上させる。また、踏切による市街地の分断を解消し、一体的で活力あるまちづくりを可能にする。これらの整備は、国の責務である国民の生命・財産の保護と、国土強靭化に直結する。
- 具体的なアクション
- 都市計画道路や連続立体交差事業に対する社会資本整備総合交付金等の国庫補助を、安定的かつ十分に確保・増額する。事業の優先順位付けを行い、計画的な整備を推進する。
- 行政側の意図
- これらの事業は受益が広域に及ぶ一方、事業費が巨額で完成までに長期間を要するため、地方自治体単独での財源確保は困難である。国の安定的な財政支援を確固たるものにすることで、長期的な見通しを持って事業を計画的に進め、首都圏全体の機能強化を図りたいという意図がある。
- 期待される効果
- 交通渋滞の緩和による経済的損失の削減と環境負荷の低減。踏切事故の撲滅。大規模災害時における避難・救助活動の円滑化と被害の軽減。
- 課題・次のステップ
- 全国の社会資本整備の必要性が高まる中で、首都圏の事業に対する予算をいかに重点的に確保していくかが課題である。用地取得の難航や事業費の高騰など、事業の長期化を招く要因への対策も求められる。
- 特別区への示唆
- 事業の必要性や効果について、地域住民への丁寧な説明を繰り返し行い、合意形成を図る努力が不可欠である。国や都に対しては、事業化による防災性向上効果などを定量的に示すことで、財源確保の必要性を具体的に訴えていく必要がある。
3. 都市インフラの改善
都市機能を向上させ、社会・経済活動を支える活力あるまちづくりを推進するためには、都市インフラの改善を図る必要がある。このため、次の方策を講じること。
(1) 国道の立体整備の推進
将来を見据えた交通安全・渋滞緩和のため、国道の立体整備を早期に推進すること。
(2) 羽田空港の機能強化に係る対応
騒音対策や落下物対策等の安全管理体制を強化するとともに、自治体や住民に対する情報提供体制を充実し、適切な情報提供を徹底すること。また、新飛行経路の固定化回避を早急に実現すること。さらに、新飛行経路下の住民に対し、防音対策を講じる際の支援を行うこと。
(3) 社会資本整備総合交付金の拡充
市街地再開発事業等による安全で安心なまちづくりを進めるため、「社会資本整備総合交付金」の十分な財政措置を図ること。
(4) 市街地再開発事業に対する補助金の増額及び税制改正
市街地再開発事業が遅滞なく実施できるよう、施行者に対する直接補助金を安定的に交付するとともに、増額を図ること。また、転出者に対しての特別控除額5,000万円の引上げ及び代替資産取得の特例の併用を認めること。加えて、権利床の相続税に係る資産評価についての特例を認めること。
(5) 電線類の地中化の促進
災害に強く安全な都市基盤整備及び都市景観の向上を図るため、自治体への財政面での支援拡充及び新工法の開発など都市部の道路条件に沿った技術支援を行うこと。また、公共インフラの埋設企業への移設補償では、施工後の精算額に基づき補助金交付ができる仕組みを講じること。さらに、宅地所有者が行う電線共同溝の地上機器移設費用の一部負担を行うこと。
(6) 都市公園の整備促進
計画的に施設利用者の安全・安心を確保するため、社会資本整備総合交付金の「公園施設長寿命化対策支援事業」における交付対象事業の面積要件及び総事業費要件を緩和し、全ての都市公園を交付対象とすること。
(7) 公共インフラの老朽化対策推進
① 先端技術の導入等技術面での支援、維持管理基準の設定等制度面での支援と併せ、財政支援の拡充を図ること。
② 国の示す「路面下空洞調査要領」を超える頻度で路面下空洞調査を行った際の調査費に対し、「社会資本整備総合交付金」を柔軟に交付できるよう基準を見直すこと。
③ 路面下空洞調査により発見された原因不明の空洞を道路管理者が復旧する場合は、その復旧経費についても「社会資本整備総合交付金」の対象に加えること。
前年度(令和7年度)からの変化
- 新規: 「市街地再開発事業に対する補助金の増額及び税制改正」が新たな項目として追加され、特別控除額の引き上げなど具体的な税制改正を求めている。
- 新規: 「公共インフラの老朽化対策推進」が新たな項目として追加され、特に道路下の空洞調査・復旧への財政支援を具体的に要望している。
- 拡充: 電線類の地中化について、「宅地所有者が行う地上機器移設費用の一部負担」という、より踏み込んだ支援策が追加された。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 都市インフラは、国民の生活と経済活動を支える基盤であり、その機能維持と向上は国の重要な責務である。特に、市街地再開発や電線類の地中化は都市の防災性・安全性を高め、公共インフラの老朽化対策は大規模事故を未然に防ぐ上で不可欠な取り組みである。
- 具体的なアクション
- 社会資本整備総合交付金を拡充し、市街地再開発、公園、老朽化対策など、都市基盤整備に関する地方の取り組みを強力に支援する。また、再開発を促進するため、施行者への直接補助や税制上の特例措置を講じる。
- 行政側の意図
- 「国土強靭化」の観点から、災害に強い都市づくりを加速させたい。民間活力を活用する市街地再開発を、補助金と税制の両面から支援することで、事業の採算性を高め、民間投資を喚起する狙いがある。また、全国的に深刻化するインフラ老朽化に対し、予防保全型のメンテナンスへ移行を促すため、点検・調査段階からの財政支援を強化したいと考えている。
- 期待される効果
- 耐震性・耐火性の高い市街地の形成、倒壊・火災の危険がある電柱・電線の地中化、インフラ事故の未然防止など、都市全体の安全性が向上する。
- 課題・次のステップ
- 限られた予算の中で、全国の多様なインフラ整備ニーズにどう応えていくか、事業の優先順位付けと効果的な予算配分が課題となる。老朽化対策については、点検技術の高度化や、専門人材の育成も急務である。
- 特別区への示唆
- 国の交付金制度を最大限活用するためには、地域の課題を明確にし、その解決に資する具体的な事業計画を早期に策定することが重要である。特に、市街地再開発事業については、地権者や地域住民との丁寧な合意形成が事業成功の鍵を握るため、まちづくり協議会の設立支援など、区が主体的にコーディネート役を担うことが期待される。
4. 都市緑地の保全の推進
都市において貴重な緑地である、生産緑地や屋敷林等の保全を図るため、次の方策を講じること。自治体の財政負担を増やさずに、都市部におけるみどりの保全を推進するために、市民緑地を公有化せずとも民有のまま継続して開設できるよう、相続税の扱いについて評価減の割合を増やす、ないしは、都市農地に係る相続税の納税猶予制度と同様の制度を創設すること。また、やむを得ず区が取得する際には、買取りに対する十分な財政支援を行うこと。
前年度(令和7年度)からの変化
- 拡充: 前年度は「緑地所有者への対応」として複数の税制措置を要望していたが、今年度は特に「市民緑地」制度に着目し、「相続税」の評価減や納税猶予制度の創設という、より具体的で踏み込んだ税制改正を求める内容に特化・強化された。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 都市内の民有緑地は、相続を機に宅地化されるケースが多く、急速に失われている。これらの緑地が持つ環境保全や防災、レクリエーションといった公益的な機能を維持するためには、所有者が土地を手放すことなく保全し続けられるようなインセンティブを与える制度が必要である。
- 具体的なアクション
- 土地所有者が自身の土地を「市民緑地」として公開する場合、その土地にかかる相続税の評価額を大幅に減額する、あるいは納税を猶予する新たな税制上の特例措置を創設する。また、自治体が緑地を買い取る場合の財政支援も継続・拡充する。
- 行政側の意図
- 自治体が全ての貴重な緑地を買い取ることは財政的に不可能である。そこで、税制をインセンティブとして活用し、民間所有者(個人・企業)に緑地の保全・公開を促すことで、行政の財政負担を抑えつつ、効率的に都市の緑を確保したい。これは、民間の力を活用した持続可能な緑地保全モデルを構築しようという意図の表れである。
- 期待される効果
- 相続税負担を理由とした緑地の売却・開発が抑制され、貴重な都市緑地が保全される。また、市民緑地として公開されることで、地域住民が利用できる新たな憩いの空間が創出される。
- 課題・次のステップ
- 新たな税制優遇措置の創設には、国税当局との慎重な調整が必要となる。制度が悪用されることのないよう、市民緑地としての公開期間や管理状況など、厳格な適用要件を設けることが課題となる。
- 特別区への示唆
- 区内に存在する生産緑地や屋敷林等の所有者に対し、市民緑地制度や既存の税制優遇措置について積極的に情報提供し、相談に応じる体制を整えることが重要である。また、所有者と地域住民、NPOなどをつなぎ、緑地の管理・活用に関する協定を結ぶといったコーディネート役を担うことも期待される。
5. 災害対策の充実
切迫性が指摘される首都直下地震及び南海トラフ地震、近年の異常気象による水害等への対策の一層の充実を図るため、次の方策を講じること。
(1) 帰宅困難者対策等の推進
帰宅困難者対策について、首都直下地震発生時だけではなく、台風などの風水害を含めた全ての自然災害に対し、各自治体、民間等が広域的な連携を図れるよう、国が主導すること。また、帰宅困難者用一時滞在施設における備蓄品整備に関し、自治体及び自治体関連施設向け補助制度の創設や、備蓄倉庫のための国有地の利活用を行うこと。さらに、民間一時滞在施設確保への課題となっている瑕疵担保責任に対する解消策として、補償制度の創設を図ること。
(2) 防災対策の推進
区市町村での災害時通信確保の観点から、区市町村が自ら契約するモバイル衛星通信機器の導入及び維持管理に係る財政措置を講じること。また、在宅避難者等への支援として、備蓄物資の購入・管理や、状況把握に係るデジタル技術活用のための財政措置を講じること。特に、高層住宅においては、ライフライン確保のためのエレベーターや上下水道接続部の耐震化、高層階での備蓄倉庫やエレベーター用防災キャビネットの設置義務化、備蓄品購入費や家具等の転倒・落下防止対策促進等、防災対策の推進に必要な法改正や財政措置を講ずること。
(3) 大規模水害等への対策の強化
豪雨・洪水・高潮・津波から都市機能の保全を図るため、河川管理者が主体的に取り組み、住民負担の軽減や地域の合意形成の円滑化につながる方策を拡大するなど、「高規格堤防整備事業」に基づく治水対策をより一層推進すること。また、一部高さの低い堤防のかさ上げ及びその整備に必要な橋梁架替事業について、河川管理者と鉄道事業者の協力の下、早急に対応すること。さらに、地域住民等の安全な避難体制が構築できるよう、国が主体となって、関係機関との連携・調整を行うなど、自治体の枠を超えた広域避難を迅速かつ統一的に行うための体制を早期に整備すること。とりわけ、広域避難先の確保、広域避難開始の判断、鉄道事業者等の協力確保、河川管理者による堤防復旧や排水機能の拡充等に関する支援等を行うこと。
(4) 災害廃棄物処理に係る仮置場の確保
地震等、大規模災害発災時に迅速に災害廃棄物の処理が進められるよう、国が広域処理を主導すること。また、広域的な処理・運営を想定している二次仮置場の確保は困難を伴うため、国で所有又は管理する緑地等を災害廃棄物仮置き場として利用できる制度等を構築すること。
前年度(令和7年度)からの変化
- 拡充: 帰宅困難者対策について、対象とする災害を地震だけでなく「台風などの風水害を含めた全ての自然災害」へと拡大するよう要望が強化された。
- 拡充: 防災対策の推進において、高層住宅対策がより具体化され、「エレベーターや上下水道接続部の耐震化」「備蓄倉庫等の設置義務化」といった法改正を伴う踏み込んだ内容となった。
- 整理: 前年度あった「住宅密集市街地への対応」に関する要望は、東京都への要望(木造密集地域対策)に集約されたものと推察される。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 首都直下地震や気候変動に起因する大規模水害は、いつ発生してもおかしくない国家的危機であり、その対策は国土強靭化の根幹である。帰宅困難者、広域避難、災害廃棄物といった課題は、一自治体の境界を越えて発生するものであり、国が司令塔となって広域的な連携体制を構築し、財政的・制度的な支援を行う責務がある。
- 具体的なアクション
- あらゆる自然災害を想定した広域的な帰宅困難者対策の計画策定を国が主導する。高層住宅の防災対策強化に向けた法改正を行う。大規模水害時の広域避難計画を策定し、関係機関との連携体制を構築する。災害廃棄物の仮置場として活用可能な国有地をリストアップし、制度を整備する。
- 行政側の意図
- 基礎自治体だけでは対応しきれない大規模・広域的な災害課題に対し、国のリーダーシップとリソース(権限、財源、国有地等)の投入を強く求めている。特に、民間事業者の協力が不可欠な帰宅困難者対策や広域避難については、国による補償制度や協力確保の枠組みがなければ実効性が担保できないという問題意識がある。
- 期待される効果
- 発災時の社会経済活動の混乱が最小限に抑えられ、都民・国民の生命・財産が守られる。また、迅速な復旧・復興が可能となる。
- 課題・次のステップ
- 広域避難計画の実効性を高めるためには、避難先の自治体や鉄道事業者など、多数の関係機関との具体的な調整と役割分担の合意形成が不可欠である。高層住宅の防災対策義務化については、既存マンションへの遡及適用の可否など、法制面での慎重な検討が課題となる。
- 特別区への示唆
- 国が策定する広域計画に地域の声を反映させるため、自区の災害リスクや避難行動要支援者の状況などを的確に把握し、国や都に情報提供することが重要である。また、タワーマンションの管理組合等と連携し、防災マニュアルの作成支援や共助の仕組みづくりを促すなど、基礎自治体ならではのきめ細かな働きかけが求められる。
教育政策
6. 学校教育の推進
学校教育の充実を図るため、学校施設の整備等について、次の方策を講じること。
(1) 学校施設の改修等に対する財政措置及び規制緩和
① 学校施設の老朽化や機能更新への対応として、円滑に建替えや改修等を行うことができるよう、「学校施設環境改善交付金」の財源を十分確保するとともに、補助対象の要件拡充、地域の実情に即した単価への見直し等の財政措置を行うこと。また、新築・増改築・改修事業に至った案件については、本体工事とは別に設計及び調査費用等に対する補助事業を新設すること。
② 建替えや大規模改修等に係る建築基準法上の規制緩和(周辺環境への十分な配慮を含む。)を行うこと。
(2) 義務教育に係る教材費や給食費等への財政措置
① 義務教育に係る教材費や行事費等については、物価高騰等により全国的に費用が増加していることから、国庫補助金による必要な財政支援を行うこと。
② 学校給食は、居住自治体や家庭の経済状況に関わらず、全ての児童生徒に等しく無償で提供されるべきものであることから、学校給食法を改正するとともに、国の負担において学校給食の無償化を進めること。
(3) 給付型奨学金制度の拡充
学ぶ意欲のある子どもが、十分な教育の機会を得ることができるよう、国の高等教育の無償化の更なる充実を行い、給付型奨学金の受給可能な世帯収入及び奨学金の上限額の拡充と、児童養護施設退所者や生活保護世帯出身の児童等、保護者からの支援が受けられない子どもへの奨学金の上乗せを実施すること。
(4) 不登校対応への財政支援の拡充
① スクールソーシャルワーカーの配置に係る費用に対する国庫補助金の補助割合を拡充すること。
② 教育支援センター(適応指導教室)に関する国庫補助金制度の補助対象を拡大するとともに、補助率を拡充すること。
前年度(令和7年度)からの変化
- 新規: 「義務教育に係る教材費や行事費等への財政措置」が、物価高騰を背景に新たな要望として追加された。
- 新規: 「給付型奨学金制度の拡充」が、高等教育の機会均等の観点から新たに追加された。
- 新規: 「不登校対応への財政支援の拡充」が、不登校児童生徒の増加という社会課題に対応するため、新たに追加された。
- 整理: 前年度あった「GIGAスクール構想」「少人数学級」に関する要望は削除され、より喫緊の課題である物価高騰や不登校対応に重点が移った。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 教育は、国の未来を担う人材を育成する根幹であり、全ての子どもに質の高い教育機会を保障することは国の責務である。老朽化した学校施設の更新、物価高騰下での教育費負担の軽減、経済的理由による進学断念の防止、そして不登校児童生徒への支援は、教育の機会均等を確保する上で喫緊の課題である。
- 具体的なアクション
- 学校施設の整備に対する国庫補助(学校施設環境改善交付金)を増額し、要件を緩和する。物価高騰に対応するため、教材費等への財政支援を行うとともに、学校給食の無償化を国の制度として実現する。給付型奨学金の対象者と支給額を拡充する。不登校対応の専門職配置等への財政支援を強化する。
- 行政側の意図
- 教育分野における様々な課題に対し、国が責任をもって財源を確保し、ナショナルミニマムを保障すべきであるという強い考えがある。特に、家庭の経済状況が子どもの教育機会を左右することのないよう、給食費の無償化や奨学金制度の拡充を求めている。また、不登校という現代的な課題に対し、専門職の配置促進を通じて学校現場の対応力を強化したい意図がある。
- 期待される効果
- 安全で快適な学習環境が整備される。子育て世帯の教育費負担が軽減される。経済的な理由で進学を諦める子どもが減少し、不登校の子どもたちが社会的に孤立することなく、学びの機会を得られる。
- 課題・次のステップ
- 教育分野への公的支出をいかに増やしていくか、国の財政全体の中での優先順位付けが大きな課題となる。学校給食の無償化や奨学金の拡充には恒久的な財源が必要であり、その負担のあり方について国民的な議論が必要となる。
- 特別区への示唆
- 国の財政支援を要望しつつも、各区の教育理念に基づいた特色ある学校づくりを進めることが重要である。例えば、老朽化した学校の改築にあたっては、地域住民に開放されるコミュニティスペースを併設するなど、新たな価値を付加する工夫が求められる。不登校対策については、フリースクール等の民間団体との連携を強化することも有効な手段である。