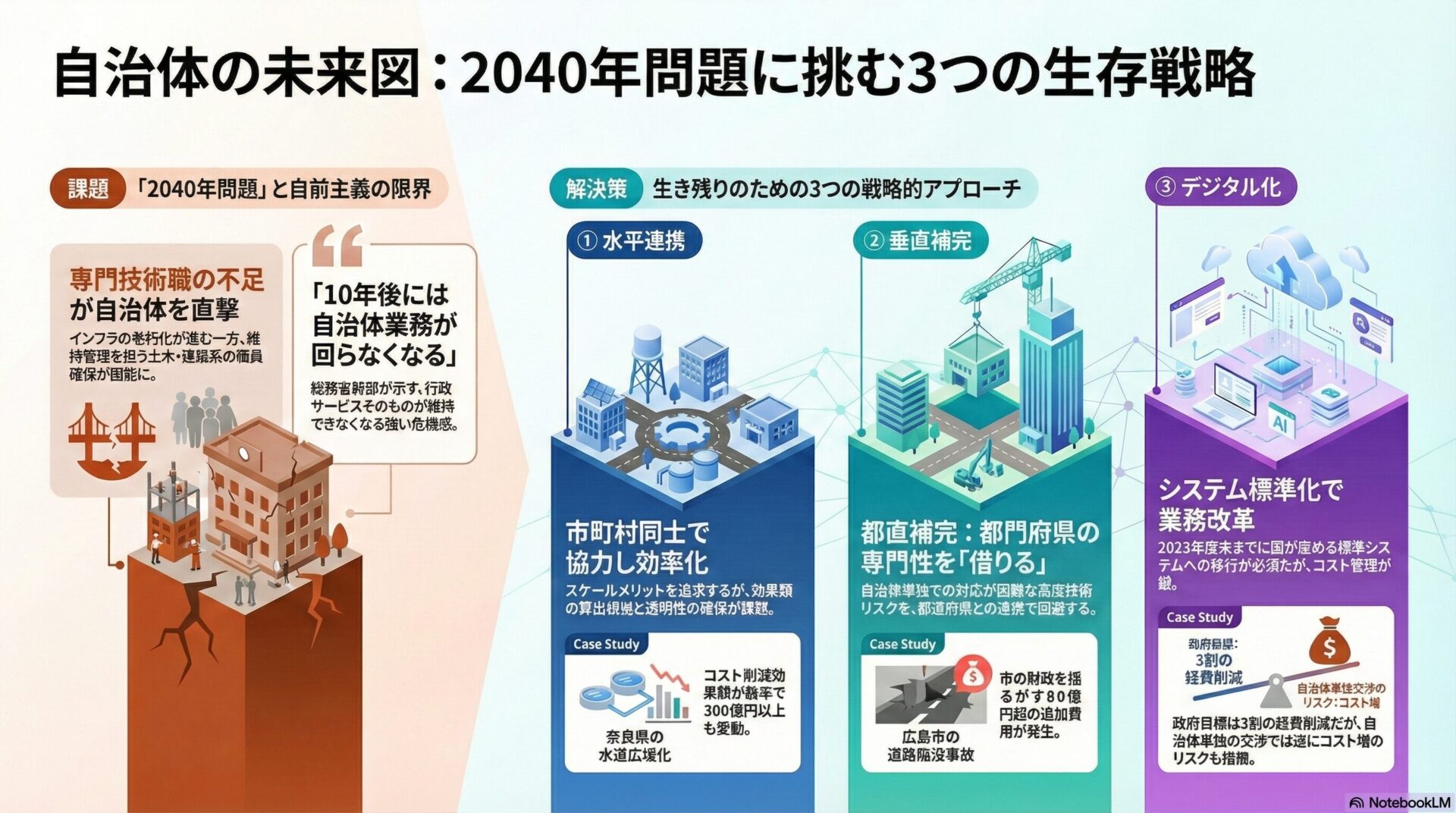【企画課】SDGs推進 完全マニュアル

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
SDGs推進の意義と基本原則
なぜ自治体、そして企画課がSDGsを推進するのか
地方自治体がSDGs(持続可能な開発目標)を推進することは、単なる国際的な流行への対応や、環境問題への限定的な取り組みではありません。それは、自治体の根源的な使命である「地域の人々が安心して生活できる環境を整備する」という役割を、2030年、そしてその先の未来を見据えて全うするための、包括的な「経営戦略」そのものです。SDGsへの取り組みは、地域住民の生活の質向上、地域経済の活性化、そしてこれまで見過ごされてきた地域の新たな課題や魅力の発見に直結します。
SDGsが画期的なのは、経済・社会・環境という三つの側面を不可分なものとして捉え、統合的に解決することを目指す点にあります。自治体が直面する人口減少、高齢化、地域経済の縮小といった根源的な課題は、もはや一つの分野の施策だけで解決できるものではありません。例えば、環境対策としての公園緑化は、高齢者の健康増進(社会)や、新たなコミュニティ形成による地域のにぎわい創出(経済)にも繋がります。
この複雑に絡み合った課題を解きほぐし、区の施策全体を一つの方向へと導く羅針盤となるのがSDGsです。そして、その舵取り役を担うのが、区の総合計画を司る企画課に他なりません。企画課の役割は、SDGsという「世界共通言語」を用いて、これまで縦割りで進められがちだった福祉、産業振興、環境、教育といった各分野の施策を横断的に再評価し、連携させることで相乗効果を生み出す「触媒」となることです。これは、単にSDGsという名の新規事業を追加するのではなく、区の行政経営そのものの質を向上させる、根源的な変革を主導することを意味します。
「地方創生」の原動力としてのSDGs
国は、SDGsの達成に向けた自治体の取り組みが「地方創生の実現に資する」と明確に位置づけています。これは、SDGsと地方創生が目指すゴール、すなわち「持続可能な地域社会の構築」が本質的に同じであるためです。「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」(ゴール8:働きがいも経済成長も)、「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」(ゴール11:住み続けられるまちづくりを)、「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」(ゴール4:質の高い教育をみんなに、ゴール5:ジェンダー平等を実現しよう)といった地方創生の基本目標は、SDGsの各ゴールと深く共鳴しています。
SDGsを地方創生の原動力として活用することの真の価値は、地方創生の評価軸を転換させる力を持つ点にあります。従来の地方創生が、ともすれば人口増減や企業誘致件数といった短期的な経済指標に偏りがちだったのに対し、SDGsは「誰一人取り残さない」という包摂性の理念を掲げ、住民一人ひとりのウェルビーイング(幸福)や、環境の持続可能性といった、長期的かつ多面的な視点を導入します。
これにより、企画課は目先の成果だけでなく、2030年、さらにはその先を見据えた真に持続可能な地域戦略を立案・推進するための、揺るぎない大義名分を得ることができます。例えば、再生可能エネルギーの導入(ゴール7)を推進するプロジェクトを立案する際、単なるCO2削減効果だけでなく、「エネルギーの地産地消による新たな雇用創出(ゴール8)」や「災害時の非常用電源確保による地域の防災力強化(ゴール11)」といった複合的な価値を明確に示し、より多くのステークホルダーの理解と協力を得ながら事業を推進することが可能になるのです。これは、地域のレジリエンス(強靭性)や住民の幸福度向上といった、より本質的な価値を追求する地域経営への転換を意味します。
SDGsの歴史的変遷と国の動向
2015年9月に国連サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、その中核として17のゴールと169のターゲットから成るSDGsが掲げられました。これを受け、日本政府は2016年5月に内閣総理大臣を本部長とする「SDGs推進本部」を設置し、同年12月には日本の国家戦略として「SDGs実施指針」を策定しました。この指針は、国内外の情勢変化に対応するため定期的に見直されており、2023年12月の最新の改定版では、地方創生の文脈における地方自治体の役割の重要性が一層強調されています。
国のこうした動きは、単なるトップダウンの指示系統を構築するものではなく、自治体が主体的にSDGsに取り組むための環境を整備し、その活動を力強く後押しすることを目的としています。具体的には、以下のような支援策が展開されています。
- SDGs未来都市:
- SDGsの達成に向けて優れた取り組みを提案する都市を国が選定する制度です。選定されることで、国の支援を受けられるだけでなく、先進事例として国内外に発信する機会を得ることができます。
- ジャパンSDGsアワード:
- 企業や団体、自治体など、SDGs達成に資する先駆的な取り組みを表彰する制度です。優れた取り組みを可視化し、ベストプラクティスを全国に共有する役割を担っています。
- 地方創生SDGs官民連携プラットフォーム:
- SDGsを軸とした地域課題解決を目指す自治体と、その解決に貢献できる技術やノウハウを持つ企業・団体等とのマッチングを促進する場として、内閣府により設置されています。
企画課の職員は、こうした国の動向を常に把握し、自区で活用できる補助金や支援制度、新たな政策の方向性をいち早く察知して区の戦略に反映させる「アンテナ」としての役割を担います。国の政策を戦略的に活用することで、区の取り組みを加速させることが可能です。
企画課におけるSDGs推進の全体像と業務フロー
根拠となる国の指針と区の計画体系
企画課が推進するSDGsに関する業務は、明確な計画の体系に基づいています。その最上位にあるのが、国の「SDGs実施指針」です。この指針は、地方自治体に対し、その最上位計画である基本構想や基本計画、さらには各分野の個別計画に至るまで、SDGsの理念や要素を反映させることを奨励しています。
この国の指針を受け、東京都特別区の先進的な自治体では、既に計画体系へのSDGsの統合が進められています。例えば、港区や墨田区では、区の基本計画において、区が推進する各政策や施策がSDGsの17ゴールのうちどれに関連するのかを明記し、行政運営のあらゆる場面でSDGsを意識する仕組みを構築しています。
企画課の業務の核心は、この計画の連鎖を管理し、一貫性を確保することにあります。具体的には、以下の流れの中でSDGsの理念が途切れることなく反映されるよう、計画の策定・改定プロセスを主導します。
「国のSDGs実施指針」 → 「区の最上位計画(基本構想・基本計画)」 → 「分野別計画(環境、福祉、産業など)」 → 「個別の事務事業」
この計画体系への紐づけ作業は、単に既存の事業をSDGsのゴールに分類するだけの「見える化」作業に留まりません。それは、区が実施する全ての事業を、SDGsという世界共通の物差しで棚卸しする「政策アセスメント」という、より戦略的な機能を果たします。このプロセスを通じて、企画課は「どのゴールに対する区の貢献が手厚く、どのゴールが手薄になっているか」「複数の部署が同じゴール達成に向けて事業を実施しているが、効果的な連携は取れているか」といった、区政全体のポートフォリオを客観的に分析することが可能となります。この分析結果こそが、限られた行政資源(予算・人材)をどこに重点的に配分すべきかを判断するための、極めて重要な根拠となるのです。
SDGs推進の標準業務フロー
企画課が主導するSDGs推進業務は、場当たり的に進められるものではなく、体系化された一連の業務フローに沿って進められます。これは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)を繰り返すPDCAサイクルそのものであり、多くの自治体で採用されている標準的な進め方です。
- ステップ1:現状分析と課題の特定 (Plan / Check)
- 地域の人口動態、経済状況、環境データ、区民意識調査などの客観的なデータを用いて、区が直面している現状と課題を分析します。
- この分析結果をSDGsの17のゴールと169のターゲットに照らし合わせ、「どのゴールの達成に課題があるか」「区の強みを活かせるのはどの分野か」を明確にします。
- ステップ2:推進体制の構築 (Plan)
- 区長をトップとする全庁的な推進本部や、実務を担う担当部署を正式に設置します。
- 企画課が事務局となり、庁内各部署との連携体制や、外部のステークホルダー(企業、NPO、大学など)との協力体制の基盤を構築します。
- ステップ3:ビジョンと目標の設定 (Plan)
- 分析結果に基づき、2030年に区が目指すべき姿(将来ビジョン)を、SDGsの言葉を用いて描きます。
- ビジョンの達成度を測るため、具体的で測定可能な目標(KPI:重要業績評価指標)を設定します。例えば、「温室効果ガス排出量を2013年度比で〇%削減する」「区民の健康寿命を〇歳まで延伸する」といった具体的な数値目標です。
- これらのビジョンと目標を、区の基本構想や基本計画に正式に位置づけます。
- ステップ4:アクションプランの策定と実行 (Do)
- 設定した目標(KPI)を達成するため、各部署が担当する具体的な事業計画(アクションプラン)を策定します。
- 企画課は、各部署のアクションプランが区全体のビジョンと整合性が取れているかを確認し、部署間の連携が必要な事業については調整役を担います。
- 計画に基づき、各部署が事業を実行します。
- ステップ5:進捗管理と評価 (Check)
- 定期的に(通常は年度ごと)、各KPIの進捗状況をモニタリングし、目標達成度を評価します。
- 計画通りに進んでいない場合は、その原因を分析します。
- ステップ6:評価結果に基づく改善とフィードバック (Action)
- 評価結果を踏まえ、アクションプランの見直しや改善を行います。
- 評価と改善の結果は、次年度の予算編成や、次期基本計画の改定に明確に反映させ、継続的な改善のサイクルを回していきます。
企画課が担う中核的役割:総合調整と旗振り役
SDGsは、その性質上、特定の部署だけで完結するものではなく、分野横断的かつ政策統合的な取り組みが不可欠です。そのため、区政全体を俯瞰し、各部署を横断的に調整できる企画経営部門がその推進役を担うことが最も望ましいとされています。実際に、墨田区では企画経営室がSDGs推進本部の事務局を担っています。
企画課の役割は、自らが個別のSDGs事業を実施すること以上に、区政全体を動かすための以下の3つの中核的な機能を発揮することにあります。
- 翻訳者 (Translator):
- 国連や国が掲げるSDGsの目標は、壮大で普遍的であるがゆえに、そのままでは日々の行政業務に落とし込みにくい側面があります。企画課は、これらの抽象的なグローバル目標を、特別区が直面する具体的な地域課題(例えば、密集市街地の防災力強化や、子どもの貧困問題など)の文脈に即した、分かりやすく実践的な政策課題へと「翻訳」する役割を担います。
- 指揮者 (Conductor):
- SDGsの推進においては、福祉部はゴール3(健康と福祉)を、環境部はゴール13(気候変動対策)を、産業振興部はゴール8(経済成長)を、といった形で各部署がそれぞれの専門分野で取り組みます。企画課は、オーケストラの指揮者のように、これらの個別の取り組みがバラバラに進行するのではなく、互いに連携し、区政全体として調和の取れた一つの交響曲(=持続可能なまちづくり)を奏でるよう、総合調整を行います。
- 羅針盤 (Compass):
- SDGsを取り巻く状況は、国内外で常に変化しています。企画課は、国の新たな政策動向、他自治体の先進事例、課題解決に繋がる新技術(DX、GXなど)、市民や企業の意識の変化などを常にモニタリングし、区のSDGs推進が常に正しい方向へ、そして最も効果的な航路を進むことができるよう、庁内への情報提供や研修の企画を通じて、全体の意識をリードする羅針盤としての役割を果たします。
全庁的な推進体制の構築と運営
庁内推進本部の設置と役割
SDGsを全庁的な取り組みとして実効性のあるものにするためには、一部署の努力だけでは限界があり、区長をトップとする強力なリーダーシップと、全部局が一体となる推進体制が不可欠です。その中核となるのが「庁内推進本部」の設置です。
先進事例である墨田区では、「墨田区SDGs推進本部設置要綱」を定め、区長を本部長、副区長を副本部長、そして教育長及び全ての部長級職員を本部員とする、区の最高意思決定機関として位置づけています。この体制は、SDGsが特定の分野の課題ではなく、区政のあらゆる分野に関わる最重要課題であることを組織内外に明確に示すメッセージとなります。
推進本部の所掌事項は、以下の通り、SDGs推進に関する包括的な権限と責任を持ちます。
- SDGsの推進に係る方針及び計画に関すること:
- 区全体のSDGs推進の方向性を定める基本方針や、基本計画等への反映内容を決定します。
- SDGsの達成に向けた取組の推進及び進行管理に関すること:
- 各部署が実施する取り組みの進捗状況を監督し、目標達成に向けた指導・助言を行います。
- SDGsの推進に係る施策の総合調整に関すること:
- 複数の部署にまたがる横断的な課題について、部署間の利害調整や役割分担を決定します。
企画課は、この推進本部の事務局として、会議の議題設定、資料作成、議事録の管理、そして本部での決定事項が各部署で着実に実行されるためのフォローアップなど、円滑な運営を支える重要な役割を担います。
全部長級職員が本部員として参画することの隠れた、しかし極めて重要な効果は、意識の変革です。これにより、SDGsは「企画課が担当する新しい仕事」ではなく、「全部署がそれぞれの所管分野で責任を負うべき共通の責務」であるという当事者意識が醸成されます。本部長である区長が、定例の会議で各部長に対し、担当分野におけるSDGsの進捗を直接問う場が生まれることで、ボトムアップの働きかけだけでは得られない、トップダウンによる強力な推進力が組織全体に浸透していくのです。
各部署との連携(庁内連携)の仕組みづくり
推進本部がトップダウンの意思決定機関であるとすれば、実務レベルでの円滑な連携を促進するボトムアップの仕組みづくりも同様に重要です。SDGsの多くのターゲットは、単一の部署だけでは達成が困難であり、部署の垣根を越えた協働が不可欠となります。
そのための有効な手法として、推進本部の下に、特定のテーマに特化した実務者レベルの「検討部会」や「ワーキンググループ」を設置することが挙げられます。これは、国の推進体制において、文部科学省と外務省が連携して教育に関する分科会を運営するような、省庁間連携のモデルを自治体レベルで応用するものです。
企画課は、以下のような手順でこの仕組みを構築・運営します。
- テーマの設定:
- 区の重要課題の中から、特に複数の部署の連携が必要なテーマを選定します。(例:「ゼロカーボンの実現」「子どもの貧困対策」「地域コミュニティの活性化」など)
- メンバーの招集:
- 設定したテーマに関連する部署(例えば「ゼロカーボン」であれば、環境課、都市計画課、建築課、財政課、広報課など)から、課長・係長クラスの実務担当者をメンバーとして招集します。
- 運営の支援:
- 企画課がファシリテーターとなり、定期的な会合を開催します。会合では、各部署の取り組み状況の共有、共通課題の分析、データの一元化、そして連携事業の企画立案などを進めます。
このような横断的なチームを組成することで、現場レベルでの円滑な情報共有が促進され、これまで見過ごされてきた連携の可能性が発見されます。例えば、環境課が推進する住宅の断熱改修補助事業と、福祉課が把握している高齢者世帯の情報を結びつけ、「高齢者世帯のヒートショック対策と省エネを同時に実現する連携事業」といった、より社会的インパクトの大きい施策を生み出す土壌が育まれるのです。
予算編成と事業評価へのSDGs視点の統合
SDGs推進の理念を全庁に浸透させ、実質的な行動変容を促す上で最も強力なツールの一つが、予算編成と事業評価のプロセスにSDGsの視点を組み込むことです。どれだけ立派な計画を策定しても、それを実行するための資源(予算)が伴わなければ「絵に描いた餅」に終わってしまいます。
先進的な自治体の行政評価では、施策や事務事業の評価結果を、次年度の予算編成における資源配分の判断材料として活用する取り組みが進められています。この仕組みをSDGsに応用し、「SDGsへの貢献度」を事業評価と予算要求の新たな軸として導入します。
企画課は、財政課と緊密に連携し、以下のような仕組みの導入を検討します。
- 予算要求プロセスへの組み込み:
- 各部署が次年度の予算を要求する際に使用する「予算要求書」の様式を改訂し、「本事業が貢献するSDGsゴール」や「期待されるSDGsへの貢献効果(定性的・定量的)」を記述する欄を設けます。
- 事業評価(行政評価)との連動:
- 毎年度実施する事務事業評価シートに、「SDGsの視点からの評価」という項目を追加します。これにより、全ての事業がSDGsという共通の物差しで評価されることになります。
- 評価結果の予算査定への活用:
- 財政課が行う予算査定の際に、事業評価における「SDGsへの貢献度」の評価結果を、予算の増減や事業の継続・見直しを判断するための一つの重要な要素として活用します。
このような仕組みを導入することで、SDGsへの貢献度が高い事業へ優先的に予算が配分されるインセンティブが働きます。各部署は、自らの事業の意義をSDGsの文脈で再定義し、より効果的な取り組みを模索するようになります。結果として、トップダウンの号令だけでなく、予算という実利的な動機付けによって、区政全体のSDGs主流化が内側から加速していくのです。
先進事例に学ぶSDGs推進戦略【東京都・特別区 比較分析】
東京都と特別区の連携体制
特別区がSDGsを推進するにあたり、単独で取り組むだけでなく、広域自治体である東京都との連携は不可欠です。東京都は、都内全体のSDGs達成に向け、基礎自治体である区市町村を支援するための様々な施策を展開しています。具体的には、先進的な取り組みを行う自治体を支援するモデル事業の実施や、各自治体の担当者が情報交換や知見の共有を行うためのネットワーク会員向けセミナーの開催など、普及啓発活動に力を入れています。
企画課は、これらの都が提供する支援策や連携の機会を最大限に活用するための、区の公式な窓口となります。都の担当部署と日常的に情報交換を行い、都が持つ広域的な視点、専門的な知見、そして財政的なリソースを、いかに自区の取り組みに効果的に結びつけるかを常に模索する、重要な橋渡し役を担います。
【SDGs未来都市】の戦略分析:墨田区・板橋区・足立区
内閣府が選定する「SDGs未来都市」は、全国の自治体の中でも特に優れた取り組みを行う、いわばSDGs推進のトップランナーです。特別区内からも複数の区が選定されており、その戦略を分析することは、これからの取り組みの方向性を定める上で極めて有益です。
- 墨田区(2021年度ダブル選定):
- 墨田区の戦略は「行政経営統合型」と位置づけられます。SDGsを特別な取り組みとしてではなく、区政運営の根幹に据えるアプローチです。区の最上位計画である基本計画をはじめ、産業観光マスタープランや健康づくり総合計画など、あらゆる主要計画の改定に合わせてSDGsの視点を全面的に導入しています。さらに、「区内製造業における付加価値額」や「65歳健康寿命」といった具体的なKPIを設定し、計画の実効性を担保しています。
- 板橋区(2022年度未来都市選定):
- 板橋区の戦略は「地域資源活用・ブランド強化型」です。区が長年培ってきた「絵本のまち」という独自の文化資源をSDGs推進の核に据え、「絵本がつなぐ『ものづくり』と『文化』のまち」を2030年のあるべき姿として掲げています。2024年度からは「板橋区SDGsプラットフォーム」を立ち上げ、区内の中小企業や団体を巻き込んだ官民連携を加速させており、地域資源を軸に経済・社会・環境の好循環を生み出そうとしています。
- 足立区(2022年度ダブル選定):
- 足立区の戦略は「地域課題解決型」です。区が長年向き合ってきた根底課題である「貧困の連鎖の解消」と、それに伴う「区に対するマイナスイメージの払拭」をSDGs推進の中心テーマとして明確に掲げています。特に、エリアデザインによって大きく変化する綾瀬地区をモデルエリアとし、子ども食堂やNPO、地域企業といった多様なステークホルダーと協働しながら、課題解決の都市型モデルを構築することを目指しています。
これらの先進区に共通しているのは、単にSDGsの17ゴールを網羅的に目指すのではなく、自区の最も重要な地域課題や地域資源とSDGsを戦略的に結びつけ、独自の「核となるテーマ」を設定している点です。これは、SDGsをスローガンで終わらせず、実質的な地域変革の駆動力とするための「自分ごと化(ローカライズ)」の要諦と言えます。これから本格的に取り組む区の企画課は、まず「我々の区にとって、SDGsを使って解決すべき最も重要な課題は何か?」という問いから始めるべきであり、その答えこそが、その区独自のSDGsビジョンの中核となるのです。
特色ある取組事例:港区・世田谷区・江戸川区
SDGs未来都市に選定されていない区においても、それぞれ特色ある優れた取り組みが進められています。
- 港区:
- 総合計画である「港区基本計画」において、防災・災害対策、エコ・3R活動、地球温暖化対策、平和・人権の取り組みといった主要な政策・施策とSDGsの17ゴールとの関連性を体系的に整理し、区政運営全体でSDGsに貢献する姿勢を明確にしています。また、「世界一幸せな『子育て・教育都市』」「確実に命を守る『リアル防災都市』」といった、区民に分かりやすい都市像を掲げ、目標の共有を図っています。
- 世田谷区:
- 環境分野を特に重視し、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言しています。その実現に向けた具体的な計画として「地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、省エネや再生可能エネルギーの導入を強力に推進しています。また、ごみの減量(3R)を区民が実践できる最も身近で重要なSDGsアクションと位置づけ、普及啓発に力を入れています。
- 江戸川区:
- SDGsを区民一人ひとりの行動変容に繋げるための工夫が際立っています。「SDGsえどがわ10の行動」として、「食品ロスを防ごう」「電気も水も大切に使おう」といった、誰でも日常生活で実践できる具体的なアクションリストを作成・配布し、「自分ごと化」を促進しています。さらに、タワーホール船堀内に「江戸川区SDGs推進センター」を設置し、区民や団体からの相談対応や情報提供、連携調整を行う物理的な拠点として機能させています。
データで見る進捗と課題:ローカル指標(KPI)の比較
SDGs推進の成果を客観的に測定し、PDCAサイクルを効果的に回すためには、具体的で測定可能な指標(KPI)の設定が生命線となります。SDGs未来都市に選定されている区では、2030年のあるべき姿からバックキャストする形で、独自のKPIを設定しています。
- 墨田区の例:
- 経済面では「区内製造業における付加価値額」、社会面では「65歳健康寿命(要介護2以上)」などをKPIとして設定しています。
- 板橋区の例:
- 社会面では子育て世代の定住化を目指し「30~49歳人口・構成割合」、環境面ではゼロカーボンシティの実現に向け「温室効果ガス削減割合(2013年度比)」などをKPIとしています。
企画課は、これらの先進区のKPI設定事例を参考にしつつも、単に模倣するのではなく、自区の基本計画で掲げる目標や、地域が抱える固有の課題に即した独自の「ローカル指標」を策定する必要があります。その際、国連地域開発センター(UNCRD)が公表している日本の自治体SDGs達成度評価レポートなども参考にすべきです。このレポートでは、日本の自治体は全体としてゴール8(働きがいも経済成長も)やゴール9(産業と技術革新の基盤をつくろう)の達成度が高い一方、ゴール2(飢餓をゼロに)やゴール5(ジェンダー平等を実現しよう)に課題があると指摘されており、こうした広域的なデータ分析から自区の弱点を客観的に把握し、それを補強するような戦略的な指標設定が求められます。
【表】特別区におけるSDGs未来都市・主要区の取組比較
以下の表は、これまで見てきた各区の多様なアプローチを一覧化したものです。自区の戦略を立案・評価する際のベンチマークとして活用することで、他区の成功事例や組織体制、KPI設定の考え方を具体的に学び、自区の取り組みを客観的に位置づけ、改善点を発見するためのツールとなります。
| 区名 | 選定状況 | 2030年の姿・中心テーマ | 推進体制の特徴 | 主なモデル事業・取組 | 主要な連携先 | 代表的なKPIの例 |
| 墨田区 | 2021年度ダブル選定 | 持続可能なまちづくり(全計画への統合) | 区長トップの推進本部 | 産業観光振興、健康長寿 | 区内事業者、地域団体 | 区内製造業付加価値額、健康寿命 |
| 板橋区 | 2022年度未来都市 | 絵本がつなぐ教育環境都市 | 官民連携プラットフォーム | 絵本のまち推進、ゼロカーボン | 区内企業、大学、NPO | 30-49歳人口、温室効果ガス削減率 |
| 足立区 | 2022年度ダブル選定 | 「貧困の連鎖」解消モデル構築 | 官民連携パートナー制度 | 綾瀬地区のエリアデザイン、子どもの居場所づくり | 子ども食堂、NPO、地域企業 | 子どもの「生き抜く力」指標、区への誇り |
| 港区 | – | 誰もが住み続けられるまち | 基本計画への統合 | 防災、3R、国際交流 | 大使館、国際機関 | (計画ごとの個別指標) |
| 世田谷区 | – | ゼロカーボンシティの実現 | 環境基本計画が主導 | 地球温暖化対策、3R推進 | 区民、環境団体 | 温室効果ガス排出量 |
| 江戸川区 | – | ともに生きるまち(共生社会) | SDGs推進センター設置 | SDGsえどがわ10の行動 | 区民、エコセンター | (行動変容に関する指標) |
外部連携とパートナーシップの深化
地方創生SDGs官民連携プラットフォームの戦略的活用
行政のリソースだけでは解決が困難な複雑な地域課題に対し、民間の持つ専門知識、技術、資金、ネットワークを呼び込むことは、SDGs達成の鍵となります。そのための最も強力なツールが、内閣府が運営する「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」です。
このプラットフォームは、単なる情報交換の場に留まりません。自治体が抱える具体的な課題を登録し、その解決策を持つ全国の企業や団体から直接提案を受けることができる、実践的なマッチングシステムです。企画課は、このプラットフォームに区として正式に会員登録し、戦略的に活用すべきです。
- 活用ステップ:
- 課題の登録:
- 企画課が庁内各部署から「民間と連携して解決したい課題」をヒアリングし、取りまとめます。(例:「増加する空き家の利活用」「災害時における要支援者への情報伝達手段の確保」「フードロス削減に向けた新たな仕組みづくり」など)
- 提案の募集・検討:
- 登録した課題に対し、プラットフォームを通じて企業等から提案が寄せられます。企画課は、提案内容を所管課と共有し、実現可能性や区へのメリットを検討します。
- 連携事業の実現:
- 具体的な連携協議を進め、協定の締結や実証実験などを通じて事業化を目指します。山形県西川町が企業の浄化槽内蔵型トイレを豪雪地での実証実験として設置した事例など、多様な連携の形が考えられます。
- 課題の登録:
また、このプラットフォームでは、他の自治体と企業の連携成功事例が多数公開されています。企画課はこれらの事例を定期的に研究し、自区で応用可能なパートナーシップのヒントを得るための情報源としても活用します。
区内事業者・金融機関・大学との連携モデル
全国規模のプラットフォームと並行して、足元の地域社会に根差したステークホルダーとの連携を深化させることも極めて重要です。企画課は、地域の多様な主体をSDGsという共通の目標の下に結集させるハブとしての役割を担います。
- 区内事業者との連携:-多くの中小企業にとって、SDGsはまだ「大企業が取り組むもの」というイメージが根強いのが現状です。企画課は、産業振興部門と連携し、SDGsに取り組むことが「企業の社会的責任」であるだけでなく、「企業価値の向上」「新たな事業機会の創出」「人材確保への貢献」といった具体的な経営上のメリットに繋がることを伝えるセミナーや勉強会を企画します。板橋区の中小企業向けSDGs/ESG経営推進支援事業や、足立区の「あだちSDGsパートナー」制度は、優れたモデルとなります。
- 地域金融機関との連携:
- 国が推進する「地方創生SDGs金融」の考え方に基づき、地域の金融機関(信用金庫、信用組合など)に働きかけを行います。具体的には、区内の事業者が行うSDGsに貢献する設備投資や新規事業に対し、低利で融資を行う制度の創設などを共同で検討します。金融機関が融資判断にSDGsの視点を取り入れることで、地域全体にサステナブルな資金が循環する流れが生まれます。
- 大学との連携:
- 特別区内及び近隣には、多くの大学が存在します。大学は、専門的な知識を持つ教員や、行動力と柔軟な発想を持つ学生という貴重な資源の宝庫です。企画課は、大学連携の担当部署と協力し、地域の課題解決をテーマとした共同研究プロジェクトを立ち上げたり、学生に地域のNPOや企業でのSDGs関連インターンシップの機会を提供したりするなど、大学の知と活力を地域に還流させるための具体的なプログラムを企画します。足立区の大学連携講座などはその一例です。
区民参加を促す「自分ごと化」の仕掛けづくり
SDGsの理念である「誰一人取り残さない」社会の実現には、行政や企業の取り組みだけでなく、区民一人ひとりがSDGsを「自分ごと」として捉え、日々の暮らしの中で行動変容を起こすことが不可欠です。企画課は、広報部門や地域振興部門と連携し、区民が楽しみながらSDGsを学び、参加できる仕掛けを企画・推進します。
- 行動の可視化と簡素化:
- 江戸川区の「SDGsえどがわ10の行動」は、SDGsという壮大な目標を、「マイバッグを持つ」「食品を使い切る」といった、具体的で誰にでもできる身近な行動に落とし込んでいる秀逸な例です。このような分かりやすいメッセージを発信することで、区民が行動を始めるきっかけを提供します。
- 参加の場の創出:
- 足立区が綾瀬地区で実施している「アヤセ未来会議」のように、地域の未来について区民が主体的に語り合い、アイデアを出し合うワークショップや対話の場を設けます。行政が一方的に計画を示すのではなく、計画段階から区民が参画することで、当事者意識が醸成されます。
- イベントとの連携:
- 板橋区が区民まつりや産業見本市でSDGs特設ブースを設置しているように、多くの区民が集まる既存のイベントを活用し、SDGsに触れる機会を創出します。クイズラリーや体験型ブースなどを通じて、子どもから高齢者まで、幅広い世代がSDGsに関心を持つきっかけを作ります。
業務改革とDXによる推進力の最大化
GIS等を活用したデータに基づく政策立案(EBPM)
SDGsの推進は、客観的なデータに基づき、最も効果的な施策に資源を集中させるEBPM(証拠に基づく政策立案)と極めて親和性が高いアプローチです。そのための強力なツールが、GIS(地理情報システム)です。GISは、様々な地理空間情報を地図上で重ね合わせて可視化・分析するシステムであり、SDGsが扱う複雑な地域課題の構造を直感的に理解することを可能にします。
企画課は、庁内のDX推進部門と連携し、GISを活用した政策立案プロセスを主導します。具体的には、以下のような分析が可能になります。
- 課題の集中エリアの特定:
- 「高齢化率が高い地域(ゴール3)」の地図と、「バリアフリー化が進んでいない道路(ゴール11)」の地図、「公共交通の空白地帯(ゴール11)」の地図を重ね合わせることで、「移動困難な高齢者が集中しているリスクの高いエリア」を視覚的に特定できます。
- 資源配分の最適化:
- 「子どもの貧困率が高い地域(ゴール1)」の地図と、「子ども食堂や学習支援拠点の配置(ゴール4, 11)」の地図を比較することで、支援が必要な地域にサービスが適切に届いているかを検証し、新たな拠点配置の計画に活かすことができます。
- 政策効果の可視化:
- ある地域で緑化事業を実施した後、その地域のヒートアイランド現象がどの程度緩和されたか(ゴール13)、あるいは周辺の住民の健康状態にどのような変化があったか(ゴール3)を時系列で比較し、政策の効果を地図上で分かりやすく示すことができます。
このようなデータに基づく分析は、これまで担当者の経験や勘に頼りがちだった政策の優先順位決定を、客観的で誰もが納得できるものへと変革させます。企画課は、GISなどのツールを駆使して作成した分析結果を庁内推進本部や議会に提示し、データに基づいた合理的な意思決定を支援する役割を担います。全国の自治体のSDGs進捗状況を可視化するプラットフォームなども存在しており、これらを活用して自区の状況を相対的に把握することも有効です。
ICT活用による業務効率化(ペーパーレス、省エネ等)
SDGsの推進は、地域社会や区民に向けた施策だけでなく、行政組織自らのあり方を変革する取り組みでもあります。「隗より始めよ」の言葉通り、区役所自身がサステナブルな組織へと変わることは、施策の説得力を高める上で不可欠です。
企画課は、総務部門や情報システム部門と連携し、庁内全体の働き方改革とSDGsを結びつけ、ICTを活用した業務効率化を推進します。
- ペーパーレス化の徹底(ゴール12:つくる責任 つかう責任):
- 会議資料の原則デジタル化、電子決裁システムの全面導入などを推進し、紙資源の消費を大幅に削減します。
- Web会議の活用(ゴール13:気候変動に具体的な対策を):
- 庁内・庁外の打ち合わせにWeb会議システムを積極的に活用することで、職員の移動に伴う時間とエネルギー消費(CO2排出)を削減します。
- 庁舎の省エネルギー化(ゴール7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに):
- 板橋区が推進しているように、庁舎の照明のLED化や高効率な空調設備への更新、公用車へのEV導入などを計画的に進めます。エネルギー使用量をリアルタイムで監視・制御するBEMS(ビルエネルギー管理システム)の導入も有効です。
これらの取り組みは、単なるコスト削減や業務効率化に留まりません。行政運営そのものをサステナブルな形に変革する実践であり、区民や区内事業者に対してSDGsへの取り組みを促す際の、最も説得力のある実例となるのです。
生成AIの戦略的活用
近年急速に発展する生成AIは、企画課の業務を根底から変革し、SDGs推進を飛躍的に加速させるポテンシャルを秘めています。既に多くの自治体で、文書作成や議事録要約といった業務での活用が始まっており、世田谷区では1人あたり1日35分の業務削減効果が報告されるなど、その効果は実証されつつあります。国も「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」を策定し、安全な利活用を強力に後押ししています。
企画課は、生成AIを戦略的に活用することで、職員を単純作業から解放し、より創造的で付加価値の高い業務へとシフトさせることができます。
- 企画立案・文書作成業務での活用:
- 具体的な業務:
- SDGs関連イベントでの区長挨拶文の作成、基本計画の素案作成、審議会の議事録要約、先進事例の調査レポート作成、プレスリリース文案の作成など。
- 活用方法:
- 過去の議事録や計画書を学習させたAIに対し、目的や要点、文体のトーンなどを指示するだけで、質の高い原案を瞬時に作成させることが可能です。これにより、職員はゼロから文章を考える膨大な時間を削減し、企画内容そのもののブラッシュアップや、多様なステークホルダーとの合意形成といった、より本質的な業務に集中できます。
- 具体的な業務:
- データ分析と政策シミュレーションでの活用:
- 具体的な業務:
- 区民アンケートの自由記述欄やパブリックコメントの意見の傾向分析、SNS上の区政に関する投稿の感情分析など。
- 活用方法:
- これまで人手では多大な時間を要した、数千件にも及ぶ定性的なテキストデータをAIに分析させ、主要な意見、頻出するキーワード、ポジティブ/ネガティブな感情などを自動で抽出・分類させることが可能です。つくば市では、市民の声を「見える化」し、政策立案に活用する試みが行われています。将来的には、各種統計データを統合し、「この地域に新たな子育て支援施設を整備した場合、周辺の若年層の転入率や出生率にどのような影響を与えるか」といった政策シミュレーションへの活用も期待されます。
- 具体的な業務:
- 広報・区民対話における活用:
- 具体的な業務:
- 区のSDGsの取り組みを、若者や外国人などターゲットに合わせて分かりやすく伝えるSNS投稿文や広報記事の作成、FAQチャットボットの開発、多言語での情報発信。
- 活用方法:
- 京都市や観音寺市のように、区の公式ウェブサイトやLINEアカウントにAIチャットボットを導入し、24時間365日、多言語での問い合わせに自動で応答する体制を構築します。複雑な行政サービスやSDGsの概念についても、AIが対話形式で平易な言葉に翻訳して説明することで、区民の理解を深め、行政サービスのアクセシビリティを向上させます。
- 具体的な業務:
生成AIの導入は、単なるツール更新以上の意味を持ちます。それは、企画課職員の役割を、自ら情報を集め、資料を作成する「情報の作成者・処理者」から、AIが出力した多様な選択肢を評価・編集し、最終的な意思決定を行う「評価者・編集者」、そしてAIを駆使して新たな価値を創造する「戦略家」へと進化させるものです。AIに代替される業務に固執するのではなく、AIを「極めて優秀な部下」として使いこなし、人間にしかできない高次の思考や判断、そして他者との共感に基づく合意形成に集中すること。これこそが、未来の企画課職員に求められる姿です。
実践的スキル:PDCAサイクルによる継続的改善
組織レベルで回すPDCAサイクル
SDGsの推進は、一度計画を立てて終わりではなく、社会の変化に対応しながら継続的に改善していくプロセスです。そのためのフレームワークが、組織全体で取り組むPDCAサイクルです。企画課は、区の基本計画の進行管理と一体化させる形で、このサイクルを主導します。
- Plan(計画)
- ステップ1:現状分析と課題の特定
- GISや各種統計データ、区民意識調査の結果などを駆使し、自区のSDGs達成に向けた現在地(強み・弱み)を客観的かつ定量的に把握します。
- ステップ2:ビジョンと目標(KPI)の設定
- 分析結果に基づき、区の基本計画の中に、2030年のあるべき姿(ビジョン)を明確に描き、その達成度を測るための具体的で測定可能なKPI(重要業績評価指標)を設定します。例えば、板橋区が設定した「温室効果ガス削減率」や「30~49歳人口の割合」などがこれにあたります。客観的な指標を設定するためのマニュアルを作成することも有効です。
- ステップ1:現状分析と課題の特定
- Do(実行)
- ステップ3:アクションプランの実行と進捗共有
- 設定されたKPIを達成するため、各事業所管課が具体的なアクションプラン(事務事業)を策定し、実行に移します。企画課は、四半期ごとなど定期的に各課から進捗状況をヒアリングし、庁内推進本部などの場で情報を共有します。また、部署間の連携が不可欠な事業については、調整役として円滑な実行を支援します。
- ステップ3:アクションプランの実行と進捗共有
- Check(評価)
- ステップ4:KPI達成度のモニタリング
- 年度末に、計画策定時に設定した各KPIの目標値に対し、実績値がどうであったかをデータに基づいて評価します。
- ステップ5:要因分析の実施
- 単に「達成できた」「できなかった」で終わらせず、その要因を深く分析することが重要です。企画課は、事業所管課と協力し、「なぜこの指標は目標を上回ったのか(成功要因)」「計画通りに進まなかった背景にはどのような外部環境の変化があったのか(阻害要因)」などを多角的に分析します。
- ステップ4:KPI達成度のモニタリング
- Action(改善)
- ステップ6:評価結果の次期計画・予算への反映
- 評価と分析の結果を基に、次期の改善アクションを具体的に決定します。成功要因が特定できた事業は他部署へ横展開し、効果が限定的だった事業は手法の見直しや統廃合を検討します。この改善方針を、次年度の予算編成プロセスや、次期基本計画の策定に明確に反映させることで、PDCAサイクルが完成し、組織として継続的に学び、進化していくことが可能になります。
- ステップ6:評価結果の次期計画・予算への反映
個人レベルで回すPDCAサイクル
組織全体の大きなPDCAサイクルを動かすのは、職員一人ひとりの日々の業務の積み重ねです。SDGs推進を「自分ごと」として捉え、自らの業務を改善していくための、個人レベルでのPDCAサイクルも同様に重要です。
- Plan(計画)
- ステップ1:自己目標の設定
- 自身が所属する課や係の組織目標(KPI)と連動させ、具体的な個人目標を設定します。例えば、「担当する〇〇プロジェクトにおいて、生成AIを活用して議事録作成時間を前年比で20%削減する」「SDGsに関する外部研修を月1回受講し、得た知見をチーム内で共有する」など、上司と相談の上で、具体的で測定可能な目標を立てます。
- ステップ1:自己目標の設定
- Do(実行)
- ステップ2:計画的な実践と活動の記録
- 設定した目標を達成するために、日々の業務を計画的に遂行します。その際、試してみた新しい工夫、うまくいった点、課題と感じた点などを、日報や業務メモに簡単に記録しておくことが重要です。
- ステップ2:計画的な実践と活動の記録
- Check(評価)
- ステップ3:定期的(週次・月次)な自己評価
- 1週間の終わりや月末に、数分でも時間を取り、設定した個人目標に対する進捗状況を振り返ります。「計画通りに進んでいるか」「なぜうまくいったのか/いかなかったのか」を客観的に自己評価します。
- ステップ3:定期的(週次・月次)な自己評価
- Action(改善)
- ステップ4:改善策の立案とナレッジの共有
- 振り返りで得られた気づきを、翌週・翌月の業務改善に活かします。(例:「この説明方法を使ったところ、関係部署の理解がスムーズだったので、他の案件でも試してみよう」「この時間帯は電話での問い合わせが多いため、集中して資料作成する時間を朝一番に確保しよう」など)。
- 小さな成功事例や改善のヒントを、チームの定例ミーティングなどで共有することで、個人の成長がチーム全体のパフォーマンス向上へと繋がり、組織全体のPDCAサイクルを力強く下支えします。
- ステップ4:改善策の立案とナレッジの共有
おわりに:持続可能な未来を創造する職員として
本マニュアルを通じて、企画課が担うSDGs推進業務の全体像と、その実践に向けた具体的な手法を学んでいただきました。SDGsの推進は、企画課の職員にとって、単なる追加業務や一時的なプロジェクトではありません。それは、自らが暮らし、働く「まち」の未来を構想し、次の世代、さらにその先の世代へとより良い社会を引き継いでいくという、地方公務員としての根源的な使命そのものを体現する、創造的でやりがいに満ちた仕事です。
目の前には、複雑で困難な課題が山積しているかもしれません。しかし、皆様は決して一人ではありません。本マニュアルで得た知識とスキルを羅針盤とし、庁内の仲間、そして地域で活動する多様なパートナーと連携しながら、地域課題の解決という大海原へ果敢に挑戦してください。
皆様一人ひとりの情熱と、日々の業務における小さな創意工夫の積み重ねこそが、持続可能な特別区を実現するための、最も確実で、そして最も力強い原動力となることを信じています。