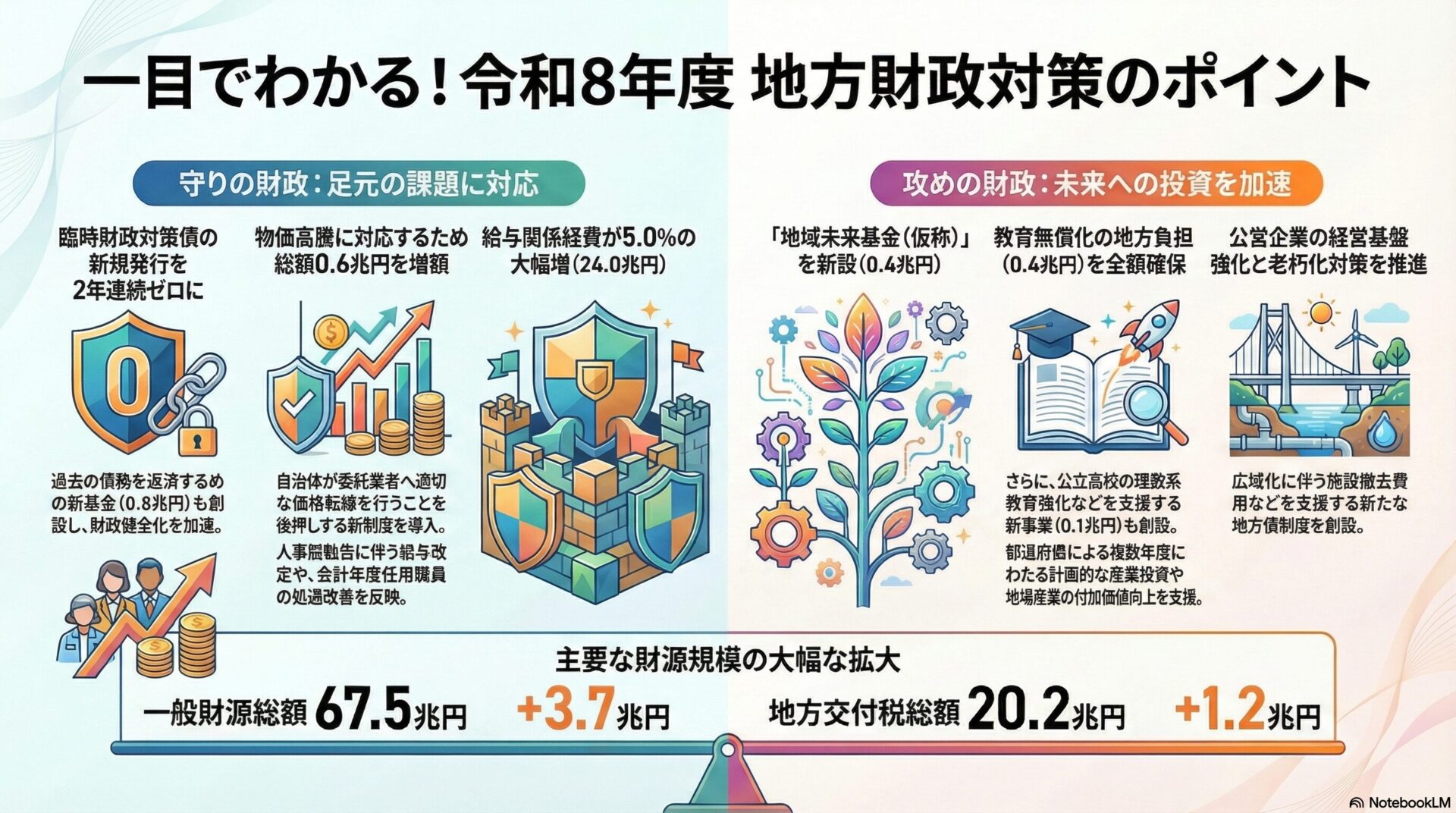高市新内閣と「サナエノミクス」:これからの予算づくりに役立つ国と地方の行政への影響をやさしく解説します

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
日本経済の新しい時代の幕明け
高市新内閣がスタートしたことは、ただ政権が変わったというだけでなく、これからの日本経済の考え方そのものが、根本から大きく変わる可能性を持っています。その中心となる経済政策が「サナエノミクス」です。この政策は、「責任ある積極財政」というスローガンを掲げ、これまでのように経済の調整役だった国の役割を、経済成長をぐいぐい引っ張っていく「エンジン」のような存在に変えようとしています。この大きな考え方の転換は、かつてのアベノミクスが始まったデフレの時代とは全く違う、物価は上がるけれどお給料はなかなか増えない、という新しい経済の状況の中で進められていきます。
この記事では、この新しい時代の経済政策が、国や私たちの身近な市町村といった行政の各分野にどのような影響を与えるのかを、様々な角度から詳しく、そして分かりやすく解説します。行政の現場で、来年度(令和7年度)の補正予算や再来年度(令和8年度)の当初予算の計画を立てる皆様が、的確に準備を進めるためのお手伝いをすることが、この記事の目的です。物価高への短期的な対策から、経済の安全保障や災害に強い国づくりといった中長期的な国の大きな投資計画まで、「サナエノミクス」の全体像を解き明かし、それぞれの行政分野で、これからどのように予算を考え、新しい事業を企画し、そしてどんなリスクに備えればよいのかを具体的に示していきます。
第1章:
今の経済状況と「サナエノミクス」の基本的な考え方
新しい政権の政策を理解するためには、まず、今の日本経済がどんな状況にあり、その政策がどんな考え方に基づいているのかを正確に知ることが大切です。この章では、現在の日本経済が抱える課題をデータで確認し、「サナエノミクス」の中心となる考え方を明らかにします。
1.1. 今の経済が抱える課題:
物価は上がるけれど、お給料は追いつかない
高市内閣が引き継いだ日本経済は、アベノミクスが始まったデフレの時代とは様子が大きく違います。一番大きな特徴は、モノの値段が上がり続けているのに、お給料の伸びがそれに追いついていない、という構造的な問題です。
最新の経済データは、この状況をはっきりと示しています。2025年8月の全国消費者物価指数(CPI)を見ると、全体の数字で前の年の同じ月と比べて2.7%も上昇しています。天候に左右されやすい生鮮食品やエネルギー価格を除いた、より基本的な物価の動きを示す数字(コアコアCPI)では、なんと3.3%も上昇しており、物価の上昇が一部の品物だけでなく、幅広い分野に広がっていることが分かります。
一方で、お給料の伸びは力強さに欠けています。2025年8月の毎月勤労統計調査によると、額面のお給料である現金給与総額は、前の年の同じ月と比べて1.5%の増加にとどまっています。このため、物価の上昇分を差し引いた実質的なお給料(実質賃金)は1.2%から1.4%のマイナスとなり、国民が実際に使えるお金は減り続けているのです。この「物価高」と「実質的なお給料の減少」の差こそが、新しい政権が真っ先に取り組まなければならない、政治的にも経済的にも最も重要な課題です。
表1:主な経済データ(2025年第3四半期時点)
| 指標 | 数値 |
| 消費者物価指数(総合、前年同月比) | +2.7% |
| 消費者物価指数(生鮮食品及びエネルギーを除く総合、前年同月比) | +3.3% |
| 現金給与総額(名目、前年同月比) | +1.5% |
| 実質賃金(現金給与総額、前年同月比) | -1.2% |
| 長期金利(10年物国債利回り) | (市場動向に基づく想定値) |
| 為替レート(ドル/円) | (市場動向に基づく想定値) |
1.2. サナエノミクスとは:
アベノミクスを受け継ぎ、さらに発展させる
「サナエノミクス」は、安倍元総理の経済政策「アベノミクス」を受け継ぎ、さらに発展させることをはっきりと打ち出しています。積極的にお金を使う財政政策と、お金を借りやすくする金融緩和政策を続けるという基本的な骨格は同じですが、政策の目的や力を入れる分野で、大きな進化が見られます。
アベノミクスが主にデフレから抜け出すために需要(モノやサービスを買う力)を生み出すことに重点を置いたのに対し、「サナエノミクス」は、国のお金を国の構造そのものを強くするために使おうとします。その考え方は、高市総理自身の著書『日本の経済安全保障』にも詳しく書かれており、海外からの部品供給網を強くしたり、電気や水道などの生活に欠かせないインフラを安定させたり、重要な技術の研究開発を支援したりといった、国の自立性と競争力を高める分野に、国が主導して投資をすることを正しいこととしています。
具体的には、AI、半導体、防衛、宇宙、海洋開発といった戦略的な分野への集中的な投資が、成長戦略の中心になります。これは、単に景気を良くするためだけでなく、国の未来の姿を描き、その実現のために資源を戦略的に配分するという、明確な産業政策への回帰を意味します。この「国としての戦略的な投資」を強く打ち出している点こそが、「サナエノミクス」がアベノミクスとは質的に違う、一番大きな特徴なのです。
1.3. 財政についての考え方:
「責任ある積極財政」と財政健全化目標の難しい関係
「サナエノミクス」が掲げる野心的な歳出拡大は、日本の厳しい財政状況と正面からぶつかります。この難しい関係をどう乗り越えていくかが、新政権の運営にとって最大の腕の見せ所となります。
内閣府が発表した最新の「中長期の経済財政に関する試算」(令和7年8月)では、高い経済成長と歳出改革を続けることを前提とした「成長実現ケース」で、国と地方を合わせた基礎的財政収支(プライマリー・バランス、以下PB)が2026年度に黒字になるという見通しが示されています。しかし、この試算は、防衛費や子ども関連予算といった決まっている歳出増は計算に入っていますが、「サナエノミクス」が掲げる大規模な新しい投資や減税策は想定していません。
特に、ガソリン税・軽油引取税の暫定税率をやめることは、国と地方を合わせて年間約1.5兆円もの恒久的な減収につながります。これに大規模な補正予算による歳出増が加わることを考えると、2026年度にPBを黒字化するという目標の達成は、事実上不可能になります。そのため、新政権はPB黒字化目標を一時的に「凍結」するか、目標の年を先延ばしにすることを宣言し、短期的な財政収支よりも成長のための投資を優先する姿勢をはっきりさせると考えられます。この方針転換は、財政規律を重視する人々からは強い批判を招く一方で、緊縮財政からの脱却を求める層からは支持を得るでしょう。
この非常に難しい舵取りを担うのが、片山さつき財務大臣です。財務省出身である彼女の起用は、積極財政を進めたい官邸の意向を、財政規律を重んじる財務省にスムーズに伝え、政策を実現するための調整を行うための戦略的な人事と見ることができます。彼女の役割は、官邸の政策をただ実行するだけでなく、それを「成長につながる責任ある投資」として市場や省内に説明し、財政規律が完全に崩壊するのを防ぎつつ、安倍政権の後半に見られたような規律の緩みをコントロールするブレーキ役となることです。
1.4. 金融政策と日本銀行:
独立性への影響
「サナエノミクス」の積極的な財政政策は、日本銀行(日銀)の金融政策の運営に非常に大きな影響を与えます。なぜなら、低い金利を維持することは、国の莫大な借金の利払いを抑え、財政出動の効果を最大限に引き出すための必須条件だからです。
高市総理は以前、日銀の利上げを「あほやと思う」と発言するなど、金融引き締めに対してはっきりと反対の意向を示してきました。新総理としては、公式には「金融政策の具体的なやり方は日銀が決めるべき」としながらも、「財政・金融政策の方向性を決めるのは政府」と述べ、政策の大きな方向性については政府が主導権を持つべきだという考えを表明しています。
この姿勢は、物価の安定を任務とする中央銀行の独立性という、近代的な経済政策の根本を揺るがすかもしれません。現在、日銀は物価が上がり続けていることを背景に、金融政策を正常な状態に戻すこと(利上げ)を模索している段階にあります。しかし、政権からの強い金融緩和維持の圧力は、日銀が適切なタイミングで利上げを行うことをためらわせる可能性があります。市場はすでにこの政治的なリスクを織り込み始めており、高市氏が総裁になるという観測が高まった時点で、短期的な利上げの確率は大幅に下がりました。政府の財政拡大の必要性と、日銀の物価安定という任務との間の緊張関係は、今後の日本経済における最大のリスク要因の一つとなるでしょう。
1.5. 経済のこれから:
長期金利、為替、そして「財政ファイナンス」のリスク
これまでの分析をまとめると、今後の金融市場は、非常に先行きが不透明な展開が予想されます。
「サナエノミクス」が掲げる積極財政は、実質的なお給料が下がっている中での需要刺激策であり、供給側の問題から起きている現在の物価上昇をさらに加速させるリスクを抱えています。この政策の組み合わせは、日銀を深刻なジレンマに陥れます。もし日銀が政府の意向を汲んで金融緩和を続ければ、金利は低く抑えられるかもしれませんが、円安が急激に進み、輸入品の価格高騰を通じてさらなるインフレを招くでしょう。これは、国民生活を圧迫し、政権の支持基盤を揺るがしかねません。最悪の場合、国債の信頼が失われ、日銀が政府の赤字を直接引き受ける「財政ファイナンス」への懸念が現実味を帯び、金利の急騰とコントロール不能なインフレを招く恐れがあります。
逆に、日銀が独立性を守り、インフレを抑えるために利上げを断行すれば、円安には歯止めがかかるものの、政府の利払い費が急増し、「サナエノミクス」が目指す戦略的な投資のためのお金を圧迫します。さらに、景気後退を引き起こす可能性も高まり、官邸と日銀の深刻な対立に発展するでしょう。
このように、「サナエノミクス」の政策パッケージは、マクロ経済運営の安定性を著しく損なう「インフレの悪循環」を作り出す危険性をはらんでいます。行政担当者の皆様は、今後の予算計画において、輸入資材価格のさらなる上昇、金利変動のリスク、そして為替の不安定化といった要因を、これまで以上に慎重に考慮に入れる必要があります。
第2章:
短期的な取り組みと当面の財政への影響(令和7年度補正予算)
新政権は発足後、目の前の物価高騰問題への対応を最優先課題とし、すぐに効果が出る政策を盛り込んだ大規模な令和7年度補正予算を組む見込みです。行政担当者の皆様は、この緊急経済対策の内容を正確に把握し、迅速に実行できる体制を整える必要があります。
2.1. 物価高騰対策:
給付金と減税
補正予算の柱となるのは、家計の負担を直接軽くするための給付金や減税措置です。
- 現金給付:
- 全国民を対象とした一律、あるいは所得に制限を設けた大規模な現金給付が実施される可能性が高いです。その際、迅速な支給と事務手続きのコストを減らすため、マイナンバー制度とそれに紐づけられた公金受取口座が最大限に活用されるでしょう。各自治体は、デジタル庁と緊密に連携し、口座情報の照会や振り込み事務をスムーズに実施できる体制を早急に確認する必要があります。
- 給付付き税額控除:
- より恒久的な低所得者支援策として長年議論されてきた「給付付き税額控除」について、本格的な導入に向けた試験的な事業や、簡素な形での導入が検討される可能性があります。しかし、これを実現するには、特に確定申告をしない人々や事業所得者の所得を正確に把握するという、制度上の長年の課題が残っています。マイナンバー制度の活用が前提となりますが、実務上のハードルは依然として高いです。
これらの施策の財源は、主に2024年度(令和6年度)の税収が予想を上回った分が充てられますが、対策の規模によっては赤字国債の追加発行が避けられない見通しです。
2.2. ガソリン税の暫定税率廃止
国民生活に身近なガソリン価格の引き下げは、政権の支持を得やすい政策として、早い段階で実行される可能性が高いです。具体的には、ガソリン税や軽油引取税に上乗せされている暫定税率の廃止が考えられます。
- 財政への影響:
- この措置による税収の減少額は、国と地方を合わせて年間約1.5兆円に達します。このうち、軽油引取税は地方税であり、その減収分は地方の財政を直接圧迫します。例えば、愛媛県では年間約55億円の減収が見込まれるとの試算もあり、多くの自治体で行政サービスの低下が心配されています。
- 行政への影響:
- 地方自治体は、この減収分を補うための代替財源の確保を国に対して強く求めることになるでしょう。国の財政担当部局は、地方交付税の増額や新たな臨時交付金の創設など、地方財政への影響を和らげるための措置を補正予算に盛り込む必要に迫られます。各自治体は、減収額の正確な試算を急ぎ、国への要望活動を組織的に展開する必要があります。
表2:主な短期政策の財政への影響(試算)(令和7年度補正予算)
| 項目 | 内容 | 財政規模(試算) | 財源 |
| 歳出 | |||
| 定額現金給付 | 全国民または低・中所得者層への一律給付 | 数兆円規模 | 税収上振れ分、赤字国債 |
| 中小企業・農林漁業支援 | 地方創生臨時交付金を通じた物価高騰対策支援 | 1兆円規模 | 赤字国債 |
| 歳入減 | |||
| ガソリン・軽油税の暫定税率廃止 | 税率引き下げによる恒久的減収(国・地方合計) | 年間▲1.5兆円 | 代替財源の議論が必須 |
| 財源調達 | |||
| 令和6年度税収上振れ分 | (実績に基づく) | – | |
| 新規赤字国債発行額 | (歳出規模に応じ変動) | – |
第3章:
中長期の戦略的な投資と構造改革(令和8年度当初予算以降)
補正予算による短期的な一時対策と並行して、新政権は日本の構造的な課題に対応するため、中長期的な視点での戦略的な投資を令和8年度の当初予算から本格的にスタートさせます。これらの投資は、「サナエノミクス」の本質であり、各省庁の予算配分に大きな変化をもたらすでしょう。
3.1. 成長のエンジン:
経済安全保障推進法と「Kプログラム」
「サナエノミクス」の成長戦略の中心となるのが、経済安全保障の枠組みです。経済安全保障推進法に基づいて、国と民間が協力して重要な技術を育てたり、部品の供給網を強くしたりする取り組みが進められます。
- 重点的に投資する分野:
- その中心となる「経済安全保障重要技術育成プログラム(通称:Kプログラム)」には、巨額の国の予算が投じられます。具体的な支援対象として、AI、量子技術、宇宙(人工衛星群)、海洋(自律型無人探査機:AUV)、バイオテクノロジー、最先端の素材などが特定されています。これらの分野を担当する経済産業省、文部科学省、内閣府などの関連部署は、大幅な予算増が見込まれます。
- 行政への影響:
- 他の省庁においても、自分たちが担当する政策を「経済安全保障」という視点から見直し、予算を要求することが非常に重要になります。例えば、厚生労働省は医薬品やワクチンの国内生産能力の強化を「健康安全保障」と位置づけ、農林水産省は食料自給率の向上を「食料安全保障」と位置づけることで、これらの戦略的な予算を獲得する道が開かれます。
3.2. 国土強靭化2.0:
DX・GXと進化した防災の統合
これまでの国土強靭化計画は継続され、さらに拡充されますが、その内容は大きく進化します。単なる公共事業ではなく、DX(デジタルトランスフォーメーション)とGX(グリーントランスフォーメーション)の要素を取り入れた、次世代のインフラ整備が主流となります。
- 技術の融合:
- 今後のインフラ関連の予算は、DXとGXにどれだけ貢献するかが重要な評価基準になります。例えば、川の改修事業においては、IoTセンサーによるリアルタイムの水位監視や、AIを活用した洪水予測システムの導入がセットで求められるでしょう。公共施設の新設や改修においては、太陽光発電設備や蓄電池の設置、避難所での電源として電気自動車(EV)を活用する仕組みの導入などが標準仕様となるでしょう。
- 先進モデルとしての東京都:
- 東京都が進める「『未来の東京』戦略」は、この統合的なアプローチの先進的な事例です。デジタルツインという仮想空間での水害シミュレーション、AIによる被害判定、グリーン水素の導入など、防災・DX・GXを一体的に進める取り組みは、他の自治体が補助金を申請したり、事業計画を立てたりする上で重要な参考になります。
3.3. エネルギー・食料安全保障という重要な課題
高市総理は、日本のエネルギー自給率(12.6%)と食料自給率(カロリーベースで38%)の低さを国の弱点だと明確に指摘しており、これらの分野への国の投資を最重要課題の一つに掲げています。
- 政策の方向性:
- 農林水産業、再生可能エネルギー、そして原子力の活用を含むエネルギー政策全般において、国内の生産基盤を強化するための補助金や戦略的な投資が大幅に拡充される見込みです。これらの政策はすべて、「国家安全保障」という大きな枠組みの下で正しいこととされます。
これらの戦略的な投資は、これまでの省庁ごとの縦割り予算とは違う仕組みで実行される傾向が強まるでしょう。Kプログラムのようなトップダウン型の戦略的な基金や、地方創生臨時交付金のような使い道の自由度が高い一括交付金が多く使われることで、予算配分の権限が実質的に総理官邸や一部の戦略的な官庁に集中していきます。この権限集中の流れは、行政の現場に大きな影響を及ぼします。これまでのボトムアップ型の陳情や、前年度の予算を踏襲するような要求は通りにくくなります。予算を獲得できるかどうかは、各省庁や自治体が、自分たちの事業をいかに官邸が示す国の最優先課題と結びつけ、その戦略的な意味を明確に説明できるかにかかっています。地方自治体にとっては、地域の個別の課題を国の大きな戦略目標(経済安保、国土強靭化など)の視点から語り直し、説得力のある事業提案を行う能力が、これまで以上に求められることになります。
第4章:
行政分野ごとの影響分析
この章では、「サナエノミクス」がもたらす変化を、16の具体的な行政分野ごとに分析し、令和7年度補正予算や令和8年度当初予算を考える上での実践的なヒントを提示します。
表3:「サナエノミクス」が各行政分野に与える影響のまとめ
| 行政分野 | 短期的な影響(R7補正) | 中長期的な影響(R8以降) | 主な財源やリスク | 予算計画へのおすすめの対応 |
| 自治体経営 | 臨時交付金が増え、自由に使えるお金が増える。ガソリン税減収分をどう補うかが注目点。 | 自治体独自の事業に使えるお金が減るリスク。国の戦略に合った事業にお金を重点的に配分する必要。 | 地方創生臨時交付金、地方交付税/財政の硬直化 | 減収額を計算し、代わりの財源を国に要請。DX・GX関連の基金活用を計画する。 |
| 環境政策 | 省エネ家電への買い替え促進など、家庭のエネルギー代負担を軽くする政策に交付金を活用。 | GX関連の投資が本格化。再生可能エネルギー導入、水素社会の実現、グリーンインフラ整備に重点配分。 | GX推進関連予算、環境省予算/技術的に実現可能か | 自治体版のGX戦略を作り、国の計画と連携したプロジェクトを立案する。 |
| DX政策 | 給付金支給事務でマイナンバーや公金受取口座を活用。行政手続きのオンライン化が加速。 | 自治体DX、防災DX、スマートシティ関連の予算が大幅増。データ連携の仕組み作りが必須に。 | デジタル田園都市国家構想交付金/サイバーセキュリティ | 全庁的なDX推進計画を見直し。防災や福祉など他の分野との連携を強化する。 |
| 防災政策 | 臨時交付金で防災備蓄品を購入したり、避難所の環境を改善したりする。 | 「国土強靭化2.0」としてDX・GXと統合。ドローン、AI、再生可能エネルギーを活用した防災が主流に。 | 国土強靭化関連予算/従来型のインフラ予算の削減 | DX・GXの要素を取り入れた次世代の防災計画を策定。Kプログラムの軍民両用技術も視野に入れる。 |
| 生活安全政策 | 経済的な困窮からくる犯罪増加への対策。地域の防犯活動への支援。 | サイバー犯罪対策を強化。経済安保関連で重要インフラの防護、セキュリティクリアランスの導入。 | 警察庁予算、経済安保関連予算/プライバシー保護 | サイバーセキュリティ人材の育成・確保。重要インフラ事業者との連携を強化する。 |
| 経済産業政策 | 中小企業への物価高・燃料費対策支援(臨時交付金)。 | Kプログラムによる先端技術開発支援。部品供給網の強化、スタートアップ育成が柱。 | 経済安保基金、経済産業省関連予算/政府の過度な介入 | 地域の主要産業を経済安保の視点で見直し、国の支援策との連携を図る。 |
| 子育て・子ども政策 | 所得の低い子育て世帯への給付金。学校給食費の負担軽減支援。 | 「こども未来戦略」の継続。ヤングケアラー支援、不登校特例校の設置など個別課題への対応強化。 | こども未来戦略関連予算/財源が恒久的か | 自治体版のこども計画に国の戦略を反映。DXを活用した支援情報の提供を強化する。 |
| 教育政策 | 学校給食費の支援。ICT環境の維持・更新費用への支援。 | 教育のDX化を推進。セキュリティクリアランス導入に伴い、大学・研究機関での情報管理を強化。 | 文部科学省関連予算/教員不足、情報格差 | GIGAスクール構想の次のステップを計画。研究機関での情報管理体制を点検する。 |
| 福祉政策 | 福祉施設(介護・保育など)への光熱費・食費高騰対策支援。 | 介護DXの推進(ロボット、ICT導入支援)。介護人材の待遇改善。孤独・孤立対策の強化。 | 厚生労働省関連予算、介護保険/介護人材不足 | 介護現場の生産性向上に向けたDX導入計画を策定。地域包括ケアシステムを強化する。 |
| 社会保障 | 低所得者・年金生活者への給付金。国民健康保険料の負担軽減措置。 | 「年収の壁」問題への対応。持続可能な制度に向けた給付と負担の見直し議論が再燃。 | 社会保障関係費/財政規律の緩みによる将来世代への負担増 | マイナンバーカードの健康保険証利用を促進。制度改革の国民的議論に備える。 |
| 健康・保健政策 | 医療機関への光熱費など高騰対策支援。 | 医薬品・医療機器の国産化支援(経済安保)。次世代医療技術開発への投資。 | 健康・医療戦略推進費/医療費の増大 | 地域の医療計画を見直し。新しい感染症対策と経済安保を連携させた計画を策定する。 |
| 地域振興政策 | プレミアム商品券発行など、地域の消費を盛り上げる策に臨時交付金を活用。 | デジタル田園都市国家構想の継続・発展。地方大学の振興、関係人口を増やす事業の強化。 | 地方創生関連交付金/大都市への一極集中是正の難しさ | 地域の強み(農産物、観光資源など)を食料・エネルギー安保の観点から見直し、事業化する。 |
| 多文化共生政策 | 外国人住民への給付金情報の提供、多言語での対応。 | 経済安保の観点から、高度な技術を持つ外国人材の受け入れ促進と管理強化が同時に進む。 | 出入国在留管理庁予算/人権への配慮とのバランス | 外国人住民への情報提供体制を強化。地域の企業と連携し、高度人材が定着する策を検討する。 |
| スポーツ政策 | 地域のスポーツ施設への運営費支援。 | 大規模な国際大会の誘致・開催支援。スポーツ産業の成長戦略。 | スポーツ庁予算/財源の優先順位 | スポーツ施設の省エネ化(GX)、DX活用による運営効率化を計画する。 |
| 文化政策 | 文化施設への光熱費支援。文化芸術活動への緊急支援。 | 日本文化の発信強化(クールジャパン戦略)。文化財のデジタルアーカイブ化、防災対策。 | 文化庁予算/財源の優先順位 | 文化財保護に防災DX技術(センサー監視など)を導入する計画を立案する。 |
| まちづくり・インフラ整備政策 | 公共交通機関への燃料費高騰対策支援。 | コンパクトシティ、スマートシティ化の推進。無電柱化の加速。インフラ老朽化対策。 | 国土交通省関連予算/建設コストの高騰 | 都市計画にDX・GX・防災の視点を統合。インフラの維持管理に予防保全技術を導入する。 |
分野別詳細分析(いくつか詳しく見ていきましょう)
防災政策
- 短期的な影響(R7補正):
- 物価高騰は、防災備蓄品の購入コストや避難所運営にかかる光熱費を直撃します。拡充される地方創生臨時交付金は、これらのコスト増に対応するための重要な財源となります。各自治体は、最新の物価動向を反映した必要経費を算出し、交付金を活用して計画的に備蓄を更新したり、避難所の生活環境を改善(例:簡易ベッド、空調設備の整備)したりすることを迅速に進めるべきです。
- 中長期的な影響(R8以降):
- 防災政策は、「国土強靭化2.0」という新しい考え方に変わっていきます。予算を要求する際には、従来のハード整備だけでなく、DXとGXの要素をいかに取り入れるかがとても大切になります。具体的には、ドローンを活用して被災状況をリアルタイムで把握したり、AIチャットボットで住民に避難情報を提供したり、SNSの情報を分析して被害状況を推定したりといったDX技術の導入が評価されるでしょう。また、避難所となる公共施設に太陽光発電や蓄電池を導入することは、災害時の電源確保(レジリエンス向上)と平時の温室効果ガス削減(GX)を両立する事業として、優先的に予算が配分されるでしょう。さらに、Kプログラムで開発される軍事と民間の両方で使える技術、例えば海洋観測用の高精度センサーを津波監視に応用するなど、安全保障技術を防災分野に活用する視点も求められます。
福祉政策
- 短期的な影響(R7補正):
- 介護施設、保育所、障害者支援施設などは、光熱費や食料品価格の高騰により、経営が非常に厳しくなっています。政府は地方創生臨時交付金などを通じて、これらの施設に対する直接的な経費支援を行います。自治体は、管内の施設の実態を迅速に把握し、公平で効果的な支援が行き渡るよう、申請手続きを簡単にしたり、丁寧に情報提供したりすることに努める必要があります。
- 中長期的な影響(R8以降):
- 働く世代の人口が減少していく中で、福祉分野が持続可能であるためには、生産性の向上が鍵となります。そのため、「介護DX」が強力に進められます。具体的には、介護ロボットや見守りセンサー、ICTを活用した記録・情報共有システムの導入に対する補助金が大幅に拡充されるでしょう。また、介護人材の確保・定着は国全体の課題であり、待遇改善のための財政措置も継続・強化される見込みです。自治体は、国の方針と連動し、地域の実情に応じた介護DX導入支援計画や、人材確保戦略を策定する必要があります。
自治体経営
- 短期的な影響(R7補正):
- 地方創生臨時交付金が増えることは、各自治体にとって当面の物価高騰対策や地域独自の経済支援策を実施する上で貴重な財源となります。しかし、その一方で、ガソリン税の暫定税率廃止による地方税収の恒久的な減少は、中長期的な財政運営に大きな影響を与えます。自治体は、短期的な交付金に安心することなく、減収額がどれくらいのインパクトを持つかを正確に分析し、国に対して恒久的で安定した代替財源を強く要求し続ける必要があります。
- 中長期的な影響(R8以降):
- 国の財政が「戦略的投資」に重点を置く中で、地方交付税の計算方法や補助金の配分ルールも変わる可能性があります。国の重点戦略(経済安保、DX、GX、国土強靭化)に合致しない自治体独自の事業は、財源を確保することがより難しくなるリスクがあります。したがって、自治体は、総合計画や各種の個別計画を見直し、地域の将来像を国の大きな戦略の方向性と合わせることが不可欠となります。これは、地域の自主性を損なうという批判もあるかもしれませんが、現実的に予算を獲得するための戦略としては避けては通れないでしょう。
第5章:
まとめと行政担当者の皆様への戦略アドバイス
この章では、これまでの分析をまとめ、「サナエノミクス」という新しい政策環境の中で、行政担当者の皆様が取るべき戦略的な行動についてアドバイスします。
5.1. 新しい財政の現実に適応する:
デフレ時代の緊縮からインフレ時代の拡大へ
行政運営の根底にあった考え方を変える必要があります。これまでは、デフレと財政赤字を背景に、効率化と歳出削減を最も大切なこととする「緊縮の考え方」が主流でした。しかし、「サナエノミクス」は、インフレ下であっても国の目標を達成するために財政を積極的に活用する「拡大の考え方」へと舵を切ります。この変化は、予算要求の論理、事業評価の基準、そしてリスク管理の対象を根本から変えるものです。
5.2. 令和7年度補正予算編成へのアドバイス
- 行動指針:
- 物価高騰による国民生活への影響を和らげるという大きな理由を最大限に活用しましょう。各部署は、担当する分野で物価高の影響を受けている事業者や生活者への支援策を迅速に立案し、臨時交付金の獲得を目指すべきです。給付金などの支給事務においては、デジタルツールを駆使して迅速さと正確さを確保し、行政の実行能力をアピールすることが重要です。地方自治体は、ガソリン税減収による財政的な損失を具体的に数値化し、その補填を国に強く働きかけるための活動を組織的に展開する必要があります。
5.3. 令和8年度当初予算編成へのアドバイス
- 行動指針:
- 既存の事業も新しい事業も、すべての政策を「サナエノミクス」が掲げる特に重要な4つのテーマ(経済安全保障、国土強靭化2.0、DX、GX)の視点から見直し、再構築しましょう。省庁や部署の壁を越えた連携(例:防災×DX、福祉×GX)による、複合的で戦略的なプロジェクト提案が、予算獲得の成功確率を格段に高めます。提案書においては、「コスト削減効果」よりも、「日本の部品供給網の強化への貢献」や「エネルギー自給率向上への寄与」といった国全体の戦略レベルでの意義を前面に打ち出すべきです。
5.4. 結び:
「サナエノミクス」のリスク管理
「サナエノミクス」が掲げる戦略的な投資と国を再興するというビジョンは、日本の長年の停滞を打ち破る可能性を秘めています。しかし、その野心的な政策は、重大なマクロ経済のリスクと表裏一体です。
内閣府が示す2026年度にPBを黒字化するという公式の見通しは、「サナエノミクス」の政策内容と明らかに矛盾しており、まるで蜃気楼のように、実態とはかけ離れた姿と言えるかもしれません。新政権はこの目標に固執することなく、事実上棚上げするでしょう。その際、「責任ある積極財政」における「責任」の意味が再定義されます。それは、帳尻を合わせるという会計的な責任ではなく、未来への投資を通じて成長を生み出し、結果として借金の持続可能性を確保するという、よりダイナミックな責任へと変わります。
この新しい考え方を市場が受け入れるかどうかが、「サナエノミクス」が成功するか失敗するかを分けます。行政担当者の皆様は、自分たちの政策がこの国全体の方針にどう貢献するかを語る能力が求められる一方で、長期金利や為替レートといった市場からのサインを注意深く監視し、市場がこの新しい「責任」の定義を信じなくなった場合に備える必要があります。万が一、成長が期待通りに実現せず、積極財政が単なる放漫財政だったと見なされた時、日本は深刻な財政・通貨危機に直面するリスクを負っています。この長期的なリスクを常に頭の片隅に置きつつ、当面の政策のチャンスを最大限に活用すること。それが、「サナエノミクス」の時代を生きる行政官に課せられた、困難かつ重要な役割です。

.jpg)