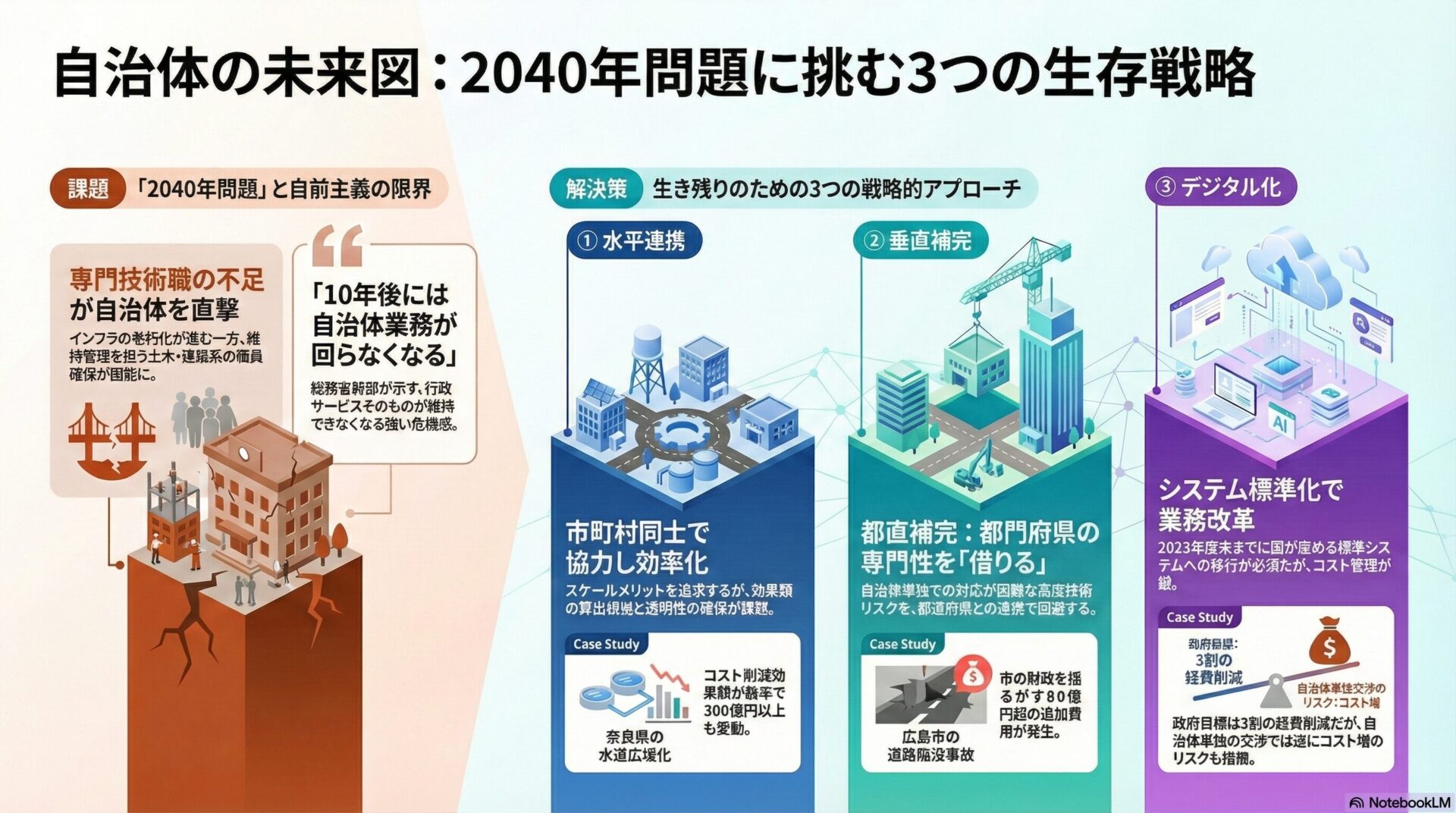金利上昇が地方財政に与える影響度シミュレーション

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
概要
日本銀行による金融政策の正常化(マイナス金利政策の解除、長短金利操作の修正)が現実のものとなり、市場金利は明確な上昇傾向を示し始めました。これは、過去数十年にわたり「金利はほぼゼロ」という前提で構築されてきた地方自治体の財政運営(特に起債管理と資産運用)の根底を揺るがす、重大な環境変化を意味します。
本記事は、このマクロ経済の転換点が、地方自治体(特に財政課)の日々の実務にどのような影響を及ぼすか、その「ミクロ(実務)編」としてシミュレーションを行います。金利が仮に0.5%、さらに1.0%上昇した場合、「公債費(地方債コスト)の増加」「一時借入金利息の上昇」という歳出面の圧力と、「基金運用の利回り改善」という歳入面のメリットを定量的に分析します。フワッとした「金利上昇リスク」という知識を、「だから、我々の来年度予算編成はこう変わる」という具体的な業務アクションに落とし込むための一助としてください。
金利上昇が地方財政に与える3つの主要な影響
金利の上昇は、地方財政において「歳出(支出)」と「歳入(収入)」の両面に同時に、しかし異なるスピードと規模で影響を及ぼします。特に注目すべきは以下の3つのチャネルです。
- 公債費(地方債コスト)の増加:
既発債の借換金利の上昇と、新規発行債の利払い負担増。(影響度:大、中長期的) - 一時借入金利息の上昇:
会計年度内の短期的な資金繰りコストの増加。(影響度:中、即時的) - 基金運用利回りの改善:
財政調整基金などの運用益の増加(歳入増)。(影響度:中、中期的)
これらの影響度は、各自治体の地方債残高、借換スケジュール(特に平均残存期間)、基金残高、そしてその運用ポートフォリオによって大きく異なります。特に、実質公債費比率が既に高い団体や、これから大規模な施設整備(例:庁舎建替、学校の長寿命化改修)で多額の起債を予定している団体は、金利上昇の影響をより深刻に受け止める必要があります。
影響シミュレーション①:
公債費(地方債コスト)の増加
金利上昇が最も直接的かつ中長期的に影響を与えるのが公債費です。総務省の発表によれば、令和4年度(2022年度)末の地方債現在高は、臨時財政対策債を含めると約193兆円に上ります。これらの多くが、今後順次、満期(償還)を迎えます。
- (出典)総務省「令和4年度 地方財政の状況」令和6年(2024年)
既発債(借換債)への影響
自治体は、満期を迎えた地方債の償還財源を確保するために「借換債」を発行します。過去10年以上の超低金利時代に発行された地方債(例:10年債金利が0.1%など)が満期を迎え、これを新たな金利(例:1.0%や1.5%)で借り換える必要が出てきます。
例えば、5年前に金利0.2%で発行した100億円の地方債が満期を迎え、これを金利1.0%の借換債で対応する場合、単純計算で年間の利払い負担は2,000万円(100億円 × 0.2%)から1億円(100億円 × 1.0%)へと、8,000万円増加することになります。
仮に、ある自治体(A市)が来年度(2026年度)、1,000億円の借換を予定しているとします。現在の市場金利(仮に1.0%)に対し、金利が0.5%上昇して1.5%で借り換えることになった場合、この借換分だけで利払い負担は年間5億円(1,000億円 × 0.5%)増加します。
同様に、金利が1.0%上昇して2.0%で借り換えることになった場合、利払い負担は年間10億円(1,000億円 × 1.0%)増加します。
重要なのは、この負担増が「単年度」で終わらない点です。10年債で借り換えれば、この先10年間にわたって高い金利負担が継続します。また、地方債残高全体の平均残存期間(デュレーション)が長い団体ほど、全体の利払いコストが上昇するまでに時間はかかりますが、一度上昇し始めるとその影響は長期間継続することになります。財政担当者は、自団体の「借換債発行予定額一覧(償還カレンダー)」を再確認し、今後5〜10年でどれだけの借換が、どの程度の金利上昇リスクに晒されているかを把握することが急務です。
新規発行債への影響
新たな施設整備や大規模改修のために発行する「建設債」などの新規発行分も、当然ながら金利上昇の影響を受けます。
金利が1.0%上昇すれば、100億円の新規事業債(償還期間30年・元金均等償還と仮定)を発行した場合、単純な総利払い額(金利負担の総額)は、金利1.0%の場合(約15.5億円)から金利2.0%の場合(約31.0億円)へと、約15.5億円も増加します。
これは、単に将来の公債費負担が増えるだけでなく、現在策定中の「公共施設等総合管理計画」や「実施計画」における事業の採算性評価(費用対効果)そのものに影響を与えかねません。金利コストの増加により、事業の優先順位の見直しや、事業規模の縮小、あるいは事業の延期といった、厳しい判断を迫られる可能性があります。
総務省が公表した令和4年度(2022年度)決算に基づく実質公債費比率の全国平均(加重平均)は7.5%ですが、一部の団体では依然として早期健全化基準(25%)に近い水準にあります。
- (出典)総務省「令和4年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要」令和6年(2024年)
こうした団体にとって、金利上昇による公債費の増加は、健全化判断比率の算定式における分子(公債費関連支出)を直接押し上げ、比率を悪化させる要因となります。財政健全化の取組を後退させかねない重大なリスクとして認識すべきです。
影響シミュレーション②:
一時借入金利息の上昇
公債費(長期)だけでなく、短期の資金繰りにも影響が及びます。多くの自治体では、税収が入る時期と経費を支払う時期のズレ(例:4月〜5月の支払い集中期)を埋めるため、「一時借入金」を利用します。
短期金利上昇の即時的インパクト
一時借入金の金利は、政策金利の動向に敏感な「短期金利」(無担保コール翌日物レートなど)に連動します。日銀がマイナス金利を解除し、今後追加利上げに踏み切れば、これまでゼロ近辺で推移してきた一時借入金の金利(支払利子)が明確に上昇します。
ある自治体(B区)が、資金不足を補うため、年度平均で100億円の一時借入金残高(見込み)があると仮定します。
短期金利が0.5%上昇した場合、年間で5,000万円(100億円 × 0.5%)の支払利子が発生します。
短期金利が1.0%上昇した場合、年間で1億円(100億円 × 1.0%)の支払利子が発生します。
これまでは「支払利子」予算をほぼゼロと見積もってきた団体も多いかもしれませんが、2026年度予算編成においては、この短期金利上昇リスクを織り込んだ予算計上が必要不可欠となります。これは純然たるコスト増であり、他の施策的経費を圧迫する要因となります。
この影響は、会計課(出納室)が管理する「歳計現金」のマネジメントの重要性を高めます。財政課と会計課は、これまで以上に緊密に連携し、日々の資金繰り予測(キャッシュフロー)の精度を高め、一時借入金の残高を可能な限り圧縮する(例:税収の早期確保、支払いの平準化)努力が求められます。
影響シミュレーション③:
基金運用の利回り改善(メリット)
金利上昇は、悪い影響ばかりではありません。自治体が保有する各種基金(財政調整基金、減債基金など)の運用にとっては、明確なプラス材料となります。
安全運用と利回り向上の両立
地方自治法上、基金の運用は「確実かつ効率的」に行う必要があり、実務上は元本保証の預金(普通預金、定期預金)や、安全性の高い債券(国債、地方債など)が中心です。
総務省の調査では、令和4年度(2022年度)末の全国の基金残高(財調・減債・その他特定目的基金の合計)は約29.8兆円と、コロナ禍の交付金積立などもあり高水準を維持しています。
- (出典)総務省「令和4年度 地方財政の状況」令和6年(2024年)
ある自治体(C市)が、基金残高1,000億円を保有していると仮定します。
金利上昇に伴い、預金金利や新規購入債券の利回りが改善し、基金全体の平均運用利回りが0.5%改善した場合、年間で5億円(1,000億円 × 0.5%)の運用益(繰入金)が歳入として期待できます。
同様に、平均運用利回りが1.0%改善した場合、年間で10億円(1,000億円 × 1.0%)の歳入増となります。
この運用益は、公債費の利払い増加分の一部を相殺する効果が期待できます。これまで超低金利下で「基金は積み立てても運用益が期待できない」状況でしたが、今後は「戦略的な基金運用による歳入確保」が再び重要な財政運営のテーマとなります。
注意点:既発債券の価格変動リスク(含み損)
ただし、基金運用において(特に債券運用を行っている場合)は重大な注意点があります。それは、市場金利の上昇が、すでに基金で保有している「既発の低金利債券」(例:金利0.1%の10年国債)の「価格(時価)」を下落させることです。
これは「含み損」と呼ばれ、満期まで保有し続ければ元本は償還されますが、何らかの理由(例:突発的な財源不足で基金を取り崩す必要が生じた)で満期前に売却(換金)する必要が生じた場合、元本割れ(売却損)が現実化するリスクがあります。
財政課・会計課の担当者は、基金の運用ポートフォリオ(預金と債券の比率、債券の残存年数、銘柄)を再点検し、流動性リスク(いざという時に換金できるか)と価格変動リスク(含み損がどの程度か)を正確に管理することが求められます。
見過ごされがちな波及経路:
公営企業会計への影響
金利上昇の影響は、一般会計だけに留まりません。上下水道、病院、交通などの公営企業会計も、多額の「企業債」を発行してインフラ整備や更新を行っています。
公営企業会計においても、一般会計と同様に、既発企業債の借換や新規発行債の金利が上昇します。これは、公営企業の経営を直接圧迫するコスト増要因となります。
公営企業は独立採算を原則としているため、このコスト増は、最終的に「使用料・料金の改定(値上げ)」への圧力として、住民サービスに跳ね返ってくる可能性があります。財政課は、公営企業担当部局とも金利上昇リスクに関する情報を共有し、全庁的な影響を把握する必要があります。
2026年度予算編成に向けた実務的論点(業務アクションプラン)
金利上昇局面への移行は、「フワッとした知識」ではなく、財政担当者の「具体的な業務」に直結します。2026年度の予算編成作業においては、以下の視点(アクション)が不可欠です。
公債費(支払利子)の「複数シナリオ」での試算
最大の焦点は公債費です。まずは、自団体の「地方債償還・借換カレンダー」を精査し、来年度(2026年度)および今後5年間の借換予定額と、現在計画中の新規発行予定額を正確に把握します。
その上で、金利が「現状維持(例:1.0%)」「0.5%上昇(例:1.5%)」「1.0%上昇(例:2.0%)」した場合の3パターン程度で、公債費(特に利子)がいくら増加するかを必ずシミュレーションすべきです。
この試算結果は、予算編成の前提(歳出見積もりの基準)として、首長部局や議会と共有するための必須資料となります。
一時借入金「支払利子」の予算計上と資金繰り精査
「一時借入金の利子など、これまで発生しなかった」という前例踏襲は通用しません。会計課と連携し、歳計現金の出入り(資金繰り予測)の精度を高め、必要な一時借入金の見込額を算出します。
その上で、短期金利の上昇を見込み、適切な「支払利子」予算を計上する必要があります。これを怠ると、年度途中の補正予算や予備費の充当が必要となり、財政運営の機動性を損ないます。
基金「運用益(繰入金)」の現実的な見積もりとポートフォリオ点検
歳入面では、金利上昇による運用益の増加(上振れ)を期待できます。ただし、過度に楽観的な見積もりは禁物です。基金の大部分がすぐに高金利で再運用されるわけではなく、定期預金の満期や債券の償還のタイミングで徐々に反映されていくためです。
現実的な利回り改善幅を見積もり、歳入予算(繰入金)に計上すると同時に、現在の基金ポートフォリオ(特に債券の「含み損」状況)を点検し、安全性を再確認します。
まとめ
金利上昇局面は、地方財政に対し、公債費や一時借入金利息の増加という「歳出圧力」と、基金運用益の増加という「歳入メリット」を同時にもたらします。しかし、多くの自治体、特に地方債残高が基金残高を大幅に上回る団体(特に実質公債費比率が高い団体)にとっては、歳出増のインパクトが歳入増のメリットを凌駕し、純粋な財政負担増となる可能性が高いのが実情です。
「金利のある世界」への回帰は、財政担当者にとって、これまでの財政運営の前提を見直す大きな転換点です。このマクロ環境の変化を「自分たちの予算」というミクロな視点に落とし込み、2026年度予算編成において具体的な数字でリスクを試算し、説明責任を果たしていくこと、そして、この変動期を「財政規律を再確認する機会」と捉え、EBPM(証拠に基づく政策立案)の観点から起債や基金の管理を高度化していくことが、今まさに求められています。




-320x180.jpg)

-320x180.jpg)