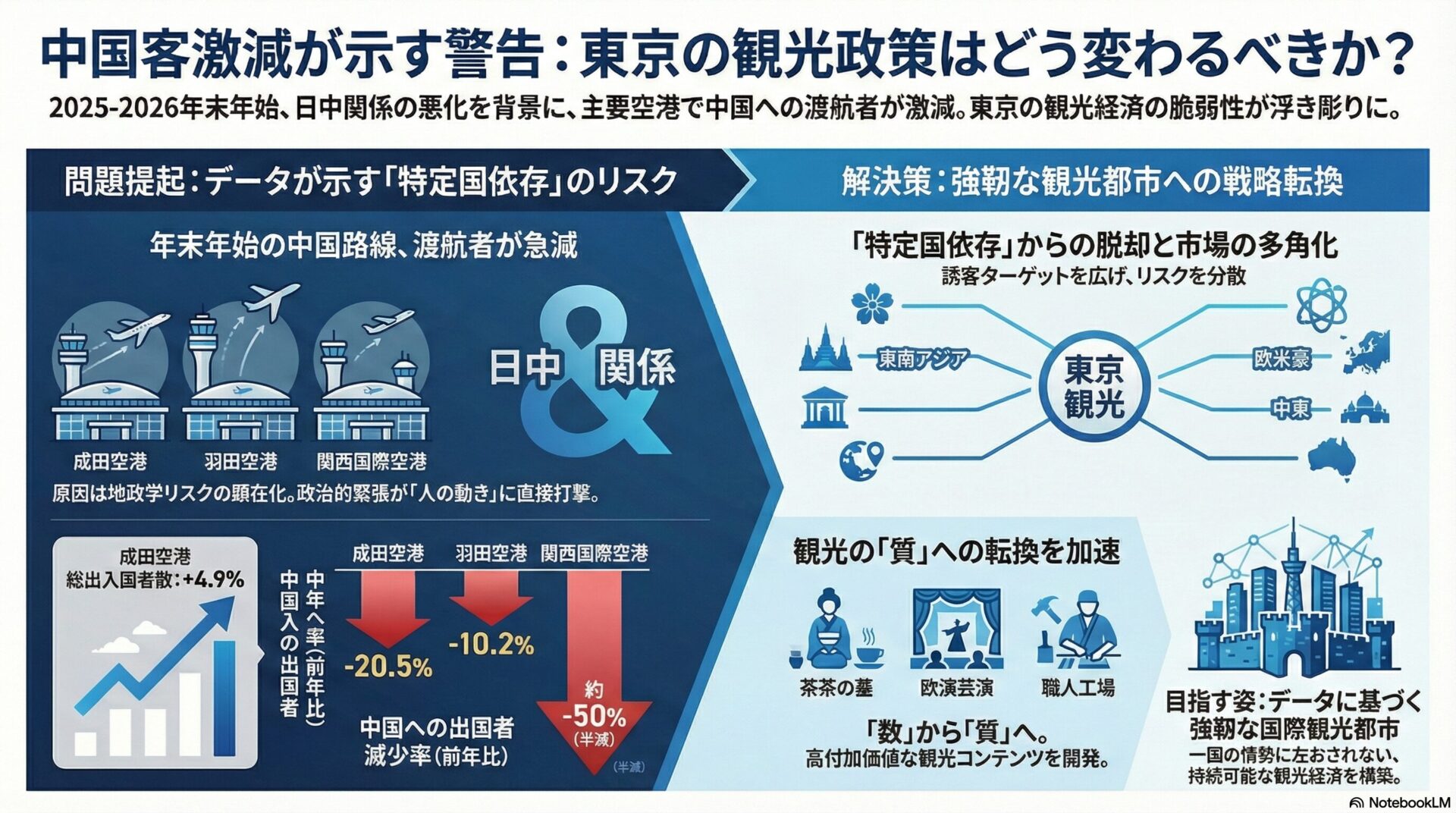受入環境整備

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
概要(観光振興を取り巻く環境)
- 自治体が受入環境の整備(観光振興)を行う意義は「観光がもたらす経済的便益の最大化」と「住民生活と調和した持続可能な観光モデルの構築」にあります。
- 新型コロナウイルス感染症の収束後、円安や旺盛な旅行需要を背景に、日本の観光、特に東京都特別区は空前の活況を呈しています。これは地域経済にとって大きな機会である一方、一部地域では「オーバーツーリズム」と呼ばれる、観光客の過度な集中が住民生活や環境に負の影響を及ぼす事態も顕在化しています。
- このような状況下で求められるのは、単に観光客の数を増やす「量的拡大」から、観光客一人ひとりの満足度と地域への経済効果を高め、同時に地域の文化や環境を保全する「質的向上」へと政策の軸足を移すことです。受入環境の整備とは、この質的転換を実現し、観光を短期的なブームで終わらせず、持続可能な成長の礎とするための戦略的取り組みを指します。
意義
住民にとっての意義
文化交流と地域への愛着醸成
- 多様な文化を持つ旅行者との交流は、住民にとって国際的な視野を広げる機会となります。
- また、地域の魅力が外部から評価されることで、住民自身が地域の文化や歴史に対する誇りと愛着を再認識するきっかけにもなります。
生活関連インフラの向上
- 観光振興によって得られた税収や利益は、交通機関の利便性向上、公園や文化施設の整備、景観の美化など、住民の日常生活の質を高める公共サービスに再投資されることが期待されます。
地域社会にとっての意義
地域経済の活性化
- 観光は、宿泊、飲食、小売、交通など裾野の広い産業であり、その振興は地域内での消費を喚起し、雇用を創出します。
- 増加した税収は、子育て支援や高齢者福祉など、地域社会全体の課題解決に向けた財源となります。
文化・自然資源の保全と継承
- 適切に管理された観光は、歴史的建造物や伝統芸能、豊かな自然環境などを維持・保全するための資金源となり得ます。
- 観光客の関心が高まることで、次世代への文化継承の機運も高まります。
行政にとっての意義
安定的な税収源の確保
- 観光産業の活性化は、法人住民税や固定資産税、特別区民税などの安定的な税収基盤を構築します。
- 人口減少社会において、交流人口の拡大による税収確保は、持続可能な行政運営にとって極めて重要です。
都市ブランドの向上
- 質の高い観光地としての評価は、東京都特別区の国際的な都市ブランドを向上させます。
- これにより、観光客だけでなく、国際的なビジネスやイベント、高度な専門性を持つ人材を惹きつける効果も期待できます。
(参考)歴史・経過
日本の観光政策は、その時々の社会経済情勢を反映し、その戦略的な位置づけを大きく変えてきました。当初は外貨獲得や国際親善といった補助的な役割でしたが、経済の成熟と人口構造の変化に伴い、今や国の成長戦略と地方創生の中核を担うに至っています。この変遷を理解することは、現在の課題を的確に捉える上で不可欠です。
1960年代:国際社会への復帰と外貨獲得の時代
- 1963年に「観光基本法」が制定されました。これは、1964年の東京オリンピック開催を控え、国際収支の改善と国際親善の促進を主な目的とするものでした。戦後復興を遂げた日本の姿を世界に示し、外貨を獲得するための手段として、インバウンド観光の基盤整備が始まりました。
- (出典)国土交通省「平成13年版 国土交通白書」平成13年度 1
- (出典)和洋女子大学 学術情報リポジトリ「観光キーワード」 2
- (出典)奈良県立大学「日本の国際観光政策の変遷と動向」令和2年度 3
1980年代:貿易摩擦緩和のためのアウトバウンド振興
- 日本の高度経済成長がもたらした巨額の貿易黒字は、欧米諸国との間に深刻な貿易摩擦を生み出しました。この解決策の一つとして、政府は日本人の海外旅行を促進する「海外旅行倍増計画(テン・ミリオン計画)」を打ち出しました。これは、海外旅行という「見えない輸入」を増やすことで、国際収支の黒字を緩和する狙いがありました。
- (出典)奈良県立大学「日本の国際観光政策の変遷と動向」令和2年度 3
1990年代~2000年代初頭:インバウンドへの再転換と戦略化の萌芽
- バブル経済崩壊後の長期的な経済停滞と産業の空洞化を受け、地域経済活性化の新たな担い手として、再びインバウンド観光に注目が集まりました。1996年の「ウェルカムプラン21」を経て、2003年には小泉政権下で「ビジット・ジャパン・キャンペーン」が開始され、「2010年までに訪日客1,000万人」という具体的な数値目標を掲げた、本格的な誘致戦略が始動しました。
- (出典)明治大学「外国人観光客の日本への誘致に関する研究」 4
- (出典)奈良県立大学「日本の国際観光政策の変遷と動向」令和2年度 3
2006年~現在:観光立国の本格始動と量的拡大の帰結
- 2006年に「観光立国推進基本法」が制定され、観光は明確に国家の基幹政策として位置づけられました。2008年には司令塔となる「観光庁」が設置され、ビザの大幅な緩和や免税制度の拡充など、国を挙げた誘致策が強力に推進されました。
- これにより訪日客数は飛躍的に増加しましたが、その成功は同時に、一部地域でのオーバーツーリズムという新たな課題を生み出しました。現在の「受入環境の整備」というテーマは、この成功した国家戦略がもたらした「産業的外部不経済」をいかに管理し、持続可能なモデルへと移行させるかという、新たな政策段階への移行を意味しています。
- (出典)和洋女子大学 学術情報リポジトリ「観光キーワード」 2
- (出典)奈良県立大学「日本の国際観光政策の変遷と動向」令和2年度 3
受入環境整備に関する現状データ
コロナ禍を経て再開した日本の観光市場は、特にインバウンド需要の急回復により、かつてない規模にまで拡大しています。各種データは、この活況がもたらす経済的恩恵の大きさと、それに伴う構造的変化や課題の深刻さを浮き彫りにしています。
訪日外国人旅行者数と消費額の爆発的増加
- 2024年の訪日外国人旅行者数は過去最高の3,687万人に達し、コロナ禍前の2019年比で15.6%増という驚異的な伸びを記録しました。
- (出典)観光庁「令和7年版 観光白書」令和7年度 5
- (出典)ツーリズムメディアサービス「2025年観光白書、世界の国際観光客数は14億4,500万人、コロナ前の水準に回復」令和7年度 6
- これに伴い、2024年のインバウンド消費額も過去最高の8兆1,257億円となり、2019年比で68.8%増と、旅行者数の伸びをはるかに上回るペースで拡大しています。
- (出典)観光庁「令和7年版 観光白書」令和7年度 5
- (出典)観光庁「訪日外国人消費動向調査 2024年 年次報告書」令和7年度 7
- 旅行者一人当たりの支出額も22.7万円(2024年)と高水準で推移しており、円安を背景とした旺盛な購買意欲や、滞在日数の長期化傾向がうかがえます。
- (出典)観光庁「訪日外国人消費動向調査 2024年 年次報告書」令和7年度 7
- (出典)(https://japan-guide.co.jp/blog/analyze_2024_inbound_consumer_trends_survey/)令和7年度 8
- (出典)国土交通省「令和7年版 観光白書」令和7年度 5
東京都への集中と経済効果
- 2024年に東京を訪れた外国人旅行者数は約2,479万人にのぼり、2019年比で63.3%増と、全国平均を大きく上回る伸びを示しています。これは、インバウンド需要が首都圏に極めて強く集中していることを示唆しています。
- この結果、都内全体の観光消費額(日本人旅行者を含む)は、2024年に過去最高の約9兆4,762億円を記録し、2019年比で56.9%増となりました。特別区の経済に与えるインパクトは計り知れません。
国内旅行市場の動向
- 日本人国内旅行消費額は2024年に約25.1兆円と、国内旅行消費額全体の7割以上を占め、依然として観光産業の根幹を支えています。特に地方部においては、延べ宿泊者数の約9割を日本人が占めており、その重要性は揺るぎません。
- (出典)観光庁「令和7年版 観光白書」令和7年度 5
- (出典)朝日新聞社「日本人国内旅行者数、伸び悩み 旅行しない70代も 2025年観光白書」令和7年度 10
- しかし、国内の延べ旅行者数や旅行経験率は長期的に伸び悩んでおり、特に70代以上の高齢層で旅行離れの傾向が見られます。旅行に行く層と行かない層の「二極化」が進行しており、国内市場は大きな構造的課題を抱えています。
- (出典)観光庁「令和7年版 観光白書」令和7年度 5
- (出典)朝日新聞社「日本人国内旅行者数、伸び悩み 旅行しない70代も 2025年観光白書」令和7年度 10
宿泊施設の稼働状況
- 2024年の全国の客室稼働率は**60.5%**でした。
- (出典)観光庁「宿泊旅行統計調査(令和6年12月・第2次速報、令和7年1月・第1次速報)」令和7年度 11
- これに対し、東京都の客室稼働率は76.3%(2024年)と際立って高く、コロナ禍前の水準に迫っています。これは、都内の宿泊施設への需要が極めて高いことを示しています。
- (出典)観光経済新聞「【観光庁統計】24年客室稼働率(速報値)、19年比2.1ポイント減の60.5%に」令和7年度 12
- 全国の延べ宿泊者数に占める外国人の割合は、2024年に過去最高の**25.0%**に達し、宿泊業界にとってインバウンドが不可欠な存在となっていることがデータから明らかです。
- (出典)観光経済新聞「24年の延べ宿泊者数、過去最高の6億5028万人泊」令和7年度 13
これらのデータを俯瞰すると、日本の観光市場が「二重構造化」している様子が浮かび上がります。一方には、円安を追い風に急成長し、東京などの大都市に集中する高単価のインバウンド市場が存在します。もう一方には、規模は大きいものの長期的に停滞し、価格感応度が高い国内旅行市場が存在します。この二つの異なる特性を持つ市場の存在は、今後の観光政策を立案する上で極めて重要な視点となります。東京の特別区は、この両方の市場と向き合う最前線であり、一方の市場に特化した施策だけでは、もう一方の市場のニーズを取りこぼしたり、あるいは新たな摩擦を生んだりする可能性があるため、両市場のバランスを考慮した、より複合的で高度な政策設計が求められます。
課題
インバウンド需要の急回復は、地域経済に大きな恩恵をもたらす一方で、その急激さゆえに様々な歪みを生じさせています。これらの課題は、住民の生活の質、地域社会の持続可能性、そして行政の対応能力という三つの側面から深刻な様相を呈しており、相互に複雑に絡み合っています。
住民の課題
オーバーツーリズムによる生活環境の悪化
- 観光客の急増は、公共交通機関の激しい混雑、交通渋滞、騒音などを引き起こし、区民の通勤・通学や日常生活に直接的な影響を及ぼしています。
- 客観的根拠:
- 観光地における住民・事業者等を対象とした調査では、日常生活エリアにおいて**60.5%**が観光客の増加による「悪い影響が出ている」と回答しています。
- (出典)じゃらんリサーチセンター「観光地のオーバーツーリズムおよび分散・平準化対策に関する現状調査報告レポート」令和6年度 14
- 浅草を訪れたインバウンド客への調査でも、約6割が「浅草は混雑している」と回答しており、その過密さが客観的にも認識されています。
- (出典)公益財団法人東京観光財団「オーバーツーリズムに関する調査・分析等業務委託報告書」令和5年度 15
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 住民のストレス増大による観光への反発感情が強まり、観光産業の社会的な基盤が揺らぎます。
- 客観的根拠:
マナー違反や文化摩擦の増加
- ゴミのポイ捨て、私有地への無断立ち入りによる写真撮影、深夜の騒音など、一部の観光客によるマナー違反が頻発し、住民との間に文化的な摩擦を生んでいます。
- 客観的根拠:
- 前述の調査で、混雑による悪影響の内容として「マナーが悪い(割り込み、路上飲酒、ポイ捨てなど)旅行者がいる」を挙げた回答者は**52.2%**にのぼり、最も深刻な問題の一つとして認識されています。
- (出典)訪日ラボ「オーバーツーリズム対策、8割が未実施。じゃらん調査で判明、必要な対策1位は「マナー啓発」」令和6年度 16
- 渋谷のスクランブル交差点周辺では迷惑行為が、浅草ではポイ捨てが問題となっており、具体的な場所での課題が顕在化しています。
- (出典)(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E7%82%B9) 17
- (出典)観光庁「インバウンド受入環境整備高度化事業 採択事業一覧」令和6年度
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 地域コミュニティと観光客との信頼関係が損なわれ、観光客を歓迎しない雰囲気が蔓延します。
- 客観的根拠:
生活コストの上昇
- インバウンド需要の増加により、地域の飲食店や小売店の価格が高騰し、これまで日常的に利用してきた住民が利用しにくくなる事態が発生しています。
- 客観的根拠:
- 同調査では、「旅行者の増加に合わせて物価や飲食店の価格が急激に上昇した」ことを問題点として挙げた回答者が**49.2%**に達しています。
- (出典)訪日ラボ「オーバーツーリズム対策、8割が未実施。じゃらん調査で判明、必要な対策1位は「マナー啓発」」令和6年度 16
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 住民向けの店舗が観光客向けの店舗に置き換わり、地域の生活基盤そのものが変容・喪失する恐れがあります。
- 客観的根拠:
地域社会の課題
観光産業における深刻な人手不足
- 宿泊業や飲食サービス業を中心に、産業の急回復に人材供給が全く追いついていません。コロナ禍で離職した人材の多くが、低賃金・長時間労働といった構造的な問題を理由に業界へ戻っておらず、人手不足がサービスの質低下や事業拡大の足枷となっています。
- 客観的根拠:
- 京都市の調査では、回答した観光事業者の7割が人手不足を実感していると回答しています。
- (出典)京都市観光協会「観光業界における人手不足についてのアンケート調査結果」令和5年度 18
- 宿泊・飲食サービス業の年間休日数は平均105.6日と、全産業平均の114.7日を大幅に下回っています。
- (出典)株式会社日本総合研究所「観光業の人手不足の現状と課題」令和4年度 19
- 非正規雇用の割合も宿泊業で5割超、飲食サービス業では8割弱と非常に高く、雇用の不安定さが人材定着を妨げています。
- (出典)株式会社日本総合研究所「観光業の人手不足の現状と課題」令和4年度 19
- (出典)日本銀行「ポストコロナのインバウンド回復に向けた宿泊業の課題と取り組み」令和5年度 20
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- サービス品質の低下が日本の観光ブランドを毀損し、国際競争力の低下を招きます。
- 客観的根拠:
公共インフラへの過剰な負荷
- 現在の観光客数は、交通機関、道路、上下水道、ごみ処理施設、公衆トイレといった公共インフラが想定していた利用者数をはるかに超えており、インフラの機能不全や劣化を招いています。
- 客観的根拠:
- 観光地の事業者等への調査で、実施が難しいオーバーツーリズム対策として「公共交通の輸送力増強」を挙げた回答が**17.9%**と最も多く、インフラの限界が強く認識されています。
- (出典)じゃらんリサーチセンター「観光地のオーバーツーリズムおよび分散・平準化対策に関する現状調査報告レポート」令和6年度 14
- 渋谷駅周辺では、1日の乗降客数約300万人に対しコインロッカーが約1,400個しかないなど、具体的なインフラのボトルネックが存在します。
- (出典)訪日ラボ「渋谷のインバウンド消費が伸びない3つの理由と、課題解決に向けた3つの対策」令和元年度 21
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- インフラの老朽化が加速し、将来的に莫大な更新費用が必要になるとともに、住民・観光客双方の利便性が著しく低下します。
- 客観的根拠:
文化・自然資源の毀損リスク
- 過度な観光客の集中は、歴史的建造物や自然景観に物理的な負荷をかけ、摩耗や劣化を早めます。また、一部の観光客による不適切な行為が、取り返しのつかない損害を与えるリスクも高まっています。
- 客観的根拠:
- 政府のオーバーツーリズム対策パッケージでは、地域資源の保全が重要な柱の一つとして掲げられており、この問題が国レベルで認識されていることを示しています。
- (出典)観光庁「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」 22
- (出典)ロスゼロ「オーバーツーリズムとは?原因や問題点、国内外の取り組み事例を解説」 23
- (出典)環境省「エコジン「観光地を大切にする快適な旅をしよう!」」令和6年度 24
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 観光の魅力の源泉である地域固有の資源が失われ、観光地としての価値そのものが長期的に低下します。
- 客観的根拠:
行政の課題
多様なステークホルダー間の合意形成の困難さ
- 「静かな生活環境」を望む住民、「経済的利益」を追求する事業者、「特別な体験」を求める観光客。これらの三者の利害は時に相反し、行政はそれらの複雑な調整と合意形成という難しい舵取りを迫られています。
- 客観的根拠:
- DMO(観光地域づくり法人)の重要な役割として「関係者の合意形成」が挙げられており、これが観光地経営の成否を分ける鍵であると同時に、最も困難な課題であることが示唆されています。
- (出典)(https://machiage.microad.jp/blog/dmo_tourismassociation) 25
- (出典)函館市「函館市DMO形成準備事業報告書」令和元年度 26
- (出典)(https://unwto-ap.org/wp-content/uploads/2021/11/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E5%85%88%E9%80%B2%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E9%9B%86.pdf)令和3年度 27
- (出典)復興庁「復興まちづくりにおける合意形成事例」 28
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 有効な対策を打ち出せないまま問題が深刻化し、行政への信頼が失われます。
- 客観的根拠:
持続可能な観光を推進する専門人材の不足
- データ分析に基づく戦略策定(EBPM)、デジタルマーケティング、サステナビリティに関する国際基準の理解、地域住民との協働を円滑に進めるファシリテーション能力など、現代の観光政策に必要な専門知識を持つ人材が、行政・民間ともに不足しています。
- 客観的根拠:
- 全国の自治体を対象とした調査では、観光事業推進における課題として「人材不足」を挙げた自治体が455件と最も多く、深刻な状況がうかがえます。
- (出典)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000055357.html)令和6年度 29
- 先進的なDMOでは、外部からCMO(最高マーケティング責任者)等の専門人材を登用する例が見られ、内部人材だけでは対応が困難であることを示しています。
- (出典)大阪公立大学学術情報リポジトリ「金沢市の観光振興とDMOの役割」令和5年度 30
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 旧来の経験と勘に頼った政策決定から脱却できず、複雑化した課題に効果的に対応できません。
- 客観的根拠:
安定的財源の確保とEBPMの導入遅れ
- 観光振興やオーバーツーリズム対策には継続的な投資が必要ですが、その財源は一般会計に依存することが多く、安定性に欠けます。宿泊税などの導入議論はありますが、安定財源の確保は多くの自治体にとって課題です。また、客観的データに基づく政策立案(EBPM)の導入も道半ばであり、施策の効果検証が不十分なまま前例踏襲に陥りがちです。
- 客観的根拠:
- 前述の自治体調査では、「予算不足」が「人材不足」に次いで2番目に多い課題として挙げられています。
- (出典)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000055357.html)令和6年度令和6年度) 29
- 宿泊税などの法定外税は、観光施策の財源として有効な選択肢ですが、その導入には慎重な検討と合意形成が必要です。
- (出典)(https://www.jri.co.jp/file/report/jrireview/pdf/11745.pdf)平成23年度 31
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 場当たり的で持続可能性のない施策に終始し、税金の効果的な活用ができず、住民の理解も得られません。
- 客観的根拠:
これらの課題が複合的に絡み合うことで、現代の都市観光が直面する本質的な問題、すなわち「ガバナンス・ギャップ」が露呈しています。今日の観光は、その規模、スピード、複雑性において、従来の縦割り型行政組織が対応できる範囲を大きく超えています。交通、環境、商業、住民サービスといった複数の部局にまたがる問題を、リアルタイムで横断的に管理・調整するための仕組みが追いついていないのです。したがって、これから提案する支援策は、個別の問題に対する対症療法ではなく、このガバナンス・ギャップを埋め、21世紀型の観光に対応できる新たな行政システムを構築するための構造改革と位置づけるべきです。
行政の支援策と優先度の検討
優先順位の考え方
- 各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
- 即効性・波及効果
- 施策の実施から効果発現までの期間が短く、複数の課題解決や多くの住民への便益につながる施策を高く評価します。
- 実現可能性
- 現在の法制度、予算、人員体制の中で実現可能な施策を優先します。
- 費用対効果
- 投入する経営資源(予算・人員・時間等)に対して得られる効果が大きい施策を優先します。
- 公平性・持続可能性
- 特定の地域・年齢層だけでなく、幅広い住民に便益が及ぶ施策を優先します。
- 客観的根拠の有無
- 政府資料や学術研究等のエビデンスに基づく効果が実証されている施策を優先します。
支援策の全体像と優先順位
- 観光客の受入環境整備は、「①需要の管理と分散」「②体験価値と持続可能性の向上」「③産業基盤の強化」という3つの柱で体系的に進める必要があります。これらは相互に補完し合う関係にあります。
- 最優先で取り組むべきは「支援策①:DXを活用したオーバーツーリズム対策と観光客の戦略的分散」です。これは、現在の最も喫緊の課題である混雑と住民生活への影響に直接対処するものであり、他の施策の効果を高めるための基盤となります。
- 次に、「支援策②:「持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)」の推進による地域価値向上」を推進します。これは、観光の質を高め、住民の理解と協力を得ることで、観光振興を長期的に持続可能なものにするための中核的な理念です。
- 最後に、これらの施策を支える土台として「支援策③:観光産業の労働環境改善と高付付加価値化支援」が不可欠です。産業の担い手がいなければ、いかなる施策も実行できません。
各支援策の詳細
支援策①:DXを活用したオーバーツーリズム対策と観光客の戦略的分散
目的
- デジタル技術を用いて混雑を可視化・予測し、観光客を特定の時間・場所に集中させず、区内全域へ戦略的に誘導することで、オーバーツーリズムを緩和します。
- 観光客の利便性と満足度を向上させながら、住民の生活環境への負荷を軽減することを目指します。
主な取組①:リアルタイム混雑状況の可視化と情報発信
- 主要な観光スポット、駅、バス停等に人流センサーやカメラを設置し、AI解析を通じて混雑状況をリアルタイムで把握します。
- 公式観光サイトやデジタルサイネージ、観光アプリ等で、混雑状況を「空いている」「やや混雑」「混雑」といった分かりやすい形で多言語で発信します。
- 客観的根拠:
- 京都市では、ライブカメラ映像や観光快適度の予測を発信し、観光客の自主的な分散を促しています。浅草でも、IoTセンサーを活用した混雑状況のリアルタイム発信が実施されています。
- (出典)京都市「令和5年度 京都市観光振興計画2025( nana )年次計画」令和5年度 32
- (出典)(https://ai-government-portal.com/%E8%A6%B3%E5%85%89%E6%94%BF%E7%AD%96/) 33
- 客観的根拠:
主な取組②:AIを活用したパーソナライズ・レコメンデーション
- 観光客の属性(国籍、興味、時間帯など)に基づき、AIが比較的空いている観光スポットや移動ルート、飲食店などを提案する機能を観光アプリ等に実装します。
- 「あなたのための静かな東京散歩」「今すぐ入れる人気ラーメン店」など、個人のニーズに合わせた情報提供により、満足度を高めつつ分散を図ります。
- 客観的根拠:
- 観光庁の観光DX推進事業では、生成AIを活用した旅行プラン提案などがモデル事業として採択されており、その有効性が期待されています。
- (出典)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/kobo12_00022.html)令和7年度令和7年度) 34
- (出典)(https://www.travelvoice.jp/20250521-157720)令和7年度令和7年度) 35
- (出典)(https://www.kankokeizai.com/2505261000jta/)令和7年度令和7年度) 36
- 客観的根拠:
主な取組③:時間帯・曜日別インセンティブの導入
- オフピーク(早朝、夜間、平日)に利用できる電子クーポンや、特定のエリアの店舗で使える特典を提供し、時間と場所の分散を経済的に誘導します。
- キャッシュレス決済データと連携し、混雑時間帯を避けて来店した観光客にポイントを付与するなどの仕組みを検討します。
- 客観的根拠:
- 早朝・夜間観光プログラムを導入した地域では、観光客の平均滞在時間が2.7時間延長し、宿泊率が23.5%向上したというデータがあります。
- (出典)(https://ai-government-portal.com/%E8%A6%B3%E5%85%89%E6%94%BF%E7%AD%96/) 33
- 客観的根拠:
主な取組④:事前予約・決済システムの導入支援
- 特に混雑が激しい文化施設、展望台、人気飲食店等に対し、オンラインでの事前日時指定予約・決済システムの導入費用を補助します。
- これにより、事業者は来場者数を平準化でき、観光客は待ち時間なくスムーズに入場できるため、双方にメリットがあります。
- 客観的根拠:
- 海外の事例では、事前予約制の導入が混雑緩和に有効な手段として広く採用されています。
- (出典)(https://www.jri.co.jp/file/report/jrireview/pdf/10798.pdf)平成24年度 37
- (出典)観光庁「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ」令和5年度 38
- 客観的根拠:
主な取組⑤:観光MaaS(Mobility as a Service)の構築
- 公共交通、シェアサイクル、タクシー、水上バスなど、区内の多様な交通手段を単一のアプリで検索・予約・決済できる仕組みを構築します。
- 混雑状況に応じて最適な交通手段を提案したり、分散化に貢献するルートに割引を適用したりすることで、スムーズな周遊を促進します。
- 客観的根拠:
- 浜松市の「浜松版MaaS」では、AI活用型オンデマンドバス等により交通空白地域を約40%削減し、利便性向上に成功しています。
- (出典)観光庁「令和7年版 観光白書」令和7年度 5
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 主要観光スポットにおけるピーク時混雑度 20% 緩和
- データ取得方法: 人流センサーデータによる滞留人数の定点観測
- 観光に対する区民のネガティブ評価率 15% 低下
- データ取得方法: 定期的な住民意識調査
- (出典)調布市「令和4年度 市民意識調査報告書」令和4年度 39
- (出典)公益財団法人東京観光財団「地域のサステナブル・ツーリズム推進事業 調査報告書」令和4年度 40
- (出典)墨田区「令和6年度 第1回区政に関する世論調査報告書」令和6年度 41
- 主要観光スポットにおけるピーク時混雑度 20% 緩和
- KSI(成功要因指標)
- 公式観光アプリにおける混雑情報・レコメンド機能の利用率 50%
- データ取得方法: アプリのログデータ解析
- 事前予約システム導入施設数 50施設
- データ取得方法: 補助金交付実績の集計
- 公式観光アプリにおける混雑情報・レコメンド機能の利用率 50%
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- オフピーク時間帯(早朝・夜間)の観光客訪問割合 10% 向上
- データ取得方法: 通信キャリア等の位置情報ビッグデータ分析
- 観光客の区内周遊エリア数(訪問区画数) 平均1.5倍 に増加
- データ取得方法: 同上
- オフピーク時間帯(早朝・夜間)の観光客訪問割合 10% 向上
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- リアルタイム混雑情報提供地点数 100箇所
- データ取得方法: センサー設置場所リスト
- 観光MaaSのダウンロード数 10万件
- データ取得方法: アプリストアの管理画面データ
- リアルタイム混雑情報提供地点数 100箇所
支援策②:「持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)」の推進による地域価値向上
目的
- 環境・文化・社会・経済の4つの側面で持続可能性を追求する観光のあり方を区の基本方針とし、地域全体のブランド価値を高めます。
- 観光客には「責任ある旅行者」としての行動を促し、住民には観光の恩恵を実感してもらうことで、観光への理解と協力を醸成します。
主な取組①:国際基準に準拠した地域版ガイドラインの策定
- GSTC(世界持続可能観光協議会)基準や観光庁の「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」を参考に、各区の特性に応じた独自のガイドラインを策定します。
- ガイドラインには、ごみの削減、地域文化の尊重、地元産品の活用、従業員の公正な処遇など、事業者が取り組むべき具体的な項目を盛り込みます。
- 客観的根拠:
- 観光庁はJSTS-Dの活用を推進しており、ロゴマークを取得した地域は持続可能な観光地として国内外にアピールできます。
- (出典)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/dmo/dmotoha.html)令和4年度令和4年度) 42
- 客観的根拠:
主な取組②:「サステナブルツーリズム認証制度」の創設と支援
- 区のガイドラインに基づき、優れた取り組みを行う宿泊施設、飲食店、体験プログラム等を認証する制度を創設します。
- 認証取得にかかるコンサルティング費用や設備投資(省エネ設備、食品ロス削減機器等)の一部を補助します。
- 認証取得事業者を公式観光サイト等で優先的に紹介し、マーケティングを支援します。
- 客観的根拠:
- Travelifeなどの国際認証は、欧米の旅行会社が提携先を選ぶ際の基準となっており、認証取得はビジネス機会の拡大に直結します。
- (出典)(https://regenetabi.jp/sustainable-tourism/17139/) 43
- (出典)やまとごころ.jp「サステナブルツーリズムの国際認証とは? 世界の旅行者を呼び込むために今、取り組むべきこと」 44
- 客観的根拠:
主な取組③:「京都観光モラル」に倣ったマナー啓発キャンペーン
- 「静かに拝観する」「無断で写真を撮らない」「ポイ捨てしない」など、観光客に守ってもらいたい具体的な行動規範を「東京観光マナー」として策定します。
- ピクトグラムや短い動画を活用し、空港、駅、宿泊施設、観光スポットなど、旅行者のあらゆる接点で多言語で発信します。
- 客観的根拠:
- 京都市では「京都観光モラル」を策定し、事業者や観光客への普及啓発に力を入れており、市民生活との調和を目指す上での中核的な取り組みとなっています。
- (出典)京都市「令和5年度 京都市観光振興計画2025( nana )年次計画」令和5年度 32
- 客観的根拠:
主な取組④:観光収益の地域還元メカニズムの構築
- 宿泊税などの独自財源の一部を、観光地の環境美化、文化財の維持修復、地域コミュニティ活動の支援など、使途を明確にした上で還元する仕組みを構築します。
- 住民が「観光客が増えることで自分たちの地域が良くなる」と実感できる「見える化」が重要です。
- 客観的根拠:
- 持続可能な観光の基本理念には、観光による利益をホストコミュニティに公平に分配することが含まれており、住民の支持を得るために不可欠な要素です。
- (出典)ロスゼロ「オーバーツーリズムとは?原因や問題点、国内外の取り組み事例を解説」 23
- (出典)(https://unwto-ap.org/wp-content/uploads/2021/11/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E5%85%88%E9%80%B2%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E9%9B%86.pdf)令和3年度 27
- 客観的根拠:
主な取組⑤:リジェネラティブ・ツーリズム(再生型観光)の推進
- 観光客が単に消費するだけでなく、地域の環境保全や文化継承に貢献できる体験プログラムを造成します。
- 例:神社の清掃活動への参加、伝統工芸品の修復体験、地域の植樹活動など。
- 客観的根拠:
- 鎌倉市などで、竹林整備や文化財修復に観光客が参加するリジェネラティブ・ツーリズムの取り組みが検討されており、新しい観光の形として注目されています。
- (出典)NIHO「リジェネラティブツーリズムとは?観光による地域再生の可能性」 45
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 「観光は地域の魅力向上に貢献している」と回答する区民の割合 70% 以上
- データ取得方法: 定期的な住民意識調査
- (出典)調布市「令和4年度 市民意識調査報告書」令和4年度 39
- (出典)公益財団法人東京観光財団「地域のサステナブル・ツーリズム推進事業 調査報告書」令和4年度 40
- (出典)墨田区「令和6年度 第1回区政に関する世論調査報告書」令和6年度 41
- 一人当たり観光消費額 10% 向上
- データ取得方法: 観光客実態調査における消費額データ
- (出典)ツーリズムメディアサービス「2024年の訪都外国人旅行者、過去最高の2,479万人、前年比26.9%増」令和7年度 9
- (出典)台東区「令和5年台東区観光統計・マーケティング調査報告書」令和6年度 46
- 「観光は地域の魅力向上に貢献している」と回答する区民の割合 70% 以上
- KSI(成功要因指標)
- 区独自のサステナブルツーリズム認証取得事業者数 100者
- データ取得方法: 認証制度の登録・管理データ
- 観光客のマナーに対する住民の満足度 20ポイント 改善
- データ取得方法: 住民意識調査における設問
- 区独自のサステナブルツーリズム認証取得事業者数 100者
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 認証取得事業者の公式観光サイト経由での予約・売上 30% 増加
- データ取得方法: 公式サイトのアクセス解析と事業者へのヒアリング調査
- リジェネラティブ・ツーリズム体験プログラム参加者数 年間5,000人
- データ取得方法: プログラム提供事業者からの実績報告
- 認証取得事業者の公式観光サイト経由での予約・売上 30% 増加
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- マナー啓発コンテンツ(動画・ポスター等)の掲出箇所数 500箇所
- データ取得方法: 設置・掲出場所リスト
- 事業者向けガイドライン説明会の開催回数 年間10回
- データ取得方法: イベント実施報告
- マナー啓発コンテンツ(動画・ポスター等)の掲出箇所数 500箇所
支援策③:観光産業の労働環境改善と高付加価値化支援
目的
- 観光産業の持続可能性を脅かす最大の要因である人手不足を解消するため、DXによる生産性向上と労働条件の改善を支援します。
- 「安売り」からの脱却を促し、質の高いサービスに見合った価格設定ができる高付加価値な産業構造への転換を支援します。
主な取組①:宿泊・飲食業向け生産性向上DX導入補助金
- 自動チェックイン機、配膳ロボット、清掃ロボット、AIによる需要予測・価格設定ツール、多言語対応オーダーシステムなど、省人化と業務効率化に資するデジタルツールの導入費用を重点的に補助します。
- 客観的根拠:
- 観光庁は「観光DX推進事業」を通じて、レベニューマネジメント等のデジタルツール導入を支援しており、生産性向上の鍵と位置づけています。
- (出典)(https://kanko-dx-hojo.go.jp/wp-content/uploads/2025/05/20250523_faq_1-2.pdf)令和7年度令和7年度) 47
- (出典)(https://www.travelvoice.jp/20250630-157964)令和7年度 48
- 客観的根拠:
主な取組②:「働きがい改革」推進事業者へのインセンティブ付与
- 法定を上回る休日数の設定、柔軟なシフト制度の導入、従業員向け研修の充実、給与水準の向上など、魅力的な職場づくりに取り組む事業者を認証し、補助金の優先採択や融資制度での優遇措置を講じます。
- 客観的根拠:
- 観光業の人手不足の根本原因は、全産業平均より劣る労働条件にあります。休日数の少なさ(全産業平均より9日少ない)や賃金の低さを改善することが、人材確保の前提となります。
- (出典)株式会社日本総合研究所「観光業の人手不足の現状と課題」令和4年度 19
- (出典)jinzaiplus「観光・宿泊業の人手不足はなぜ起こる?原因と有効な対策を解説」 49
- 客観的根拠:
主な取組③:高付加価値な体験コンテンツ造成支援
- 地域の文化施設、伝統工芸職人、アーティスト等と観光事業者が連携して開発する、ユニークで質の高い体験プログラムの造成費用(企画費、専門家謝礼、マーケティング費等)を支援します。
- 例:美術館の閉館後貸切ツアー、著名シェフによる料理教室、職人から直接学ぶ伝統工芸体験など。
- 客観的根拠:
- 観光庁の「プレミアムインバウンドツアー造成支援事業」は、高単価な特別体験が富裕層の消費拡大に繋がることを期待するものです。
- (出典)環境省「令和7年度 国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業等の要求・要望額」令和6年度 50
- (出典)潮見行政書士事務所「【2025年最新】観光庁のインバウンド向け補助金3選!概要や目的を解説」令和7年度 51
- 客観的根拠:
主な取組④:多能工化・スキルアップ研修の実施支援
- 一人の従業員がフロント、レストラン、コンシェルジュなど複数の業務をこなせる「多能工化」を促進するための研修費用を補助します。
- これにより、事業者は繁閑に応じた柔軟な人員配置が可能となり、従業員はスキルアップによるキャリア形成が図れます。
- 客観的根拠:
- 人手不足対策として、従業員のマルチタスク化は労働生産性を高める有効な手段とされています。
- (出典)株式会社日本総合研究所「観光業の人手不足の現状と課題」令和4年度 19
- 客観的根拠:
主な取組⑤:地域一体での人材確保・育成プラットフォーム構築
- 区内の観光事業者と教育機関(専門学校、大学)が連携し、インターンシップのマッチングや共同での採用説明会、地域共通の研修プログラムなどを実施するプラットフォームを構築・運営します。
- 客観的根拠:
- 地域一体での採用活動や人材育成は、個々の事業者が単独で行うよりも効率的であり、地域の魅力を総合的にアピールできます。
- (出典)株式会社日本総合研究所「観光業の人手不足の現状と課題」令和4年度 19
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 観光産業(宿泊・飲食)の離職率を 全産業平均レベルまで低減
- データ取得方法: 厚生労働省「雇用動向調査」及び事業者へのヒアリング調査
- 宿泊施設の客室単価(ADR) 20% 向上
- データ取得方法: 宿泊旅行統計調査および業界データ
- 観光産業(宿泊・飲食)の離職率を 全産業平均レベルまで低減
- KSI(成功要因指標)
- 生産性向上DXを導入した事業者における従業員一人当たり売上高 15% 向上
- データ取得方法: 補助金交付事業者の実績報告データ
- 「働きがい改革」認証取得事業者数 50者
- データ取得方法: 認証制度の登録・管理データ
- 生産性向上DXを導入した事業者における従業員一人当たり売上高 15% 向上
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 観光産業の有効求人倍率の 適正化(過度な上昇の抑制)
- データ取得方法: 公共職業安定所の統計データ
- 高付加価値体験プログラムの平均販売単価 5万円以上
- データ取得方法: 補助金交付事業者の販売実績データ
- 観光産業の有効求人倍率の 適正化(過度な上昇の抑制)
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 生産性向上DX導入補助金の交付件数 年間100件
- データ取得方法: 補助金交付実績の集計
- スキルアップ研修の受講者数 年間1,000人
- データ取得方法: 研修実施事業者からの実績報告
- 生産性向上DX導入補助金の交付件数 年間100件
先進事例
東京都特別区の先進事例
中央区「地域資源と商業機能が連携した高付加価値型まちづくり」
- 中央区は、日本橋の老舗や伝統文化、銀座の高級商業施設やアートギャラリーといった、歴史と現代が融合する多様な資源を有しています。これらの資源を個々にアピールするだけでなく、相互に連携させた高付加価値な観光体験の創出に官民連携で取り組んでいます。
- 特に、一般社団法人中央区観光協会がDMOとして中心的な役割を担い、地域の事業者を巻き込んだ「中央区推奨土産品~Central Tokyo Premium Selection~」の選定・PRや、自主財源確保を目的としたECサイト「東京まんなか ippin堂」でのオリジナル商品・ツアー販売など、戦略的な事業を展開しています。これにより、地域の魅力を統一感をもって発信し、参加事業者の収益向上にも直接的に貢献しています。
- 客観的根拠:
- 中央区観光協会は、観光情報センターの運営やガイド育成に加え、ECサイトの活用やオリジナルグッズ開発など、自主財源の確保と地域の魅力発信を両立させる事業を積極的に推進しています。
- (出典)公益財団法人東京観光財団「令和3年度 地域における観光まちづくり支援事業 取組事例集」令和4年度 52
- (出典)一般社団法人中央区観光協会「令和5年度 事業計画書」令和5年度 53
- 客観的根拠:
台東区(浅草)「住民・事業者・行政一体の観光ガバナンスと文化体験の深化」
- 国内有数の観光地である浅草は、オーバーツーリズムという深刻な課題に直面しています。これに対し、台東区は「浅草文化観光振興協議会」を核として、地域住民、事業者、行政が一体となった観光ガバナンス体制を構築し、課題解決に取り組んでいます。
- IoTセンサーを活用して混雑状況をリアルタイムで可視化・発信するなどDXを導入する一方で、江戸文化の象徴である「歌舞伎」をテーマにした専門ガイド付きのまち歩きツアーを造成するなど、文化的な深掘りによる「量から質へ」の転換を具体的に進めています。これにより、単なる混雑緩和だけでなく、観光客の満足度向上と消費単価の上昇を目指しています。
- 客観的根拠:
- 「浅草・歌舞伎まち歩きガイド認定制度」を創設し、専門知識を持つ質の高いガイドを育成することで、浅草の歴史や文化を深く伝えるストーリー性のある観光商品を開発し、他との差別化に成功しています。
- (出典)公益財団法人東京観光財団「平成30年度 地域における観光まちづくり支援事業 取組事例集」平成30年度 54
- 客観的根拠:
渋谷区「世界的な知名度を活かしたインバウンド課題への直接的対応」
- 世界的に有名なスクランブル交差点を擁する渋谷区は、急増するインバウンド観光客が直面する具体的な課題に、民間と連携しながら迅速に対応しています。例えば、常に課題となる手荷物問題に対しては、コインロッカーの絶対数不足を補うため、荷物預かりシェアリングサービス「ecbo cloak」と連携し、店舗の空きスペースを活用する仕組みを導入しました。
- また、「来訪者数に比して消費額が低い」という経営課題を特定し、その解決のために継続的なマーケティング調査を実施。データに基づき、滞在時間や消費額の向上を目的とした施策立案を進めています。
- 客観的根拠:
- 令和5年度の調査では、訪日外国人の渋谷での平均消費額は7.1万円と、令和元年度の3.3万円から倍増。宿泊率も**15%から30%**へと大幅に向上しており、単なる通過点から滞在・消費の拠点へと変貌しつつあることがデータで示されています。
- (出典)訪日ラボ「渋谷のインバウンド消費が伸びない3つの理由と、課題解決に向けた3つの対策」令和元年度 1
- (出典)公益財団法人東京観光財団「渋谷エリアにおけるマーケティング実態調査」令和5年度
- 客観的根拠:
全国自治体の先進事例
京都市「市民生活と調和した『京都モデル』の構築」
- 京都市は、日本で最も早くからオーバーツーリズム問題に直面し、その対策の先進地として知られています。「量より質へ」という明確な方針のもと、「市民生活との調和」を最優先課題に掲げた包括的な施策パッケージ「京都モデル」を推進しています。
- 具体的には、①観光客と市民の生活動線の分離(例:観光特急バスの導入)、②時間・場所の分散化(例:朝観光・夜観光の推進、非公開文化財の特別公開)、③マナー啓発(例:「京都観光モラル」の策定と普及)など、多角的なアプローチを体系的に実行しています。これらの取り組みは、持続可能な観光地経営のモデルとして国内外から注目されています。
- 客観的根拠:
- 京都市は観光庁の「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」に採択されており、観光案内所のDX化やライブカメラによる混雑状況の発信など、デジタル技術を駆使した情報提供を強化し、科学的根拠に基づいた対策を進めています。
- (出典)regenetabi.jp「京都市のサステナブルツーリズム|具体的な取り組み事例を解説」
- (出典)京都市「令和5年度 京都市観光振興計画2025( nana )年次計画」令和5年度 2
- (出典)観光庁「「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」の一次公募における採択事業の決定について」令和7年度 3
- 客観的根拠:
金沢市「歴史的景観の保全と創造的活用による持続可能な観光まちづくり」
- 金沢市は、北陸新幹線開業による観光客の急増という機会を捉えつつ、「保存と開発の調和」を基本理念とした持続可能な観光まちづくりを実践しています。国の重要伝統的建造物群保存地区が全国最多の4地区ある一方で、金沢21世紀美術館のような現代的な文化施設を戦略的に配置することで、歴史と現代が融合した独自の都市魅力を創出しています。
- 特筆すべきは、市民生活との調和を計画段階から重視している点です。「金沢市持続可能な観光振興推進計画」を策定し、定期的な住民意識調査の結果を政策に反映させる仕組みを構築。また、金沢市観光協会を強力なDMOとして位置づけ、市のOBを事務局に配置するなど、行政と民間が緊密に連携した推進体制を築いています。
- 客観的根拠:
- 金沢市は「金沢市持続可能な観光振興推進計画2021」を策定し、市民生活との調和を明確な目標として掲げています。この計画は、観光客数だけでなく、市民の満足度も重要な指標としています。
- (出典)金沢市「金沢市持続可能な観光振興推進計画2021」令和3年度 4
- (出典)大阪公立大学学術情報リポジトリ「金沢市の観光振興とDMOの役割」令和5年度 5
- 客観的根拠:
参考資料[エビデンス検索用]
- 観光庁
- (出典)観光庁「令和7年版 観光白書」令和7年度 6
- (出典)観光庁「訪日外国人消費動向調査(2024年年次報告書)」令和7年3月 7
- (出典)観光庁「宿泊旅行統計調査」令和6年度
- (出典)観光庁「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ」関連資料 令和5年 8
- (出典)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/dmo/dmotoha.html)令和4年度令和4年度) 9
- (出典)(https://www.google.com/search?q=https://kanko-dx.go.jp/)%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B3%87%E6%96%99 8
- 東京都
- (出典)ツーリズムメディアサービス「2024年の訪都外国人旅行者、過去最高の2,479万人、前年比26.9%増」令和7年度 10
- (出典)港区「第4次港区観光振興ビジョン策定にかかる観光動態基礎調査報告書」令和5年度
- (出典)台東区「令和5年台東区観光統計・マーケティング調査報告書」令和6年度 11
- (出典)公益財団法人東京観光財団「渋谷エリアにおけるマーケティング実態調査」令和5年度
- (出典)公益財団法人東京観光財団「地域における観光まちづくり支援事業 取組事例集」
- その他調査機関
- (出典)株式会社日本総合研究所「観光業の人手不足の現状と課題」令和4年12月 12
- (出典)じゃらんリサーチセンター「観光地のオーバーツーリズムおよび分散・平準化対策に関する現状調査報告レポート」令和6年度 13
- (出典)京都市観光協会「事業報告書」 14
- (出典)大阪公立大学学術情報リポジトリ「金沢市の観光振興とDMOの役割」令和5年度 5
まとめ
東京都特別区における観光振興は、歴史的な活況を迎える一方で、オーバーツーリズムや人手不足といった深刻な課題に直面しており、もはや単なる量的拡大を目指す段階にはありません。今後は、DXを活用して観光需要を賢く管理・分散させるとともに、国際基準の持続可能な観光を推進し、地域全体の価値を高める質的転換が不可欠です。同時に、産業の担い手である人材の労働環境を抜本的に改善し、高付加価値なサービスを創出する産業基盤の強化が、全ての施策の成功の鍵を握ります。
本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。




-320x180.jpg)

-320x180.jpg)