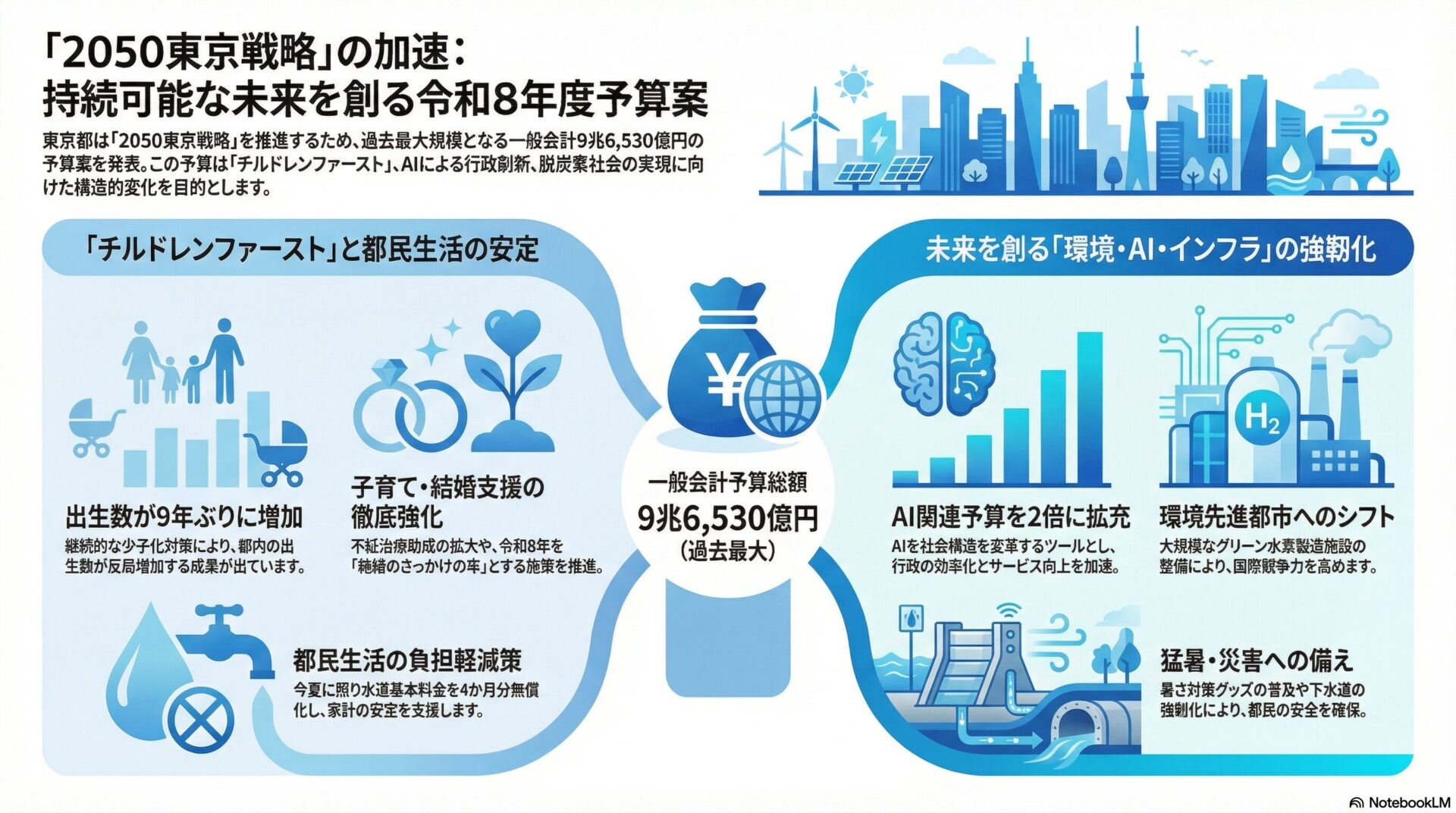利用料金制度

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
概要(利用料金制度を取り巻く環境)
- 自治体が利用料金制度を適切に運用する意義は「住民負担の公平性の確保」と「持続可能な公共サービスの提供」にあります。
- 本制度は、地方自治法に基づき、公共施設の管理運営を指定管理者に委ねる際に、その利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる仕組みです。これにより、施設の利用者(受益者)が維持管理費用の一部を負担する「受益者負担の原則」を具体化しつつ、指定管理者の経営努力を促し、行政サービスの質的向上と効率化を図ることを目的とします。
- 少子高齢化に伴う社会保障費の増大と公共施設の老朽化という二重の課題に直面する東京都特別区において、本制度の合理的な設計と運用は、財政の持続可能性を確保し、将来世代に過度な負担を残さないために不可欠な行政課題です。
意義
住民にとっての意義
負担の公平性確保
- 施設を利用する人と利用しない人の間の費用負担の公平性を確保します。施設維持管理費の不足分は税金で賄われるため、利用料金制度は非利用者への負担を軽減する役割を果たします。
- 客観的根拠:
- 地方自治法では、公の施設の利用について使用料を徴収できると定められており、その趣旨は受益と負担の公平化にあります。岐阜市の算定基準では、この「受益者負担の原則」が基本方針として明確に掲げられています。
- 客観的根拠:
サービスの質の向上
- 利用料金が指定管理者の収入に直結するため、利用者を増やし満足度を高めようとするインセンティブが働きます。これにより、民間ならではの柔軟な発想やノウハウが活かされ、サービスの質の向上が期待できます。
- 客観的根拠:
- 利用料金制度では、利用料金収入が指定管理者の収益に直結するため経営努力が働き、市民サービス向上の可能性が高いとされています。
- 杉並区の指定管理者制度導入施設の検証では、利用者満足度は非常に高い水準で維持されており、指定管理者の創意工夫がサービスの質向上に寄与していることが確認されています。
- 客観的根拠:
地域社会にとっての意義
持続可能な施設利用環境の維持
- 適切な受益者負担により、施設の維持管理に必要な財源が安定的に確保され、地域社会の共有財産である公共施設を将来にわたって維持・活用することが可能になります。
- 客観的根拠:
- 公共施設の維持管理には人件費や光熱水費などの経費が必要であり、使用料はこれらの経費に充てられることで、施設の持続可能性を支えています。
- 客観的根拠:
コミュニティ活動の活性化
- 料金設定や減免制度を工夫することで、特定の活動や団体を支援し、地域コミュニティの活性化を促進するツールとしても機能します。ただし、制度設計を誤ると逆に不公平感を生むリスクもあります。
- 客観的根拠:
- 京丹後市の事例では、公民館の減免制度の有無が団体の活動回数に影響を与えており、料金制度がコミュニティ活動に直接的な影響を及ぼすことが示されています。
- 客観的根拠:
行政にとっての意義
財政負担の軽減と効率化
- 受益者から応分の負担を求めることで、施設の維持管理に係る一般財源(税金)からの支出を抑制できます。また、指定管理者の経営努力により、管理運営経費そのものが削減される効果も期待できます。
- 客観的根拠:
- 岐阜市の算定基準では、使用料が維持管理費を下回る場合、不足分は公費で賄うことになり、受益者負担の原則が財政負担の軽減に繋がることが示されています。
- 宇治市の資料では、利用料金制度の目的として「施設の管理運営経費の削減」が挙げられています。
- 客観的根拠:
行政事務の簡素化
- 利用料金制度では、料金の収受から経理までを指定管理者が行うため、自治体側の会計事務が大幅に簡素化・迅速化されます。
- 客観的根拠:
- 藤井寺市の資料では、利用料金制度のメリットとして「市や指定管理者の会計事務の簡素化・迅速化」が明確に挙げられています。
- 客観的根拠:
(参考)歴史・経過
~2002年:使用料制度の時代
- 地方自治法に基づき、自治体が条例で定めた「使用料」を徴収し、直接市の歳入とする「使用料制」が一般的でした。施設の管理は直営または管理委託制度が中心で、運営者に経営改善のインセンティブは働きにくい構造でした。
2003年:指定管理者制度の導入
- 平成15年(2003年)の地方自治法改正により、指定管理者制度が導入されました。これは、民間事業者の能力活用による住民サービスの向上と経費削減を目的としたものでした。
- これに伴い、指定管理者の収入として料金を収受できる「利用料金制度」が創設され、多くの自治体で導入が進みました。
2000年代中盤:三位一体の改革と財政的圧力
- 国から地方への補助金削減と税源移譲を進めた「三位一体の改革」により、地方自治体の財政は一層厳しくなりました。
- (出典)(https://www.clair.or.jp/j/forum/honyaku/hikaku/pdf/up-to-date_jp2.pdf)
- この財政的圧力が、自主財源確保の一環として、使用料や手数料の見直し、利用料金制度の積極的な活用を後押しする要因となりました。
2010年代以降:公共施設マネジメントと料金見直しの本格化
- 公共施設の大量更新時期を迎え、公共施設等総合管理計画の策定が全国で進みました。施設の維持管理コストの「見える化」が進み、受益者負担の適正化、すなわち利用料金の算定根拠を明確にし、定期的に見直す動きが活発化しました。江東区では平成12年度以降、複数回の料金改定を実施しています。
利用料金制度に関する現状データ
特別区全体の施設使用料収入と受益者負担率
- 東京都特別区の公共施設使用料収入は、区全体で年間約437億円(令和4年度)です。
- 一方で、施設の維持管理コストは年間約2,378億円(令和4年度)に上り、過去10年間で約23.7%増加しています。このコスト増は、施設の老朽化に加え、近年の物価高騰、特に光熱水費の上昇が大きく影響しています。
- この結果、維持管理コストに対する使用料収入の割合(受益者負担率)は、特別区平均で**18.3%**にとどまっています。これは、施設の維持管理に必要な費用のうち、8割以上が利用料金以外の一般財源、すなわち税金で賄われていることを意味します。
受益者負担率の区間格差
- 受益者負担率は区によって大きく異なり、**8.7%から32.6%**まで約3.7倍の開きがあります。
- この大きな格差は、各区の料金設定の考え方、施設の種別構成、減免制度のあり方に大きな違いがあることを示唆しており、統一的な方針が存在しない現状を浮き彫りにしています。
料金改定の効果と課題
- 総務省の調査によれば、使用料を改定した自治体における収入増加率は平均15.3%ですが、これも自治体によって5.2%から32.7%まで大きな差があります。
- 料金改定が財源確保に一定の効果を持つ一方で、その効果の度合いは一様ではなく、改定の進め方によって成果が大きく左右されることがわかります。
歳入全体に占める割合
- 令和5年度の特別区の歳入総額は、特別区税や特別区財政調整交付金の増加により、前年度比で増加傾向にあります。
- 使用料及び手数料は、歳入の柱である区税や交付金と比較すると、歳入全体に占める割合は限定的です。しかし、社会保障費の増大などで財政の硬直化が進む中、政策的にコントロール可能な自主財源としての重要性は増しています。
- これらのデータは、特別区が抱える「持続可能性のギャップ」が拡大していることを示しています。施設の老朽化や物価高騰により維持管理コストは構造的に上昇し続ける一方、それを賄うべき利用料金収入の割合(受益者負担率)は平均18.3%と低い水準に留まっています。このコストと収入の差額、すなわち毎年約1,941億円(2,378億円 – 437億円)に上る赤字は、全て税金によって補填されています。このギャップは、福祉や教育といった他の重要施策に充てるべき財源を圧迫する静かな脅威です。区によって受益者負担率に最大3.7倍もの差があるという事実は、この問題が不可避なものではなく、各区の政策判断の結果であることを物語っています。このまま放置すれば、財政状況の悪化は避けられず、将来的に大幅なサービス水準の低下か、住民への急激な負担増という厳しい選択を迫られることになります。
課題
住民の課題
料金設定の不公平感と負担増
- 類似施設でも自治体によって料金が異なる、あるいは近隣市では無料のサービスが有料であるといった状況があり、住民の不公平感につながっています。
- 物価高騰などを背景とした料金の値上げは、家計を直接圧迫するため、住民の理解を得ることが難しい場合があります。
- 客観的根拠:
- 秦野市の陳情では、近隣市では無料の公民館が有料化されたことへの不満が示されています。
- 秩父市のパブリックコメントでは、料金値上げはやむを得ないとしつつも、家計への影響を懸念する声が寄せられています。
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 行政への不信感が増大し、今後の料金改定や他の政策に対する住民協力が得られにくくなります。
- 客観的根拠:
複雑で分かりにくい減免制度
- 障害者、高齢者、子どもなどを対象とした減免制度は、公平な利用機会を確保する上で重要ですが、制度が複雑で分かりにくかったり、団体によって適用が異なったりすることで、かえって不公平感を生むことがあります。
- 申請手続きが煩雑で、利用のハードルとなっている場合もあります。
- 客観的根拠:
- 京丹後市の住民からは、公民館利用で減免される団体とされない団体があり、活動回数に差が出るなど不公平が生じているとの意見が出ています。
- 豊島区では、減免を受けるためには事前の申請手続きが必要であり、利用の都度、証明書等を提示する必要があります。
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 本来支援すべき層が制度を利用できず、公共施設が提供するセーフティネット機能が形骸化します。
- 客観的根拠:
地域社会の課題
コミュニティ活動への障壁
- 公共施設は、地域のサークル活動やNPOの拠点として重要な役割を担っています。しかし、利用料金が活動の継続にとって過度な負担となり、コミュニティの活力を削ぐ要因となることがあります。
- 特に、減免制度の不公平感は、団体間の軋轢を生む可能性も指摘されています。
- 客観的根拠:
- 京丹後市の事例では、減免のない団体が活動回数を減らしている実態が報告されており、料金制度が直接的にコミュニティ活動に影響を与えていることがわかります。
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 地域コミュニティの担い手が減少し、地域全体の活力低下や社会的孤立の増加につながります。
- 客観的根拠:
行政の課題
料金算定根拠の欠如と不統一
- 多くの自治体で、使用料算定の明確な基準(ルール)がありません。料金が合併前の旧町のものを引き継いでいたり、どんぶり勘定であったりするため、料金の妥当性を住民に説明することが困難です。
- 算定の基礎となる原価(コスト)の範囲や、受益者と公費の負担割合が不明確であることが根本的な課題です。
- 客観的根拠:
- あま市の調査では、「負担割合が不明確」「原価の範囲が不明確」「算定方式が不明確」といった課題が明確に指摘されています。
- 京丹後市でも、統一ルールがなく、合併前の料金を継承しているため地域間で不均衡が生じていると認めています。
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 客観的根拠に基づかない料金改定は住民の合意を得られず、財政状況が悪化しても料金を改定できない「政策の塩漬け」状態に陥ります。
- 客観的根拠:
硬直的な料金改定プロセス
- 料金改定のタイミングが定まっておらず、長期間にわたって料金が据え置かれるケースが多く見られます。
- 一度に大幅な値上げをせざるを得なくなり、住民の反発を招く「激変緩和」の問題が生じます。江東区では、負担の激変を避けるために、本来必要な改定率を圧縮する措置を講じています。
- 客観的根拠:
- 秩父市では20年間も料金改定が行われてこなかったことが指摘されています。
- 江東区では、本来89%の引き上げが必要なところを、負担割合の考え方を変えることで20%の引き上げに抑制する案を検討しています。
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 維持管理コストの上昇分を税金で補填し続けることになり、財政の硬直化を招き、他の新規・重点事業に資源を配分できなくなります。
- 客観的根拠:
- これらの行政課題は、互いに連鎖し「政策麻痺の悪循環」を生み出しています。まず、明確な算定ルールがないため、行政担当者は住民の反発を恐れて料金改定の提案を躊躇し、結果として長期間の「塩漬け」状態が生まれます。やがて財政的圧力が限界に達すると、行政はついに、積み重なったコスト増を反映した大幅な値上げ案を提示せざるを得なくなります。しかし、その算定根拠が不透明なため、住民からは「唐突で不公平な値上げ」と見なされ、強い反対に直面します。この反発を乗り切るため、行政は江東区の負担割合の調整や、かつての練馬区の特例回数券のような「激変緩和措置」という複雑な妥協策を導入します。これにより当面の危機は回避されますが、料金体系はさらに不透明で複雑になり、根本的な問題である「ルールの不在」は解決されないままです。この一連のプロセスで経験する政治的な痛みは、行政と議会の双方をさらに萎縮させ、次の見直しをさらに遠のかせるのです。この悪循環を断ち切るには、個別の料金改定を議論する前に、まず誰もが納得できる「ルールの確立」そのものに注力することが不可欠です。
行政の支援策と優先度の検討
優先順位の考え方
※各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
即効性・波及効果
- 施策の実施から効果発現までの期間が短く、複数の課題解決や多くの住民への便益につながる施策を高く評価します。
実現可能性
- 現在の法制度、予算、人員体制の中で実現可能な施策を優先します。
費用対効果
- 投入する経営資源(予算・人員・時間等)に対して得られる効果が大きい施策を優先します。
公平性・持続可能性
- 特定の地域・年齢層だけでなく、幅広い住民に便益が及ぶ施策を優先します。一時的な効果ではなく、長期的・継続的に効果が持続する制度的・構造的な改革を高く評価します。
客観的根拠の有無
- 先進事例や調査研究によって効果が示されている、客観的根拠に基づいた施策を優先します。
支援策の全体像と優先順位
- 課題の根源が「ルールの不在」と「制度の複雑化」にあることを踏まえ、**①ルールの標準化(基盤整備)→②制度の再構築(体系化)→③運用の高度化(価値創造)**の3段階で施策を構築します。
- 最優先は**「支援策①:利用料金算定・改定ルールの標準化」**です。これは全ての課題の根源にある問題であり、他の施策の前提となるため、即効性は低いものの波及効果と持続可能性が極めて高く、最優先で取り組むべきです。
- 次に**「支援策②:減免制度の体系的再構築」**を位置づけます。標準化されたルールを基に、複雑化した減免制度を整理・統合することで、住民の公平感を確保し、行政コストを削減します。
- 最後に**「支援策③:指定管理者制度の活用によるサービス向上と財源確保」**を進めます。明確化されたルールと制度の下で、指定管理者の能力を最大限に引き出し、新たな財源確保やサービス向上といった付加価値を創造します。
各支援策の詳細
支援策①:利用料金算定・改定ルールの標準化
目的
- 料金算定・改定プロセスの客観性、透明性、公平性を確保し、住民の理解と納得を得やすくします。
- 行政内部での統一的な基準を設け、担当者による判断のブレをなくし、継続的かつ計画的な料金見直しを可能にします。
- 客観的根拠:
- あま市や京丹後市の事例で、統一ルールの不在が料金の不均衡や説明責任の欠如につながっていることが指摘されており、ルール策定の必要性が裏付けられています。
- 客観的根拠:
主な取組①:『公共施設使用料算定ガイドライン』の策定
- 全庁的なガイドラインを策定し、料金算定の考え方を明文化します。
- 原価の範囲の明確化: 人件費、物件費、維持補修費に加え、減価償却費を原則として原価に算入することを明記します。
- 算定方式の標準化: 会議室等の「占有利用」とプールの「個人利用」など、施設の利用形態に応じた標準的な算定式を定めます。
- 客観的根拠:
- 岐阜市や鎌倉市、加古川市などが具体的な算定基準やガイドラインを策定・公表しており、実効性のあるモデルとなります。
- 客観的根拠:
主な取組②:受益者負担割合の段階的設定
- 施設の性質(公共性・市場性)に応じて、受益者負担割合を複数段階で設定する基準を設けます。
- 例えば、鎌倉市のように「必需性」「公益性」を軸としたマトリクスで施設を分類し、負担割合を「0%, 25%, 50%, 75%, 100%」のように段階的に定めます。
- 客観的根拠:
- 鎌倉市や岐阜市の事例では、サービスの性質に応じて負担割合を機械的に決定する仕組みを導入しており、行政の裁量の余地を減らし、客観性を高める工夫が見られます。
- (出典)岐阜市「公の施設の使用料算定基準」
- (出典)鎌倉市「公共施設使用料等算定基準」
- 鎌倉市や岐阜市の事例では、サービスの性質に応じて負担割合を機械的に決定する仕組みを導入しており、行政の裁量の余地を減らし、客観性を高める工夫が見られます。
- 客観的根拠:
主な取組③:定期的な見直しサイクルのルール化
- 原則として「4年ごと」など、定期的に料金を見直すサイクルをガイドラインに明記します。
- 見直しのトリガー(きっかけ)として、「現行料金と算定結果が15%以上乖離した場合」など、具体的な数値基準を設けます。
- 客観的根拠:
- 江東区は原則4年ごとの見直しを方針として掲げています。
- 市原市は料金改定の基準として「15%以上の乖離」という具体的な数値を設定しています。
- 客観的根拠:
主な取組④:住民合意形成プロセスの標準化
- 料金改定案の策定段階から、住民参加の機会を設けます。
- 審議会への住民代表の参加、住民説明会やワークショップの開催、分かりやすい資料を用いたパブリックコメントの実施などをプロセスとして定めます。
- 客観的根拠:
- 雲南市の事例では、住民懇談会での意見聴取が、料金改定への理解を得る上で有効であったことが示唆されています。
- パブリックコメントで寄せられた意見と市の考え方を丁寧に公表することが、住民の納得感を高める上で重要です。
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 料金改定案に対する住民の納得度(パブリックコメント等での賛成意見割合): 50%以上
- データ取得方法: パブリックコメント意見の集計・分析、住民意識調査
- 料金改定案に対する住民の納得度(パブリックコメント等での賛成意見割合): 50%以上
- KSI(成功要因指標)
- ガイドラインに基づく料金見直しを実施した施設数の割合: 100%
- データ取得方法: 財政主管課による各施設所管課への進捗確認
- ガイドラインに基づく料金見直しを実施した施設数の割合: 100%
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 料金改定に関する住民説明会・意見交換会の参加者数: 各回平均30人以上
- データ取得方法: 各所管課での開催実績報告
- 料金改定に関する住民説明会・意見交換会の参加者数: 各回平均30人以上
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 『公共施設使用料算定ガイドライン』の策定・公表: 令和X年度末まで
- データ取得方法: 策定完了の事実確認
- 『公共施設使用料算定ガイドライン』の策定・公表: 令和X年度末まで
支援策②:減免制度の体系的再構築
目的
- 複雑化・不統一な減免制度を整理・体系化し、公平性・透明性を向上させます。
- 本当に支援が必要な層に確実にサービスが届くようにするとともに、行政手続きの簡素化・効率化を図ります。
- 客観的根拠:
- 江東区は減免規定の整理を継続的な検討課題としており、練馬区は団体利用の減免条件を明確に規定しています。これらの動きは、減免制度の体系化が多くの自治体で課題となっていることを示しています。
- 客観的根拠:
主な取組①:全区統一的な減免基準の策定
- 「障害者」「高齢者」「子ども」「低所得者」など、対象者ごとの減免基準(対象者の範囲、減免率)を全区的に統一します。
- 特に、障害者手帳を持つ方とその介助者については、多くの自治体で減免対象となっており、これを標準的な基準として位置づけます。
- 客観的根拠:
- 豊島区や練馬区では、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の種類に応じて明確な減免規定を設けています。こうした具体的な規定を参考に、全区的な基準を策定します。
- 客観的根拠:
主な取組②:利用目的による減免の整理・統合
- 「地域コミュニティ活動」「公益活動」など、利用目的による減免についても、その公益性の度合いに応じて基準を明確化し、乱立する制度を整理・統合します。
- 団体の構成員要件(例:区民の割合、高齢者・障害者の割合)を明確に定めます。
- 客観的根拠:
- 練馬区では、構成員の半数以上が高齢者や障害者、中学生以下である団体など、具体的な構成員要件に基づいて減免を適用しており、客観的な基準設定の参考になります。
- 客観的根拠:
主な取組③:申請手続きのデジタル化と簡素化
- 減免申請をオンラインで完結できるようにし、添付書類の削減を図ります。
- 一度登録すれば、有効期間内は証明書の提示を不要とする「減免資格登録証」のような仕組みを導入します。
- 客観的根拠:
- 豊島区では有効期限付きの「免除承認証」を発行しており、練馬区では公共施設予約システムに減免団体として登録する仕組みがあります。これらの仕組みをデジタル化することで、利用者・行政双方の負担を軽減できます。
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 減免制度の利用者満足度: 80%以上
- データ取得方法: 施設利用者アンケート(減免制度利用者対象)
- 減免制度の利用者満足度: 80%以上
- KSI(成功要因指標)
- 減免申請のオンライン化率: 80%以上
- データ取得方法: 電子申請システムの利用実績データ
- 減免申請のオンライン化率: 80%以上
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 減免制度に関する問い合わせ件数: 30%削減
- データ取得方法: 各施設窓口、コールセンターでの問い合わせ件数集計
- 減免制度に関する問い合わせ件数: 30%削減
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 全区統一減免基準の策定: 令和Y年度末まで
- データ取得方法: 策定完了の事実確認
- 全区統一減免基準の策定: 令和Y年度末まで
支援策③:指定管理者制度の活用によるサービス向上と財源確保
目的
- 利用料金制度が持つインセンティブ機能を最大限に活用し、指定管理者の経営努力によるサービス向上と新たな財源確保を促進します。
- 利用料金の値上げだけに頼らない、持続可能な施設経営モデルを構築します。
- 客観的根拠:
- 利用料金制度は、指定管理者の収益に直結することで経営努力を促し、市民サービス向上の可能性を高める仕組みです。このポテンシャルを最大限に引き出すことが目的です。
- 客観的根拠:
主な取組①:インセンティブを高める指定管理料の設定
- 指定管理料の算定において、利用料金収入の増加努力を評価する仕組みを導入します。
- 例えば、基準となる利用料金収入額を設定し、それを超えた分の一部を指定管理者の利益として明確に認める、あるいは次期指定管理料に反映させるなどのインセンティブ条項を協定に盛り込みます。
- 客観的根拠:
- 利用料金収入は指定管理者の収入となり、管理業務の必要経費に充てられるため、指定管理料は利用料金収入を見込んで減額設定されます。この関係性を活用し、より経営努力が報われるスキームを設計します。
- 客観的根拠:
主な取組②:ネーミングライツの導入促進
- 指定管理者と連携し、施設のネーミングライツ(命名権)パートナーを積極的に募集します。
- 得られた収入は、施設の改修や利用者サービスの向上、利用料金の抑制などに充当することを明確にし、住民の理解を得ます。
- 客観的根拠:
- ネーミングライツは新たな財源確保の手法として多くの自治体でガイドラインが整備されています。指定管理者制度を導入している施設も対象とすることができ、指定管理者の意見を聴取しながら進めることが重要です。
- 客観的根拠:
主な取組③:自主事業の奨励とルール明確化
- 指定管理者が行う自主事業(例:特別な講座やイベント)を奨励し、施設の魅力を高めます。
- 自主事業の料金設定の自由度を高める一方、公共施設としての性格を逸脱しないためのルール(例:事業内容の事前協議)を明確にします。
- 客観的根拠:
- 杉並区の報告書では、指定管理者の創意工夫によるサービス提供が高い満足度につながっていると評価されており、自主事業はその中核をなすものです。
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 利用料金以外の収入(ネーミングライツ、自主事業収益等)の割合: 全収入の10%以上
- データ取得方法: 指定管理者からの事業報告書の分析
- 利用料金以外の収入(ネーミングライツ、自主事業収益等)の割合: 全収入の10%以上
- KSI(成功要因指標)
- ネーミングライツ導入施設数: 年間3施設以上
- データ取得方法: 契約実績の集計
- ネーミングライツ導入施設数: 年間3施設以上
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 指定管理者による自主事業の参加者数: 対前年度比10%増
- データ取得方法: 指定管理者からの事業報告書の分析
- 指定管理者による自主事業の参加者数: 対前年度比10%増
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- ネーミングライツ導入に関するガイドラインの策定・公表: 令和Z年度末まで
- データ取得方法: 策定完了の事実確認
- ネーミングライツ導入に関するガイドラインの策定・公表: 令和Z年度末まで
先進事例
東京都特別区の先進事例
江東区「定期的な見直しと段階的アプローチ」
- 江東区は、受益者負担の原則に基づき、定期的に(原則4年ごと)使用料の検証・見直しを行う方針を明確にしています。原価計算に減価償却費を含めるなど、算定根拠の精緻化にも取り組んでいます。
- 令和5年の報告では、物価高騰等により大幅な料金引き上げが必要と試算されたものの、住民負担の激変を緩和するため、負担割合の考え方を工夫し、段階的なアプローチを検討しています。
- 成功要因とその効果: 算定根拠をデータで示しつつも、社会経済情勢を鑑みた柔軟な判断を行うことで、財政規律と住民感情のバランスを取ろうとする姿勢は、合意形成を進める上で参考になります。
- 客観的根拠:
杉並区「指定管理者制度の成果評価と住民ニーズの反映」
- 杉並区は、指定管理者制度を導入した施設の運営状況について、利用者満足度調査や経費削減効果の検証を含む包括的な報告書を公表しています。
- 検証の結果、高い利用者満足度と一定の経費削減効果が確認される一方、今後の課題として「利用していない区民への周知徹底」や「利用者・地域住民のアイデアを運営に活かす仕組み」を提言しています。
- 成功要因とその効果: 利用料金制度と一体である指定管理者制度の成果を客観的に評価し、次のステップ(住民参加の促進)につなげるPDCAサイクルを実践している点が先進的です。
- 客観的根拠:
練馬区「キャッシュレス化と一体となった制度見直し」
- 練馬区は、スポーツ施設の利用料支払いにキャッシュレス決済を導入するのに伴い、20年以上続いてきた高齢者向けの特例回数券(割引制度)を廃止することを決定しました。
- これは、システムの更新という技術的な制約をきっかけに、長年の懸案であった激変緩和措置を見直すという、戦略的な政策判断です。
- 成功要因とその効果: 制度改正の「大義名分」として、多くの住民が利便性を享受できる「キャッシュレス化」を掲げることで、一部の利用者にとっては不利益となる制度変更の理解を得ようとしています。政策変更におけるコミュニケーション戦略として注目されます。
全国自治体の先進事例
鎌倉市「マトリクスによる受益者負担割合の客観化」
- 鎌倉市は、「公共施設使用料等算定基準」を策定し、受益者負担割合を決定するための客観的な仕組みを導入しています。
- 施設のサービスを「必需性」と「公益性」の2軸で9つに分類し、それぞれに標準的な受益者負担割合(0%~100%の5段階)を割り当てています。これにより、担当者の主観を排し、公平で透明性の高い料金設定を目指しています。
- 成功要因とその効果: 料金設定の根幹である「負担割合」という最も政治的になりがちな部分に、客観的な基準を導入することで、住民への説明責任を果たしやすくし、合意形成の土台を築いています。
- 客観的根拠:
雲南市「住民との対話を通じた合意形成」
- 雲南市は、公共施設使用料の改定にあたり、住民懇談会などを通じて丁寧な意見聴取を行いました。
- その結果、「物価高騰の中で改定はやむを得ない」「近隣と比較しても安い」といった、市の財政状況や社会情勢を踏まえた理解ある意見が多数寄せられました。
- 成功要因とその効果: 一方的な値上げ通告ではなく、市の現状をデータで示し、住民と対話するプロセスを経ることで、料金改定という痛みを伴う政策に対する住民の納得感を醸成することに成功しています。
- 客観的根拠:
参考資料[エビデンス検索用]
国・自治体等の報告書・ガイドライン
- 総務省「令和5年版 地方財政の状況(地方財政白書)」
- 東京都「特別区の財政状況等に関する調査」令和5年度
- 特別区長会「令和5年度 特別区決算(見込)の概要」
- 江東区「公共施設の使用料等の見直しに関する報告書」令和6年1月
- 杉並区「指定管理者制度の検証に関する報告書」令和5年9月
- 鎌倉市「公共施設使用料等算定基準」
- 岐阜市「公の施設の使用料算定基準」
- 京丹後市「使用料・手数料の改正について」
- 雲南市「公共施設使用料の改定(見直し)に係る意見聴取の結果について」
地方自治法関連
まとめ
東京都特別区における利用料金制度は、受益者負担の公平性を確保し、持続可能な公共サービスを提供する上で極めて重要です。しかし現状では、算定根拠の不明確さや区間格差、複雑な減免制度といった課題を抱え、財政圧迫の一因となっています。今後は、客観的データに基づく「算定・改定ルールの標準化」を最優先で進め、公平で透明な減免制度を再構築し、指定管理者制度のインセンティブを最大限に活用することで、料金の値上げだけに頼らない新たな価値創造を目指すべきです。
本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。




-320x180.jpg)

-320x180.jpg)