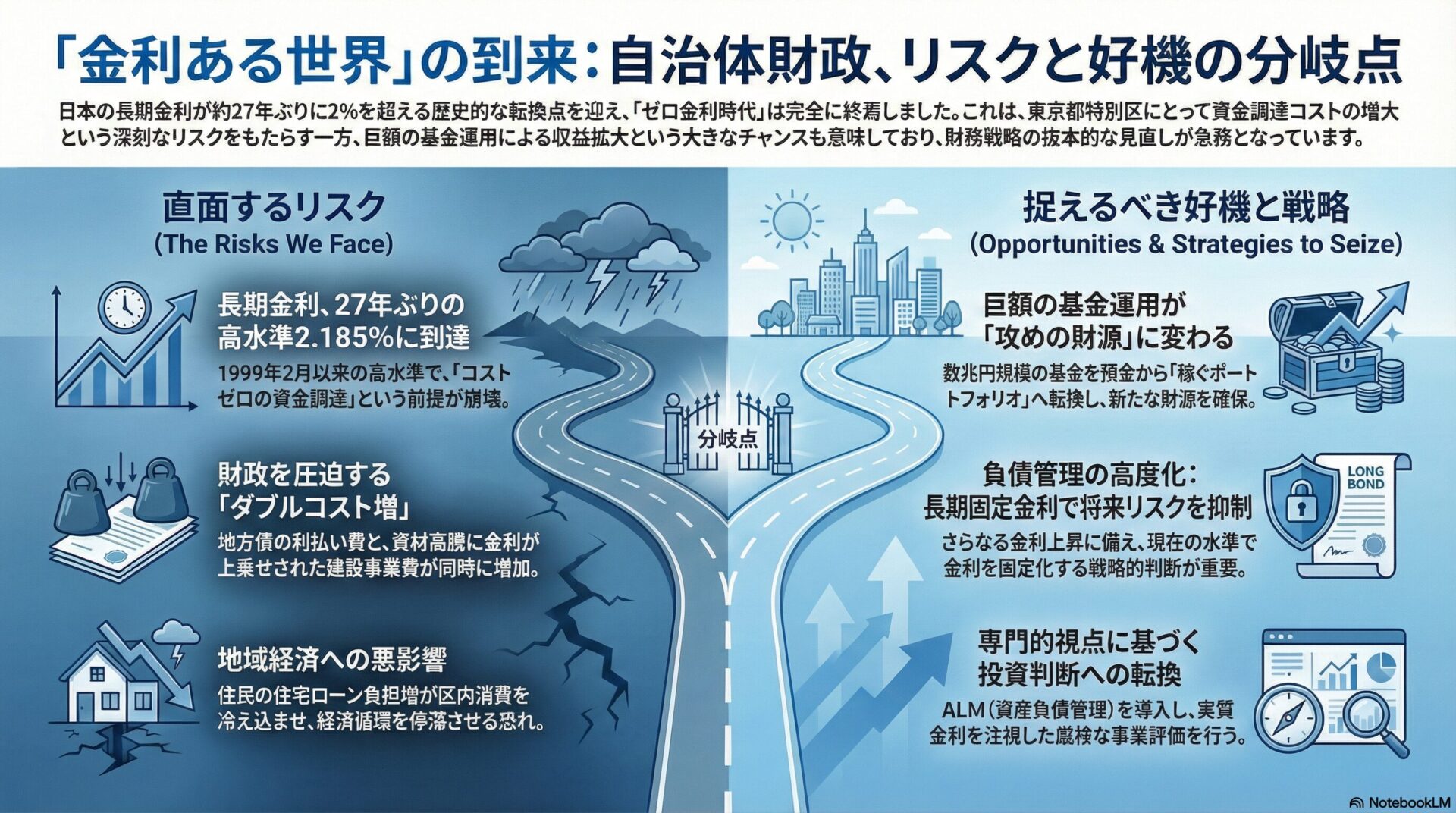【財政課】繰越明許費 完全マニュアル

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
繰越制度の基礎知識:会計年度独立の原則とその例外
なぜ繰越制度を理解する必要があるのか
東京都特別区の財政を担う職員の皆様にとって、予算の繰越制度を正確に理解することは、単なる事務手続きの習得以上の重要な意味を持ちます。繰越は、年度内に完了しなかった事業を翌年度に引き継ぎ、区民への行政サービスを確実に提供するための不可欠な仕組みです。しかし、その運用を誤れば、違法な支出につながり、監査での指摘や区民からの信頼失墜を招くリスクもはらんでいます。したがって、繰越制度の知識は、日々の業務を適正に執行するための「守り」の知識であると同時に、複数年度にわたる大規模な建設計画や予測不能な事態に柔軟に対応し、区の発展を支える「攻め」の財政運営を実現するための専門スキルでもあるのです。本研修資料は、この重要な繰越制度について、その根幹にある思想から具体的な事務手続き、さらには応用的な知識までを網羅的に解説し、皆様が自信を持って実務に臨めるようになることを目的としています。
地方財政の根幹「会計年度独立の原則」
地方公共団体の財政運営における最も基本的なルール、それが「会計年度独立の原則」です。これは、地方自治法第208条第2項に「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない」と定められており、地方財政の根幹をなす大原則です。
具体的には、「ある年度(n年度)の事業に必要な経費は、そのn年度の税収や交付金などの収入で賄わなければならない」という考え方です。翌年度(n+1年度)の収入を見越して今年度の事業費に充てたり、前年度(n−1年度)に余ったお金を自由に取り崩して使ったりすることは、原則として認められません。これは、各年度の財政状況と経営成績を明確にし、議会や区民に対する説明責任を果たすために不可欠な規律です。この原則があるからこそ、財政の健全性が保たれ、計画的な行政運営が可能となるのです。
例外規定としての繰越制度の意義と歴史的変遷
しかし、この会計年度独立の原則をあまりにも厳格に適用すると、かえって非効率で不経済な事態が生じることがあります。例えば、大規模な公共施設の建設や、年度末近くに国からの補助金が決定した事業など、物理的に単年度で完了することが不可能な、あるいは著しく困難な事業は少なくありません。もし繰越が一切認められなければ、年度末に無理に予算を使い切ろうとする無駄遣いや、事業そのものの中断を余儀なくされる可能性があります。
そこで、会計年度独立の原則の「例外」として、合理的な理由がある場合に限り、予算を翌年度に使用することを認める「繰越制度」が法律で定められています。この制度は、財政規律を維持するという原則の精神を守りつつ、行政の実態に即した弾力的かつ効率的な予算執行を可能にするための重要な仕組みです。国の財政法においても詳細な規定が設けられ、財務省が「繰越しガイドブック」を発行するなど、その適正な運用が重視されており、これは地方自治体においても同様です。繰越制度は、厳格な財政規律と、効果的な事業遂行という二つの要請を両立させるための、高度な財政技術と言えるでしょう。
繰越明許費の実務詳解
繰越明許費の定義と法的根拠
繰越明許費(くりこしめいきょひ)とは、会計年度独立の原則の例外の一つであり、地方自治法第213条第1項にその根拠が定められています。条文では、「歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる」と規定されています。
この条文の重要なポイントは二つです。第一に、繰越が認められる理由が「その性質上」と「予算成立後の事由」の二種類に限定されていること。第二に、「予算の定めるところにより」とあるように、必ず事前に議会の議決を経た予算書に「繰越明許費」として計上されなければならない、という点です。つまり、行政の判断だけで勝手に行えるものではなく、民主的なコントロールの下で計画的に行われる繰越である、という点が最大の特徴です。
対象となる経費:「性質上」と「予算成立後の事由」
繰越明許費の対象となる経費は、法律で定められた二つの理由のいずれかに該当する必要があります。
- 性質上、年度内に支出を終わらない見込みのある経費:
- これは、事業の計画段階から、その内容や規模、工程などから判断して、単年度で完了することが本質的に困難であると客観的に認められる経費を指します。
- 具体例:
- 大規模な庁舎や学校の建設・改修工事
- 広範囲にわたる都市計画道路の整備事業
- 複雑な情報システムの設計・開発・導入事業
- 長期間の調査研究を要する事業
- 具体例:
- これは、事業の計画段階から、その内容や規模、工程などから判断して、単年度で完了することが本質的に困難であると客観的に認められる経費を指します。
- 予算成立後の事由に基づき、年度内に支出を終わらない見込みのある経費:
- これは、当初予算が成立した時点では年度内の完了が見込まれていたものの、その後に発生した予測可能な範囲の事由によって、年度内の支出が困難になった経費を指します。
- 具体例:
- 年度後半に国や都から内示された補助事業。予算を補正して計上しても、年度末までに事業を完了する時間的余裕がない場合。
- 道路建設などにおける用地買収交渉が、地権者との調整に想定以上の時間を要し、年度内に契約締結の目途が立たなくなった場合。
- 事業の実施に必要な許認可の取得や、関係機関との協議に不測の日数を要した場合。
- 具体例:
- これは、当初予算が成立した時点では年度内の完了が見込まれていたものの、その後に発生した予測可能な範囲の事由によって、年度内の支出が困難になった経費を指します。
標準業務フロー:予算編成から決算まで
繰越明許費の事務は、予算編成プロセスと密接に連携して進められます。以下に標準的な業務フローを示します。
予算要求段階での検討と財政課との協議
各事業所管課は、翌年度予算を要求する段階で、事業の性質や工程を精査し、年度内に支出が完了しない可能性を検討します。繰越の必要性が見込まれる場合は、その理由、繰越見込額、事業スケジュールなどを明確にした上で、早期に財政課と協議を開始します。この事前協議が、後の円滑な手続きの鍵となります。
予算案の作成と議会議決(当初予算・補正予算)
財政課は、事業所管課からの要求内容を審査し、繰越の妥当性が認められれば、予算案に「繰越明許費」として計上します。予算書では、通常の歳出予算とは別に「第2表 繰越明許費」といった形式で、事業名と限度額が明示されます。この予算案が議会で審議され、可決されることによって、初めて翌年度への繰越が法的に可能となります。年度途中で繰越の必要性が生じた場合は、補正予算を編成し、同様に議会の議決を得る必要があります。
年度末における繰越額の見積と手続き
年度末が近づくと、事業所管課は事業の進捗状況を最終的に確認し、翌年度に繰り越す必要のある経費の正確な金額を確定させます。その上で、例えば「繰越明許費繰越調書」といった正式な書類を作成し、定められた期日までに財政課(または企画担当部署)へ提出します。東京都の財務会計規則では、局長が財務局長に繰越見積書を提出することが定められており、特別区においてもこれに準じた手続きが取られています。
繰越計算書の作成と議会への報告
会計年度が終了した後、財政課は各課から提出された調書を取りまとめ、区全体の繰越明許費の実績を示す「繰越計算書」を作成します。この繰越計算書は、決算書類の一部として、最終的に議会へ報告されます。これは、予算段階で議決された繰越が、実際にいくら執行され、いくら繰り越されたのかを事後的に明らかにし、行政の説明責任を果たすための重要な手続きです。
実務上の留意点とケーススタディ
ケーススタディ1:国の補正予算に対応する繰越
年度後半の11月、国から「GIGAスクール構想」の追加支援として、区内の小中学校のネットワーク環境強化に関する補助金が内示されました。事業所管課である教育委員会は、直ちに事業計画を策定しましたが、設計、入札、工事を年度末の3月31日までに完了させることは物理的に不可能です。
- 対応:
- 教育委員会は財政課と協議の上、2月区議会定例会に補正予算案を提出。
- 歳入として国庫補助金を追加すると同時に、歳出にネットワーク整備事業費を計上。
- さらに、この事業費の全額を「繰越明許費」として設定する議案も併せて提出し、議決を得ます。
- これにより、翌年度に腰を据えて事業を実施する法的根拠が確保されます。
ケーススタディ2:用地買収の遅延による繰越
区道の拡幅工事のため、年度当初から用地買収交渉を進めていましたが、対象地権者のうち1名との交渉が難航し、年度内の契約締結が見通せない状況となりました。工事契約は用地取得後に行うため、工事費の支出も翌年度にずれ込むことが確実となりました。
- 対応:
- 道路整備所管課は、交渉の状況と今後の見通しを整理し、財政課に報告。
- 年度末までに支出が見込めない用地買収費と工事費の合計額を算定。
- 2月の補正予算において、当該事業費を減額することなく、「予算成立後の事由」に基づく繰越明許費として設定する議決を得ます。
ケーススタディ3:複数年にわたる計画の一部としての繰越
3か年計画で進める区の基幹情報システムの刷新プロジェクトの1年目。初年度は要件定義と基本設計を完了させる計画で、そのための委託費用が予算化されています。しかし、ベンダーとの詳細な仕様調整に時間を要し、基本設計の完了と、それに基づく委託費の支払いが翌年度の4月にずれ込む見込みとなりました。
- 対応:
- 情報システム所管課は、プロジェクトの進捗遅延を早期に把握し、財政課と共有。
- 当初予算編成時に、事業の性質上、遅延リスクがあることを踏まえ、あらかじめ繰越明許費として設定しておくことが理想的です。
- もし当初予算で設定していない場合は、年度末の補正予算で繰越明許費を設定し、計画の遅延に柔軟に対応します。
事故繰越の実務詳解
事故繰越の定義と法的根拠
事故繰越(じこくりこし)は、繰越明許費とは性格を全く異にする、緊急かつ例外的な繰越制度です。その根拠は、地方自治法第220条第3項ただし書にあります。条文では、「歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(…)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる」と規定されています。
この制度は、計画的な繰越である繰越明許費とは対照的に、予測不能な事態に対応するためのものです。そのため、繰越明許費のように事前の議会議決を必要としません。これは、議会を開く時間的余裕のない年度末の突発的な事態にも行政が機動的に対応できるようにするための規定ですが、その適用は極めて厳格に解釈されるべきものです。
適用要件:「支出負担行為済み」と「避け難い事故」
事故繰越が認められるためには、以下の二つの要件を両方とも満たす必要があります。
- 年度内に支出負担行為済みであること:
- 「支出負担行為」とは、地方公共団体が支出の原因となる契約などを締結し、法律上の支払義務を負う行為を指します。最も典型的な例は、事業者と工事請負契約や物品購入契約を正式に締結することです。この要件は、事故繰越が単なる予算の未執行分を翌年度に回すものではなく、既に支払義務が確定しているにもかかわらず、不測の事態で支払いが年度内に完了しなかった経費を救済するための制度であることを示しています。契約締結前の経費は、事故繰越の対象にはなり得ません。
- 「避け難い事故」の発生:
- 「避け難い事故」とは、社会通念上、予見することが困難で、かつ地方公共団体の責めに帰すことができない客観的な事由を指します。単なる事務の遅れや、計画の甘さ、担当者の過失などは「事故」には該当しません。その判断は慎重に行う必要があり、なぜそれが「避け難い」ものであったのかを合理的に説明できなければなりません。
標準業務フロー:事故発生から事後報告まで
事故繰越は、突発的な事態への対応となるため、その業務フローは迅速さと正確性が求められます。
事故発生時の初期対応と状況把握
事業所管課は、工事の中断や納品の遅延といった事故が発生した場合、直ちにその事実関係、原因、および事業への影響(特に年度内完了の可否)を把握し、速やかに財政課へ第一報を入れます。
支出負担行為の確認と繰越要件の判断
報告を受けた財政課は、事業所管課と連携し、まず当該経費について年度内に有効な支出負担行為(契約等)が行われているかを確認します。その上で、発生した事象が法に定める「避け難い事故」に該当するかどうかを、過去の事例や法令解釈に基づき厳格に審査します。この段階での的確な判断が、適正な事務執行の生命線となります。
事故繰越調書の作成と決裁
要件を満たすと判断された場合、事業所管課は「事故繰越見積書」や「事故繰越調書」といった内部決裁文書を作成し、財政課(または企画担当部署)へ提出します。この手続きは、区の内部規定に従って進められ、最終的に区長の決裁を得て完了します。議会の議決は不要です。
繰越計算書の作成と議会への報告
繰越明許費と同様に、会計年度終了後、財政課は事故繰越の実績を「繰越計算書」に取りまとめ、決算の一部として議会に報告します。議会にとっては、この事後報告が事故繰越の妥当性をチェックする唯一の機会となるため、報告書には事故の具体的な内容や繰越の理由を明確に記載する必要があります。
「避け難い事故」の具体的判断基準とケーススタディ
何が「避け難い事故」に該当するかの判断は、実務上最も難しい点の一つです。以下に、国のガイドライン等で示されている典型的な事例を基にしたケーススタディを挙げます。
ケーススタディ1:自然災害(台風、豪雨)による工事中断
年度末の完成を目指していた公園整備工事の現場が、3月に発生した記録的な豪雨により冠水し、大規模な土砂崩れが発生。復旧作業に数週間を要するため、年度内の工事完了および代金の支払いが不可能となりました。
- 判断:
- 自然災害は典型的な「避け難い事故」です。契約済みの工事費のうち、未払となっている金額が事故繰越の対象となります。
ケーススタディ2:地中障害物・遺跡の発見
公民館の建て替え工事で、基礎工事のために地面を掘削したところ、設計図にない旧建物の巨大なコンクリート基礎や、文化財保護法上の遺跡が発見されました。撤去作業や文化庁との協議のため、工事は長期間中断せざるを得なくなりました。
- 判断:
- 事前の地質調査等で発見が困難であった地中障害物や遺跡の発見は、「避け難い事故」と認められます。
ケーススタディ3:受注事業者の倒産
区立保育園の増築工事を請け負っていた建設会社が、3月上旬に突然倒産しました。工事は9割方完了していましたが、残りの工事と最終的な支払手続きが年度内に完了できなくなりました。
- 判断:
- 受注者の倒産は、区の責めに帰すことができない外部要因であり、「避け難い事故」に該当します。
ケーススタディ4:住民調整の難航・訴訟の発生
ごみ処理施設の中間処理設備の設置工事について、契約締結後、一部の周辺住民から、事前に想定されていなかったほどの強硬な反対運動が起こり、工事差し止めの仮処分申請が裁判所に提出されました。これにより、工事は中断を余儀なくされました。
- 判断:
- 契約締結後に発生した、社会通念上予測不能なレベルの住民との対立や訴訟は、「避け難い事故」と判断される可能性があります。ただし、計画段階での住民説明が不十分であったと見なされる場合は、区の責任が問われることもあり、慎重な判断が必要です。
ケーススタディ5:世界情勢に起因する資材納入の遅延
新しい清掃工場の基幹設備として、ドイツから特殊な焼却炉を輸入する契約を締結していました。しかし、中東情勢の緊迫化により、輸送船が喜望峰への大幅なルート変更を余儀なくされ、日本への到着が2か月遅れることが確定しました。これにより、設備の据付と支払いが年度内に間に合わなくなりました。
- 判断:
- 国際紛争など、一地方公共団体の管理能力を完全に超える世界情勢の変化に起因する納期の遅延は、「避け難い事故」と認められます。
繰越明許費と事故繰越の比較と応用知識
両制度の相違点と使い分け
繰越明許費と事故繰越は、どちらも予算を翌年度に持ち越す制度ですが、その性格と手続きは全く異なります。実務においては、直面した事態がどちらの制度で対応すべきかを正確に見極めることが極めて重要です。繰越明許費は「計画的・予防的」な措置であり、事前の民主的統制(議決)を前提とします。一方、事故繰越は「緊急的・事後的」な措置であり、行政の機動性を確保するために議決を不要としますが、その分、適用要件が厳格に定められています。この根本的な思想の違いを理解することが、適切な使い分けの第一歩です。
以下の比較表は、両制度の重要な違いをまとめたものです。日々の業務における判断の拠り所としてご活用ください。
| 比較項目 | 繰越明許費 (Approved Carry-over) | 事故繰越 (Accident Carry-over) |
| 法的根拠 | 地方自治法 第213条 | 地方自治法 第220条第3項ただし書 |
| 議会の関与 | 事前の議決が必要(予算の一部として) | 事前の議決は不要(事後の報告のみ) |
| 対象経費の性質 | 予測可能な事由により年度内支出が困難な経費 | 予測不能な「避け難い事故」により支出不能となった経費 |
| 前提条件 | 特になし(予算計上そのものが条件) | 年度内に支出負担行為済みであること |
| 手続きの時期 | 予算編成時または補正予算編成時 | 事故発生後、年度末から翌年度当初 |
| 典型的な事例 | 用地買収の難航、国の交付金決定の遅れ、設計に時間を要する事業 | 自然災害、受注者の倒産、地中障害物の発見 |
関連制度との連携:継続費と債務負担行為
繰越制度は、他の複数年度にわたる予算制度と連携して活用することで、より効果的な財政運営が可能となります。
- 継続費 (Continuing Expenses):
- 数年度にわたる建設事業や大規模な計画など、その履行に複数年度を要する経費について、あらかじめ事業全体の経費総額と各年度の支払額(年割額)を一体として議会の議決を得ておく制度です。一度議決されれば、各年度は年割額の範囲内で支出が可能となり、年度ごとの予算議決が不要になる点が特徴です。繰越明許費が原則1年限りの繰越であるのに対し、継続費は当初から複数年度にわたる支出を約束する、より計画性の高い制度と言えます。
- 債務負担行為 (Commitment of Obligations):
- 将来の年度にわたって債務(支払義務)を負担する行為を、あらかじめ議会の議決を得て約束しておく制度です。例えば、庁舎の5年間の賃貸借契約や、複数年にわたるリース契約などを締結する場合に用いられます。これは、将来の支出を約束するものであり、必ずしも当年度の歳出予算を伴いません。繰越明許費が「予算の執行時期」を翌年度にずらす制度であるのに対し、債務負担行為は「将来の支出の約束」そのものを可能にする制度であり、性質が異なります。
応用知識:翌債(繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担)
「翌債(よくさい)」とは、国の財政法に基づく高度な財政技術であり、繰越明許費として予算計上された経費について、予算執行上のやむを得ない事由がある場合に、財務大臣(地方公共団体の場合はこれに準ずる手続き)の承認を経て、年度内に翌年度にわたる支出の原因となる契約(債務負担)をすることができる制度です。これは、繰越明許費の執行をより柔軟にするための特例的な措置であり、特に国庫補助事業などにおいて、国の会計手続きと歩調を合わせる必要がある場合に活用されることがあります。
会計検査における指摘事例とその対策
繰越制度は会計年度独立の原則の例外であるため、その運用は会計検査院(地方公共団体においては監査委員)による厳しいチェックの対象となります。特に、繰越が常態化していたり、その理由が不明確であったり、あるいは単なる計画の遅延を糊塗するために安易に事故繰越が用いられたりする事態は、予算統制を形骸化させるものとして厳しく指摘されます。
- 対策:
- 理由の明確化と文書化:
- 繰越を行う際は、なぜ繰越が必要なのか、その客観的な理由を誰が読んでも理解できるように詳細に記録し、決裁文書として残すことが不可欠です。
- 適時適切な手続き:
- 繰越明許費であれば、予測できた段階で速やかに補正予算を編成する、事故繰越であれば、事故の発生後、直ちに所定の手続きに着手するなど、手続きの遅延を避けることが重要です。
- 事故繰越の厳格な適用:
- 安易に「事故」と判断せず、本当に「避け難い」ものであったかを多角的に検証する。少しでも計画の甘さや人為的なミスが原因である可能性がある場合は、事故繰越の適用を躊躇すべきです。
- 理由の明確化と文書化:
先進事例と比較分析:東京都と特別区の動向
東京都における繰越事務の取扱要領と特徴
特別区の財政運営は、東京都との連携や制度的な整合性が求められる場面が多々あります。東京都の財務会計規則では、第25条において、各局長が繰越明許費を繰り越そうとする際には、財務局長が指定する期日までに「繰越見積書」を提出しなければならないと定められています。これは、都全体の財政状況を財務局長が一元的に把握し、調整するための重要な手続きです。特別区においても、区長部局と教育委員会など、組織内の各部署から財政担当部署へ繰越情報を集約し、区全体の財政を統括管理するという点で、同様のガバナンス構造が求められます。
特別区(千代田区・世田谷区等)の予算・決算における繰越事例分析
実際の特別区の予算書や決算書を見ることで、繰越制度がどのように活用されているかを具体的に理解することができます。
- 千代田区の事例:
- 令和6年度の予算審議の記録では、低所得世帯への給付金事業や旧区立住宅の区分所有権取得など、8事業・合計10億円余りの経費について繰越明許費を設定する議案が提出されています。給付金事業のように、国の政策決定を受けて年度末に実施される事業は、繰越明許費の典型的な活用例です。
- 世田谷区の事例:
- 令和4年度の繰越明許費繰越計算書によると、議決額約145億円に対し、実際に約135億円(62件)が繰り越されています。主な内訳として、「本庁舎等整備工事」に約43億円、「新型コロナワクチン住民接種事業」に約25億円などが挙げられており、大規模な建設事業や、社会情勢の変動に左右される事業で繰越が活用されていることがわかります。また、この年度において事故繰越は該当なしとなっており、計画的な予算執行が行われていることが窺えます。
- 練馬区・中野区の内部規則:
- 練馬区や中野区の予算事務・会計事務に関する規則を見ると、繰越手続きにおける担当部署(企画部長など)や提出書類(繰越調書など)、手続きの流れが具体的に定められています。これらの規則は、各区における繰越事務の標準的なプロセスを定めたものであり、自区の規則と他区の規則を比較検討することは、業務改善のヒントにつながります。
財政状況と繰越額の相関分析:計画的執行の指標として
繰越額の規模や内容は、単なる決算上の数字ではなく、その区の財政運営の質を示す重要な指標(KPI)として分析することができます。例えば、毎年度、特定の種類の事業で恒常的に多額の繰越明許費が発生している場合、それは個別の事業の問題ではなく、区の事業計画の策定プロセスや進捗管理体制に構造的な課題がある可能性を示唆しています。また、他区と比較して事故繰越の発生件数や金額が突出して多い場合は、リスク管理体制や契約事務のあり方を見直す必要があるかもしれません。財政課は、これらの繰越データを経年で分析し、その根本原因を探ることで、より計画的で効率的な予算執行を促すための提言を行うという、戦略的な役割を担うことが期待されます。
業務改革とDX:繰越事務の高度化・効率化
繰越事務における課題と費用対効果の考え方
従来の繰越事務は、紙の調書作成、押印のための庁内回覧、各部署への進捗確認の電話連絡など、手作業に依存する部分が多く、非効率な側面がありました。これらの作業は、職員の貴重な時間を奪うだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを誘発するリスクも抱えています。業務改革とDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する目的は、単にITツールを導入することではなく、これらの非効率を解消し、職員がより付加価値の高い分析業務や企画立案業務に集中できる環境を整えることにあります。新潟県三条市が目指す「市民と職員の楽ちん化」のように、テクノロジーを活用して業務負担を軽減し、行政サービス全体の質を向上させるという視点が重要です。
ICT活用による業務効率化
RPAによる繰越調書・計算書作成業務の自動化
RPA(Robotic Process Automation)は、定型的なパソコン操作を自動化する技術です。繰越事務においては、財務会計システムやプロジェクト管理システムから必要なデータ(事業名、予算額、契約額、支出済額など)を抽出し、「繰越調書」や「繰越計算書」の様式に自動で転記する、といった活用が考えられます。これにより、手作業による入力の手間とミスを大幅に削減できます。札幌市や長岡市など、他の自治体業務でRPAが大きな時間削減効果を上げている事例は、繰越事務への応用可能性を示唆しています。
プロジェクト管理ツールを用いた進捗管理と繰越予測
全庁的なプロジェクト管理ツール(例:Backlog, Asanaなど)を導入し、大規模な建設事業やシステム開発案件の進捗を関係部署(事業所管課、契約課、財政課)がリアルタイムで共有できる仕組みを構築します。これにより、財政課は各事業の進捗遅延の兆候を早期に察知し、年度末に慌てて手続きを行うのではなく、早い段階から計画的に繰越明許費の補正予算編成に着手できるようになります。これは、繰越事務の精度と計画性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。
生成AIの活用可能性
近年注目を集める生成AIは、繰越事務の高度化においても大きな可能性を秘めています。
繰越理由書のドラフト自動生成
繰越明許費の予算要求や、事故繰越の決裁伺いに添付する「理由書」の作成は、論理的で分かりやすい文章を作成する必要があり、職員の負担となっています。過去の承認された理由書のデータを学習させた生成AIに、事業の概要や遅延の要因といった要点を入力するだけで、説得力のある理由書のドラフトを瞬時に生成させることが可能です。これにより、文書作成時間を大幅に短縮し、内容の質を標準化することができます。
過去の議会答弁や類似事例の瞬時検索・要約
繰越明許費の予算を議会で説明する際、「過去の類似事業での繰越理由は何か」「この種の事業について議員からどのような質問があったか」といった情報を迅速に把握することが求められます。生成AIを活用すれば、過去の膨大な議事録データの中から関連する質疑応答を瞬時に検索・抽出し、その要点を整理して提示させることができます。これにより、担当者はより深く、的確な答弁準備を行うことが可能となります。
職員向けAIチャットボットによる手続き照会対応
「繰越調書の提出期限はいつですか?」「このケースは事故繰越に該当しますか?」といった、庁内からの定型的な問い合わせに24時間365日対応するAIチャットボットを構築します。このマニュアルや区の内部規則を学習させることで、職員はいつでも気軽に疑問を解消でき、財政課の担当者はより専門的な相談業務に集中することができます。横須賀市の事例のように、AIチャットボットは住民サービスだけでなく、庁内業務の効率化にも有効です。
実践的スキル:計画的な予算執行と繰越の適正化
組織レベルでの取組み:PDCAサイクル
繰越の適正化は、個々の職員の努力だけでなく、組織全体での継続的な改善活動が不可欠です。以下のPDCAサイクルを組織的に回していくことが求められます。
Plan(計画)
予算編成の段階で、特に大規模な投資的経費については、事業所管課に事業工程表と併せてリスク分析シートの提出を義務付けます。「用地買収の難航」「許認可の遅延」「資材価格の高騰」など、想定されるリスクと、それが発生した場合の対応策(繰越明許費への移行判断基準など)をあらかじめ計画に織り込ませます。
Do(実行)
年度が始まったら、主要な事業について、事業所管課と財政課による四半期ごとの進捗確認会議を制度化します。会議では、計画と実績の乖離を確認し、年度内完了に向けた課題を共有します。遅延が顕在化した場合は、その場で繰越明許費の手続きに向けた準備を開始します。
Check(評価)
会計年度終了後、財政課は繰越が発生した全ての事業について、その原因を「①計画・設計要因」「②契約・入札要因」「③施工・管理要因」「④外部環境要因」などに分類・分析した「繰越事業分析報告書」を作成します。繰越を単なる結果として処理するのではなく、その背景にある組織的な課題を可視化します。
Action(改善)
作成した「繰越事業分析報告書」を、次年度の予算編成方針や、事業計画策定の手引きに反映させます。例えば、「②契約・入札要因」での繰越が多発しているなら、契約手続きの見直しや早期発注の徹底を全庁に通達するなど、具体的な改善策に繋げます。
個人レベルでの取組み:PDCAサイクル
組織の仕組みとともに、担当者一人ひとりの意識と行動も重要です。自身の担当事業について、以下のPDCAを実践することが、計画的な予算執行能力の向上につながります。
Plan(計画)
事業を担当する際、まず詳細なマイルストーン(中間目標)を設定した工程表を作成します。どの工程が遅れると全体に影響が出るか(クリティカルパス)を意識し、特に注意すべきポイントを明確にしておきます。
Do(実行)
事業者との打ち合わせ内容、関係機関との協議の経緯など、事業の進捗に関する記録を丁寧に、かつ正確に残します。万が一、繰越が必要となった際に、これらの記録が客観的な状況を説明するための重要な証拠となります。
Check(評価)
「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにせず、マイルストーンの遅れが判明した時点で、直ちに年度内完了への影響を再評価します。少しでも繰越の可能性があると判断した場合は、速やかに上司に報告し、財政課への相談を仰ぎます。早期の報告・連絡・相談が、手遅れを防ぎます。
Action(改善)
担当した事業で繰越が発生した場合、手続きが完了したらそれで終わりにするのではなく、「なぜ繰越が必要になったのか」「もっと早く対応できなかったか」を自ら振り返ります。その経験から得た教訓を、次の事業計画や後輩への指導に活かします。
まとめ:未来の特別区を支える財政課職員として
本研修資料を通じて、繰越明許費と事故繰越という二つの制度について、その法的根拠から具体的な実務、そして未来に向けた業務改革まで、多角的に学んでいただきました。
繰越制度の習熟は、単に会計ルールを覚えることではありません。それは、会計年度独立の原則という財政規律の根幹を守りながら、区民のために計画された事業が、予期せぬ困難に直面しても着実に遂行されるよう、知恵と工夫を凝らす専門的な営みです。繰越明許費の手続きを通じて計画性を担保し、事故繰越の厳格な運用を通じて危機に対応する。この両輪を的確に使い分ける能力は、まさしく財政のプロフェッショナルとしての腕の見せ所と言えるでしょう。
皆様は、日々の伝票処理や予算査定の先に、区民の暮らしを支え、より良い未来を築くという大きな使命を担っています。本資料で得た知識とスキルを自信とし、誇りを持って日々の業務に臨んでください。皆様一人ひとりの着実な仕事が、特別区の健全な財政と、持続可能な行政サービスの提供を支える礎となることを心から期待しています。





-320x180.jpg)

-320x180.jpg)