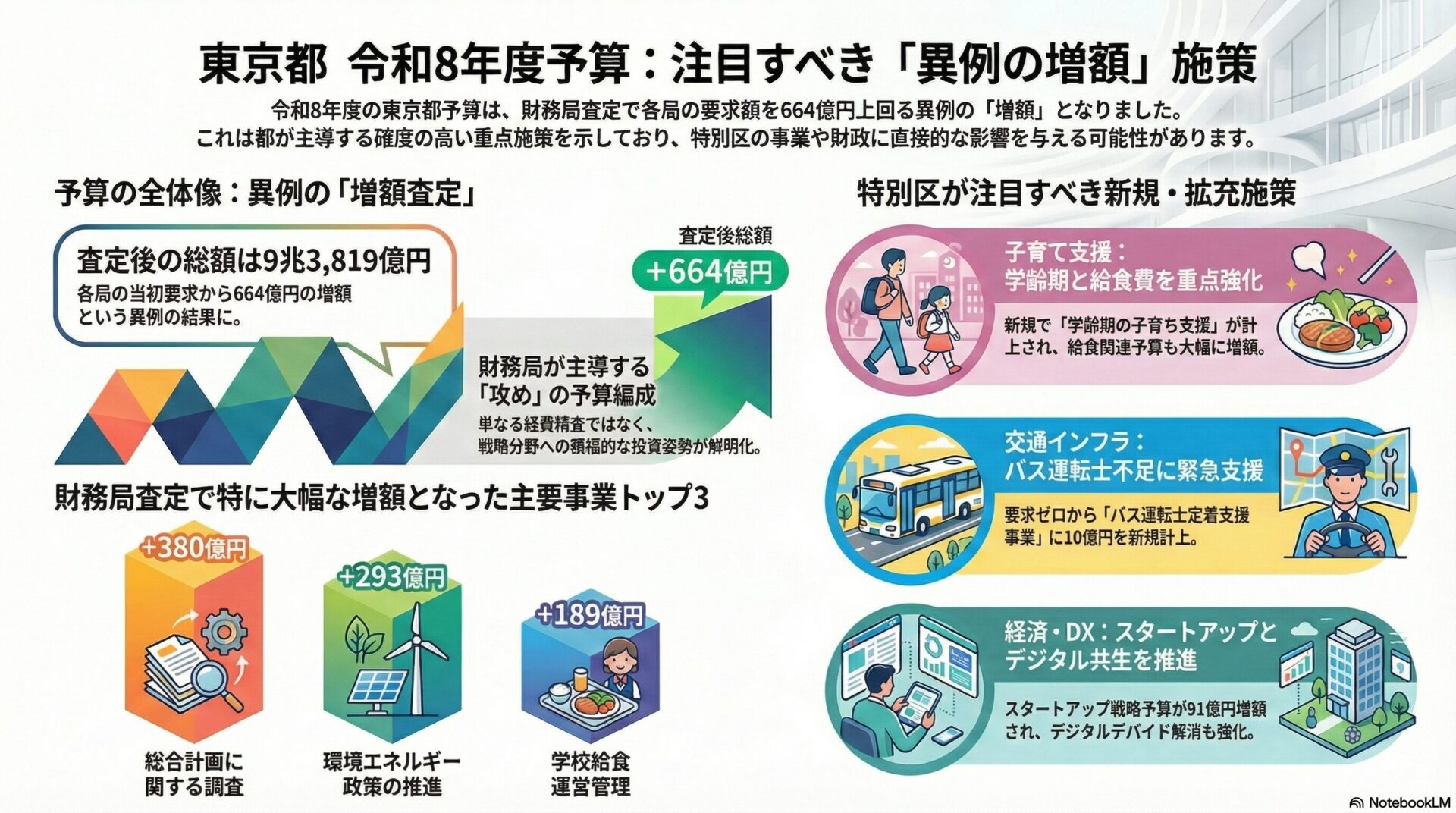【広報課】シティプロモーション業務 完全マニュアル

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
シティプロモーションの基礎知識
業務の意義と目的
シティプロモーションとは、自治体が自らの地域の認知度を高め、その魅力を内外に広く伝えていくための一連の戦略的活動を指します。これは単なる観光PRや情報発信に留まらず、地域再生、観光振興、住民協働といった多様な概念を内包する、自治体経営の根幹に関わる重要な業務です。人口減少や地域間競争が激化する現代において、シティプロモーションは自治体が存続し、持続的に発展していくための不可欠な生存戦略と言えます。
この業務の目的は、大きく二つの側面から構成されています。それは、地域外に向けた「アウタープロモーション」と、地域内に向けた「インナープロモーション」です。
- アウタープロモーション(地域外への働きかけ):
地域外から「ヒト・モノ・カネ」を呼び込むことを主眼とします。具体的には、観光客の誘致、移住・定住者の増加、企業誘致の促進、ふるさと納税の寄付額向上などが挙げられます。これにより、地域経済を活性化させ、税収の増加を通じて住民サービスの向上に必要な財源を確保することが期待されます。 - インナープロモーション(地域内への働きかけ):
地域住民が自らのまちに対して抱く愛着や誇り、すなわち「シビックプライド」を醸成することを目的とします。住民が「このまちに住んでよかった」「これからも住み続けたい」と感じることで、若者世代の人口流出を抑制し、地域の祭りやイベントへの参加を促し、住民満足度を高める効果があります。
ここで極めて重要なのは、シティプロモーションの現代的な潮流が、かつての「シティセールス」という考え方から大きく転換している点です。「シティセールス」という言葉は、時に「自治体を売り込む」という一方的なニュアンスで捉えられがちでした。しかし、現在主流となっている「シティプロモーション」の考え方では、まずインナープロモーションを通じて住民のシビックプライドを育むことが、効果的なアウタープロモーションの絶対的な基盤であると認識されています。なぜなら、自らのまちを愛し、誇りに思う住民こそが、最も信頼性の高い「生きた広告塔」となるからです。行政が発信する情報よりも、そこに住む人々の満足した声や自発的な情報発信の方が、はるかに強い説得力と拡散力を持ちます。したがって、シティプロモーションの本質は、単なるマーケティング活動ではなく、住民と共にまちの価値を創造し、誇りを育む「コミュニティビルディング」そのものであると言えるのです。
歴史的変遷と現代的課題
シティプロモーションという言葉が広く使われるようになったのは比較的最近ですが、その取り組みの源流は1980年代まで遡ることができます。しかし、全国の自治体でこの活動が本格的に活発化したのは、2010年前後とされています。
この時期に活動が急増した背景には、日本の社会構造が直面する深刻な課題、すなわち「人口減少」と「少子高齢化」があります。これらの問題が自治体経営を揺るがす喫緊の課題として顕在化し、各自治体は地域間競争の中で「選ばれる自治体」になるための生存戦略として、シティプロモーションに本格的に乗り出さざるを得なくなったのです。
しかし、多くの自治体が参入した結果、新たな課題も生まれています。
- プロモーションの飽和と差別化の困難(シティプロモーション疲れ):
今やほとんどの自治体がシティプロモーションに取り組んでおり、情報が氾濫しています。その結果、似通った魅力発信が多くなり、他地域との差別化を図ることが極めて困難になっています。受け手の側から見れば、どの情報も同じように見えてしまい、心に響きにくい状況、いわゆる「シティプロモーション疲れ」が指摘されています。 - 効果測定の難しさ:
移住者の増加や観光客数の増加といった最終的な成果(KGI)が、特定のプロモーション活動の直接的な結果であると証明することは容易ではありません。天候、経済情勢、社会のトレンドなど、多くの外部要因が複雑に絡み合うため、投じた予算に対する費用対効果を明確に示すことが難しいという課題があります。 - 住民と来訪者の意識の乖離:
観光客誘致に偏重したプロモーションは、交通渋滞や騒音、マナー問題などを引き起こし、地域住民の生活満足度を低下させるリスクを孕んでいます。住民の理解や共感を得られないプロモーションは、本来目的とすべきシビックプライドの醸成とは逆行する結果を招きかねません。
これらの課題は、シティプロモーションが新たなステージに進化したことを示唆しています。かつてはパンフレットを作成し、イベントを開催するといった「活動」そのものが目的化されがちでした。しかし、現代において求められるのは、データに基づいた現状分析、明確なターゲット設定、独自のブランド構築、そして客観的な効果測定といった一連のプロセスに裏打ちされた「戦略」です。担当職員に求められるスキルも、単なる広報実務の担い手から、データアナリスト、マーケター、ブランドマネージャーといった、より高度で専門的な能力へと変化しているのです。本マニュアルは、そうした現代の要請に応えるための知識と技術を提供することを目的としています。
戦略的シティプロモーションの業務フロー
現状分析と課題抽出
効果的なシティプロモーションは、思いつきのアイデアではなく、客観的な現状分析から始まります。まずは自らの自治体が持つ資産と置かれている状況を正確に把握することが、戦略策定の揺るぎない土台となります。
- 内部環境分析(地域の魅力・資源の棚卸し):
自らが担当する地域の「当たり前」にこそ、価値が眠っています。歴史、文化、自然景観、特産品、産業技術、そして「人」といった、あらゆる地域資源をリストアップし、その価値を再評価します。この際、担当課の職員だけでなく、庁内の他部署の職員や、地域で活動するキーパーソンなどを巻き込み、多角的な視点で洗い出すことが重要です。プロモーションチーム内で、発信すべき魅力の方向性について共通認識を持つことが不可欠です。 - 外部環境分析(機会と脅威の把握):
自らの自治体を取り巻く外部の環境変化を捉えます。近隣の競合自治体がどのようなプロモーションを展開しているか、国や都道府県はどのような観光振興策を打ち出しているか、ワーケーションやマイクロツーリズムといった新しい旅のスタイルがどのように変化しているかなどを分析します。 - 分析フレームワークの活用:
- SWOT分析:
内部環境と外部環境の分析結果を、「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4つのカテゴリーに整理するフレームワークです。これにより、自らの立ち位置が明確になり、「強みを活かして機会を掴む」「弱みを克服して脅威に備える」といった戦略の方向性を見出すことができます。 - 住民・来訪者調査:
行政側の思い込みを排除し、客観的なデータを収集するために、住民や観光客、移住者などを対象としたアンケート調査やヒアリングを実施します。彼らが実際にまちの何に価値を感じ、何に不満を抱いているのか、といった「生の声」は、最も信頼できる情報源となります。
- SWOT分析:
戦略策定:ターゲットとコンセプトの設定
現状分析で得られた客観的なデータに基づき、プロモーション戦略の核となる「誰に」「何を」伝えるかを決定します。
- 目的(KGI)の明確化:
戦略策定において最も重要なことは、「何をもって成功とするか」という最終目標(KGI: Key Goal Indicator)を具体的かつ定量的に設定することです。「地域を元気にする」といった曖昧な目標ではなく、「3年後までに30代の子育て世代の転入者数を$10%増加させる」「ふるさと納税寄付額を前年比20%$アップさせる」のように、誰もが達成度を判断できる明確なゴールを掲げます。このゴールがなければ、施策の評価も改善もできません。 - ターゲットの具体化:
「すべての人」に向けたメッセージは、結局「誰の心にも響かない」メッセージに終わります。プロモーションの効果を最大化するためには、情報を届けたい相手(ターゲットオーディエンス)を具体的に絞り込む必要があります。「首都圏在住で、地方移住に関心のある30代のITエンジニア」「歴史や文化に関心が高い台湾からの個人旅行客」といったように、ペルソナ(具体的な人物像)を描けるレベルまで具体化することが理想です。千葉県流山市が「30代から40代前半の子育て世帯」を明確なターゲットに設定し、「母になるなら、流山市。」という強力なメッセージで成功を収めた例は、ターゲット設定の重要性を示しています。 - ブランドコンセプトの策定:
ターゲットに対して、自らの自治体が提供できる独自の価値を、一貫性のある魅力的な物語として言語化したものがブランドコンセプトです。これは、他の自治体との差別化を図り、「なぜ、他のどこでもなく、このまちを選ぶべきなのか」という問いに答える、プロモーション活動全体の背骨となります。コンセプトは、ロゴマークやキャッチフレーズ、ウェブサイトのデザイン、イベントの企画など、すべての情報発信のトーン&マナーを規定する指針となります。
実行計画とKPI設定
策定した戦略を絵に描いた餅で終わらせないために、具体的な行動計画へと落とし込み、その進捗を客観的に測定する仕組みを構築します。
- アクションプランの策定:
戦略を実現するための具体的な事業(アクション)を洗い出します。SNSキャンペーンの実施、プロモーション動画の制作、移住体験ツアーの企画など、各事業の目的、内容、担当者、スケジュール、予算を明確にした実行計画を作成します。 - KPI(重要業績評価指標)の設定:
シティプロモーションの「効果が見えづらい」という課題を克服するために、KPI(Key Performance Indicator)の設定が不可欠です。KPIとは、最終目標であるKGIの達成に向けたプロセスが順調に進んでいるかを測るための中間指標です。 行政の現場では、しばしば「パンフレットを何部作成したか」「イベントを何回開催したか」といった「アウトプット(活動量)」が成果として報告されがちです。しかし、本当に重要なのは、それらの活動によって「住民の意識や行動がどう変化したか」という「アウトカム(成果)」です。KPIフレームワークを導入することは、単に活動量を報告するだけの自己満足から脱却し、真の成果を追求する組織文化への転換を促します。KPIを通じて活動の成果を客観的なデータで示すことができれば、予算要求や事業継続の説明責任を果たすことが可能となり、広報部門は単なるコストセンターではなく、自治体経営に貢献する戦略部門へと進化することができるのです。
以下に、目的別のKPI設定のフレームワーク例を示します。自らの自治体の状況に合わせてカスタマイズし、活用してください。
| KGI(最終目標) | ターゲット | KSF(重要成功要因) | KPI(重要業績評価指標)の例 |
| 移住者数$10%$増 | 30代の子育て世帯 | 「子育てしやすい街」としての認知度No.1獲得 | – 移住相談窓口への問い合わせ件数 – 公式サイト「子育て支援ページ」のPV数 – SNSでの「#〇〇市で子育て」投稿数 – ターゲット層における市の認知度・好感度調査スコア |
| 観光消費額$20%$増 | 首都圏在住の20代女性 | 「フォトジェニックな週末旅」のデスティネーション化 | – Instagramでの指定ハッシュタグ投稿数 – 観光情報サイト特集記事から予約サイトへの送客率(CVR) – 市内カフェ・雑貨店等の売上データ(連携先) – 観光客アンケートにおける平均滞在時間・消費額 |
| シビックプライド指数15ポイント向上 | 全住民 | 住民が地域の魅力を再認識し、自ら発信する機会の創出 | – 市民意識調査における「市に誇りを感じる」と回答した割合 – 市民参加型イベントの参加者数・満足度 – 市民発の情報発信量(ブログ、SNS投稿等)のモニタリング結果 – 住民推奨度(NPS)スコア |
法的根拠と関連法規
地方自治法における位置づけ
シティプロモーションは、「シティプロモーション法」といった個別の法律によって直接規定されているわけではありません。その活動の根拠は、地方自治の基本法である地方自治法の解釈によって支えられています。自治体職員として、自らの業務の正当性を理解し、説明責任を果たすために、これらの法的根拠を正しく認識しておくことが重要です。
- 包括的な事務処理権(地方自治法第2条第2項):
地方自治法第2条第2項は、「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」と定めています。この「地域における事務」は非常に広範な概念であり、法律で禁止または他の行政主体に限定されていない限り、地域の発展と住民福祉の向上のために必要な事務を、自治体が自主的に行うことができると解釈されています。シティプロモーションは、地域の経済を活性化させ、定住人口を確保し、コミュニティの活力を維持・向上させる活動であり、まさにこの「地域における事務」の典型例と位置づけられます。 - 住民福祉の増進(地方自治法第1条の2):
同法第1条の2では、地方公共団体の役割を「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」と規定しています。税収の安定化による行政サービスの維持、雇用の創出、住民の地域への愛着心の醸成といったシティプロモーションがもたらす効果は、すべて「住民の福祉の増進」に直結します。したがって、シティプロモーションは地方自治体の根源的な目的に合致した正当な行政活動です。 - 条例制定権(地方自治法第14条):
自治体は、法令に違反しない範囲で、その事務に関して条例を制定する権限を持っています。これに基づき、シティプロモーションに関する基本理念や推進体制を定めた条例を制定したり、総合計画の中に戦略を明確に位置づけたりすることで、属人的な取り組みではなく、全庁的かつ継続的な公式の取り組みとして推進するための法的基盤を固めることができます。
関連条例とガイドライン
地方自治法という大きな傘の下で、各自治体はより具体的な計画やルールを定めることで、シティプロモーションを体系的に推進しています。
- 総合計画との連携:
シティプロモーション戦略は、自治体経営の最上位計画である「総合計画」に示された将来像や基本目標を実現するための具体的な手段として位置づけられることが一般的です。総合計画との整合性を図ることで、プロモーション活動に一貫性が生まれ、予算確保や他部署との連携が格段に進めやすくなります。 - シティプロモーションガイドラインの策定:
多くの先進自治体では、プロモーション活動の品質と一貫性を担保するために、独自の「シティプロモーションガイドライン」を策定しています。これは、庁内職員や外部の協力事業者がプロモーション活動を行う際の「共通の教科書」となるものです。 ガイドラインには通常、以下のような内容が盛り込まれます。- 定義と目的:
自治体独自のシティプロモーションの定義や目指す姿。 - ブランドコンセプト:
キャッチフレーズやステートメント、ブランドロゴの使用規定など。 - 推進体制:
「ALL〇〇(自治体名)体制」を掲げ、広報課だけでなく全職員、さらには市民や事業者一人ひとりがプロモーションの担い手であることを宣言。 - 情報発信の基本姿勢:
ターゲットを意識した情報発信の考え方や、インナープロモーションとアウタープロモーションの連動についての指針。
- 定義と目的:
以下に、シティプロモーション業務の法的根拠を整理した表を示します。予算説明や議会答弁など、様々な場面でご活用ください。
| 法令・計画 | 関連条文・位置づけ | 概要 | 実務上の意義 |
| 地方自治法 | 第2条第2項 | 普通地方公共団体は、地域における事務を処理する。 | シティプロモーションが、地域の活性化や住民福祉の向上に資する「地域における事務」として正当な行政活動であることを示す根拠となる。 |
| 地方自治法 | 第1条の2 | 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本とする。 | 住民の定住促進や地域経済の活性化は「住民の福祉の増進」に直結するため、シティプロモーションの目的そのものが法の理念に合致していることを示す。 |
| 地方自治法 | 第14条 | 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができる。 | 自治体独自のシティプロモーション戦略やブランドコンセプトを条例や計画として正式に位置づけ、全庁的な取り組みとするための法的根拠となる。 |
| 各自治体の総合計画 | 個別計画 | 自治体運営の最上位計画。将来像や基本目標を定める。 | シティプロモーション戦略を総合計画の個別施策として位置づけることで、活動の正当性を高め、予算確保や他部署との連携を円滑にする。 |
プロモーション手法の実践詳解
オウンドメディアとSNSの戦略的活用
現代のシティプロモーションにおいて、デジタルメディアの活用は不可欠です。特に、自らが管理・運営する「オウンドメディア(Owned Media)」と、拡散力に優れた「SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)」は、戦略の根幹をなす重要なツールです。これらを効果的に組み合わせることで、低コストでターゲットに直接情報を届け、継続的な関係を築くことが可能になります。
- オウンドメディアの役割と構築:
- オウンドメディア(自治体公式ウェブサイト、特設プロモーションサイト、公式ブログなど)は、情報発信の「基地」です。断片的な情報が流れやすいSNSとは異なり、地域の魅力を体系的かつ詳細に伝え、信頼性の高い情報を蓄積する役割を担います。観光、移住、子育て支援、産業など、テーマごとに整理された質の高いコンテンツは、検索エンジン経由での安定したアクセスを生み出し、長期的な資産となります。
- 構築のポイント:
- ターゲット視点のコンテンツ設計:
行政が発信したい情報だけを並べるのではなく、ターゲットが「知りたい」「役に立つ」と感じるコンテンツを企画します。例えば、移住希望者向けには、スーパーや病院の場所、家賃相場、先輩移住者のインタビューといった生活に密着した情報が求められます。 - 定期的な更新:
常に新しい情報が提供されることで、再訪を促し、ファンを育成します。 - 多様な表現:
テキストだけでなく、写真や動画、インフォグラフィックなどを活用し、視覚的に魅力を伝えます。日本政府観光局(JNTO)の「Japan’s Local Treasures」は、動画や美しい写真で地域の魅力を海外に発信する優れた事例です。
- ターゲット視点のコンテンツ設計:
- SNSの特性とプラットフォームの使い分け:
SNSは、オウンドメディアで作成したコンテンツを拡散させ、ターゲットとの双方向コミュニケーションを図るための「拡声器」です。各プラットフォームの特性を理解し、戦略的に使い分けることが重要です。- X(旧Twitter):
リアルタイム性と拡散力に優れています。イベントの告知や災害時の緊急情報発信、住民からの問い合わせへの迅速な対応などに適しています。シャープ株式会社の公式アカウントのように、親しみやすいキャラクターでユーザーと積極的に交流し、ファンを増やす戦略も有効です。 - Instagram:
写真や動画といったビジュアルでの訴求力が非常に高いプラットフォームです。美しい風景、美味しそうなグルメ、おしゃれなカフェなど、「フォトジェニック」な魅力を発信するのに最適です。ハッシュタグ(例: #〇〇市の絶景)を活用することで、同じ興味を持つユーザーに情報を届けることができます。 - Facebook:
実名登録が基本で、比較的高い年齢層の利用者が多いのが特徴です。地域コミュニティの醸成や、詳細な情報を含むイベントページの作成、ターゲットを絞った広告配信などに強みがあります。 - TikTok:
10代〜20代の若年層に絶大な人気を誇るショート動画プラットフォームです。地域の魅力をリズミカルな音楽に乗せて紹介したり、ダンスチャレンジ企画を実施したりすることで、若者世代にリーチできます。江崎グリコの「ポッキーの日」キャンペーンのように、インフルエンサーを起用した企画も効果的です。 - YouTube:
より長い時間で、物語性のある情報を伝えるのに適しています。地域の伝統文化のドキュメンタリー、移住者の一日を追ったVlog、ドローンで撮影した絶景映像など、深く魅力を伝えるコンテンツを発信できます。
- X(旧Twitter):
- 連携戦略(オウンドメディア + SNS):
オウンドメディアとSNSは、それぞれ単独で使うのではなく、連携させることで相乗効果が生まれます。基本的な流れは、「①オウンドメディアで質の高い詳細なコンテンツ(記事や動画)を作成 → ②SNSでそのコンテンツの魅力を要約して発信し、オウンドメディアへ誘導 → ③SNS上でユーザーと交流し、ファンを育成 → ④ファンになったユーザーが自発的に情報を拡散(UGC: User Generated Contentの創出)」というサイクルです。この好循環を生み出すことが、デジタルプロモーション成功の鍵となります。
メディアリレーションズとプレスリリース
テレビ、新聞、雑誌、ウェブニュースといったマスメディアに取り上げられることは、第三者の客観的な視点を通じて情報を発信できるため、極めて高い信頼性と広範なリーチを獲得できる強力なプロモーション手法です。これを実現するための活動が「メディアリレーションズ」であり、その中心的なツールが「プレスリリース」です。
- メディアリレーションズの重要性:
メディアリレーションズとは、報道機関の記者や編集者と良好な関係を築き、維持していく活動全般を指します。これは単なる情報提供に留まりません。日頃から地域の情報や面白いネタを提供し、記者が記事を書きやすいように協力することで、「〇〇市の情報なら信頼できる」というパートナーとしての関係を構築することが目的です。神奈川県相模原市のように、定期的にメディア向けイベントを開催し、記者との交流を深める取り組みも有効です。 - プレスリリースの基本構成:
プレスリリースは、メディアに記事化してもらうための「公式な案内状」です。記者が多忙な中でも内容を瞬時に理解し、記事化の判断ができるよう、簡潔で分かりやすい構成が求められます。- 発信日・発信者:
いつ、誰が発信した情報かを明記します。 - タイトル:
最も重要な要素です。30文字前後で、ニュースの核心が最も魅力的に伝わるように工夫します。 - リード文:
プレスリリースの要約です。「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」を簡潔にまとめます。 - 本文:
リード文の内容を補足し、背景や社会的意義、独自性などを詳しく説明します。専門用語は避け、誰が読んでも理解できる平易な言葉で記述します。 - 画像・動画:
視覚的なインパクトは絶大です。高解像度の写真や動画を必ず添付します。 - 問い合わせ先:
担当部署、担当者名、電話番号、メールアドレスを明記します。担当者は2名体制にしておくと、確実な対応が可能です。
- 発信日・発信者:
- 記者の目に留まるプレスリリースのポイント:
毎日大量のプレスリリースを受け取る記者の関心を引くためには、単なる「お知らせ」ではなく、「ニュース価値」のある情報として提供する必要があります。- 社会性・時事性:
「SDGsへの貢献」「DX推進」「コロナ禍からの回復」など、世の中の関心事やトレンドと関連付けることで、ニュースとしての価値が高まります。 - 新規性・独自性:
「全国初」「県内唯一」といった新規性や、他にはないユニークな取り組みであることを強調します。 - 具体的なデータ・数字:
「観光客数が前年比$20\%$増加」「満足度$95\%$」のように、客観的な数字を用いることで信頼性が増します。 - ストーリー性:
なぜこの取り組みを始めたのか、どのような困難があったのか、といった背景にある物語を伝えることで、記者の共感を呼び、読者の心に響く記事につながります。
- 社会性・時事性:
イベント・MICEの企画と運営
イベントは、地域の魅力を五感で体験してもらい、人々の交流を生み出す強力なプロモーション手法です。特に、ビジネスイベントの総称であるMICEの誘致・開催は、大きな経済効果と都市のブランドイメージ向上に繋がるため、近年注目されています。
- イベント企画の基本フロー:
- 目的とターゲットの明確化:
「何を達成するために、誰を集めるイベントなのか」を最初に定義します。例えば、「子育て世代の移住関心層に、本市の教育環境の魅力を伝える」など。 - コンセプトとコンテンツの決定:
目的に沿ったイベントのコンセプト(例: 「親子で楽しむサイエンスフェスティバル」)を定め、具体的なプログラム(講演、ワークショップ、展示など)を企画します。 - 計画立案:
日時、会場、予算、集客方法、運営体制などを具体的に計画します。 - 広報・集客:
プレスリリース、SNS、ウェブサイト、チラシなど、ターゲットに合わせた媒体で告知を行います。 - 運営準備:
会場設営、備品手配、スタッフ配置、マニュアル作成など、当日に向けた準備を進めます。 - 当日運営:
マニュアルに基づき、参加者が安全かつ快適に過ごせるよう運営します。 - 事後評価:
アンケートや参加者数、メディア掲載数などから効果を測定し、次回の改善に繋げます。
- 目的とターゲットの明確化:
- 運営マニュアルの重要性と記載項目:
イベントを成功させるためには、関係者全員が同じ情報を共有し、スムーズに連携できるための「運営マニュアル」が不可欠です。マニュアルは、当日の混乱を防ぎ、トラブル発生時にも迅速に対応するための生命線です。- 記載すべき主要項目:
- イベント概要:
イベント名、目的、日時、会場、主催者、ターゲット層などの基本情報。 - 運営体制:
責任者、各チームのリーダー、担当業務、連絡先を網羅した組織図と連絡網。 - タイムテーブル:
設営開始から完全撤収までの詳細なスケジュールを分単位で記載。 - 会場レイアウト図:
受付、ステージ、各ブース、控室、救護室、トイレなどの配置を図示。 - 業務内容一覧:
各担当(受付、誘導、ステージ進行、広報など)の具体的な作業手順と注意点。 - トラブル対応:
急病人、火災、地震、クレームなど、想定されるトラブルへの対応フローと緊急連絡先。 - 備品リスト:
必要となる全ての備品とその数量、管理担当者を記載したチェックリスト。
- イベント概要:
- 記載すべき主要項目:
- MICE誘致の意義とアプローチ:
- MICEとは:
Meeting(企業等の会議)、Incentive Travel(報奨・研修旅行)、Convention(国際会議)、Exhibition/Event(展示会・見本市)の頭文字を取った造語です。 - 意義:
MICEで訪れるビジネスパーソンは、一般の観光客に比べて滞在期間が長く、消費額も大きい傾向にあります。また、会議や展示会を通じて地域の産業や文化に触れることで、将来的なビジネス展開や再訪に繋がる可能性も高く、地域経済への波及効果が非常に大きいのが特徴です。デンマークのコペンハーゲンでは、戦略的なMICE誘致により、国際会議の件数を10年余りで倍増させることに成功しています。 - アプローチ:
MICE誘致は、コンベンションビューローなどの専門機関や旅行会社と連携して行われることが一般的です。地域の強み(例: 特定の産業集積、ユニークな文化体験、交通の便)をアピールし、学会や企業に対して開催地としての魅力を売り込みます。
- MICEとは:
公民連携と市民協働の推進
行政だけのリソースには限界があります。シティプロモーションの効果を最大化し、持続可能なものにするためには、民間企業や団体、そして何よりも市民を巻き込んだ「公民連携(Public-Private Partnership)」と「市民協働」が不可欠です。
- 公民連携のパターンとメリット:
行政と民間事業者が互いの強みを持ち寄り、共通の目的のために協力する関係です。- 連携パターン:
- 包括連携協定:
特定の事業分野に限らず、まちづくり全般に関して企業や大学、金融機関などと包括的な連携協定を締結する。これにより、多岐にわたる分野で継続的な協力関係を築けます。 - 事業ごとの連携:
イベントの共同開催(例: 音楽フェス)、プロモーションコンテンツの共同制作(例: 観光PR動画)、特産品の共同開発など、特定のプロジェクト単位で連携します。 - ネーミングライツ:
公共施設に企業名や商品名を付与する権利を販売し、新たな財源を確保するとともに、企業のPRにも貢献します。
- 包括連携協定:
- メリット:
行政にはない民間のノウハウ、資金、ネットワーク、スピード感を活用できます。また、企業にとっては地域貢献(CSR)活動となり、ブランドイメージの向上に繋がります。
- 連携パターン:
- 市民協働の重要性:
市民はプロモーションの「受け手」であると同時に、最も重要な「担い手」です。市民が自らのまちの魅力に気づき、自発的に情報発信や地域活動に参加するようになると、プロモーションは行政の手を離れて自律的に展開していきます。これを「自走するシティプロモーション」と呼びます。郷土愛は、行政から与えられるよりも、自らが発信し、行動する中で育まれるものです。- 福井県鯖江市の「鯖江市役所JK課」:
地元の女子高生(JK)が主体となり、アプリ開発やイベント企画などを行うプロジェクトです。若者自身の視点でまちの魅力を発掘・発信することで、多くの共感を呼び、参加した高校生が卒業後も地域に定着するという成果を生んでいます。これは、市民協働が人口流出抑制にも繋がることを示す画期的な事例です。
- 福井県鯖江市の「鯖江市役所JK課」:
- 連携・協働を促進するための仕組みづくり:
- ワンストップ窓口の設置:
民間企業や市民が連携の提案をしやすいように、専門の相談窓口(例: 大阪府羽曳野市の「公民協創デスク」)を設置します。 - プラットフォームの構築:
地域の課題と、それに関わりたい企業や市民をマッチングするウェブサイトや交流イベントを企画します。 - 補助金・助成金制度:
市民や団体が主体となって行うプロモーション活動や地域活性化の取り組みに対して、資金的な支援を行います。川崎市の「都市ブランド推進事業」は、市民団体の活動を支援する好例です。 - 情報共有と表彰:
連携・協働の成功事例を広報紙やウェブサイトで積極的に紹介し、優れた活動を行った団体や個人を表彰することで、参加へのインセンティブを高めます。
- ワンストップ窓口の設置:
応用知識と特殊ケースへの対応
「関係人口」の創出と拡大
シティプロモーションの対象は、「定住人口(住民)」と「交流人口(観光客)」だけではありません。近年、この二つの中間に位置する「関係人口」という概念が極めて重要視されています。
- 関係人口の定義:
関係人口とは、移住には至らないものの、特定の地域に継続的に多様な形で関わる人々を指します。具体的には、ふるさと納税の寄付者、特定の地域に繰り返し訪れるファン、地域産品の購入者、副業やボランティアで地域プロジェクトに参加する人などが含まれます。 - なぜ関係人口が重要なのか:
人口減少社会において、全ての自治体が移住者を増やし続けることには限界があります。関係人口は、移住のハードルを越えられない都市部の人々が地域と関わるための、新しい選択肢です。彼らは地域に新たな視点やスキルをもたらし、地域産品を消費することで経済を支え、SNS等で魅力を発信してくれる強力な「応援団」となります。また、関係人口の中から将来の移住者が生まれる可能性も高く、移住・定住に向けた重要なステップと位置づけられています。 - 関係人口を創出・拡大するための具体的な取り組み:
関係人口を増やすには、一度きりの訪問で終わらせず、継続的な関わりを持つための「きっかけ」と「仕組み」を提供することが重要です。 - 体験プログラムの提供:
- ワーケーション:
都市部の企業や個人を対象に、地域の魅力を楽しみながら仕事ができる環境を提供します。長期滞在を通じて、地域住民との交流が生まれやすくなります。 - お試し移住・週末移住:
空き家などを活用し、短期間の地域暮らしを体験できるプログラムを提供します。福井県美浜町では、移住体験施設を整備し、移住希望者を積極的に受け入れています。 - テーマ型体験:
農業体験(奈良県明日香村「あすかオーナー制度」)、伝統工芸体験、地域課題解決ワークショップ(福井県若狭町「なりわいビジネスカレッジ」)など、参加者の興味関心に合わせた多様なプログラムを用意します。 - ファンコミュニティの形成:
- ふるさと住民制度:
香川県三木町のように、「ふるさと住民カード」を発行し、会報誌の送付や特典を提供することで、継続的なつながりを維持します。 - オンラインサロン・ファンクラブ:
SNSや専用サイトを活用し、地域ファンが集うオンラインコミュニティを運営します。愛媛県西条市の「Love Saijoファンクラブ」は良い事例です。
- ふるさと住民制度:
- 多様な関わり方の提示:
- ふるさと納税:
単なる寄付ではなく、寄付者を地域の応援団と位置づけ、活動報告会や現地視察会などを開催し、関係を深化させます。北海道上士幌町は、ふるさと納税をきっかけに関係人口を増やした代表例です。 - ボランティア・プロボノ募集:
瀬戸内国際芸術祭のサポーター「こえび隊」のように、イベント運営や専門スキルを活かしたプロボノ(専門家によるボランティア)を募集し、地域貢献の機会を提供します。 - 地域商社・ECサイト:
地域の特産品を販売するECサイトを運営し、購入を通じて地域を応援する仕組みを作ります。
- ふるさと納税:
- ワーケーション:
インバウンド向けプロモーション
訪日外国人観光客(インバウンド)の誘致は、地域経済に大きなインパクトを与える重要なプロモーション分野です。国内観光客とは異なるニーズや情報収集の方法を理解し、戦略的にアプローチする必要があります。
- ターゲット国・地域の選定:
全世界を対象とするのではなく、地理的な近さ、交通アクセスの良さ、親和性の高さなどを考慮し、ターゲットとする国・地域を絞り込むことが効果的です。例えば、台湾や香港、韓国、東南アジア諸国などが主要なターゲットとなり得ます。 - インバウンドに響く魅力の磨き上げ:
- 「コト消費」への対応:
モノの購入だけでなく、その地域でしかできない体験(コト消費)へのニーズが非常に高まっています。伝統文化体験(着物、茶道)、アニメ・マンガの聖地巡礼、自然アクティビティ(スキー、ダイビング)、食文化体験(酒蔵見学、寿司握り体験)など、地域の資源を体験型コンテンツとして造成することが重要です。 - 高付加価値化:
和歌山県高野山や長崎県佐世保市のように、VRやARといったデジタル技術を活用し、文化遺産や自然景観の魅力をより深く、多言語で伝えることで、体験の付加価値を高める取り組みも進んでいます。 - ストーリーテリング:
単に場所を紹介するのではなく、その背景にある歴史や物語を伝えることで、訪問者の興味と理解を深めます。世界遺産・熊野古道を核とした和歌山県田辺市の着地型観光は、ストーリー性を重視した成功事例です。
- 「コト消費」への対応:
- 効果的な情報発信とプロモーション手法:
- 多言語対応:
公式ウェブサイト、パンフレット、観光案内板、施設内の表示などを、ターゲットの言語(最低でも英語、できれば中国語・韓国語など)に対応させることは必須です。 - 海外向けウェブメディア・SNSの活用:
ターゲット国でよく利用されている旅行サイトやSNSプラットフォームを活用します。特に中華圏では、口コミサイト「大衆点評」やライフスタイル共有アプリ「小紅書(RED)」での情報発信が極めて有効です。 - 海外の旅行博・商談会への出展:
現地の旅行会社やメディアに直接魅力を売り込むための重要な機会です。「ツーリズムEXPOジャパン」のような国内で開催される国際的なイベントへの出展も効果的です。 - 海外OTA(Online Travel Agent)との連携:
ExpediaやBooking.comといった海外のオンライン旅行予約サイトに地域の宿泊施設や体験プログラムを掲載し、予約の利便性を高めます。 - インフルエンサーの招聘:
ターゲット国で影響力のあるインフルエンサーを地域に招待し、その体験をSNSなどで発信してもらうことで、現地の言葉でリアルな魅力を届けることができます。
- 多言語対応:
- 受け入れ環境の整備:
プロモーションと並行して、訪日客が快適に過ごせる環境を整備することが不可欠です。- キャッシュレス決済の導入:
クレジットカードやモバイル決済(Alipay, WeChat Payなど)への対応。 - 無料Wi-Fi環境の整備:
主要な駅、観光施設、商店街などでのアクセスポイント設置。 - 交通の利便性向上:
多言語対応の交通案内や、観光地を巡る周遊バスの運行など。
- キャッシュレス決済の導入:
危機管理広報の要点
シティプロモーションは常に順風満帆とは限りません。自然災害、事件・事故、不祥事、SNSでの炎上など、予期せぬ危機が発生した際に、いかに迅速かつ誠実に対応するかで、その後の信頼回復が大きく左右されます。危機管理広報は、ダメージを最小限に食い止め、住民や関係者の不安を払拭するための重要な業務です。
- 平時からの備え(クライシス・マネジメント):
危機は突然訪れます。平時から備えておくべきこと。- リスクの洗い出しとシナリオ策定:
自治体で起こりうる危機(自然災害、情報漏洩、職員の不祥事、イベントでの事故など)を想定し、それぞれの対応シナリオを準備しておきます。 - 危機管理広報マニュアルの作成:
危機発生時の情報収集ルート、指揮命令系統、広報対応の責任者、情報発信の基準(何を、いつ、誰が、どの媒体で発表するか)、記者会見の設営手順などを定めたマニュアルを整備します。 - 緊急連絡網の整備:
首長、関係部署、広報担当者間の緊急連絡網を常に最新の状態に保ちます。 - メディアリレーションズ:
平時からメディアと良好な関係を築いておくことで、危機発生時に正確な情報を迅速に伝達しやすくなります。
- リスクの洗い出しとシナリオ策定:
- 危機発生時の対応(クライシス・コミュニケーション):
実際に危機が発生した場合の行動原則。- 迅速性(Speed):
第一報は可能な限り迅速に行います。情報が錯綜する中で行政が沈黙していると、憶測やデマが拡散し、事態を悪化させます。 - 一元性(Single Voice):
情報は必ず公式発表として、広報部門や危機管理部門から一元的に発信します。各部署がバラバラに情報を出すと、内容の矛盾が生じ、混乱を招きます。 - 誠実性(Sincerity):
事実を隠蔽したり、矮小化したりせず、判明している事実を誠実に伝えます。不明な点は「現在調査中」と正直に述べ、進展があり次第報告することを約束します。被害者や関係者への配慮とお詫びの表明も不可欠です。 - 共感性(Sympathy):
特に住民が被害を受けている場合、行政手続きのような冷たい言葉ではなく、住民の不安や悲しみに寄り添う姿勢を示すことが重要です。
- 迅速性(Speed):
- SNS時代の危機管理広報における注意点:
- 炎上への対応:
不適切な投稿(差別的表現、誤情報、個人情報漏洩など)による炎上が発生した場合、速やかに事実関係を確認し、謝罪と投稿の削除を行います。外部委託業者による投稿であっても、最終的な責任は自治体にあります。言い訳や責任転嫁はさらなる炎上を招きます。 - デマ・フェイクニュースへの対処:
特に災害時には、悪意のあるデマや救助を装った偽情報がSNSで拡散されることがあります。公式アカウントを通じて、正確な情報を繰り返し発信し、デマに対しては明確に否定することが重要です。 - アカウントの管理徹底:
公式アカウントと個人アカウントの誤投稿(いわゆる「誤爆」)は、組織の信頼を著しく損ないます。複数人によるチェック体制を構築するなど、運用ルールを徹底する必要があります。
- 炎上への対応:
先進事例の比較分析
東京都と特別区の先進的取組
日本の首都である東京都、特にその中心をなす特別区(23区)は、シティプロモーションの最前線であり、他の自治体が学ぶべき先進的な取り組みの宝庫です。ここでは、特徴的な戦略を持つ3つの区を比較分析します。
- 足立区:インナープロモーションによるイメージ変革
- 戦略の核心:
足立区のシティプロモーションは、当初から一貫して「区内・区民向け(インナープロモーション)」に重点を置いてきた点が最大の特徴です。かつて「治安が悪い」といったネガティブなイメージに悩まされていた同区は、まず区民自身が区の本当の姿を知り、誇りを持てるようになることがイメージ変革の第一歩だと考えました。 - 具体的な取り組み:
「伝わる」広報への徹底的な改革が核となっています。行政が作成するチラシやポスターのデザイン、言葉遣いを「住民目線」で改善する地道な取り組みを全庁的に展開。治安、学力、健康といった課題解決の成果を、分かりやすく効果的に区民に伝え続けました。この結果、区民の「足立区を誇りに思う」割合は10年間で約$30%から50%$超へと劇的に向上しました。このインナープロモーションの成功が、シティプロモーションアワード金賞受賞という外部評価にも繋がっています。 - 示唆:
シティプロモーションは、派手な対外PRだけではないこと、行政の日常業務である「情報伝達」そのものを磨き上げることが、住民の信頼と誇りを醸成する最も確実な道であることを示しています。
- 戦略の核心:
- 渋谷区:「公民共創」による国際都市ブランディング
- 戦略の核心:
渋谷区は「ちがいを ちからに 変える街。」という基本構想を掲げ、多様性(ダイバーシティ)と公民の共創をシティプロモーションの原動力としています。行政が主導するのではなく、企業、大学、NPO、そしてクリエイティブな個人といった多様な主体が混ざり合うことで生まれるイノベーションこそが渋谷の魅力であると定義しています。 - 具体的な取り組み:
産官学民共創組織「一般社団法人渋谷国際都市共創機構(Shibuya Innovation Institute)」を設立し、スタートアップ支援や社会課題解決プロジェクトを推進。また、ハロウィーン時の来街者抑制のように、時には「来ないでください」という強いメッセージを発信し、観光の「量」よりも「質」や住民の安全・安心を優先する姿勢を示すことで、都市のブランド価値を管理・向上させています。産業・観光ビジョンでは、ビジネスと文化・エンタテイメントの融合による、国際競争力のある都市づくりを目指しています。 - 示唆:
地域の特性を最大限に活かし、行政は「主役」ではなく、多様なプレイヤーが活躍するための「プラットフォーム」としての役割に徹することで、予測不能な化学反応を生み出し、都市の魅力を進化させ続けることができるというモデルを示しています。
- 戦略の核心:
- 港区:多彩な魅力の編集とグローバルな発信
- 戦略の核心:
港区は、ビジネス、文化、自然、歴史、国際性といった極めて多様で質の高い地域資源を持つ都心区です。そのプロモーション戦略は、これらの多彩な魅力を「6つの都市イメージ」として再編集し、国内外の幅広いターゲットに向けて戦略的に発信することに主眼が置かれています。 - 具体的な取り組み:
区の広報戦略では、区民生活の向上を第一に、区民ニーズを的確に捉えた「伝わる広報」を目指しています。区報のリニューアル、ウェブアクセシビリティの向上、SNSの戦略的活用(LINE、X、YouTube)などを通じて、情報伝達の最適化を図っています。また、地域活動協議会の広報活動支援など、住民による情報発信も後押ししています。プロモーション活動は、地方創生を掲げる民間企業とも連携して行われています。 - 示唆:
元々多くの魅力を持つ地域であっても、それをただ羅列するのではなく、ターゲットに響くよう戦略的に「編集」し、最適なメディアを通じて届けることの重要性を示しています。広報の基本である「誰に、何を、どう伝えるか」を地道に追求することが、都市のブランド価値を維持・向上させる王道であると言えます。
- 戦略の核心:
シティプロモーションアワード受賞事例の考察
シティプロモーションアワードは、全国の優れた取り組みを表彰する制度であり、その受賞理由を分析することは、成功の要諦を学ぶ上で非常に有益です。受賞事例には、いくつかの共通した成功要因が見られます。
- データと調査に基づく戦略性:
多くの受賞団体は、感覚的な企画ではなく、住民意識調査や各種データ分析に基づいた緻密な戦略を立てています。本庄市のように、ターゲットやペルソナを細かく設定し、丁寧な調査プロセスを経ている点が評価されています。データに基づいてPDCAサイクルを回し、改善を重ねながら成果を向上させている点が、高く評価される傾向にあります。 - 住民・市民の主体的な参画(自走する仕組み):
行政主導のトップダウン型ではなく、市民が企画・運営の中心となり、資金的にも自立している、いわゆる「自走」しているプロジェクトが高く評価されます。島根県飯南町では、住民と共に「余白あります」というブランドメッセージを作成し、プロジェクトの全過程に住民が参画することで、住民が主体的にまちに関わる文化を醸成している点が評価されました。 - インナープロモーションの重視:
前述の足立区の事例が象徴的ですが、対外的なアピールだけでなく、まず地域内部の住民の誇りや愛着を育むことに注力した取り組みが評価される傾向にあります。住民の共感と参画こそが、持続可能なプロモーションの基盤であるという考え方が根底にあります。 - 明確なロジックモデルと庁内連携:
単発のイベントで終わるのではなく、その取り組みが最終的にどのような成果(移住者増加、シビックプライド向上など)に繋がるのかという、論理的な道筋(ロジックモデル)が明確に示されていることが重要です。また、広報課だけでなく、関連部署を巻き込んだ全庁的な取り組みへと発展する可能性を秘めている点も評価のポイントとなります。
このアワードは、単に成功事例を表彰するだけでなく、応募した全ての団体に評価内容をフィードバックすることで、全国の自治体職員のスキルアップとモチベーション向上を図るという目的も持っています。受賞事例から学ぶべきは、奇抜なアイデア以上に、地道な調査、住民との対話、そして戦略的な思考プロセスの重要性です。
業務改革とDXの推進
ICT活用による費用対効果の向上
限られた予算と人員の中でシティプロモーションの効果を最大化するためには、ICT(情報通信技術)の活用による業務効率化と費用対効果の向上が不可欠です。
- SMS(ショートメッセージサービス)の活用:
携帯電話番号さえ分かっていれば、ほぼ確実に情報を届けることができるSMSは、イベントの直前リマインドや緊急連絡、アンケート調査への協力依頼など、特定の対象者に確実に情報を伝えたい場面で有効です。開封率が非常に高いというメリットがあります。 - RPA(Robotic Process Automation)による定型業務の自動化:
- RPAとは:
これまで人間がパソコンで行ってきた定型的な事務作業を、ソフトウェアのロボットが代行して自動化する技術です。データ入力、転記、集計、システム間の情報連携といった、ルールが決まっている繰り返し作業を得意とします。 - 広報業務での活用例:
- プレスリリース配信リストの自動更新:
各メディアの担当者情報を定期的にウェブサイトから収集し、配信リストを最新の状態に保つ。 - SNS投稿の予約・実行:
指定した日時に、あらかじめ作成した投稿文と画像を各SNSプラットフォームに自動で投稿する。 - メディア掲載情報の自動収集・報告書作成:
特定のキーワード(自治体名など)を含むウェブニュースを自動で検索・収集し、クリッピングレポートを日次・週次で作成する。 - イベント申込者データの集計と名簿作成:
ウェブフォームから申し込まれた参加者情報を自動でExcelに転記し、名簿や宛名ラベルを作成する。
- プレスリリース配信リストの自動更新:
- 導入効果:
RPAの導入により、職員は単純作業から解放され、企画立案やクリエイティブな業務といった、より付加価値の高い仕事に集中できるようになります。これにより、残業時間の削減や精神的負担の軽減といった働き方改革に繋がるだけでなく、人的ミスをなくし、業務の正確性とスピードを向上させることができます。広島県三原市では、約40業務にRPAを活用し、年間約9,700時間もの業務時間削減を実現しています。
- RPAとは:
- 民間活力の活用(デジタルマーケティング):
SNS広告やウェブ広告の運用、データ分析といった専門性の高い分野では、民間のデジタルマーケティング企業の知見を活用することも有効な手段です。JR東日本の移動・購買データなどを活用したターゲティング広告のように、民間が保有するビッグデータを活用することで、地域に関心を持つ可能性の高い潜在層に、より効率的にアプローチすることが可能になります。
生成AIの活用可能性と具体例
ChatGPTに代表される生成AIは、自治体業務に革命をもたらす可能性を秘めた技術です。広報・シティプロモーション業務においても、その活用範囲は非常に広く、業務の効率化と質の向上に大きく貢献します。
- 生成AI活用の基本姿勢:
生成AIは、あくまで業務を補助する「優秀なアシスタント」です。最終的な判断や責任は人間が負うことを前提とし、生成された内容の事実確認(ファクトチェック)は必須です。個人情報や機密情報を含むプロンプト(指示文)を入力しないなど、セキュリティに関するガイドラインを遵守することが重要です。 - 多様な文章の自動生成・校正:
- プレスリリースの草案作成:
イベントの概要を箇条書きで与え、「メディアの関心を引くような魅力的なプレスリリースの文章を作成してください」と指示するだけで、質の高い草案が完成します。 - SNS投稿文の作成:
「このイベントの魅力を、20代女性に響くような、絵文字を多用したInstagram投稿文として150字以内で作成してください」といった、ターゲットや媒体に合わせた文章を瞬時に生成できます。 - 挨拶文・スピーチ原稿の作成:
首長や幹部職員の式典挨拶などの原稿作成にかかる時間を大幅に短縮できます。 - 文章の要約・校正:
長文の報告書や議事録を要約したり、作成した文章の誤字脱字や不適切な表現をチェックさせたりすることが可能です。 - 企画・アイデア出しの壁打ち相手として:
- キャッチコピーのブレインストーミング:
「『歴史と自然が共存する〇〇市』の魅力を伝えるキャッチコピーを30案提案してください」と指示し、アイデアの種を大量に得ることができます。 - イベント企画の立案:
「若者向けの移住促進イベントの企画案を、ターゲット、コンセプト、コンテンツ、集客方法の観点から5つ提案してください」といった壁打ち相手として活用できます。 - ペルソナ分析:
神戸市では、広報紙作成の際に生成AIを活用してペルソナ(読者像)やカスタマージャーニーマップを作成し、企画の質を高めています。
- キャッチコピーのブレインストーミング:
- 多言語翻訳とインバウンド対応:
- プレスリリースやウェブサイトのコンテンツを、高精度で多言語に翻訳できます。インバウンド向けの情報発信を、低コストかつ迅速に行うことが可能になります。
- 住民問い合わせ対応の効率化:
- AIチャットボット:
自治体のウェブサイトに生成AIを組み込んだチャットボットを設置することで、住民からの定型的な問い合わせに24時間365日自動で応答できます。これにより、職員の電話対応業務の負担が大幅に軽減されます。京都市では、事業者からの問い合わせ対応にAIチャットボットを活用し、業務効率化を図っています。
- AIチャットボット:
- プレスリリースの草案作成:
- プロンプト(指示文)のコツ:
生成AIから質の高い回答を引き出すためには、指示の出し方(プロンプト)が重要です。以下の要素を盛り込むと、より意図に沿った回答が得やすくなります。- 役割の指定:
「あなたは優秀なコピーライターです」「あなたは経験豊富なイベントプランナーです」 - 背景・文脈の提供:
「当市は人口減少に悩んでおり、特に若者世代の流出が課題です」 - 具体的な条件設定:
「100字以内で」「箇条書きで」「小学生にも分かる言葉で」 - 出力形式の指定:
「表形式で」「マークダウン形式で」
- 役割の指定:
実践的スキル:プロモーション効果を最大化するために
組織レベルで回すPDCAサイクル
シティプロモーションを継続的に改善し、成果を出し続けるためには、組織全体でPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回す仕組みを構築することが不可欠です。
- Plan(計画):
- 全庁的な戦略の共有:
シティプロモーション戦略やブランドコンセプトを、広報課だけでなく全庁の職員が理解し、共有する場を設けます。年度当初に、市長や副市長などのトップマネジメントが全庁に向けて方針を明確に発信することが重要です。 - 部署横断の目標設定:
総合計画やシティプロモーション戦略に基づき、各部署が関連するKPIを設定します。例えば、商工観光課は「観光客入込数」、企画課は「移住相談件数」、市民協働課は「市民イベント参加者数」など、それぞれの業務がシティプロモーションにどう貢献するかを意識させます。 - 予算と人員の戦略的配分:
策定した計画に基づき、重点的に取り組む事業に予算と人員を配分します。データに基づいた客観的な根拠を示すことで、予算要求の説得力が高まります。
- 全庁的な戦略の共有:
- Do(実行):
- プロジェクトチームの組成:
重要なプロモーション事業については、広報課がハブとなり、関係部署の職員からなる部署横断のプロジェクトチームを組成して実行します。 - 情報共有の徹底:
定期的な連絡会議や庁内イントラネットを活用し、各部署の取り組み状況や成功事例、課題などをリアルタイムで共有します。 - ガイドラインの遵守:
全ての部署が情報発信を行う際に、シティプロモーションガイドラインに定められたブランドコンセプトやロゴマークの使用ルールを遵守するよう徹底します。
- プロジェクトチームの組成:
- Check(評価):
- KPIの定点観測:
設定したKPIの進捗状況を、四半期ごとなど定期的に測定・評価します。ウェブサイトのアクセス解析、SNSのエンゲージメント率、市民意識調査、メディア掲載件数(広告換算額)などをダッシュボード化し、誰もが進捗を可視化できるようにします。 - 定性的な評価の実施:
数字だけでなく、住民や事業者からのフィードバック、イベント参加者の声、メディアの論調といった定性的な情報も収集し、多角的に評価します。 - 定期的なレビュー会議:
幹部職員を含めたレビュー会議を定期的に開催し、計画と実績のギャップを分析し、その要因を議論します。
- KPIの定点観測:
- Act(改善):
- 戦略・計画の見直し:
評価結果に基づき、戦略やアクションプランを柔軟に見直します。効果の低い事業は縮小・中止し、成果の出ている事業にリソースを集中させるなど、改善策を次年度の計画に反映させます。宮城県亘理町では、ビッグデータを活用してPR記事の効果を分析し、次にアプローチすべきターゲットを明確化するという改善サイクルを実践しています。 - ナレッジの共有と横展開:
成功事例や失敗から得られた教訓を「ナレッジ」として蓄積し、全庁的な研修などを通じて共有します。これにより、組織全体のプロモーション能力が向上します。
- 戦略・計画の見直し:
個人レベルで回すPDCAサイクル
組織のPDCAが大きな歯車だとすれば、職員一人ひとりが日々の業務の中で回す個人のPDCAは、それを動かす小さな歯車です。担当者レベルでの実践が、組織全体の成果に繋がります。
- Plan(計画):
- 担当業務の目標設定:
組織のKPIをブレークダウンし、自らが担当する業務の具体的な目標(例: 「今月はSNSのフォロワーを100人増やす」「担当するイベントのプレスリリースを3つのウェブメディアに掲載させる」)を立てます。 - タスクの洗い出しと段取り:
目標達成のために必要な作業(情報収集、原稿作成、アポイント取りなど)をリストアップし、優先順位をつけて1週間、1日のスケジュールに落とし込みます。 - スキルアップ計画:
業務に必要なスキル(例: 写真撮影、動画編集、ウェブ解析)を特定し、研修に参加したり、書籍で学んだりする自己研鑽の計画を立てます。
- 担当業務の目標設定:
- Do(実行):
- まずやってみる:
計画に時間をかけすぎず、まずは行動に移すことを意識します。特にSNSの投稿などは、完璧を目指すより、まず発信してみることで得られるフィードバックが重要です。 - プロセスの記録:
どのような手順で作業を行ったか、誰に連絡してどのような反応があったか、何に時間がかかったかなどを簡単に記録しておきます。この記録が、後の「Check」の段階で貴重な材料となります。 - 周囲との連携:
一人で抱え込まず、上司や同僚にこまめに「報・連・相」を行い、協力を仰ぎながら業務を進めます。
- まずやってみる:
- Check(評価):
- 日次・週次の振り返り:
1日の終わりや週末に、その日の計画が達成できたか、できなかった場合は何が原因だったかを振り返ります。 - 具体的な数値での評価:
「SNS投稿の『いいね』数は平均より多かったか、少なかったか」「プレスリリースの既読率は何%だったか」など、具体的なデータで結果を客観的に評価します。 - 成功・失敗要因の分析:
うまくいった場合は「なぜうまくいったのか(成功要因)」を、うまくいかなかった場合は「どうすれば改善できるか(課題)」を考え、言語化します。
- 日次・週次の振り返り:
- Act(改善):
- 業務プロセスの改善:
振り返りで明らかになった課題を解決するための具体的な改善策を考え、次回の計画に反映させます。「A社への電話は午前中の方が繋がりやすい」「このテーマの投稿は写真より動画の方が反応が良い」といった小さな改善の積み重ねが、大きな生産性の向上に繋がります。 - テンプレート化・マニュアル化:
うまくいったメールの文面や作業手順などをテンプレートとして保存し、誰でも同じ品質で作業できるように標準化します。 - 新たな挑戦:
これまでのやり方にとらわれず、新しいツールを試したり、異なるアプローチを考えたりするなど、常に改善と挑戦を続けます。
- 業務プロセスの改善:
まとめ:未来を創る広報担当者へのエール
本マニュアルを通じて、シティプロモーションという業務の奥深さと、その戦略的な重要性についてご理解いただけたことと存じます。この仕事は、単に情報を右から左へ流すだけの作業ではありません。地域の未来を描き、人々の心を動かし、まちの価値を創造していく、極めてクリエイティブでやりがいに満ちた仕事です。
人口減少という大きな時代のうねりの中で、皆さんの双肩には、自らが愛するまちの未来がかかっています。それは決して平坦な道ではなく、時には成果が見えずに悩んだり、前例のない挑戦に不安を感じたりすることもあるでしょう。
しかし、忘れないでください。あなたの発信する一つひとつの言葉、一枚の写真、一つの企画が、誰かの心を動かし、このまちを訪れるきっかけとなり、やがては「ここに住みたい」という決断に繋がるかもしれないのです。そして何よりも、あなたの仕事は、今このまちに住む人々の心に「誇り」という灯をともし、コミュニティをより豊かにしていく力を持っています。
本マニュアルで示した知識や手法は、皆さんがその大きな使命を果たすための羅針盤であり、武器です。しかし、最も大切なのは、皆さん自身が誰よりも自分のまちを愛し、その可能性を信じる熱意です。その情熱こそが、あらゆる戦略やテクニックに命を吹き込みます。
明日からの業務において、ぜひ、住民一人ひとりの顔を思い浮かべてください。未来の子どもたちが笑顔で暮らすまちの姿を想像してください。その未来を創る主役は、他の誰でもない、広報担当者であるあなた自身です。
誇りと自信を持って、未来を創る仕事に邁進されることを心から応援しています。




-320x180.jpg)

-320x180.jpg)