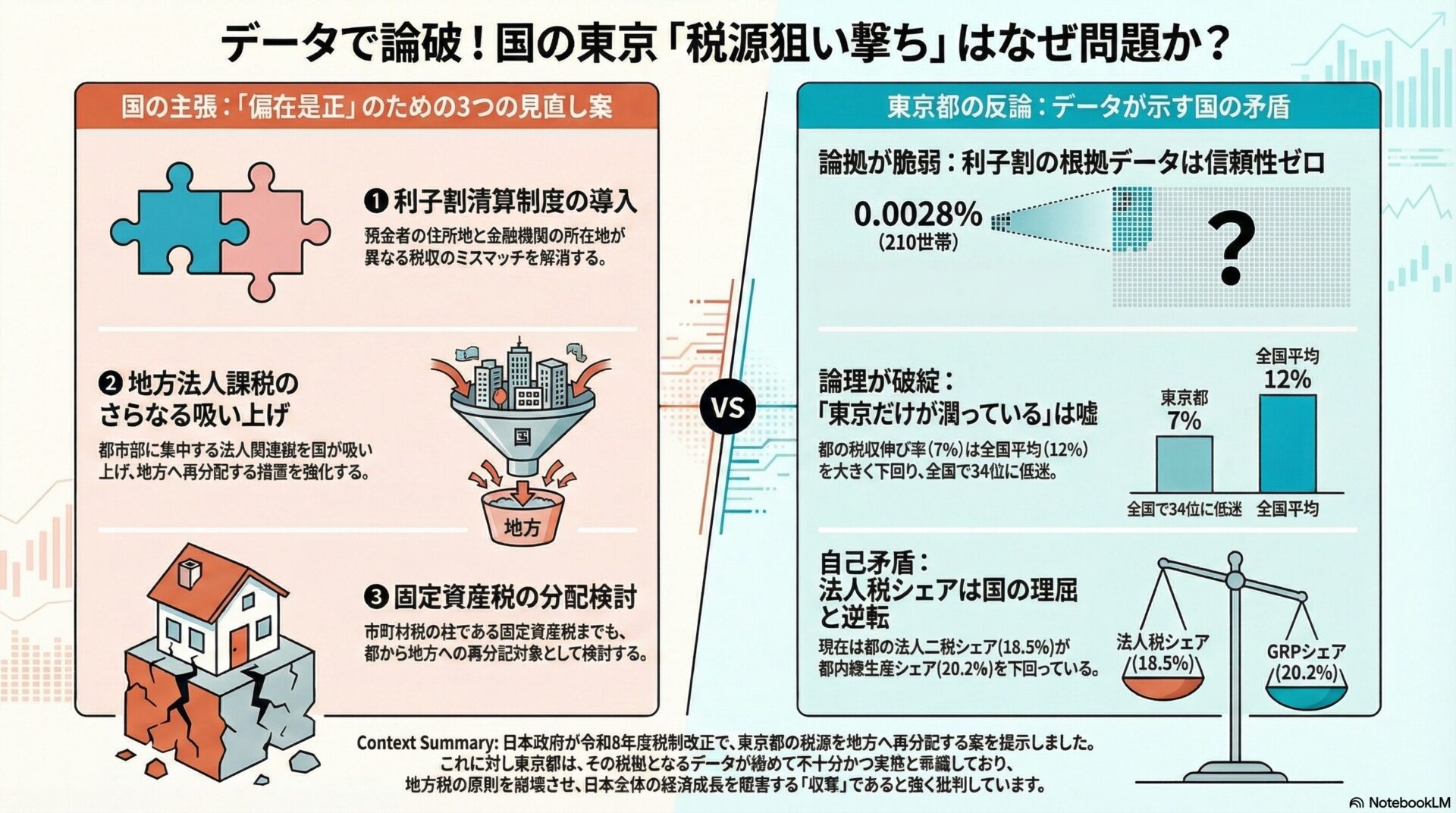個別施設計画の策定・推進

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
概要
自治体が個別施設計画の策定・推進を行う意義は「住民の安全確保と公共サービスの持続可能性の実現」と「将来世代を見据えた最適な資源配分と財政健全化の達成」にあります。
個別施設計画とは、自治体が保有する膨大な公共施設(庁舎、学校、公民館、公園、道路、橋梁など)について、その上位計画である「公共施設等総合管理計画」で示された大きな方針に基づき、施設一つひとつの具体的な長寿命化や修繕、更新、統廃合などの方針を定める実行計画です。
人口減少・少子高齢化、そして厳しい財政状況という大きな社会構造の変化に直面する現代において、この計画は単なる施設の維持管理計画にとどまりません。限られた資源をいかに効率的・効果的に活用し、将来にわたって質の高い行政サービスを提供し続けるかという、自治体経営の根幹に関わる戦略的な取り組みと言えます。
意義
住民にとっての意義
安全な生活環境の確保
- 個別施設計画に基づく計画的な点検や予防保全的な修繕は、老朽化に起因する外壁の落下や天井の崩落といった予期せぬ事故を未然に防ぎ、住民が安心して施設を利用できる環境を確保します。
- 多くの住民は公共施設の老朽化による事故のリスクを日常的に強く意識しているわけではありませんが、潜在的な危険性を管理し、重大な事故を未然に防ぐことは、行政の重要な責務です。
- 客観的根拠:
- ある全国調査では、住民の72.5%が「老朽化した公共施設の事故が起きるかもしれないという不安を身近で感じたことがない」と回答しています。しかし、行政側は多くの施設が老朽化し、潜在的なリスクを抱えていることを認識しており、計画的な対策の必要性が高まっています。
- (出典)株式会社日本経済研究所「公共施設に関する住民意識調査(平成26年度版)」 1
- 客観的根拠:
公共サービスの持続的提供
- 計画的な管理により、施設の突発的な故障による急な閉鎖などを回避できます。これにより、図書館や公民館、保育所といった住民生活に不可欠なサービスが、将来にわたって安定的に提供されることが可能になります。
- これは、事後対応的な修繕から計画的な予防保全へと管理手法を転換することで、施設の機能を長期にわたり維持し、サービス提供の継続性を担保するものです。
- 客観的根拠:
- 東京都港区では、過去のエレベーター事故を教訓に、設備の計画的な更新や安全対策を徹底する方針を計画に盛り込んでおり、これはサービスの安全かつ持続的な提供を目的としています。
- (出典)港区「港区公共施設等総合管理計画」 2
- 客観的根拠:
地域社会にとっての意義
まちづくりのビジョン具現化
- 施設の統廃合や複合化は、単なるコスト削減策ではなく、地域コミュニティの新たな拠点をつくり出す機会となります。例えば、老朽化した複数の施設を一つの現代的な複合施設に集約することで、世代間交流を促進したり、新たな地域活動を生み出したりするなど、まちの活性化に貢献します。
- 個別施設計画は、維持管理という守りの視点だけでなく、地域の将来像を描く「まちづくり」と一体で進めるべき攻めの戦略でもあります。
- 客観的根拠:
- 総務省の指針では、総合管理計画がまちづくりのあり方に関わるものであることから、施設再編が地域に与える影響を考慮し、計画的に進めることの重要性が示されています。
- (出典)総務省「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」 3
- 客観的根拠:
住民参加による合意形成
- どの施設を残し、どのサービスを優先するのかという議論は、地域の将来を住民と行政が共に考える重要なプロセスです。個別施設計画の策定過程を公開し、住民参加を促すことで、行政への信頼を高め、より実態に即した計画を策定することが可能になります。
- 施設の再編は住民の生活に直結するため、計画策定の段階から議会や住民への十分な情報提供を行い、対話を通じて合意形成を図ることが不可欠です。
- 客観的根拠:
- 総務省は、総合管理計画の策定・改訂段階において、議会や住民への十分な情報提供等を行いつつ進めていくことが望ましいとしており、これは個別施設計画においても同様に重要です。
- (出典)総務省「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針の改定について」令和5年10月 4
- 客観的根拠:
行政にとっての意義
財政負担の平準化とトータルコストの縮減
- 個別施設計画の最大の目的の一つは、財政の健全化です。場当たり的な大規模修繕や建て替えによる巨額の単年度支出を避け、計画的な修繕・更新によって長期的な財政負担を平準化します。
- さらに、施設の損傷が軽微なうちに対策を講じる「予防保全」へ転換することで、大規模な工事が不要となり、施設の生涯にわたる総費用(ライフサイクルコスト)を大幅に削減できます。
- 客観的根拠:
- 東京都品川区では、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき予防保全型の維持管理へ転換することで、今後50年間で約273億円のコスト縮減が可能と見込んでいます。
- (出典)品川区「品川区公共施設等総合管理計画(令和6年改定)」 5
- 客観的根拠:
計画的・戦略的な資産管理の実現
- これまで施設類型ごと、所管部署ごとに個別最適で管理されがちだった公共施設を、全庁的な視点から横断的に、かつ戦略的に管理する体制へと移行させます。
- 全ての公共施設を「資産(アセット)」として捉え、その価値を最大化するためのマネジメント(アセットマネジメント)を実現する上で、個別施設計画は中核的な役割を担います。
- 客観的根拠:
- 総務省の指針では、施設類型ごとに各部局で管理され、情報が全庁的に共有されていない現状を課題とし、総合的かつ計画的に管理できる全庁的な取組体制の構築を求めています。
- (出典)総務省「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」 3
- 客観的根拠:
(参考)歴史・経過
- 2013年(平成25年)
- 国が「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、社会資本の戦略的な維持管理・更新を推進する方針を打ち出しました。
- 2014年(平成26年)
- 総務省が全国の地方公共団体に対し、平成28年度末までに「公共施設等総合管理計画」を策定するよう要請しました。これが、自治体における公共施設マネジメントの本格的な始まりとなります。
- (出典)総務省「公共施設等総合管理計画の策定要請について」平成26年 3
- 2018年(平成30年)頃まで
- 全ての都道府県・市区町村(東京都特別区を含む)で、公共施設等総合管理計画の策定が完了しました。
- 2022年(令和4年)頃まで
- 総務省は、総合管理計画に基づき、施設ごとの具体的な対応方針を定める「個別施設計画」を令和4年度までに策定するよう要請しました。これにより、計画は「戦略」から具体的な「実行」の段階へと移行しました。
- (出典)総務省「公共施設等の適正管理の推進について」令和7年4月 6
- 2023年(令和5年)
- 総務省が総合管理計画の指針を改訂し、脱炭素化、ユニバーサルデザイン化、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進といった新たな視点を盛り込むとともに、計画の不断の見直しを要請しました。
- (出典)総務省「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針の改定について」令和5年10月 4
- 2024年(令和6年)以降
- 計画の「実行・見直し」が中心的な課題となっています。国は、施設の集約化・複合化や長寿命化などを財政的に支援するため、「公共施設等適正管理推進事業債」といった財政措置を講じ、自治体の取り組みを後押ししています。
- (出典)総務省「公共施設等の適正管理の推進について」令和7年4月 6
個別施設計画に関する現状データ
深刻化する施設の老朽化
- 東京都特別区では、高度経済成長期に集中的に整備された公共施設の老朽化が深刻な課題となっています。
- 例えば、大田区では築40年以上の施設が延床面積全体の53.3%を占めています。また、品川区では築30年以上の施設が全体の60.0%に達しており、全施設の平均築年数は33.7年と、計画的な更新が待ったなしの状況です。
- このように、特定の時期に建設された施設が一斉に更新時期を迎える「老朽化の波」が、特別区全体の財政に大きな影響を与えようとしています。
- 客観的根拠:
膨大な将来の更新費用
- 老朽化の進行に伴い、将来必要となる施設の更新費用は膨大な額に上ります。
- 品川区の試算では、今後30年間の公共施設の更新等に年平均で151.8億円が必要と見込まれています。
- この莫大な財政需要に対し、特別区はふるさと納税制度による税収減(令和6年度で約930億円)や、社会保障費の増大といった構造的な財政課題にも直面しており、既存の施設すべてを同規模で維持・更新していくことは事実上不可能です。このギャップを埋めるためにも、個別施設計画に基づく戦略的な施設再編が不可欠です。
- 客観的根拠:
- (出典)品川区「品川区公共施設等総合管理計画(令和6年改定)」 5
- (出典)特別区長会「特別区財政の現状と課題」令和6年 8
- 客観的根拠:
人口動態の変化とニーズの変容
- 日本全体の人口は減少局面に入っていますが、東京都特別区では区によって人口が増加している地域もあります。例えば港区では、令和18年(2036年)の人口が令和7年(2025年)比で18.6%増加すると推計されています。
- しかし、その内実を見ると、高齢化率は上昇し、外国人住民も増加するなど、人口構造は大きく変化しています。このため、既存の公共施設が現在の住民ニーズと合わなくなっている「機能のミスマッチ」が起きています。
- 今後は、施設の老朽化対策と同時に、変化する住民ニーズに合わせて施設機能を見直していく視点が不可欠です。
- 客観的根拠:
- (出典)港区「港区将来人口推計」令和7年 9
- (出典)総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」令和5年 10
- 客観的根拠:
課題
住民の課題
老朽化に伴う安全性への不安
- 日常的に強く意識されることは少ないものの、老朽化した施設が引き起こす事故への不安は、住民の中に潜在的に存在します。特に、過去の事故報道や、地震時の天井崩落などへの懸念は根強くあります。
- 客観的根拠:
- 全国の住民を対象とした調査では、7割以上が「不安を身近で感じたことがない」と回答していますが、20代、30代の若年層では2割以上が「不安を身近で感じたことがある」と回答しており、世代間で意識の差が見られます。
- (出典)株式会社日本経済研究所「公共施設に関する住民意識調査(平成26年度版)」 1
- 東京都港区では、平成18年に発生した区民向け住宅でのエレベーター死亡事故を教訓とし、施設の安全対策を最優先課題として取り組んでいます。
- (出典)港区「港区公共施設等総合管理計画」 2
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 万が一重大事故が発生した場合、住民の行政に対する信頼が失墜し、自治体は深刻な責任問題に直面します。
- 客観的根拠:
施設の統廃合による利便性の低下
- 住民にとって最も直接的で切実な課題は、施設の統廃合による利便性の低下です。最寄りの図書館や公民館がなくなることで、特に高齢者や子育て世帯、交通弱者にとっては、サービスへのアクセスが困難になる可能性があります。
- 客観的根拠:
- ある自治体の調査では、施設の集約・複合化に反対する理由として、「移動に時間をかけたくないから」「適切な交通手段がないから」といったアクセスに関する懸念が上位を占めています。
- (出典)福生市「公共施設に関するアンケート調査」令和3年度 11
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 必要な行政サービスや地域活動への参加を諦める住民が増え、社会的孤立や健康格差の拡大を招く恐れがあります。
- 客観的根拠:
地域社会の課題
「総論賛成・各論反対」の壁と合意形成の困難さ
- 公共施設の再編における最大の障壁は、地域住民との合意形成です。「財政が厳しいのだから、施設の見直しは仕方ない」という総論では多くの住民が理解を示す一方で、いざ自分の身近な施設が廃止や統合の対象になると、強い反対運動が起こる「総論賛成・各論反対」の状況に陥りがちです。
- これは、行政が「区全体の財政健全化」という視点で判断するのに対し、住民は「個人の利便性や地域への愛着」という視点で判断するため、両者の間に価値観の対立が生まれることが根本的な原因です。
- 客観的根拠:
- 全国の住民の88.3%が公共施設の再編成に「賛成」または「やむを得ない」と回答しており、抽象的なレベルでは高い理解が得られています。
- (出典)日本政策投資銀行「公共施設に関する住民意識調査(平成26年度版)」 1
- しかし、総務省の調査では、特別区で施設削減目標の達成率が低い最大の理由は「住民の合意形成が困難」(72.7%)であり、次いで「議会の理解が得られない」(54.5%)が続いています。
- (出典)総務省「公共施設等総合管理計画の進捗状況調査」令和5年度 11
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 必要な施設再編が先送りされ続け、老朽化による危険性の増大と将来世代への財政負担の転嫁が深刻化します。
- 客観的根拠:
行政の課題
計画を推進する専門人材の不足
- 公共施設マネジメントを効果的に推進するには、建築・土木の技術的知識、ライフサイクルコスト計算などの財務知識、そして住民との合意形成を円滑に進めるためのファシリテーション能力など、複合的な専門スキルを持つ人材が不可欠です。しかし、多くの自治体ではこうした専門人材が不足しており、計画策定後の実行段階でつまずくケースが少なくありません。
- 客観的根拠:
- 自治体における公共施設マネジメントの課題として、「マネジメント専任組織がない」「庁内人材が確保できない」が上位に挙げられています。特に、技術職と事務職の両面のスキルを併せ持つ職員は不足しています。
- (出典)多摩市町村自治調査会「公共施設マネジメントに関する調査研究報告書」 12
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 計画が策定されても実行に移せず、効果的なコスト削減やサービス向上が実現できない「計画倒れ」の状態が続きます。
- 客観的根拠:
縦割り行政の弊害
- 従来、公共施設は教育委員会が学校を、福祉部門が福祉施設を、といったように、所管部署ごとに個別に管理されてきました。この「縦割り行政」の構造が、部署を横断して施設を複合化したり、機能を再編したりする際の大きな障壁となっています。
- 全庁的な視点での最適化を図ろうとしても、部署間の利害調整や連携が進まず、非効率な施設配置が温存されがちです。
- 客観的根拠:
- 学校施設と他の公共施設との複合化における課題として、「地方公共団体内の部局間の連携、教職員や地域住民との合意形成」が明確に指摘されています。
- (出典)文部科学省「学校施設の複合化の特徴と取組事例」平成27年 11
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 全体最適の視点を欠いた非効率な施設配置が温存され、コスト削減やサービス向上の機会が失われます。
- 客観的根拠:
データに基づいた意思決定基盤の未整備
- 客観的なデータに基づいた合理的な意思決定を行うためには、施設の基本情報(築年数、構造等)、劣化状況、修繕履歴、利用状況、運営コストといった情報を一元的に管理・分析する基盤が必要です。
- しかし、多くの自治体ではこれらのデータが各部署に散在していたり、そもそも収集されていなかったりするため、場当たり的な判断にならざるを得ない状況があります。
- 客観的根拠:
- 総務省の調査によれば、多くの自治体で施設情報を活用する仕組みが未整備であり、収集したデータが意思決定に十分に活かされていない実態があります。
- (出典)総務省「公共施設マネジメントの情報基盤に関する調査」令和4年度 13
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 場当たり的で非効率な投資判断が続き、限られた財源が有効に活用されず、行政運営の非効率性が固定化します。
- 客観的根拠:
行政の支援策と優先度の検討
優先順位の考え方
※各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
- 即効性・波及効果
- 施策の実施から効果発現までの期間が短く、複数の課題解決や多くの住民への便益につながる施策を高く評価します。
- 実現可能性
- 現在の法制度、予算、人員体制の中で実現可能な施策を優先します。既存の仕組みを活用できる施策は優先度が高くなります。
- 費用対効果
- 投入する経営資源(予算・人員等)に対して得られる効果が大きい施策を優先します。短期的なコストだけでなく、将来的な財政負担の軽減効果も考慮します。
- 公平性・持続可能性
- 特定の層だけでなく、幅広い住民に便益が及ぶ施策を優先します。一時的な効果ではなく、長期的に効果が持続する施策を高く評価します。
- 客観的根拠の有無
- 政府資料や先行事例等で効果が実証されている施策を優先します。
支援策の全体像と優先順位
個別施設計画の実行を確実なものにするため、支援策を以下の3つの柱で体系化し、優先順位を設定します。
- 優先度【高】:支援策① 計画実行を支える基盤の強化
- 計画を絵に描いた餅に終わらせないためには、まず実行部隊である「人」と、判断材料である「データ」という足腰を徹底的に強化することが不可欠です。専門人材の不足やデータ基盤の未整備といった根本的な課題を解決する本施策を最優先とします。
- 優先度【中】:支援策② 戦略的な再編・長寿命化の推進
- 基盤が整った上で、次に具体的な実行手法(How)を高度化します。予防保全や複合化、公民連携といったコスト削減とサービス向上を両立させるための具体的なツールを提供し、計画の実効性を高めます。
- 優先度【低】:支援策③ 住民との価値共創による合意形成プロセスの構築
- 最も困難な課題である住民合意形成は、行政側の基盤が強固で、かつ具体的なメリット・デメリットを提示できる状態になって初めて、実効性のある対話が可能になります。そのため、①と②を土台として、丁寧に進めるべき施策と位置付けます。
各支援策の詳細
支援策①:計画実行を支える基盤の強化
目的
- 個別施設計画を全庁的かつ客観的データに基づいて推進するための「人材」と「情報」の基盤を構築し、計画の実効性を担保します。
- 客観的根拠:
- 公共施設マネジメントは自治体内部の最適化目標であり、外部人材を有効に活用するためにも、相応のスキルを持つ内部人材の育成が不可欠です。
- (出典)地方自治研究機構「JIAM Journal 第122号」 14
- 客観的根拠:
主な取組①:公共施設マネジメント専門人材の育成・確保
- 職員の階層や役割に応じた多層的な研修プログラムを構築します。
- 全職員向け:公共施設マネジメントの基礎知識や意義を学ぶ意識啓発研修
- 施設担当者向け:日常点検、小規模修繕、コスト管理などの実務スキル研修
- 専門チーム向け:PPP/PFI、ライフサイクルコスト分析、不動産活用などの高度専門研修
- 専門人材がキャリアを形成できる専門職制度や、民間企業(不動産、建築、金融等)からの専門人材の中途採用を積極的に推進します。
- 客観的根拠:
- 東京都では、職員の能力開発のため、職務を通じたOJT、職場外研修(Off-JT)、自己啓発を連携させた多様な研修プログラムを実施しており、こうした仕組みを公共施設マネジメント分野にも応用することが有効です。
- (出典)東京都「職員研修」 15
- 客観的根拠:
主な取組②:全庁横断的な推進体制の構築
- 財政部門、企画部門、各施設所管部門などを横断する、首長直轄の恒常的な「資産経営推進室(仮称)」を設置します。
- この推進室に、施設情報の集約・分析、個別施設計画の進捗管理、部署間調整、全庁的な方針策定などの権限を付与します。
- 各部署が立案する大規模な施設関連事業については、原則としてこの推進室のレビューを経ることを義務付け、計画との整合性を確保します。
- 客観的根拠:
- 総務省は、総合管理計画の推進には、各部局の進捗を管理する部署を定め、部局横断的な検討の場を設けるなど、全庁的な体制構築が不可欠であるとしています。
- (出典)総務省「公共施設等の適正管理の推進について」令和7年4月 6
- 客観的根拠:
主な取組③:施設情報の一元管理データベースの構築・活用
- 全ての公共施設に関する情報を一元的に管理・可視化する「ファシリティマネジメント(FM)システム」を導入します。
- 統合するデータ:
- 施設台帳情報(所在地、面積、構造、築年数等)
- 劣化診断・点検結果
- 修繕・改修履歴
- 利用率、利用者数などの利用状況データ
- 光熱水費、維持管理委託費などのコストデータ
- 新築・大規模改修時にはBIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)の導入を原則とし、設計から維持管理、解体までのライフサイクルを通じた情報活用を推進します。
- 客観的根拠:
- 固定資産台帳等の情報を活用することで、中長期的な経費の見込みを精緻化でき、事業別・施設別の効率的・効果的な対策の検討が可能になります。
- (出典)総務省「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改定について」令和5年10月 4
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 30年間の施設更新・維持管理に係るトータルコストを20%削減
- データ取得方法: 長期財政シミュレーションと実績の比較分析
- KSI(成功要因指標)
- 公共施設マネジメント専門研修を修了した職員の割合 10%
- データ取得方法: 人事課の研修受講記録
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- データに基づく施設再編・改善提案の件数 年間20件
- データ取得方法: 資産経営推進室による議案・報告の集計
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 全施設の基本情報・財務情報のデータベース入力率 100%
- データ取得方法: FMシステムの進捗管理レポート
支援策②:戦略的な再編・長寿命化の推進
目的
- 予防保全、複合化、公民連携といった具体的な手法を駆使し、将来の財政負担を軽減するとともに、住民サービスの質を維持・向上させる戦略的な施設マネジメントを実践します。
- 客観的根拠:
- 計画的な施設マネジメントにより、更新費用を約30%削減した事例もあり、戦略的な取り組みが財政負担の軽減に直結します。
- (出典)国土交通省「公共施設等総合管理計画の効果検証」令和4年度
- 客観的根拠:
主な取組①:予防保全型メンテナンスへの完全移行
- 点検・診断データに基づき、施設ごと・部位ごとの詳細な長期修繕計画を策定します。
- 予算編成において、突発的な不具合に対応する「事後保全」予算から、計画的な修繕を行う「予防保全」予算へと重点をシフトします。
- これにより、施設の長寿命化を図り、大規模改修や建替えの回数を減らすことで、ライフサイクルコストを最適化します。
- 客観的根拠:
- 東京都品川区は、橋梁の長寿命化修繕計画により、予防保全型管理へ転換することで今後50年間で約273億円のコスト縮減を見込んでいます。また、公園施設においても同様の計画で年間約952万円のコスト縮減効果を試算しています。
- (出典)品川区「品川区公共施設等総合管理計画(令和6年改定)」 5
- 客観的根拠:
主な取組②:施設の複合化・多機能化の推進
- 老朽化した複数の公共施設(例:公民館、図書館、児童館)を一つの拠点に集約し、多世代が利用できる複合施設として再整備する取り組みを積極的に推進します。
- 新設・大規模改修時には、原則として複合化・多機能化を検討するルールを設けます。
- 客観的根拠:
- 山口県下関市では、老朽化した3つの保育園と1つの幼稚園を、児童発達支援センターの機能も併せ持つ「認定こども園」として複合化し、施設の効率化とサービスの拡充を両立させています。
- (出典)昭島市「公共施設マネジメントに関する先進事例調査」 16
- 客観的根拠:
主な取組③:PPP/PFI等、民間活力の積極的活用
- 施設の設計・建設から維持管理・運営までを一体的に民間事業者に委ねるPPP/PFI手法の導入を標準的な選択肢と位置付けます。
- 区内にPPP/PFIの導入を支援する専門部署を設置し、事業所管課へのノウハウ提供や、標準的な契約モデルの作成支援を行います。
- 客観的根拠:
- 横浜市では、市営自転車駐車場の土地を民間に貸し付けて賃貸住宅等と一体で再整備させたり、バス停上屋の設置・維持管理を広告収入で賄う事業者に委託したりするなど、多様な公民連携手法を実践しています。
- (出典)横浜市ウェブサイト「ファシリティマネジメントの推進」 17
- 客観的根拠:
主な取組④:脱炭素化・ユニバーサルデザイン化の標準装備
- 全ての公共施設の新築・大規模改修において、省エネルギー性能の高いZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化や、太陽光発電設備の設置を原則とします。
- 同時に、高齢者や障害者、子育て世代など、誰もが安全で快適に利用できるユニバーサルデザインを標準仕様として導入します。
- 客観的根拠:
- 令和5年10月に改訂された総務省の指針では、総合管理計画に「脱炭素化の推進方針」や「ユニバーサルデザイン化の推進方針」を記載することが新たに求められており、これらは今後の公共施設整備における必須要件となります。
- (出典)総務省「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針の改定について」令和5年10月 4
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 施設総延床面積の15%削減(10年間)
- データ取得方法: 公共施設台帳の経年比較
- KSI(成功要因指標)
- PPP/PFI手法を導入した事業の割合(新規・大規模改修事業費ベース) 30%
- データ取得方法: 財政課・資産経営推進室の事業契約記録
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 複合化・再編後の施設の利用者満足度 80%以上
- データ取得方法: 利用者アンケート調査
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 複合化・多機能化の検討・実施件数 年間5件
- データ取得方法: 資産経営推進室のプロジェクト管理記録
支援策③:住民との価値共創による合意形成プロセスの構築
目的
- 行政が一方的に説明し理解を求める従来型の合意形成から脱却し、住民と行政が共に地域の課題を考え、施設の将来像を創り上げていく「価値共創」型のプロセスを構築することで、困難な意思決定に対する納得感を醸成します。
- 客観的根拠:
- 公共施設の統廃合など、住民の利害に直結する課題の合意形成には、行政からの丁寧な情報提供と対話のプロセスが不可欠です。
- (出典)総務省「公共施設の広域連携に関する調査研究報告書」 18
- 客観的根拠:
主な取組①:情報公開の徹底と「見える化」
- 区が保有する全施設の情報を網羅した、分かりやすい「公共施設白書」を作成・公表します。
- さらに、施設一つひとりの「通信簿」として、築年数、劣化状況、利用率、運営コストなどをまとめた「施設カルテ」を整備し、ウェブサイトで誰もが閲覧できるようにします。
- これらの情報を地図上で確認できるインタラクティブな「施設マップ」を公開し、住民の関心と理解を促進します。
- 客観的根拠:
- 住民の8割が公共施設の見直しに賛成している背景には、老朽化度合いや利用実態の開示が重要という認識があります。情報の「見える化」が、住民との対話の第一歩となります。
- (出典)株式会社日本経済研究所「公共施設に関する住民意識調査」 19
- 客観的根拠:
主な取組②:熟議型ワークショップの導入
- 施設の統廃合など、特に合意形成が難しい案件については、住民説明会だけでなく、無作為抽出で選ばれた住民が参加する「熟議型ワークショップ」を実施します。
- 専門家の支援のもと、参加者が数日間にわたり課題を学び、多様な意見を交わし、熟慮の上で政策提言をまとめるプロセスを通じて、単なる賛成・反対を超えた質の高い民意を形成します。
- 客観的根拠:
- 浜松市では、無作為抽出による13歳以上の市民を対象としたワークショップを実施し、将来を見据えた計画に多様な市民の意見を取り入れることで、合意形成の円滑化を図っています。
- (出典)地方公共団体金融機構「公共施設マネジメントの先進的取組事例」 20
- 客観的根拠:
主な取組③:代替案・インセンティブの提示
- 施設の廃止・統合を提案する際には、必ずセットで具体的な代替サービス案(例:移動図書館の運行、民間施設利用への補助、統合先施設へのコミュニティバス運行等)を提示し、住民の不便を最小化する配慮を示します。
- 廃止した施設の跡地を売却して得た収益の一部を、当該地域の別の公共サービス(公園の再整備、防犯灯のLED化など)に充当する仕組みを設け、地域への還元を明確にします。
- 客観的根拠:
- 秋田県美郷町では、施設の統廃合にあたり、住民の利便性を損なわないよう、出張所の設置や巡回検診の実施といった代替措置を講じることで、地域間のバランスを保ち、円滑な合意形成につなげています。
- (出典)地方公共団体金融機構「公共施設マネジメントの先進的取組事例」 20
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 施設再編計画に対する住民合意形成率 80%(住民説明会アンケート等で賛成が反対を上回る)
- データ取得方法: 各事業の住民説明会記録、アンケート結果の分析
- KSI(成功要因指標)
- 熟議型ワークショップの実施率(統廃合対象事業ごと) 100%
- データ取得方法: 事業実施記録の確認
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- パブリックコメントにおける建設的・具体的提案の割合 30%
- データ取得方法: 提出されたパブリックコメントの内容分析
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 「公共施設白書」「施設カルテ」の公表率 100%
- データ取得方法: 自治体ウェブサイトの公表状況の確認
先進事例
東京都特別区の先進事例
品川区「計画的な長寿命化によるコスト縮減と安全確保の両立」
- 品川区は、個別施設計画の代表例として「橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、予防保全型の維持管理を徹底しています。区が管理する66の橋梁について、定期的な点検に基づき計画的な修繕を行うことで、安全性を確保しつつ、将来の財政負担を大幅に軽減することを目指しています。
- この計画により、事後対応型の管理を続けた場合と比較して、今後50年間で約273億円ものコスト縮減が可能になると試算されています。データに基づいた長期的な計画を策定し、予防保全投資の財政的メリットを明確に示した好事例です。
- 客観的根拠:
港区「エレベーター事故を教訓とした徹底的な安全対策」
- 港区は、平成18年に発生した区民向け住宅でのエレベーター死亡事故という悲劇を教訓に、公共施設の安全対策を最優先課題と位置付け、徹底した取り組みを進めています。
- 個別施設計画の中に、エレベーター設備の計画的な更新や、戸が開いたまま動くことを防ぐ「戸開走行保護装置」の設置などを明確に盛り込み、利用者の安全・安心を確保するための具体的な対策を体系的に実行しています。危機を改革の契機とし、安全への投資を断行した事例として評価できます。
- 客観的根拠:
- (出典)港区「港区公共施設等総合管理計画」 2
- 客観的根拠:
世田谷区「公共施設白書による徹底した情報公開」
- 世田谷区は、公共施設マネジメントの第一歩として、区が保有する886施設もの全施設の情報を網羅した詳細な「公共施設白書」を早期に作成・公表しました。
- この白書では、施設の築年数や運営形態、用途地域といった基本情報がデータに基づいて整理されており、行政内部での議論の基礎となると同時に、住民が地域の施設状況を理解するための重要な情報源となっています。複雑な課題に取り組む上で、まず透明性を確保するという基本姿勢を示した先進的な取り組みです。
- 客観的根拠:
- (出典)世田谷区「世田谷区公共施設白書」 21
- 客観的根拠:
全国自治体の先進事例
横浜市「多様な公民連携(PPP/PFI)手法の活用」
- 横浜市は、民間事業者の資金やノウハウを積極的に活用する公民連携(PPP/PFI)の先進都市です。例えば、市営自転車駐車場の土地を民間の開発事業者に貸し付け、賃貸住宅などと一体で再整備する事業や、バス停上屋の設置・維持管理を広告事業者が広告収入で賄う事業などを展開しています。
- これにより、市は財政負担を抑えながら公共サービスやアメニティを向上させており、公共資産の新たな価値を創出する柔軟な発想が特徴です。
- 客観的根拠:
- (出典)横浜市「ファシリティマネジメントの推進」 17
- (出典)総務省「地方創生のための公民連携(PPP/PFI)事例集」 22
- 客観的根拠:
北九州市「公共施設マネジメントと環境政策の融合」
- 北九州市は、公共施設の再編・管理を、市の重要戦略である「グリーン成長戦略」と一体で推進しています。具体的には、公共施設への再生可能エネルギー供給を目的とした地域エネルギー会社を設立したり、施設の改修時にZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を推進したりしています。
- この取り組みは、施設の光熱水費といったライフサイクルコストの削減と、CO2排出量の削減という二つの大きな課題を同時に解決するものであり、インフラ管理をより大きなまちづくりのビジョンと結びつけた総合的なアプローチとして注目されます。
- 客観的根拠:
- (出典)環境省「脱炭素先行地域提案書」 23
- (出典)北九州市「北九州市公共施設マネジメント実行計画」 24
- 客観的根拠:
参考資料[エビデンス検索用]
総務省関連資料
- 「公共施設等の適正管理の推進について」令和7年4月 6
- 「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」 3
- 「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針の改定について」令和5年10月 4
- 「公共施設等総合管理計画の進捗状況調査」令和5年度 11
- 「公共施設マネジメントの情報基盤に関する調査」令和4年度 13
- 「公共施設の広域連携に関する調査研究報告書」 18
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」令和5年 10
国土交通省関連資料
- 「公共施設等総合管理計画の効果検証」令和4年度
文部科学省関連資料
- 「学校施設の複合化の特徴と取組事例」平成27年 11
環境省関連資料
- 「脱炭素先行地域提案書」 23
東京都関連資料
- 「職員研修」 15
特別区関連資料
- 特別区長会「特別区財政の現状と課題」令和6年 8
- 品川区「品川区公共施設等総合管理計画(令和6年改定)」 5
- 港区「港区公共施設等総合管理計画」 2
- 世田谷区「世田谷区公共施設白書」 21
- 大田区「(仮称)大田区公共施設等総合管理計画」令和4年 7
全国自治体関連資料
- 横浜市「ファシリティマネジメントの推進」 17
- 北九州市「北九州市公共施設マネジメント実行計画」 24
- 福生市「公共施設に関するアンケート調査」令和3年度 11
- 昭島市「公共施設マネジメントに関する先進事例調査」 16
研究機関・その他
- 株式会社日本経済研究所「公共施設に関する住民意識調査(平成26年度版)」 1
- 地方自治研究機構「JIAM Journal 第122号」 14
- 多摩市町村自治調査会「公共施設マネジメントに関する調査研究報告書」 12
- 地方公共団体金融機構「公共施設マネジメントの先進的取組事例」 20
まとめ
東京都特別区において、個別施設計画の策定、そして実行は、財政制約と人口構造の変化を乗り切るための最重要課題です。課題は「計画策定」から「計画実行」へと移っており、住民合意形成の困難さ、専門人材の不足、縦割り行政がその障壁となっています。今後は、①人材・データという実行基盤の強化、②予防保全や公民連携といった戦略的実行、③住民との価値共創による合意形成、という三位一体の改革が不可欠です。
本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。




-320x180.jpg)

-320x180.jpg)