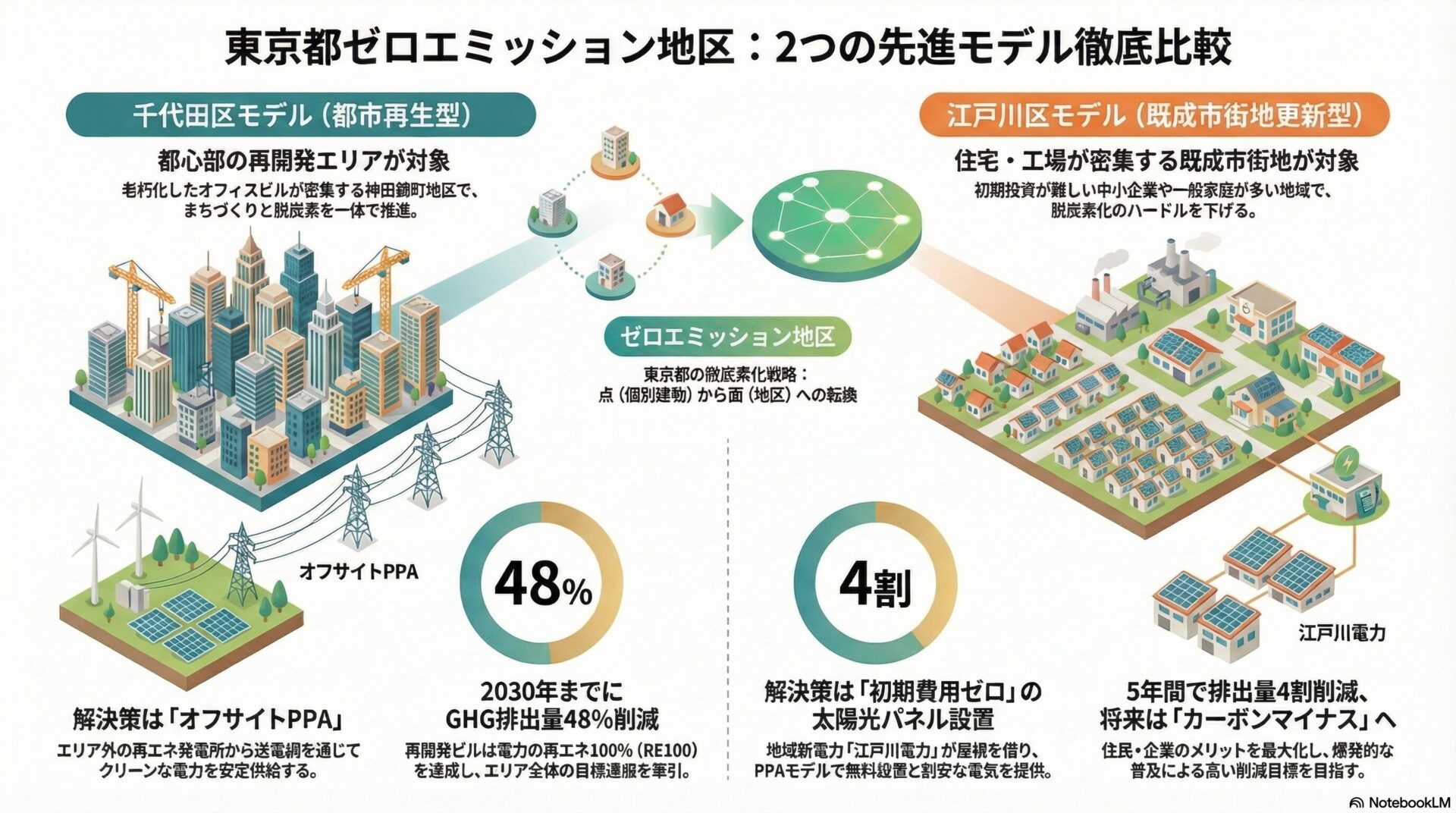3R(リデュース・リユース・リサイクル)

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
概要(3Rを取り巻く環境)
- 自治体が3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進する意義は、「持続可能な循環型経済の実現」と「将来にわたる環境的・財政的負荷の低減」にあります。
- 3Rとは、廃棄物の発生を抑制する「リデュース」、繰り返し使用する「リユース」、資源として再利用する「リサイクル」の3つの取り組みの総称です。これらは、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から脱却し、持続可能な社会を構築するための基本原則です。
- 我が国では、2000年に制定された「循環型社会形成推進基本法」において、取り組むべき優先順位が①リデュース、②リユース、③リサイクルの順で明確に法定化されています(1)。
- 最新の政策動向として、令和7年版環境白書・循環型社会白書では、3Rを単なる廃棄物対策として捉えるのではなく、「『新たな成長』を導くグリーンな経済システムの構築」の中核的要素と位置づけています。これは、3Rの推進が、環境保全に留まらず、新たな産業競争力の創出や国民のウェルビーイング向上に貢献する、積極的な経済戦略であることを示しています(3)。
意義
住民にとっての意義
環境意識の向上とライフスタイルの質の向上
- 3R活動への参加は、資源の有限性や環境問題への理解を深め、ものを大切にする意識を育みます。これにより、過剰な消費に頼らない、より満足度の高いライフスタイルへの転換が期待されます(6)。
経済的負担の軽減可能性
- ごみの排出量に応じて手数料が変動する制度を導入している自治体では、リデュース(ごみの発生抑制)が直接的な経済的メリットにつながります。
- また、フリーマーケットや修理サービスの活用など、リユースを実践することで、新たな支出を抑えることができます(8)。
地域社会にとっての意義
循環型ビジネスの創出と地域経済活性化
- リユースショップ、修理工房、アップサイクル(創造的再利用)事業者など、3Rに関連する新たなビジネスや雇用が生まれる可能性があります。
- 国が2030年までに循環経済関連の市場規模を80兆円以上に拡大する目標を掲げている通り、3Rの推進は地域経済を活性化させるエンジンとなり得ます(9)。
持続可能な地域ブランドの構築
- 3Rへの先進的な取り組みは、「環境に配慮した持続可能なまち」という強力な地域ブランドを形成します。
- 徳島県上勝町の事例のように、優れた取り組みは環境意識の高い住民や企業を惹きつけ、視察や観光の対象となることで、地域全体の魅力を高める効果が期待できます(11)。
行政にとっての意義
廃棄物処理コストの削減
- ごみの総量を削減することは、収集、運搬、焼却、埋立にかかる莫大な行政コストを直接的に削減します。
- これにより、他の重要な住民サービスへ財源を再配分することが可能になります(13)。
最終処分場の延命
- 埋立処分される廃棄物の量を減らすことは、限りある最終処分場の残余年数を延ばす上で極めて重要です。
- 特に首都圏では最終処分場の確保が困難であり、その延命は喫緊の課題です。全国の最終処分場の残余年数は令和5年度末時点で24.8年とされており、危機的な状況が続いています(14)。
国や都の目標達成への貢献
- 「第五次循環型社会形成推進基本計画」などの国の計画や、東京都の計画が掲げる目標を達成することは、基礎自治体としての重要な責務です。
- 3Rの着実な推進は、法令遵守と優れたガバナンスの証となります(15)。
(参考)歴史・経過
- 2000年
- 「循環型社会形成推進基本法」が制定され、3Rの優先順位(リデュース>リユース>リサイクル)が法的に確立されました(1)。
- 2000年代
- 容器包装リサイクル法や家電リサイクル法など、個別の品目に対するリサイクル法制度が整備され、第一次循環型社会形成推進基本計画が策定されました。
- 2018年
- 中国が廃プラスチック等の輸入を禁止したことにより、国内で処理しきれない資源が滞留し、処理コストが高騰。「リサイクル危機」が表面化し、輸出に依存した体制の脆弱性が露呈しました(18)。
- 2022年4月
- 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(プラスチック資源循環法)が施行。製品設計から廃棄物処理までの一貫した対策を促進し、自治体が製品プラスチックも一体的に回収することが可能となりました(19)。
- 2024年8月
- 「第五次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定。循環経済への移行を国の成長戦略として明確に位置づけ、新たな国家目標を設定しました(10)。
- 2025年6月
- 「令和7年版環境白書・循環型社会白書」が公表。新たな国家計画の下での進捗と課題を分析し、3Rを「グリーンな経済システム」の構築という、より広い文脈で捉え直しました(3)。
3Rに関する現状データ
全国および東京都特別区のデータは、3R推進における重要な示唆を与えています。すなわち、ごみの総排出量は着実に減少している(リデュースの成功)一方で、リサイクル率は長年にわたり停滞、あるいは微減しているという「大きな乖離」です。これは、単なる分別意識の啓発だけでは解決できない、より構造的な問題が存在することを示唆しています。これまで比較的リサイクルしやすかった品目の回収は一巡し、今後は処理コストの高い複合素材プラスチックなど、質の向上やリサイクル市場の経済性を根本から改善する施策に転換しなければ、リサイクル率の向上は望めない段階に来ていることをデータが物語っています。
全国の一般廃棄物排出量と処理状況の推移
- 総排出量
- 着実な減少傾向にあります。令和5年度の全国の総排出量は3,897万トンで、令和4年度の4,034万トンから3.4%減少しました(14)。
- 1人1日当たりの排出量
- 同様に減少しており、令和5年度は851グラムで、令和4年度の880グラムから減少しています(14)。
- 最終処分量
- こちらも着実に減少しており、令和5年度は316万トンと、令和4年度の337万トンから6.5%の大幅な減少を達成しました(14)。
- リサイクル率
- これが最も深刻な指標です。令和5年度のリサイクル率は**19.5%**と、令和4年度の19.6%から微減し、過去10年以上にわたり20%前後で完全に停滞しています。これは、リサイクルシステムの構造的なボトルネックを示しています(14)。
東京都特別区のごみ排出量と資源化状況の推移
- ごみ総量
- 全国と同様に減少傾向です。令和5年度の23区のごみ総量(区収集・持込ごみ)は約249万トンで、前年度から2.1%減少しました(24)。
- 資源回収量
- 憂慮すべきことに、こちらも減少しています。令和5年度の資源回収量(ステーション・拠点・集団回収の合計)は約52.4万トンで、前年度から2.3%減少しており、リサイクルの取り組みが後退していることを示唆しています(25)。
- リサイクル率
- 目標に遠く及ばず、停滞しています。近年の統合された数値は資料にありませんが、過去のデータ(平成28年度18.7%、平成30年度18.0%)や、令和4年度の目標値(約27%)が達成困難であった状況から、目標と現実の間に大きな乖離が継続していることがわかります(26)。
- 排出形態
- 特別区、特に千代田区、中央区、港区などの都心部では、事業活動に伴うごみが家庭ごみを上回るという都市特有の課題があります。このため、事業者に特化した施策が不可欠です(29)。
課題
住民の課題
住民が抱える最大の課題は、環境意識の欠如ではなく、複雑で手間のかかる分別システムそのものにあります。「意識と行動のギャップ」は、住民の怠慢ではなく、行動の対価(手間の多さ)と利益(環境改善の実感の薄さ)のアンバランスが生み出すシステム設計上の欠陥と捉えるべきです。この視点の転換は、政策の方向性を「住民を教育する」から「住民が行動しやすいシステムをデザインする」へと根本的に変えることを要求します。
意識と行動のギャップ:分別の「面倒くささ」
- 3Rに対する高い認知度(88.3%)と、日常的に徹底して行動している人の割合(18.0%)との間には、大きなギャップが存在します。これが行動変容を阻む最大の壁です。
- 客観的根拠:
- 分別が徹底されない最大の理由は、「面倒だから、手間がかかるから」という回答が最多であり、住民が感じる負担の大きさを物語っています。
- 客観的根拠:
- (出典)日本コカ・コーラ株式会社「ゴミの分別に関する意識調査」によれば、分別が十分にできていない理由の第1位は「めんどうだから、手間がかかるから」(29.5%)でした(30)。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:資源化可能な物が可燃ごみに混入し続け、リサイクル率の向上は望めず、処理コストも高止まりします。
分別の複雑さと知識不足
- 分別ルールが区ごとに異なり、また細かく複雑であるため、善意の住民でさえ意図せず誤った分別をしてしまい、資源の品質を低下させる一因となっています。
- 客観的根拠:
- (出典)筑波大学社会工学類「学生宿舎におけるゴミの分別行動に関する研究」によれば、分別を行っていると自己認識している学生でも、必ずしも全員が正しい知識を持っているわけではないことが示唆されています(32)。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:回収された資源の品質が低下し、リサイクル工程での選別コストが増大、最悪の場合は資源化できずに処分されます。
リデュース・リユース意識の浸透不足
- 住民の意識や行動が、3Rの中で最も優先順位の低い「リサイクル」に偏りがちです。より効果の高い「リデュース」(使い捨て容器を避ける等)や「リユース」(修理して使う等)の実践は、まだ十分に浸透していません。
- 客観的根拠:
- (出典)環境省「3Rに関する意識調査」では、ペットボトルや缶の分別といったリサイクル行動に比べ、「壊れたものを修理して使う」といったリユース行動の実践率は低い傾向にあります(8)。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:ごみの発生総量が根本的に減らず、リサイクル・処分システムへの負荷が恒久的に高いままとなります。
地域社会の課題
食品ロスの継続的な発生
- 家庭や事業者から排出されるごみの中に、依然として多くの食品ロスが含まれています。これは経済的・環境的資源の大きな無駄であり、温室効果ガス発生の原因ともなっています。
- 客観的根拠:
- (出典)豊島区「食品ロス削減推進計画」が実施した燃やすごみの組成分析調査では、未利用食品が全体の3.2%を占めていました(33)。国もこの問題を重視し、2030年度までに2000年度比で食品ロスを半減させる目標を掲げています(15)。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:貴重な食料資源が無駄になると同時に、本来不要な廃棄物処理に多大な環境的・財政的コストが費やされ続けます。
地域コミュニティにおける協力体制の希薄化
- 町会やPTAなどが主体となる「集団回収」は、行政コストをかけずに資源を回収できる有効な手段ですが、担い手の高齢化や地域コミュニティの希薄化により、その活動基盤が揺らいでいます。
- 客観的根拠:
- (出典)東京二十三区清掃一部事務組合「資源回収の状況」において「集団回収」が独立した回収区分として統計管理されている事実は、その重要性を示しています。一方で、全国的な地域コミュニティの弱体化という社会背景と合わせると、この制度の持続可能性に課題があることは明らかです(25)。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:効率的かつ低コストな資源回収ルートが失われ、その分を行政が直接回収せざるを得なくなり財政負担が増加します。
行政の課題
行政が直面する課題は、リサイクルシステムの経済的な破綻です。「逆有償」、つまりお金を払って資源を引き取ってもらう取引が常態化している事実は、多くのリサイクル市場が機能不全に陥っていることを示す明確なシグナルです。自治体は、国や世界レベルで歪んだシステムの経済的損失を吸収させられており、これは持続不可能なモデルです。この問題は、単なる地域の収集・啓発活動をはるかに超えた、市場全体に働きかける政策介入を必要としています。
リサイクル事業の採算性悪化(逆有償問題)
- 特にプラスチック類や小型家電など一部の品目では、自治体がリサイクル事業者に処理費用を支払って引き取ってもらう「逆有償」が一般化しており、深刻な財政負担となっています。
- 客観的根拠:
- (出典)経済産業省「小型家電リサイクルワーキンググループ 資料」において、小型家電リサイクルにおいて、逆有償取引の割合は平成25年度のわずか0.3%から、令和5年度には**63.3%**へと爆発的に増加しており、自治体への直接的なコスト負担が急増しています(35)。(出典)多摩市「プラスチック使用製品の分別収集と再商品化」の施行後も、多くの自治体がこのコスト負担を懸念し、製品プラスチックの回収に踏み出せずにいます(36)。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:リサイクルを行う経済的インセンティブが完全に失われ、新たな資源化の取り組みが停滞し、回収された資源が適正処理されず滞留するリスクが高まります。
リサイクル率の伸び悩みと目標未達
- 長年の取り組みにもかかわらず、国全体および23区のリサイクル率は横ばい状態で、行政が掲げる政策目標を恒常的に達成できていません。
- 客観的根拠:
- (出典)環境省「一般廃棄物処理事業実態調査(令和5年度実績)」によると、国のリサイクル率は過去10年間、19.5%~20%台で停滞しています(14)。(出典)東京二十三区清掃一部事務組合「一般廃棄物処理基本計画」では、23区は令和4年度に約27%の目標を掲げましたが、実績は18%程度に留まっており、目標と現実の大きな乖離が続いています(27)。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:循環型社会への移行が停滞し、資源の海外依存や最終処分場の逼迫といった根本的な問題が解決されません。
施策の費用対効果の検証不足
- 多くの3R施策が、その費用に対してどれほどの効果があったのか、客観的なデータに基づく厳密な評価(EBPM)がなされないまま継続されています。これにより、限られた財源の最適配分が妨げられています。
- 客観的根拠:
- これは3R分野に限った話ではありませんが、行政改革全体の大きな潮流としてEBPMの推進が強く求められています。特に逆有償のような見えにくいコストや、効果が拡散しやすい廃棄物行政は、より厳密なデータ駆動型の政策評価が不可欠な分野です。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:効果の低い施策に予算が投入され続け、より効果的な施策へ資源を再配分できず、行政システム全体の非効率化を招きます。
行政の支援策と優先度の検討
優先順位の考え方
※各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
- 即効性・波及効果
- 施策の実施から効果発現までの期間が短く、複数の課題解決や多くの住民への便益につながる施策を高く評価します。
- 実現可能性
- 現在の法制度、予算、人員体制の中で実現可能な施策を優先します。既存の仕組みを活用できる施策は優先度が高くなります。
- 費用対効果
- 投入する経営資源(予算・人員等)に対して得られる効果が大きい施策を優先します。将来的な財政負担の軽減効果も考慮します。
- 公平性・持続可能性
- 特定の層だけでなく、幅広い住民に便益が及ぶ施策を優先します。一時的ではなく、長期的に効果が持続する施策を高く評価します。
- 客観的根拠の有無
- 政府資料や先行事例等で、エビデンスに基づく効果が示されている施策を優先します。
支援策の全体像と優先順位
- 3R推進の施策は、「行動変容・ライフスタイル転換」「制度・インフラ改革」「市場創出・経済的インセンティブ」の3つの柱で総合的に展開する必要があります。
- 特に、住民が直面する「面倒くささ」を直接解消し、かつ最も優先順位の高い「リデュース」「リユース」に直結する施策は、費用対効果と波及効果の観点から優先度を最も高く設定します。
- 具体的には、支援策①「リデュース・リユース最優先のライフスタイル転換支援」を最優先とし、次にリサイクルシステムの構造的課題に取り組む支援策②「持続可能な資源循環システムの構築」、そしてこれらの施策効果を最大化するための基盤として**支援策③「データとDXを活用した行動変容と施策最適化」**を位置づけます。
各支援策の詳細
支援策①:リデュース・リユース最優先のライフスタイル転換支援
目的
- 廃棄物ヒエラルキーの最上位であるリデュースとリユースを徹底することにより、ごみの発生量そのものを根本的に削減することを目指します。
- 客観的根拠:
- (出典)環境省「循環型社会形成推進基本法」は、発生抑制(リデュース)を最も優先すべき取り組みとして定めています(1)。
- 客観的根拠:
主な取組①:食品ロス削減プログラムの強化
- 地域のスーパーやコンビニと連携し、消費期限の近い商品を積極的に選んでもらう「てまえどり」を強力に推進します(37)。
- 港区や豊島区の事例を参考に、飲食店での食べ残し削減を促す「食べきり協力店」制度を拡充し、参加店舗や利用者へのインセンティブ導入を検討します(33)。
- 区の施設を常設のフードドライブ拠点とし、家庭で余った食品の回収を促進するとともに、企業版フードドライブの展開により事業系食品ロスも捕捉します(39)。
- 段ボールコンポストなど、家庭で手軽に始められる生ごみ堆肥化の講座開催や初期費用の助成を行います(39)。
- 客観的根拠:
- (出典)港区「港区一般廃棄物処理基本計画(第3次)」では、一般廃棄物処理基本計画の中に食品ロス削減推進計画を包含し、フードドライブの拡充や食べきり協力店制度を重点施策として位置づけています(42)。
- 客観的根拠:
主な取組②:リユース文化の醸成
- 徳島県上勝町の「くるくるショップ」をモデルに、区が運営または補助するリユース拠点を設置し、不要になった日用品を手軽に譲り合える場を提供します(44)。
- 家具や自転車、小型家電などを対象とした修理費用の助成制度を創設し、製品の長寿命化を支援します。
- 地域の商店街等と連携し、テイクアウト容器やコーヒーカップのリユース(デポジット制の導入や割引インセンティブ等)を促進します。
- 客観的根拠:
- (出典)環境省「循環型社会形成推進基本法」によると、リユースはリサイクルよりも優先順位が高く、製品そのものを再使用するため、資源化に伴うエネルギー消費やコストを大幅に削減できます(2)。
- 客観的根拠:
主な取組③:次世代への行動変容を促す環境教育
- 板橋区の「かたつむり運動」のように、子どもたちが楽しみながら3Rを学べるキャラクター主導の教育プログラムを開発し、区内の小中学校やイベントで展開します。
- 「かたづけじょうず」「たいせつにつかう」といった具体的な行動目標を掲げ、歌やぬり絵を通じて幼少期からごみを減らす生活習慣を育みます(7)。
- 客観的根拠:
- (出典)板橋区「板橋区一般廃棄物処理基本計画」では、「板橋かたつむり運動」を一般廃棄物処理基本計画の主要施策と位置づけ、区民・事業者・行政の連携による実践を目指しています(46)。
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 区民一人一日当たりの家庭系ごみ排出量の削減(例:令和14年度までに令和5年度比15%削減)
- データ取得方法: 毎年のごみ収集実績データ及び組成分析調査
- KSI(成功要因指標)
- 食品ロス量の削減(例:令和12年度までに平成30年度比50%削減)
- データ取得方法: ごみ組成分析調査による食品ロス割合の測定
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 「てまえどり」実践率、食べきり協力店登録店舗数
- データ取得方法: 店頭でのアンケート調査、店舗登録台帳
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- フードドライブ回収重量、環境教育プログラムの年間参加者数
- データ取得方法: 回収拠点での計量記録、イベント参加者名簿
支援策②:持続可能な資源循環システムの構築
目的
- リサイクル率の停滞を打破し、逆有償問題に代表される経済的な持続不可能性を解消するため、住民にとって分かりやすく、経済的に成立する資源循環システムを構築します。
- 客観的根拠:
- (出典)経済産業省「小型家電リサイクルワーキンググループ 資料」によると、小型家電の逆有償取引の割合が63.3%に達するなど、現行のリサイクルシステムは経済的に限界を迎えており、構造的な改革が急務です(35)。
- 客観的根拠:
主な取組①:プラスチック資源の一括回収の段階的導入
- 富山市などの先進事例を参考に、これまで別々に回収していた「容器包装プラスチック」と「製品プラスチック」を一体で回収する「プラスチック資源一括回収」をモデル地区で試行し、段階的に全区へ展開します。
- これにより、住民の分別負担(「これはどっち?」という迷い)を大幅に軽減し、回収率の向上を目指します(20)。
- 客観的根拠:
- (出典)富山市「プラスチック資源の一括回収について」によると、令和4年4月に施行されたプラスチック資源循環法により、市町村が製品プラスチックを含めて一体的に分別回収し、再資源化することが可能となりました(20)。
- 客観的根拠:
主な取組②:分別ルールの簡素化と「わかりやすさ」の追求
- 区内の分別ルールを全面的に見直し、簡素化・統一化できる部分がないか検討します。
- 飲料メーカー等と連携し、分別時の手間(面倒くささ)の大きな原因であるラベルを剥がす作業が不要な「ラベルレスボトル」の普及を積極的に後押しします(50)。
- 客観的根拠:
- (出典)日本コカ・コーラ株式会社「ゴミの分別に関する意識調査」によると、消費者の声として「ペットボトルのラベルはがしが面倒」という意見が多く、ラベルレス製品は分別時の負担を軽減する有効な手段です(50)。
- 客観的根拠:
主な取組③:公共調達における再生材利用の率先(グリーン購入)
- 区が発注する公共工事や購入する物品(事務用品、ベンチ等)において、再生材を一定割合以上使用した製品の利用を義務化または優先する「グリーン購入方針」を策定・徹底します。
- これにより、再生材の安定的な需要を創出し、リサイクル市場を内側から支えます。
- 客観的根拠:
- (出典)環境省「循環型社会形成推進基本法」は、国や地方公共団体に対し、再生品の使用促進に努めることを求めています(1)。
- 客観的根拠:
主な取組④:逆有償問題への対策支援
- 国や東京都に対し、再生材の利用を製品メーカーに義務付ける制度(リサイクル材利用目標の設定)や、高度なリサイクル技術への補助金拡充など、市場を正常化させるための政策を積極的に提言します。
- 光学選別機などを備えた高度な選別施設を公民連携(PPP)で整備することを検討し、回収した資源の品質と市場価値を高めることで、逆有償取引の解消を目指します(52)。
- 客観的根拠:
- (出典)環境省「循環型社会形成推進基本法」によると、自治体単独での解決は困難であり、国レベルでの拡大生産者責任の徹底や、技術開発支援といった施策が不可欠です(2)。
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- リサイクル率の向上(例:令和14年度までに35%達成)
- データ取得方法: 毎年の清掃事業年報等の統計データ
- KSI(成功要因指標)
- プラスチック資源の総回収量の増加
- データ取得方法: ごみ収集実績データ
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 逆有償取引にかかる区の財政負担額の削減
- データ取得方法: 廃棄物処理委託契約に関する会計データ
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 公共調達における再生材利用製品の購入額・購入割合
- データ取得方法: 契約管財部門の調達実績データ
支援策③:データとDXを活用した行動変容と施策最適化
目的
- デジタル技術を活用して、住民一人ひとりへの情報提供やフィードバックを強化し、参加のハードルを下げるとともに、収集データを分析して施策の最適化を図ります。
主な取組①:ごみ分別促進スマートフォンアプリの開発・提供
- 「これは何ごみ?」と検索できるAIチャットボット機能、収集日をお知らせするプッシュ通知機能、リサイクル活動への参加でポイントが貯まるゲーミフィケーション機能などを搭載した、利便性の高い公式アプリを開発・提供します。
- 客観的根拠:
- (出典)東京都環境局「事業系廃棄物3Rガイド」によると、行政手続きのオンライン化は国全体のDX推進計画の柱であり、ごみ分別という身近な行政サービスにDXを適用することは住民の利便性向上に直結します(53)。
- 客観的根拠:
主な取組②:住民へのフィードバック強化
- アプリや広報誌を通じて、「今月、皆さんの協力で回収されたペットボトルは、Tシャツ〇〇枚分に生まれ変わりました」といった、具体的で分かりやすい成果を定期的にフィードバックします。
- これにより、自分の行動が社会貢献につながっているという実感(自己効力感)を高め、継続的な協力意欲を引き出します(54)。
- 客観的根拠:
- (出典)徳島県上勝町「ゼロ・ウェイストの取り組み」では、資源の売却益をポイントで住民に還元するなど、行動の成果を「見える化」することが、高いリサイクル率を維持する要因の一つとなっています(54)。
- 客観的根拠:
主な取組③:データ分析に基づく重点的啓発
- 収集ごみの量や組成調査から得られるエリア別のデータ(異物混入率など)を分析し、分別の徹底度が低い地域や集合住宅などを特定します。
- 画一的な広報ではなく、特定されたエリアに対して集中的に啓発資材を配布したり、出前講座を実施したりするなど、データに基づいた効率的なアプローチを行います。
- 客観的根拠:
- EBPM(証拠に基づく政策立案)の考え方に基づき、客観的データを用いて課題を特定し、的を絞った介入を行うことで、施策の効果を最大化します。
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 住民の分別満足度・協力意欲の向上(例:満足度80%以上)
- データ取得方法: 毎年の区民意識調査
- KSI(成功要因指標)
- ごみ分別アプリのダウンロード数・アクティブ利用率
- データ取得方法: アプリの管理サーバーからのアクセス解析データ
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 資源ごみの異物混入率の低下
- データ取得方法: 中間処理施設でのサンプル調査
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- アプリを通じた情報発信回数、プッシュ通知の開封率
- データ取得方法: アプリ管理システムのログデータ
先進事例
東京都特別区の先進事例
港区「官民学連携による包括的3R推進」
- 港区は、区民・事業者・行政の三者で構成される「3R推進行動会議」を平成18年から設置し、協働による3R推進のプラットフォームとして機能させています。この会議を通じて、多様な主体の意見を計画に反映し、地域一体となった取り組みを展開している点が先進的です(57)。
- また、「一般廃棄物処理基本計画(第3次)」では、食品ロス削減推進計画を内包し、令和14年度に資源化率50%という高い目標を掲げるなど、包括的かつ意欲的な計画を策定しています。フードドライブの拡充や食べきり協力店の表彰制度など、具体的施策も充実しています(43)。
- 客観的根拠:
板橋区「『かたつむり運動』による次世代への環境教育」
- 板橋区は、「かたつむり運動」と名付けたユニークな普及啓発活動を展開しています。これは、「かたづけじょうず」「たいせつにつかう」「つかいきる」「むだにしない」「りさいくる」の5つのおやくそくを、キャラクター(かたつむりん)や歌、ぬり絵などを通じて、特に子どもたちに楽しく学んでもらう取り組みです(7)。
- 難しい環境問題を、親しみやすい社会的マーケティング手法で浸透させ、幼少期からの行動変容を促す優れたモデルケースと言えます。この運動は、区の一般廃棄物処理基本計画にも主要施策として位置づけられています(46)。
- 客観的根拠:
世田谷区「2R重視への転換を掲げた新基本計画」
- 世田谷区は、令和7(2025)年度から始まる新たな「一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。この計画の大きな特徴は、これまでの3R推進から、さらに発生抑制(リデュース)と再使用(リユース)の「2R」に重点を置く方針を明確に打ち出した点です(60)。
- これは、全国的にリサイクル率が伸び悩む中、廃棄物問題の根本解決には、より優先順位の高いリデュース・リユースが不可欠であるという、国のデータが示す課題認識に的確に対応した戦略的な方針転換であり、他の自治体が参照すべき先進的な動きです。
- 客観的根拠:
全国自治体の先進事例
徳島県上勝町「ゼロ・ウェイスト宣言と住民参加の仕組み」
- 上勝町は、2003年に日本で初めて「ゼロ・ウェイスト宣言」を行ったことで知られています。その成功の鍵は、有名な45分別だけでなく、住民の参加を支える巧みな社会インフラにあります。
- ごみを持ち込む「ごみステーション」が住民同士の交流の場として機能し、不要品を無料で譲り合える「くるくるショップ」がリユースを具体的に促進しています(44)。
- さらに、資源の売却益を日用品と交換できる「ちりつもポイント」制度が直接的なインセンティブとなり、高齢者などごみの持ち込みが困難な世帯には無料の運搬支援制度を提供するなど、誰も取り残さない仕組みが構築されています(54)。
- 客観的根拠:
熊本県水俣市・福岡県みやま市「地域資源循環モデルの構築」
- 水俣市とみやま市は、生ごみやし尿汚泥といった有機性廃棄物を、地域のバイオマスセンターで資源化するモデルを構築しています。
- 水俣市は水俣病の教訓から「ごみになるものを家に持ち込まない」暮らしを提唱し、生ごみ処理機「キエーロ」の無償貸与などを通じてリサイクルを推進しています(63)。
- みやま市では、メタン発酵施設「ルフラン」で生ごみからバイオガス(発電)と液肥を生成。エネルギーと肥料の地産地消を実現し、ごみ処理費用の削減と温室効果ガス削減を同時に達成しています(66)。これらは、廃棄物を地域内で価値ある資源に変える、具体的な循環経済の好事例です。
- 客観的根拠:
参考資料[エビデンス検索用]
政府(省庁)関連資料
- 環境省「令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」令和7年度(3)
- 環境省「一般廃棄物処理事業実態調査(令和5年度実績)」令和7年3月公表(14)
- 環境省「第五次循環型社会形成推進基本計画」令和6年8月閣議決定(10)
- 環境省「循環型社会形成推進基本法」(1)
- 経済産業省「産業構造審議会 産業技術環境分科会 廃棄物・リサイクル小委員会 小型家電リサイクルワーキンググループ 資料」(35)
- 内閣府「世論調査 循環型社会に関する意識について」(69)
東京都・特別区関連資料
- 東京二十三区清掃一部事務組合「清掃事業年報(令和5年度版)」(24)
- 東京二十三区清掃一部事務組合「資源回収の状況(令和5年度)」(25)
- 港区「港区一般廃棄物処理基本計画(第3次)」令和3年度(43)
- 板橋区「板橋区一般廃棄物処理基本計画」平成30年度(46)
- 世田谷区「世田谷区一般廃棄物処理基本計画(2025年度~2034年度)」令和7年度(61)
- 豊島区「食品ロス削減推進計画」関連資料(33)
その他機関・団体資料
- (https://www.3r-suishin.jp/?p=938)(70)
- 株式会社はぐくみプラス「環境意識と詰め替え商品についてのアンケート」2024年(71)
- 日本コカ・コーラ株式会社「ゴミの分別に関する意識調査」2020年(30)
まとめ
東京都特別区における3Rの推進は、重大な転換点にあります。ごみ総量の削減(リデュース)では一定の成果が見られるものの、リサイクル率の長期的な停滞は、住民が感じる分別の煩わしさ(ハッスルファクター)と、行政が直面するリサイクル事業の経済的持続不可能性(逆有償問題)という二つの構造的課題に起因しています。今後の政策は、リサイクル一辺倒の発想から脱却し、食品ロス削減を筆頭に、より優先度の高いリデュース・リユース施策に大胆に舵を切るべきです。リサイクルに関しては、単なる回収量の増加を目指すのではなく、住民にとっての分かりやすさを追求した分別システムの簡素化、DX活用による行動変容の促進、そして公共調達などを通じた再生材の国内市場創出による、真に持続可能な循環システムの構築が不可欠です。この統合的かつエビデンスに基づいたアプローチこそが、真の循環型経済を実現し、特別区の長期的な環境的・財政的健全性を確保する鍵となります。
本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。




-320x180.jpg)

-320x180.jpg)