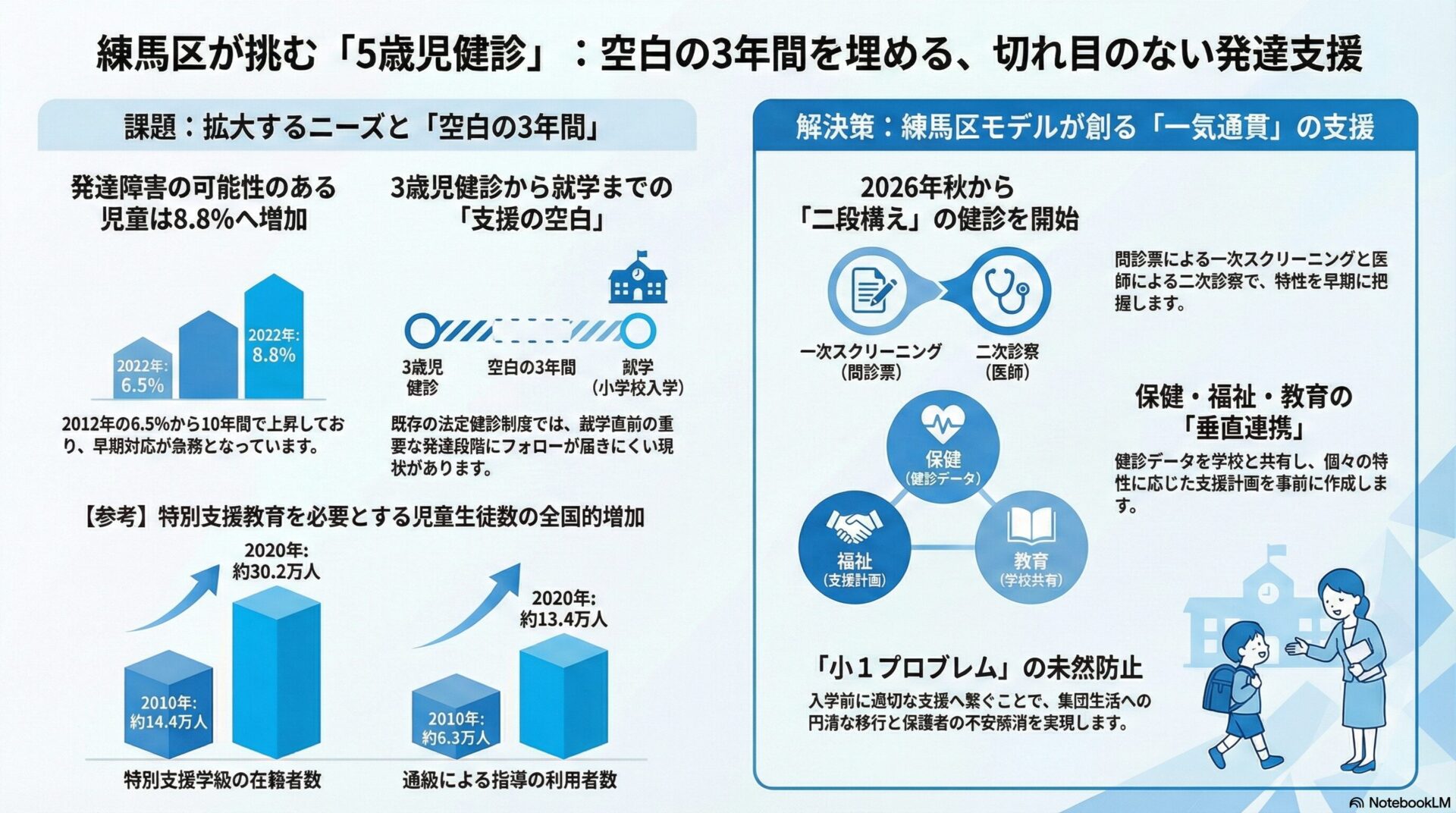認知症施策の推進

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
概要(認知症施策を取り巻く環境)
- 自治体が認知症施策を推進する意義は、第一に、令和5年に施行された認知症基本法が掲げる「共生」の理念を具現化し、認知症を単なる医療の問題から社会全体で支える課題へと転換することにあります。第二に、2040年には高齢者の約3.3人に1人が認知症またはその予備群である軽度認知障害(MCI)になると推計される超高齢社会に備え、強靭で包摂的な地域コミュニティを構築することにあります。
- 本記事では、東京都特別区における認知症施策の現状を客観的データに基づき分析し、直面する課題を明確化した上で、具体的な政策提言を優先度とともに示します。
意義
住民にとっての意義
- 尊厳の保持と希望ある暮らしの継続
- 認知症になっても、住み慣れた地域で尊厳と希望を持ち、自分らしい暮らしを続けることが可能になります。早期からの適切な支援は、本人の意思決定を支え、生活の質(QOL)を維持・向上させます。
- 介護者の負担軽減と孤立防止
- 認知症初期集中支援チームや認知症カフェ、ピアサポート活動など、公的およびインフォーマルな支援ネットワークが整備されることで、介護を一人で抱え込みがちな家族の身体的・精神的負担が軽減され、社会からの孤立を防ぎます。
地域社会にとっての意義
- 「認知症にやさしいまち」の実現
- 認知症サポーターの養成や地域活動を通じて、認知症に対する偏見や誤解が解消され、誰もが支え手となり、また受け手ともなり得る相互扶助の文化が醸成されます。これは、全ての住民にとって暮らしやすい「認知症フレンドリーな社会」の実現につながります。
- (出典)板橋区「チームオレンジ 活動の手引き」 7
- (出典)(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/000382001.pdf) 8
- 認知症サポーターの養成や地域活動を通じて、認知症に対する偏見や誤解が解消され、誰もが支え手となり、また受け手ともなり得る相互扶助の文化が醸成されます。これは、全ての住民にとって暮らしやすい「認知症フレンドリーな社会」の実現につながります。
- 地域コミュニティの活性化と安全網の強化
- 見守りネットワークや認知症カフェといった活動は、地域住民間のつながりを再構築し、コミュニティを活性化させます。この強化された地域のつながりは、認知症の人だけでなく、子どもや障害者など、支援を必要とする全ての人々を守るセーフティネットとして機能します。
- (出典)練馬区「練馬区高齢者見守りネットワーク事業協定」 9
- 見守りネットワークや認知症カフェといった活動は、地域住民間のつながりを再構築し、コミュニティを活性化させます。この強化された地域のつながりは、認知症の人だけでなく、子どもや障害者など、支援を必要とする全ての人々を守るセーフティネットとして機能します。
行政にとっての意義
- 社会的コストの最適化
- 発症初期からの予防や支援に重点を置くことで、症状の重度化を防ぎ、高コストな施設入所や入院医療への依存を軽減します。これにより、長期的な視点での社会保障給付費の最適化が期待できます。
- 法令遵守と計画的な行政運営
- 認知症基本法に基づく施策推進は、自治体に課された責務です。国の基本計画や都の推進計画と連携し、客観的データに基づいた計画的な行政運営(EBPM)を行うことで、効果的かつ効率的な政策展開が可能となります。
- (出典)厚生労働省「認知症施策のこれまでの主な取組」 12
- (出典)厚生労働省「認知症施策推進基本計画」令和6年 13
- 認知症基本法に基づく施策推進は、自治体に課された責務です。国の基本計画や都の推進計画と連携し、客観的データに基づいた計画的な行政運営(EBPM)を行うことで、効果的かつ効率的な政策展開が可能となります。
(参考)歴史・経過
- 2004年
- 厚生労働省が「痴呆」を「認知症」に改めることを決定し、呼称変更を機に偏見の払拭と正しい理解の促進を目指しました。これは、認知症施策における象徴的な転換点となりました。
- (出典)日本ヘルスプロモーションネットワーク「認知症施策の変遷」 14
- 厚生労働省が「痴呆」を「認知症」に改めることを決定し、呼称変更を機に偏見の払拭と正しい理解の促進を目指しました。これは、認知症施策における象徴的な転換点となりました。
- 2005年
- 地域で認知症の人や家族を支える応援者「認知症サポーター」の養成事業が開始されました。住民一人ひとりの理解を深めることで、社会全体の支援基盤を構築する草の根の取り組みです。
- (出典)全国キャラバン・メイト連絡協議会「認知症サポーターキャラバンとは」 15
- (出典)厚生労働省「認知症施策のこれまでの主な取組」 12
- 地域で認知症の人や家族を支える応援者「認知症サポーター」の養成事業が開始されました。住民一人ひとりの理解を深めることで、社会全体の支援基盤を構築する草の根の取り組みです。
- 2012年
- 「認知症施策推進五か年計画(オレンジプラン)」が策定され、初めて国の総合的な戦略が示されました。この中で、認知症初期集中支援チームや認知症カフェといった、現在の施策の原型となる概念が導入されました。
- (出典)日本ヘルスプロモーションネットワーク「認知症施策の変遷」 14
- 「認知症施策推進五か年計画(オレンジプラン)」が策定され、初めて国の総合的な戦略が示されました。この中で、認知症初期集中支援チームや認知症カフェといった、現在の施策の原型となる概念が導入されました。
- 2015年
- 「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」が策定され、地域の実情に応じた支援体制の構築がより一層重視されるようになりました。7つの柱を掲げ、各種施策の具体的な数値目標が設定されました。
- (出典)(https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/appContents/wamnet_orangeplan_explain.html) 16
- (出典)厚生労働省「認知症施策のこれまでの主な取組」 12
- 「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」が策定され、地域の実情に応じた支援体制の構築がより一層重視されるようになりました。7つの柱を掲げ、各種施策の具体的な数値目標が設定されました。
- 2019年
- 「認知症施策推進大綱」が閣議決定され、「共生」と「予防」が施策の2つの柱として明確に位置づけられました。これは、認知症の発症を遅らせ、なっても希望を持って暮らし続けられる社会を目指すという国の強い意志を示すものです。
- (出典)厚生労働省「認知症施策のこれまでの主な取組」 12
- (出典)日本医療政策機構「認知症政策の変遷」 17
- 「認知症施策推進大綱」が閣議決定され、「共生」と「予防」が施策の2つの柱として明確に位置づけられました。これは、認知症の発症を遅らせ、なっても希望を持って暮らし続けられる社会を目指すという国の強い意志を示すものです。
- 2023年6月
- 「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立しました。これにより、認知症施策は単なる行政計画から、国民の権利と尊厳を守るための法的基盤を持つものへと格上げされ、国および地方自治体に施策推進計画の策定が義務付けられました。
- (出典)厚生労働省「認知症施策のこれまでの主な取組」 12
- (出典)日本医療政策機構「認知症施策推進基本計画(案)の閣議決定に寄せて」 17
- 「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立しました。これにより、認知症施策は単なる行政計画から、国民の権利と尊厳を守るための法的基盤を持つものへと格上げされ、国および地方自治体に施策推進計画の策定が義務付けられました。
- 2024年12月
- 認知症基本法に基づき、今後おおむね5年間の国の施策の方向性を示す「認知症施策推進基本計画」が閣議決定されました。これにより、都道府県・市町村は、この基本計画を基に、地域の実情に応じた具体的な計画を策定することが求められます。
- (出典)厚生労働省「認知症施策推進基本計画」令和6年 13
- 認知症基本法に基づき、今後おおむね5年間の国の施策の方向性を示す「認知症施策推進基本計画」が閣議決定されました。これにより、都道府県・市町村は、この基本計画を基に、地域の実情に応じた具体的な計画を策定することが求められます。
認知症施策に関する現状データ
- 認知症高齢者数の将来推計
- 全国の動向(2024年最新推計): 厚生労働省の研究班による最新の推計では、日本の65歳以上の認知症高齢者数は、2022年の約443万人(有病率12.3%)から、高齢者人口がピークを迎える2040年には約584万人(有病率14.9%)に達すると見込まれています。これは2012年の推計(2040年に802万人)からは下方修正されたものの、依然として大幅な増加傾向にあります。
- 軽度認知障害(MCI)の動向: 今回の推計では、初めてMCI(軽度認知障害)の有病者数が算出されました。2022年時点で約559万人(有病率15.5%)と、認知症の人数を上回っており、2040年には約613万人(有病率15.6%)になると推計されています。認知症とMCIを合わせると2022年時点で1,000万人を超えており、高齢者の約3.6人に1人が認知症またはその予備群であるという現状は、政策の対象を「認知症ケア」から、より広い「脳の健康支援」へと拡大する必要性を示唆しています。
- 東京都の動向(2025年推計): 東京都では、団塊の世代が後期高齢者となる2025年(令和7年)には、認知症高齢者数が約56万人に達すると推計されています。そのうち、見守りや何らかの支援が必要な人は約42万人に上ると見込まれており、大都市特有の課題の深刻さが浮き彫りになっています。
- 若年性認知症の現状
- 有病者数と有病率: 65歳未満で発症する若年性認知症の全国の有病者数は、約3.57万人と推計されています。18歳から64歳までの人口10万人当たりでは50.9人となり、前回調査(2009年)の47.6人から有病率は上昇しています。これは、対象となる生産年齢人口の減少が背景にあり、決して問題が軽くなったわけではないことを示しています。
- (出典)社会保険研究所「若年性認知症の有病者数は3.57万人」2020年 21
- (出典)厚生労働省「若年性認知症実態調査結果概要」令和2年 22
- 経済的影響: 若年性認知症は、働き盛りの世代を直撃するため、経済的な影響が極めて深刻です。発症時に就労していた人のうち、調査時点で約7割が退職に追い込まれていました。また、約6割が世帯収入の減少を実感しており、主たる収入源が障害年金(約4割)や生活保護(約1割)となっている実態があります。
- 有病者数と有病率: 65歳未満で発症する若年性認知症の全国の有病者数は、約3.57万人と推計されています。18歳から64歳までの人口10万人当たりでは50.9人となり、前回調査(2009年)の47.6人から有病率は上昇しています。これは、対象となる生産年齢人口の減少が背景にあり、決して問題が軽くなったわけではないことを示しています。
- 支援体制の普及状況
- 認知症サポーター: 国民の理解を広げる基盤として、認知症サポーターの養成は着実に進展しています。全国のサポーター数は2017年の約892万人から、2023年6月末には1,464万人を超え、当初の目標を大幅に上回っています。東京都内でもその数は増加を続けており、2022年3月末の約92.7万人から、2023年3月末には約98.7万人へと増加しました。
- 認知症カフェ: 認知症の人や家族の身近な居場所である認知症カフェは、令和4年度時点で全国1,563市町村(設置率89.8%)に8,182箇所設置されています。コロナ禍で一時的に減少(令和2年度末7,737箇所)しましたが、回復傾向にあります。東京都内では令和5年3月末時点で615箇所が設置されており、地域共生の拠点として重要な役割を担っています。
- 認知症初期集中支援チーム: 早期診断・早期対応の中核を担う認知症初期集中支援チームは、2017年度までに全国のほぼ全ての市町村(98%)に設置が完了しました。東京都内では、令和5年4月時点で特別区および市町村に合計232チームが配置され、活動しています。
- 行方不明者の状況
- 警察庁の発表によると、令和6年に全国の警察に届け出があった認知症(またはその疑い)が原因の行方不明者数は、のべ18,121人でした。前年よりは減少したものの、依然として1日に約50人が行方不明になっている計算となり、極めて高い水準で推移しています。
- (出典)警察庁「令和6年における行方不明者届受理等の状況」 29
- (出典)ケア・フロント「令和6年の認知症に係る行方不明者数」 30
- 行方不明者の多くは発見・保護されていますが(令和4年中の所在確認率は96.6%)、発見時に死亡が確認されるケースも後を絶ちません(令和4年中に491人)。これは、捜索・発見体制の強化が、文字通り人命に直結する喫緊の課題であることを示しています。
- (出典)警察庁「令和4年中の行方不明者の状況」 31
- (出典)NHK「認知症 去年の行方不明者 死亡の7割以上が5キロ圏内 警察庁」 30
- 警察庁の発表によると、令和6年に全国の警察に届け出があった認知症(またはその疑い)が原因の行方不明者数は、のべ18,121人でした。前年よりは減少したものの、依然として1日に約50人が行方不明になっている計算となり、極めて高い水準で推移しています。
課題
住民の課題
- 深刻な介護者の負担と孤立
- 認知症の人を在宅で介護する家族は、終わりが見えない介護に対する精神的・身体的な負担を抱えています。調査では、介護者の45%が介護を「非常に負担」「まあまあ負担」と感じており、具体的な感情として「漠然とした不安がある」(45.5%)、「いらいらする」(32.7%)、「気分が落ち込む」(25.6%)といったネガティブな回答が高い割合を占めています。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 介護を理由とした離職(介護離職)の増加や、介護者の心身の健康悪化、さらには介護疲れを背景とした虐待へと発展するリスクが高まります。
- 認知症の人を在宅で介護する家族は、終わりが見えない介護に対する精神的・身体的な負担を抱えています。調査では、介護者の45%が介護を「非常に負担」「まあまあ負担」と感じており、具体的な感情として「漠然とした不安がある」(45.5%)、「いらいらする」(32.7%)、「気分が落ち込む」(25.6%)といったネガティブな回答が高い割合を占めています。
- 若年性認知症の経済的・社会的困難
- 働き盛りの世代で発症する若年性認知症は、本人のキャリアだけでなく、家族全体の生活基盤を揺るがします。調査によると、発症時に就労していた人の約7割が退職しており、これが世帯収入の減少に直結しています。また、子育て世代と重なることも多く、子どもの進学や将来設計にも深刻な影響を及ぼすという、高齢者の認知症とは異なる特有の課題があります。
- 客観的根拠:
- (出典)厚生労働省「若年性認知症実態調査結果概要」令和2年 22
- (出典)埼玉県「若年性認知症について」令和4年 32
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 個々の家庭の経済的破綻に留まらず、子どもの貧困や教育機会の格差といった、世代を超えて連鎖する新たな社会問題を生み出します。
- 客観的根拠:
- 働き盛りの世代で発症する若年性認知症は、本人のキャリアだけでなく、家族全体の生活基盤を揺るがします。調査によると、発症時に就労していた人の約7割が退職しており、これが世帯収入の減少に直結しています。また、子育て世代と重なることも多く、子どもの進学や将来設計にも深刻な影響を及ぼすという、高齢者の認知症とは異なる特有の課題があります。
- 早期診断への心理的・制度的障壁
- 本人や家族が「何かおかしい」と感じても、認知症への偏見や、「年だから仕方ない」という思い込みから、医療機関への受診をためらうケースが多く見られます。ある調査では、初期症状が疑われても3人に2人は早期受診をしないと回答しており、診断に至るまでに長い時間がかかっています。また、どこに相談すればよいか分からないという情報不足も大きな障壁となっています。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 治療可能な認知症の見逃しや、症状が軽いうちに介入できる機会を失い、BPSD(行動・心理症状)の重度化を招くことで、本人と家族双方の生活の質を著しく損ないます。
- 本人や家族が「何かおかしい」と感じても、認知症への偏見や、「年だから仕方ない」という思い込みから、医療機関への受診をためらうケースが多く見られます。ある調査では、初期症状が疑われても3人に2人は早期受診をしないと回答しており、診断に至るまでに長い時間がかかっています。また、どこに相談すればよいか分からないという情報不足も大きな障壁となっています。
地域社会の課題
- 根強い偏見と理解不足
- 認知症サポーター養成講座などを通じて普及啓発が進む一方、内閣府の世論調査では、認知症になっても地域で暮らし続けることは難しいと考える人が約6割に上るなど、依然として認知症に対するネガティブなイメージや誤解が根強く残っています。この社会的偏見が、当事者の社会参加を阻み、孤立を深める最大の要因となっています。
- 客観的根拠:
- (出典)内閣府「認知症に関する世論調査」平成27年度 35
- (出典)島根県「認知症に関する意識調査」令和3年度 36
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 認知症の人が持つ能力や経験が社会で活かされず、本人の尊厳が損なわれるとともに、地域全体の活力が低下します。
- 客観的根拠:
- 認知症サポーター養成講座などを通じて普及啓発が進む一方、内閣府の世論調査では、認知症になっても地域で暮らし続けることは難しいと考える人が約6割に上るなど、依然として認知症に対するネガティブなイメージや誤解が根強く残っています。この社会的偏見が、当事者の社会参加を阻み、孤立を深める最大の要因となっています。
- 見守り・捜索ネットワークの広域連携の欠如
- 認知症の人の行方不明事案では、発見場所が居住する市区町村の外であるケースが少なくありません。しかし、自治体の捜索ネットワークは自身の行政区域内に限定されていることが多く、広域連携の体制が十分に構築されていません。ある調査では、近隣自治体と広域ネットワークを構築しているのは44.4%に留まっており、特に交通網が発達し、区境を越えた移動が容易な東京都特別区においては、これが致命的な弱点となり得ます。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 捜索活動の初動が遅れ、発見までの時間が長期化することで、本人が事故に遭ったり、最悪の場合、命を落としたりする危険性が著しく高まります。
- 認知症の人の行方不明事案では、発見場所が居住する市区町村の外であるケースが少なくありません。しかし、自治体の捜索ネットワークは自身の行政区域内に限定されていることが多く、広域連携の体制が十分に構築されていません。ある調査では、近隣自治体と広域ネットワークを構築しているのは44.4%に留まっており、特に交通網が発達し、区境を越えた移動が容易な東京都特別区においては、これが致命的な弱点となり得ます。
- 地域資源の担い手不足と活動の持続性
- 認知症カフェや本人ミーティングなどの地域活動は、地域包括支援センターの職員や一部の熱心なボランティアの善意によって支えられている場合が多く、常に担い手不足という課題を抱えています。特にコロナ禍を経て活動が休止・縮小したところも多く、運営者のモチベーション維持や活動の持続可能性が大きな課題となっています。
- 客観的根拠:
- (出典)愛知県「認知症カフェ運営者交流会における課題」 38
- (出典)Wellness Labo「認知症カフェのメリット・デメリット」 39
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 認知症の人や家族にとって貴重な「居場所」や社会との接点が失われ、再び孤立状態に陥り、地域包括ケアシステムの基盤そのものが脆弱化します。
- 客観的根拠:
- 認知症カフェや本人ミーティングなどの地域活動は、地域包括支援センターの職員や一部の熱心なボランティアの善意によって支えられている場合が多く、常に担い手不足という課題を抱えています。特にコロナ禍を経て活動が休止・縮小したところも多く、運営者のモチベーション維持や活動の持続可能性が大きな課題となっています。
行政の課題
- 専門人材の不足と育成の遅れ
- 認知症医療・ケアの質は、専門的な知識を持つ人材の確保に大きく依存します。しかし、日本老年精神医学会専門医などの数は十分とは言えず、増加するニーズに追いついていないのが現状です。認知症サポート医の養成は進んでいますが(2025年度末に1.6万人の目標)、地域偏在や、かかりつけ医との連携といった活動の質にはばらつきが見られます。
- 客観的根拠:
- (出典)日本老年精神医学会「会員数の推移」2015年 40
- (出典)厚生労働省「令和4年度事前分析表(施策目標ⅩⅠ-1-3)」2022年 41
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 診断の遅れや不適切な治療・ケアにつながり、住民が受けるサービスの質に地域間格差が生じ、医療・介護費の非効率な増大を招きます。
- 客観的根拠:
- 認知症医療・ケアの質は、専門的な知識を持つ人材の確保に大きく依存します。しかし、日本老年精神医学会専門医などの数は十分とは言えず、増加するニーズに追いついていないのが現状です。認知症サポート医の養成は進んでいますが(2025年度末に1.6万人の目標)、地域偏在や、かかりつけ医との連携といった活動の質にはばらつきが見られます。
- 施策の縦割りと連携不足
- 認知症施策は、保健、福祉、医療、介護、さらには若年性の場合は就労支援など、多岐にわたる分野が関係しますが、行政組織の縦割り構造が障壁となり、一体的な支援が提供できていないケースが散見されます。例えば、若年性認知症の人が就労継続の相談をしても、福祉窓口と労働窓口の連携が不十分で、適切な支援につながりにくいといった課題があります。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 利用者が制度の狭間でたらい回しにされ、必要な支援を受けられない「制度の谷間」が生じ、問題がより複雑化・深刻化します。
- 認知症施策は、保健、福祉、医療、介護、さらには若年性の場合は就労支援など、多岐にわたる分野が関係しますが、行政組織の縦割り構造が障壁となり、一体的な支援が提供できていないケースが散見されます。例えば、若年性認知症の人が就労継続の相談をしても、福祉窓口と労働窓口の連携が不十分で、適切な支援につながりにくいといった課題があります。
- 施策効果の評価指標(KPI)の課題
- 現在の認知症施策のKPIは、「認知症サポーター養成数」や「初期集中支援チーム設置率」といったアウトプット指標(事業量)に偏りがちです。認知症基本法が目指す「本人の尊厳の保持」や「共生社会の実現」といったアウトカム(施策の成果)を直接的に測る指標が不足しています。例えば、初期集中支援チームのKPIが「医療・介護サービスへの接続率65%」であるため、サービス利用に至らないが支援を必要とする人への活動が評価されにくい構造になっています。
- 客観的根拠:
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 施策が数値目標の達成自体を目的化してしまい、本人の生活の質の向上という本来の目的から乖離した、実効性の低い事業に陥る危険性があります。
- 現在の認知症施策のKPIは、「認知症サポーター養成数」や「初期集中支援チーム設置率」といったアウトプット指標(事業量)に偏りがちです。認知症基本法が目指す「本人の尊厳の保持」や「共生社会の実現」といったアウトカム(施策の成果)を直接的に測る指標が不足しています。例えば、初期集中支援チームのKPIが「医療・介護サービスへの接続率65%」であるため、サービス利用に至らないが支援を必要とする人への活動が評価されにくい構造になっています。
行政の支援策と優先度の検討
優先順位の考え方
※各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
- 即効性・波及効果: 施策の実施後、比較的短期間で効果が期待でき、かつ、他の課題解決にも良い影響を及ぼす度合いを評価します。
- 実現可能性: 現行の法制度、財源、人材等の制約の中で、実現に向けた具体的な道筋が描ける度合いを評価します。
- 費用対効果: 投じる予算や人的資源に対し、住民のQOL向上や将来的な社会的費用の抑制といった便益がどの程度見込めるかを評価します。
- 公平性・持続可能性: 特定の地域や住民層に不利益が生じることなく、長期にわたって安定的に継続できる制度設計であるかを評価します。
- 客観的根拠の有無: 国の計画や白書、先進自治体の成功事例、各種調査研究など、政策効果を裏付ける客観的なエビデンスが存在するかを評価します。
支援策の全体像と優先順位
- 認知症基本法が掲げる「共生」と「予防」を両輪とし、東京都の新たな計画も踏まえ、施策を以下の3つの柱で体系化します。特に、住民の生命と尊厳に直結し、他の課題への波及効果も大きい施策を**「優先度:高」と位置づけ、緊急かつ重点的に取り組むべき領域とします。「優先度:中」は共生社会の基盤を着実に強化する施策、「優先度:低」**は長期的な視点で継続的に取り組むべき施策と整理します。
- 【優先度:高】支援策①:早期診断・早期支援体制のシームレス化
- 認知症の疑い段階から診断、その後の生活支援までを切れ目なくつなぎ、本人と家族の最も不安な時期を支える、いわば「生命線」となる施策です。
- 【優先度:高】支援策③:ICTと地域連携による重層的な見守り・捜索ネットワークの強化
- 行方不明は生命の危険に直結する最重要課題であり、ICTの活用と広域連携によって、発見率の向上と死亡者ゼロを目指す、安全確保の根幹をなす施策です。
- 【優先度:中】支援策②:地域共生社会を推進する「居場所」と「出番」の創出
- 認知症の人が社会から孤立せず、役割を持って活躍できる場を提供することで、本人の尊厳を守り、地域全体の活性化につなげる、共生社会の土台を築く施策です。
各支援策の詳細
支援策①:早期診断・早期支援体制のシームレス化
目的
- 認知症の疑いがある段階から診断、その後の支援までを円滑につなぎ、本人と家族が抱える不安を早期に軽減します。
- 適切な医療・介護サービスへの早期接続を促すことで、症状の安定化を図り、可能な限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう支援します。
- 客観的根拠:
主な取組①:認知症初期集中支援チームの機能強化とアウトリーチ推進
- チームの役割を、単に医療・介護サービスへつなぐ「橋渡し役」に限定せず、サービス利用には至らない軽度の人や若年性認知症の人に対して、生活課題の整理や家族支援を行う「伴走支援役」としての機能を強化します。
- 民生委員や協力事業者、地域ケア会議等から寄せられる「気になる情報」を基に、支援が届いていないと思われる世帯へのアウトリーチ(訪問活動)を積極的に行い、潜在的なニーズを掘り起こします。
- 活動評価の指標に、サービス接続率だけでなく、相談件数や本人・家族の不安軽減度などを加え、多面的な活動を評価する仕組みを導入します。
主な取組②:「認知症サポート検診事業」の全区展開とフォローアップ体制の構築
- 東京都の補助事業「認知症サポート検診事業」を全ての特別区で導入し、50歳以上の区民が身近な場所で認知機能のチェックを受けられる機会を提供します。
- 検診の結果、支援が必要と判断された人に対しては、本人の同意を前提として、検診結果を地域包括支援センターと共有し、認知症地域支援推進員等が定期的な電話連絡や訪問を行うフォローアップ体制を構築します。
- フォローアップでは、不安の傾聴や相談に応じるとともに、介護予防事業や地域の通いの場、認知症カフェなどの社会資源に関する情報提供を積極的に行います。
- 客観的根拠:
- (出典)東京都福祉保健局「令和6年度の東京都における認知症施策について」 46
- (出典)日野市「日野市認知症検診 事業概要」 47
- 客観的根拠:
主な取組③:かかりつけ医と認知症サポート医・専門医療機関の連携強化
- 区医師会と連携し、かかりつけ医を対象とした「認知症対応力向上研修」の受講を強力に推進します。オンライン研修の活用や、診療報酬上の評価なども含めて受講のインセンティブを高めます。
- 東京都の「認知症サポート医地域連携促進事業」を活用し、認知症サポート医が中心となって、地域の医療・介護関係者が集う症例検討会や研修会を定期的に開催します。
- ICT(情報通信技術)を活用した連携ツールを導入し、かかりつけ医が認知症サポート医や専門医療機関に気軽に相談できるオンライン相談体制を整備します。
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標):
- 認知症の診断を受けてから1年以内の人のうち、生活のしづらさが「改善した」または「変わらない」と回答した人の割合:70%以上
- データ取得方法: 地域包括支援センターまたは区が主体となり、診断後1年が経過した当事者および主たる介護者を対象とした記名式アンケート調査を年1回実施。
- 認知症の診断を受けてから1年以内の人のうち、生活のしづらさが「改善した」または「変わらない」と回答した人の割合:70%以上
- KSI(成功要因指標):
- 認知症の診断を受けた人のうち、診断後3ヶ月以内に公的またはインフォーマルな支援(相談のみも含む)に繋がった人の割合:80%以上
- データ取得方法: 認知症疾患医療センター、初期集中支援チーム、地域包括支援センターの活動記録から、新規相談者の支援接続状況を四半期ごとに集計。
- 認知症の診断を受けた人のうち、診断後3ヶ月以内に公的またはインフォーマルな支援(相談のみも含む)に繋がった人の割合:80%以上
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標:
- 認知症サポート検診の年間受診率(対象年齢人口比):10%
- 検診後のフォローアップ対象者のうち、実際にフォローアップ(連絡・訪問)を実施した割合:95%
- データ取得方法: 各区が実施する認知症サポート検診事業の実績報告書から年1回集計。
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標:
- 認知症初期集中支援チームによる年間新規訪問実人数:各区の人口規模に応じて設定(例:人口10万人あたり年間50件)
- かかりつけ医認知症対応力向上研修の累計修了者数:各区のかかりつけ医総数の50%
- データ取得方法: 初期集中支援チームの活動報告、東京都への研修実績報告から年1回集計。
支援策②:地域共生社会を推進する「居場所」と「出番」の創出
目的
- 認知症の人が社会的に孤立することなく、自らの経験や能力を活かせる「居場所」と「出番」を提供し、生きがいと役割を持って地域で暮らし続けられる環境を整備します。
- 認知症サポーター等の地域住民が活動に参画する機会を創出することで、認知症への理解を深め、誰もが支え手にもなり手にもなれる地域文化を醸成します。
- 客観的根拠:
主な取組①:認知症カフェの多様化と運営支援
- 既存の認知症カフェに対して、会場費や消耗品費などの運営費補助を継続するとともに、運営者間の情報交換会や合同研修会を定期的に開催し、運営ノウハウの共有や課題解決を支援します。
- 地域包括支援センターがハブとなり、カフェ運営を手伝いたいボランティア(認知症サポーター等)と運営団体とのマッチングを支援します。
- 若年性認知症の人やその家族を対象とした「本人ミーティング併設カフェ」、就労意欲のある人が働く「就労準備型カフェ」、園芸や音楽など特定の趣味活動に特化した「趣味活動型カフェ」など、多様なニーズに応える新たなカフェの立ち上げを企画・公募し、立ち上げ経費を助成します。
- 客観的根拠:
- (出典)愛知県「認知症カフェ運営マニュアル」 51
- (出典)厚生労働省「認知症カフェ 継続に向けた手引き」 52
- 客観的根拠:
主な取組②:認知症サポーターの活動促進(チームオレンジの組織化)
- 認知症サポーター養成講座の受講者に対し、本人の同意を得た上で名簿に登録し、地域のボランティア情報やイベント情報を定期的に提供することで、活動への参加を促します。
- 認知症サポーターが主体的に活動するボランティアグループ「チームオレンジ」の結成を奨励します。区への登録制とし、活動に必要な経費(保険料、交通費等)の一部を助成します。
- チームオレンジの活動内容として、認知症カフェの運営補助、地域の見守り活動、イベントでの普及啓発、個別の困りごと(ゴミ出し、買い物同行など)の支援などを想定し、地域包括支援センターが活動のコーディネートを担います。
- 客観的根拠:
- (出典)全国キャラバン・メイト連絡協議会「認知症サポーターの人数」 15
- (出典)板橋区「チームオレンジ 活動の手引き」 7
- 客観的根拠:
主な取組③:若年性認知症の人の就労・社会参加支援の強化
- 東京都が配置する若年性認知症支援コーディネーター、地域のハローワーク、商工会議所、企業等が参画する「若年性認知症就労・社会参加支援協議会」を区ごとに設置します。
- 協議会では、本人の能力や意向に応じた業務内容の調整、職場環境の改善、障害者雇用枠の活用など、就労継続や再就職に向けた個別支援計画を検討・実施します。
- 東京都の「認知症の人の社会参加推進事業」を活用し、本人が自らの経験を語るピアサポート活動や講演活動、地域のイベント運営、企業の製品開発への協力など、就労以外の多様な社会参加(出番)の機会を創出・マッチングします。
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標):
- 区内在住の認知症の人のうち、「自分には社会的な役割がある(出番がある)」または「安心して過ごせる場所がある(居場所がある)」と感じる人の割合:50%以上
- データ取得方法: KGI(支援策①)と同様の当事者・家族向けアンケート調査に設問を追加して年1回測定。
- 区内在住の認知症の人のうち、「自分には社会的な役割がある(出番がある)」または「安心して過ごせる場所がある(居場所がある)」と感じる人の割合:50%以上
- KSI(成功要因指標):
- 認知症サポーター登録者のうち、過去1年間にチームオレンジ活動や認知症カフェのボランティアなど、何らかの関連活動に参加した人の割合:20%
- データ取得方法: チームオレンジ登録状況、認知症カフェ等のボランティア参加記録から年1回集計。
- 認知症サポーター登録者のうち、過去1年間にチームオレンジ活動や認知症カフェのボランティアなど、何らかの関連活動に参加した人の割合:20%
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標:
- 若年性認知症と診断された人のうち、診断から1年後において就労を継続している、または何らかの社会参加活動に月1回以上参加している人の割合:60%
- データ取得方法: 若年性認知症支援コーディネーターによる個別ケースの追跡調査結果を集計。
- 若年性認知症と診断された人のうち、診断から1年後において就労を継続している、または何らかの社会参加活動に月1回以上参加している人の割合:60%
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標:
- 区内の認知症カフェの総数:人口5万人あたり1箇所以上
- チームオレンジの登録チーム数:各地域包括支援センター圏域に1チーム以上
- データ取得方法: 区の事業実績報告から年1回集計。
支援策③:ICTと地域連携による重層的な見守り・捜索ネットワークの強化
目的
- 認知症の人が一人で外出した際に行方不明になるリスクを低減し、万が一発生した場合には、迅速な情報共有と捜索協力により早期に発見・保護し、生命の安全を守ります。
- 地域住民や民間事業者が日常の中で気軽に見守りに参加できる仕組みを構築し、地域全体の「見守りの目」を増やすことで、認知症の人が安心して外出できる社会を実現します。
主な取組①:行方不明時における広域連携体制の制度化
- 特別区間および隣接する市との間で、「行方不明高齢者等に関する情報連携協定」を締結します。協定には、行方不明者発生時の情報提供の様式、連絡体制、個人情報の取り扱い等を明記します。
- 警察、消防、鉄道・バス・タクシー等の公共交通事業者、地域の協力事業者を含めた広域の捜索協力ネットワークを構築します。
- 年に1回以上、ネットワーク参加機関合同で、行方不明者発生を想定した情報伝達訓練を実施し、連携体制の実効性を検証・改善します。
- 客観的根拠:
- (出典)国立長寿医療研究センター「愛知県内市町村における認知症高齢者等の行方不明時の捜索に関する調査」2020年 37
- (出典)(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/000382001.pdf) 8
- 客観的根拠:
主な取組②:GPS・QRコード等見守りツールの導入支援
- 徘徊のおそれがある高齢者を介護する家族に対し、GPS(全地球測位システム)端末の貸与、または購入・利用にかかる費用の一部(初期費用および月額利用料)を助成する制度を創設・拡充します。
- 衣類や持ち物に貼付できるQRコード付きシールの無料配布を行います。発見者がスマートフォンでQRコードを読み取ると、事前に登録された家族等の連絡先に通知が届く仕組みを導入します。
- 地域の協力店(コンビニ等)や公共施設、交番等にQRコード読み取りへの協力を依頼し、発見・保護時に迅速に身元確認ができる体制を整備します。
- 客観的根拠:
主な取組③:民間事業者との見守り協定の拡大と深化
- 新聞販売店、牛乳配達店、宅配業者、金融機関、コンビニエンスストア、ガソリンスタンドなど、日常業務で地域を巡回し、住民と接する機会の多い民間事業者との「高齢者見守りネットワーク事業協定」の締結を推進します。
- 協定締結事業者向けに、認知症サポーター養成講座の出張開催や、「声かけのポイント」「異変に気づくサイン」などをまとめた研修会を定期的に実施し、見守りの質的向上を図ります。
- 協定締結事業者からの通報実績や好事例を広報紙等で紹介し、事業者のモチベーション向上と、さらなる協力事業者の拡大につなげます。
- 客観的根拠:
- (出典)練馬区「練馬区高齢者見守りネットワーク事業協定」 9
- (出典)内閣府「平成27年版高齢社会白書 コラム3」 57
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標):
- 認知症が原因の行方不明による死亡者数:ゼロ
- データ取得方法: 警察庁の行方不明者統計、区への警察からの情報提供。
- 認知症が原因の行方不明による死亡者数:ゼロ
- KSI(成功要因指標):
- 行方不明者届出から発見・保護までの平均時間:12時間以内
- データ取得方法: 区への警察からの情報提供に基づき、個別事案ごとに集計。
- 行方不明者届出から発見・保護までの平均時間:12時間以内
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標:
- 行方不明者のうち、届出を受理した当日中に発見・保護された割合:85%以上(参考:全国平均 令和4年 77.5%)
- データ取得方法: 区への警察からの情報提供に基づき集計。
- 行方不明者のうち、届出を受理した当日中に発見・保護された割合:85%以上(参考:全国平均 令和4年 77.5%)
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標:
- GPS・QRコード等見守りツールの利用登録者数:年間100人増
- 見守り協定締結事業者数:年間10事業者増
- 広域連携・情報伝達訓練の年間実施回数:1回以上
- データ取得方法: 区の各事業実績報告書から年1回集計。
先進事例
東京都特別区の先進事例
(出典)練馬区「練馬区高齢者見守りネットワーク事業協定」 9
世田谷区「認知症とともに生きる希望条例」
2020年10月に施行されたこの条例は、全国の自治体に先駆けて「希望」という言葉を名称に掲げた点が画期的です。認知症を単なる病気としてではなく、個人の尊厳と権利擁護の観点から捉え直し、「認知症になっても希望を持って暮らし続けられる地域社会」の実現を基本理念としています。条例の策定プロセスにおいて、認知症の当事者本人や家族の意見を徹底的に反映させた点が最大の特徴です。さらに、施策の進捗を評価し、改善提案を行うための第三者機関として「認知症施策評価委員会」を設置し、実効性を担保するPDCAサイクルを制度的に組み込んでいます。
客観的根拠:
(出典)世田谷区「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」 3
(出典)世田谷区「世田谷区認知症施策評価委員会【令和2年10月以降】」 58
板橋区「チームオレンジによる本人主体の活動支援」
板橋区では、養成した認知症サポーターが単なる「理解者」に留まらず、具体的な「活動者」となるための仕組みとして「チームオレンジ」を組織化しています。このチームは、認知症サポーターが主体となり、認知症の人や家族のニーズに合わせた支援を企画・実行します。活動内容は、本人ミーティングの運営支援、外出同行、地域のイベントでの食事作りなど多岐にわたります。特に、認知症の当事者自身がチームのメンバーやファシリテーターとして活躍する場を提供している点が重要です。これにより、サポーターという豊富な人材資源を有効活用し、当事者の「出番」を創出するという、共生社会の理念を具体化しています。
客観的根拠:
(出典)板橋区「板橋区チームオレンジ 活動の手引き」 7
(出典)東京都福祉保健局「とうきょう認知症希望大使」 59
練馬区「多機関連携による高齢者見守りネットワーク」
- 練馬区「多機関連携による高齢者見守りネットワーク」
- 練馬区は、行政や地域包括支援センターといった公的機関だけでなく、郵便局、ガス・水道・電力会社、新聞販売店、宅配業者、金融機関など、地域に根差した多様な民間事業者と「高齢者見守りネットワーク事業協定」を広範に締結しています。この協定に基づき、事業者が日常業務の中で「郵便受けに新聞が溜まっている」「同じ洗濯物が干しっぱなし」といった高齢者の異変に気づいた際に、速やかに区や地域包括支援センターに通報する体制を構築しています。この「ゆるやかな見守りの目」を地域全体に張り巡らせることで、孤立死の防止や、支援が必要な高齢者の早期発見に大きな成果を上げています。
- 客観的根拠:
- (出典)練馬区「練馬区高齢者見守りネットワーク事業協定」 1
- (出典)内閣府「平成27年版高齢社会白書」 2
- 客観的根拠:
- 練馬区は、行政や地域包括支援センターといった公的機関だけでなく、郵便局、ガス・水道・電力会社、新聞販売店、宅配業者、金融機関など、地域に根差した多様な民間事業者と「高齢者見守りネットワーク事業協定」を広範に締結しています。この協定に基づき、事業者が日常業務の中で「郵便受けに新聞が溜まっている」「同じ洗濯物が干しっぱなし」といった高齢者の異変に気づいた際に、速やかに区や地域包括支援センターに通報する体制を構築しています。この「ゆるやかな見守りの目」を地域全体に張り巡らせることで、孤立死の防止や、支援が必要な高齢者の早期発見に大きな成果を上げています。
全国自治体の先進事例
- 静岡県富士市「多様なニーズに応える認知症カフェの展開」
- 富士市では、行政が主導する画一的なモデルではなく、NPO、社会福祉法人、介護事業者、地域住民グループなど、多様な主体がそれぞれの特色を活かした認知症カフェを市内各所で運営しています。これにより、参加者は「専門職に相談したい」「同じ立場の仲間と話したい」「趣味活動を楽しみたい」といった自らのニーズに合わせてカフェを選ぶことができます。行政は、これらの多様な活動を財政面や広報面で後方支援する役割に徹することで、住民の自主性を引き出し、持続可能な運営モデルを確立しています。
- 客観的根拠:
- 富士市では、行政が主導する画一的なモデルではなく、NPO、社会福祉法人、介護事業者、地域住民グループなど、多様な主体がそれぞれの特色を活かした認知症カフェを市内各所で運営しています。これにより、参加者は「専門職に相談したい」「同じ立場の仲間と話したい」「趣味活動を楽しみたい」といった自らのニーズに合わせてカフェを選ぶことができます。行政は、これらの多様な活動を財政面や広報面で後方支援する役割に徹することで、住民の自主性を引き出し、持続可能な運営モデルを確立しています。
- 福岡県大牟田市「住民参加型のSOSネットワーク模擬訓練」
- 大牟田市は、2004年から「認知症SOSネットワーク模擬訓練」を毎年実施しています。この訓練では、認知症の人が行方不明になったというシナリオの下、地域の小中学生から高齢者、協力事業者までが参加し、情報伝達、声かけ、保護までの一連の流れを実践的に体験します。この取り組みの成功要因は、単なる捜索技術の習得ではなく、「住民同士の関係性づくり」と「認知症への理解促進」を主目的に置いている点です。訓練を重ねることで、認知症が「自分たちの地域の問題」であるという当事者意識が醸成され、顔の見える関係に基づいた強力なセーフティネットが構築されています。
- 客観的根拠:
- 大牟田市は、2004年から「認知症SOSネットワーク模擬訓練」を毎年実施しています。この訓練では、認知症の人が行方不明になったというシナリオの下、地域の小中学生から高齢者、協力事業者までが参加し、情報伝達、声かけ、保護までの一連の流れを実践的に体験します。この取り組みの成功要因は、単なる捜索技術の習得ではなく、「住民同士の関係性づくり」と「認知症への理解促進」を主目的に置いている点です。訓練を重ねることで、認知症が「自分たちの地域の問題」であるという当事者意識が醸成され、顔の見える関係に基づいた強力なセーフティネットが構築されています。
参考資料[エビデンス検索用]
- 政府(省庁)
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」(※公表され次第、要確認)
- 厚生労働省「令和7年版厚生労働白書」(※公表され次第、要確認)
- 厚生労働省「認知症施策推進基本計画」令和6年12月
- (出典)厚生労働省「認知症施策」 3
- 厚生労働省「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」令和5年度
- 厚生労働省「若年性認知症実態調査結果概要」令和2年3月
- (出典)(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000706870.pdf) 5
- 警察庁「令和6年における行方不明者の状況」
- 内閣府「認知症に関する世論調査」令和元年
- (出典)内閣府「令和元年度 認知症に関する世論調査」 7
- 東京都
- 東京都福祉局「東京都認知症施策推進計画(令和7年度~令和11年度)」
- 東京都福祉局「都内区市町村における認知症施策の実施状況」令和5年
- 東京都福祉局「東京都認知症対策推進会議」議事録・資料
- 自治体(特別区)
- 世田谷区「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」及び関連資料
- (出典)世田谷区「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」 10
- 板橋区「チームオレンジ 活動の手引き」
- (出典)板橋区「板橋区チームオレンジ 活動の手引き」 11
- 練馬区「練馬区高齢者見守りネットワーク事業協定」
- (出典)練馬区「練馬区高齢者見守りネットワーク事業協定」 1
- 世田谷区「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」及び関連資料
- シンクタンク・研究機関等
- 国立長寿医療研究センター「認知症初期集中支援チーム活動に関する調査」
- 国立長寿医療研究センター「認知症高齢者等の行方不明時の捜索に関する調査」
- 公益社団法人認知症の人と家族の会 各種調査報告書・要望書
まとめ
認知症基本法の施行により、我が国の認知症施策は「共生」を基本理念とする新たな時代を迎えました。東京都特別区においても、これまでの個別的・事後的な対応から、地域全体で支える統合的・予防的な戦略への転換が急務です。本記事で示したように、その鍵は、早期診断から途切れることのない支援体制の構築、100万人近くに達する都内の認知症サポーターを具体的な活動に繋げる仕組みづくり、そしてICTと広域連携を駆使した強固なセーフティネットの確立にあります。これらの施策は、認知症の本人の声を中心に据え、客観的データに基づいて推進されることで、誰もが認知症になっても尊厳と希望を持って暮らし続けられる社会の実現に繋がります。
本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。




-320x180.jpg)

-320x180.jpg)