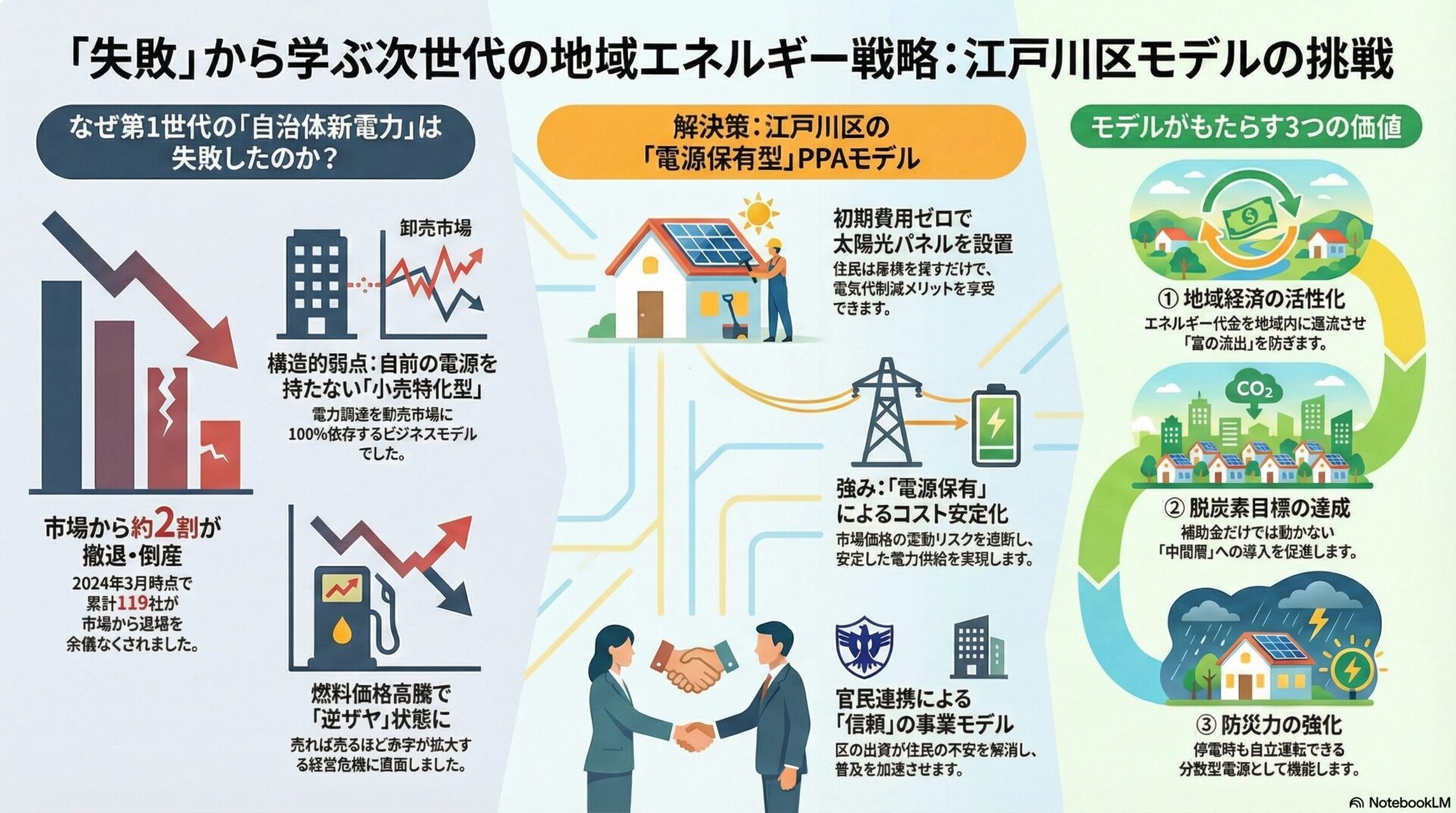江東区が全国初「燃料電池ごみ収集車」を本格導入!自治体がFCEVを推進する意義と課題

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
エグゼクティブサマリー
行政サービスの現場において、環境負荷低減と市民生活の質の向上を両立させることは、現代の自治体経営における最重要課題の一つです。2024年(令和6年)11月19日、東京都江東区は、水素を燃料とし走行時に二酸化炭素(CO2)を一切排出しない「燃料電池ごみ収集車(以下、FCごみ収集車)」の運用を本格的に開始しました。これは、これまで台東区や町田市、あるいは福岡市などで散発的に行われてきた「試験運用」や「実証実験」の枠を超え、都内で初めての「本格導入」として位置づけられる画期的な政策決定です。
本記事は、この江東区の先駆的な事例を起点として、自治体がゼロエミッション車(ZEV)を公用車として導入する際の政策的意義、技術的特性、財政スキーム、そして運用上の課題を網羅的に分析するものです。特に、1台あたり6年間で約7,500万円という高額なリース料に対し、国や東京都の特定財源を巧みに活用することで区の実質負担を約4分の1に圧縮した財政手法や、全長が通常車両より約1.2メートル長いことに伴う収集ルート選定の難しさ、さらには区内に存在する水素ステーションの稼働実態(一部休止中などのリスク)を踏まえたインフラ戦略について詳述します。
また、福岡市における夜間収集への活用事例や、電気自動車(EV)との補助金格差など、多角的な視点から比較検証を行います。静音性による住民サービスへの貢献や、災害時における非常用電源としての活用可能性(レジリエンス強化)を含め、本記事が、特別区のみならず全国の自治体職員の皆様にとって、次世代の清掃行政・環境行政を構想するための実務的な指針となることを目指します。
序論:脱炭素社会への転換と自治体行政の責務
世界的な環境規制の潮流と都市部の課題
2050年のカーボンニュートラル実現に向け、世界規模で産業構造やエネルギー需給の変革が進む中、基礎自治体には、地域特性に応じた具体的な温室効果ガス削減策の実行が求められています。特に大都市圏においては、運輸部門からのCO2排出量が無視できない割合を占めており、公用車の脱炭素化は、自治体が率先垂範して取り組むべき象徴的な施策と位置づけられています。
東京都が掲げる「ゼロエミッション東京」戦略においても、商用車の電動化は重要施策の一つです。しかし、ごみ収集車(パッカー車)は、一般的な乗用車とは異なる過酷な稼働環境に置かれています。低速での走行、数百回に及ぶ頻繁な発進・停止(ストップ・アンド・ゴー)、そしてごみ圧縮装置(プレス機等)の駆動による高いエネルギー負荷など、従来のディーゼルエンジン車でさえ、燃費効率の悪化や排出ガス浄化装置(DPF)のトラブルが頻発する領域でした。
こうした中で、水素と酸素の化学反応によって電気を生み出し、モーター駆動で走行・作業を行う燃料電池自動車(FCV)は、走行時に水しか排出しない究極のエコカーとして、また、内燃機関を持たないことによる圧倒的な静粛性を提供する次世代のソリューションとして、大きな期待を集めています。
「試験」から「本格実装」へのパラダイムシフト
これまでのFCごみ収集車の導入事例の多くは、メーカーや国主導の「実証実験」の域を出ないものでした。例えば、福岡市では2024年3月からFCごみ収集車の試験運用を開始していますが、これは社会実装の効果や課題を抽出するためのデータ収集が主目的でした。
対して、今回の江東区の事例が画期的なのは、これを「本格運用」として位置づけた点にあります。江東区は、今年度中に追加でもう1台、さらに2027年度以降には3台を追加し、計5台体制での運用を計画しています。これは、実験的なフェーズを終え、FC車両を通常の行政サービスの基盤インフラとして組み込むという強い政治的意思の表れであり、他の自治体に対しても「もはやFCVは実験段階ではない」という強力なメッセージを発信するものです。
1
導入車両の全貌:スペックと技術的特性の詳細分析
車両諸元とサイズアップがもたらす実務的影響
今回江東区が導入したFCごみ収集車は、新明和工業やCJPT(Commercial Japan Partnership Technologies)等の技術協力によって開発されたモデルであると考えられます。行政の実務担当者として最も注目すべきは、その車両サイズです。
公表されたデータによれば、全長は約6.5メートルに達し、一般的な2トンから3トンクラスの中型パッカー車と比較して、約1.2メートル長くなっています。この「プラス1.2メートル」は、都市部の収集業務において極めて大きな意味を持ちます。
1
表1:一般的なごみ収集車とFCごみ収集車のサイズ比較
| 項目 | 一般的な中型パッカー車(推定) | 江東区導入 FCごみ収集車 | 差分 | 影響と対策 |
| 全長 | 約5.3m 前後 | 約6.5m | +1.2m | 狭隘道路への進入不可、交差点での内輪差増大。ルート再編が必須。 |
| 動力 | ディーゼルエンジン | モーター(水素燃料電池) | – | 排ガスゼロ、騒音低減、振動低減。 |
| 燃料 | 軽油 | 水素 | – | 専用スタンドでの充填が必要(インフラ制約)。 |
従来のパッカー車であれば進入・転回が可能であった路地裏の集積所も、FC車両ではアクセス不能となるケースが想定されます。江東区の導入においては、こうした車両特性を綿密にシミュレーションし、道路幅員に余裕のある豊洲エリアや幹線道路沿いのルートを中心に配車計画が組まれていると推測されます。
この事実は、導入を検討する他自治体にとって重要な教訓となります。単に予算を確保して車両を購入するだけでなく、既存の収集ルート(数千箇所に及ぶ集積所)の総点検と、FC車両専用ルート(あるいは広路専用ルート)の策定という、膨大な事務作業が前提条件となるからです。
1
環境性能と「静音性」という最大の付加価値
FCごみ収集車の機能面における最大のメリットは、ゼロエミッション性能と静音性です。
江東区の大久保朋果区長は、導入初日の試乗体験において「静かで排ガスも出ないので、収集作業をする職員にも優しい車だと感じた」と述べています。この「職員にも優しい」という視点は極めて重要です。
作業環境の改善
従来のディーゼル車では、パッカー(塵芥圧縮装置)を作動させる際、PTO(Power Take-Off)を通じてエンジンの回転数を上げる必要があり、車両後部で作業する職員は常に排気ガスと騒音に晒されていました。FC車両では、バッテリーおよびFCスタックからの電力でモーターを回して油圧ポンプや電動アクチュエータを駆動するため、エンジンの唸り声や排ガスから解放されます。
住民サービスとしての騒音低減
また、福岡市ではFCごみ収集車の導入目的の一つとして「夜間にごみを回収する際の騒音低減」を挙げています。福岡市のように夜間収集を実施している自治体にとって、深夜の住宅街におけるパッカー車の作動音は最大の苦情要因の一つです。FC車両の導入は、環境政策であると同時に、住民の生活環境改善(騒音対策)という即効性のある住民サービス向上施策として機能します。
1
財政スキームの徹底解剖:高コスト構造をどう攻略するか
衝撃的なコスト格差の実態
政策立案において最大の障壁となるのが、導入コストです。一般的なごみ収集車(パッカー車)の新車価格相場は、仕様(プレス式、回転板式など)やサイズによって異なりますが、概ね以下の通りです。
表2:ごみ収集車の新車価格相場(従来型ディーゼル車)
| 車両サイズ | 価格帯(新車) | 備考 |
| 小型 | 400〜600万円 | 狭隘路向け |
| 中型 | 500〜800万円 | 一般的な収集車 |
| 大型 | 800〜1,000万円 | 事業系ごみ等の大量輸送向け |
6
これに対し、今回江東区が導入したFCごみ収集車のリース料金は、車両1台につき6年間で約7,500万円と報じられています。単純比較で、従来型の中型車の10倍近いコストがかかる計算となります。通常の一般財源だけでこれを賄うことは、納税者の理解を得る観点からも、財政規律の観点からも極めて困難です。
1
補助金活用のマジック:実質負担「4分の1」への圧縮
江東区はこの圧倒的なコスト差を埋めるために、国と東京都の補助金をフル活用するスキームを構築しました。報道によれば、区の実質負担は約4分の1まで軽減されています。
具体的には、以下のような補助金制度の活用が想定されます。
環境省・国土交通省連携事業(商用車電動化促進事業等)
公益財団法人日本自動車輸送技術協会(LEVO)などが執行団体となる補助金です。FCトラックの導入に対し、標準的な車両価格との差額の大部分(通常は3分の2から4分の3程度)を補助する制度設計となっています。ただし、この補助金を受けるためには、「非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者」であることや、車両の「適正な財産管理」など、厳格な要件(公募要領参照)を満たす必要があります。
7
東京都 ZEV普及促進補助金
東京都は、国の補助金に上乗せする形で独自の助成を行っています。令和6年度の制度では、FCV(燃料電池自動車)のごみ収集車等に対し、非常に手厚い支援を行っています。
特筆すべきは、EV(電気自動車)とFCV(燃料電池車)の補助額の差です。EV・PHEVトラックの場合、給電機能ありで最大45万円の上乗せですが、FCVトラックの場合、給電機能ありで最大110万円の上乗せが設定されています。
この制度設計からも、東京都がFCVの普及、特に大型・商用車分野での水素活用を強力に推進しようとしている意図が読み取れます。江東区はこの政策誘導に巧みに乗ることで、財政負担を最小化しました。
8
表3:東京都ZEV普及促進補助金(令和6年度・事業者向け)の比較
| 車種 | 給電機能の有無 | 補助金額(上乗せ最大額) | 政策的意図 |
| EV・PHEV | なし | 35万円 | EVは普及期に入りつつあるため補助は抑制的。 |
| EV・PHEV | あり | 45万円 | V2H等の防災活用を推奨。 |
| FCV | なし | 100万円 | FCVは導入ハードルが高く、強力な支援が必要。 |
| FCV | あり | 110万円 | 水素による大容量給電能力を高く評価。 |
8
結果として、江東区の負担は6年間で約1,875万円(7,500万円の1/4)程度になると推計されます。これを年換算すれば約312万円/年であり、これは高級なディーゼルパッカー車の減価償却費+燃料費と比較しても、十分に「手の届く範囲」の行政コストに着地します。
なお、他自治体の事例として、埼玉県戸田市ではFCV導入に50万円、鶴ヶ島市では上限10万円といった独自の補助制度を設けていますが、東京都区部のような大規模な上乗せ補助がない地域では、依然として導入のハードルは高いと言わざるを得ません。
1
インフラ環境のリアリティ:水素ステーションの配置と稼働リスク
「水素ステーションがある」だけでは不十分
FCV導入の成否を握る最大の鍵は、水素ステーションの確保です。江東区が本格導入に踏み切れた最大の要因は、区内に都内最多となる4箇所の水素ステーションが存在するという「地政学的優位性」にあります。
表4:江東区内の水素ステーション一覧と稼働状況(2025年時点の調査情報に基づく)
| ステーション名称 | 所在地 | 運営事業者 | 特記事項・稼働状況 |
| 新砂水素ステーション | 江東区新砂1-7-9 | バス事業者系 | 大型車対応が可能と推測される。 |
| 豊洲水素ステーション | 江東区豊洲6-5-27 | 東京ガス等 | **「休止中」**の情報あり(要確認)。 |
| 岩谷コスモ水素ステーション有明 | 江東区有明3-9-25 | 岩谷産業・コスモ石油 | 有明地区の物流拠点に近い。 |
| 潮見ステーション(参考) | 江東区潮見1-3-2 | – | トヨタのサイトでは**「休止中」**との記載あり。 |
10
ここで特筆すべきリスク管理のポイントがあります。トヨタ自動車等の公開情報によれば、豊洲や潮見といった一部のステーションには「休止中」や「不定休」というステータスが見受けられます。
行政サービスであるごみ収集は、雨の日も風の日も止めることはできません。「ステーションがメンテナンス中だから今日は収集できません」という言い訳は通用しないのです。江東区内に4箇所あるといっても、その全てが常時、ごみ収集車のような大型商用車を受け入れ、フル稼働しているわけではありません。
江東区の事例では、「4箇所のうち2箇所を使う」と報道されていますが、これは単に「近いから」選んだのではなく、**「確実に稼働し、かつ大型車の充填スペースが確保されているステーション」**を選定した結果(リスク分散)であると分析できます。
これから導入を検討する自治体は、単に地図上でステーションの有無を確認するだけでなく、その「稼働率」「営業時間(早朝・夜間の対応可否)」「大型車受入可否」「メンテナンス頻度」まで踏み込んだ詳細な調査が不可欠です。
1
燃料コストの変動リスク
ランニングコストにおける懸念材料は水素価格です。岩谷産業の公表データによれば、水素価格は1kgあたり1,100円(税抜・2014年当時の目標価格基準)などの水準で推移していますが、昨今のエネルギー情勢により価格変動のリスクは常に存在します。ディーゼル車の軽油価格と比較して、単位走行距離あたりの燃料コストがどの程度になるのか、長期的な視点での試算も求められます。
13
比較分析:EVパッカー車 vs FCパッカー車
自治体の脱炭素施策において、FCVと並んで選択肢となるのが電気自動車(EV)です。なぜ江東区はEVではなくFCVを選択したのでしょうか。ここではその技術的・運用的特性を比較します。
表5:ごみ収集車におけるEVとFCVの特性比較
| 比較項目 | EVパッカー車 | FCパッカー車(江東区事例) | 政策的示唆 |
| 航続距離 | △ 短〜中距離向け | ◎ 長距離も対応可能 | 一日の走行距離が長いルートや、焼却場が遠隔地にある場合はFCVが有利。 |
| 充填・充電時間 | × 急速充電でも数十分〜数時間 | ◎ 数分〜十数分 | 連続稼働が必要な場合や、充電待機時間を嫌う場合はFCV。 |
| 車両重量 | × バッテリーにより重くなる | ○ 比較的小幅な重量増 | 最大積載量(ごみの量)を確保するにはFCVが有利な場合がある。 |
| 導入コスト | △ 高いがFCVよりは安価 | × 非常に高額 | イニシャルコスト重視ならEV、運用効率重視ならFCV。 |
| インフラ | ○ 車庫に充電器設置が可能 | × 水素ステーション必須 | ステーションがない地域はEV一択となる。 |
EVパッカー車は、車庫(清掃事務所)に充電設備を設置すれば運用が完結するため、インフラ面でのハードルは低いです。しかし、ごみ収集車はパッカーの圧縮動作に多大な電力を消費するため、バッテリー容量によっては一日の作業を完遂できないリスクや、積載量(ペイロード)がバッテリー重量分だけ減ってしまうという課題があります。
水素はエネルギー密度が高く、短時間での充填が可能です。江東区のように水素ステーションへのアクセスが良い地域であれば、EVのデメリット(充電時間、航続距離)を解消できるFCVの方が、運用の柔軟性が高いと判断された可能性があります。また、新明和工業等のメーカーも、CJPTと連携してFCトラックベースの塵芥車開発に力を入れており、技術的な選択肢が増えてきたことも背景にあります。
4
特別区および他自治体への包括的政策提言
ステップ1:徹底的な事前調査(フィジビリティ・スタディ)
江東区の事例から学ぶべき第一の教訓は、事前のインフラ調査とルート選定の重要性です。
導入を検討する自治体は、まず管内の道路事情をGIS(地理情報システム)等で分析し、全長6.5メートル級の車両が安全に運行できるルートを洗い出す必要があります。同時に、近隣の水素ステーション運営事業者と協議し、ごみ収集車の定期的な充填受け入れが可能か、契約に向けた内諾を得る必要があります。
ステップ2:BCP(事業継続計画)への組み込み
FCごみ収集車導入の稟議を通す際、単なる「環境対策」以上の説得材料として有効なのが「防災対策」です。
FCVは大容量の電力を供給できる「移動式発電所」としての機能を持っています。災害発生時、避難所となる学校や公民館にFCごみ収集車を派遣し、照明や通信機器への電力供給を行う運用フローを確立することで、車両の高額なコストに対する費用対効果(ROI)を高めることができます。東京都の補助金が「給電機能あり」に対して高額な加算を行っているのも、この防災レジリエンス強化を意図しているからです。
福岡市ではFC救急車の実証実験も始まっており、「緊急車両×水素」の組み合わせは、今後の都市防災のスタンダードになる可能性があります。
3
ステップ3:広域連携によるスケールメリットの追求
水素ステーションがない自治体単独での導入は現実的ではありません。しかし、隣接する複数の自治体(例えば世田谷区・目黒区・大田区の城南エリアなど)が連携し、共同で水素ステーションの誘致を行ったり、車両の共同調達(一括発注)によってメーカーとの価格交渉力を高めたりするアプローチは有効です。特別区清掃一部事務組合のような既存の枠組みを活用し、広域的な「水素ごみ収集ネットワーク」を構想することも、次なる政策ステップとして検討に値します。
結論と今後の展望
2027年へ向けたロードマップと残された課題
江東区は、2027年度以降にさらに3台を追加し、計5台体制とする明確なロードマップを描いています。この継続性は、メーカーに対する需要のシグナルとなり、FC車両の量産化・低価格化を後押しする重要な要素です。
しかし、課題も残されています。第一に、水素燃料価格の高止まりです。化石燃料由来ではない「グリーン水素」の普及が進まなければ、トータルでの脱炭素効果は限定的になりかねません。第二に、車両のメンテナンス体制です。FCシステムという特殊な機構を持つため、故障時の修理対応や部品調達に時間を要するリスクがあり、予備車(バックアップ車両)の確保も含めた運用計画が必要です。
江東区の挑戦は、日本の自治体行政における「水素社会実装」の試金石です。
本記事をご覧の職員の皆様におかれましては、この事例を「特殊な事例」として片付けるのではなく、自区の将来像と重ね合わせ、既存の清掃事業の中にどのように「脱炭素」と「防災」の価値を組み込んでいくか、具体的なシミュレーションを開始する契機としていただければ幸いです。
「静かで、空気を汚さず、災害時には電気も運ぶごみ収集車」が街を走る風景は、住民が実感できる「未来の行政サービス」の最も身近な形なのかもしれません。
1