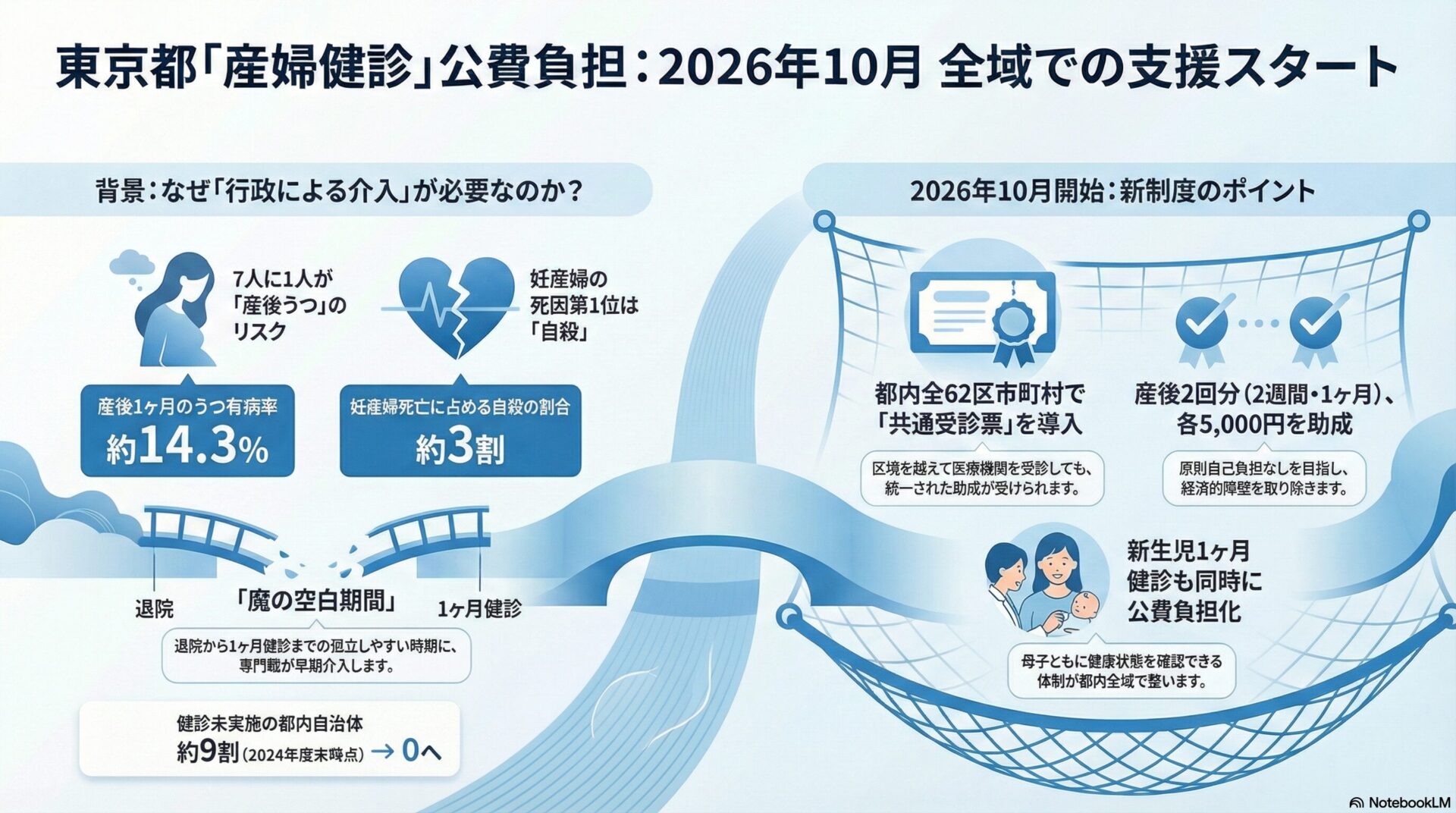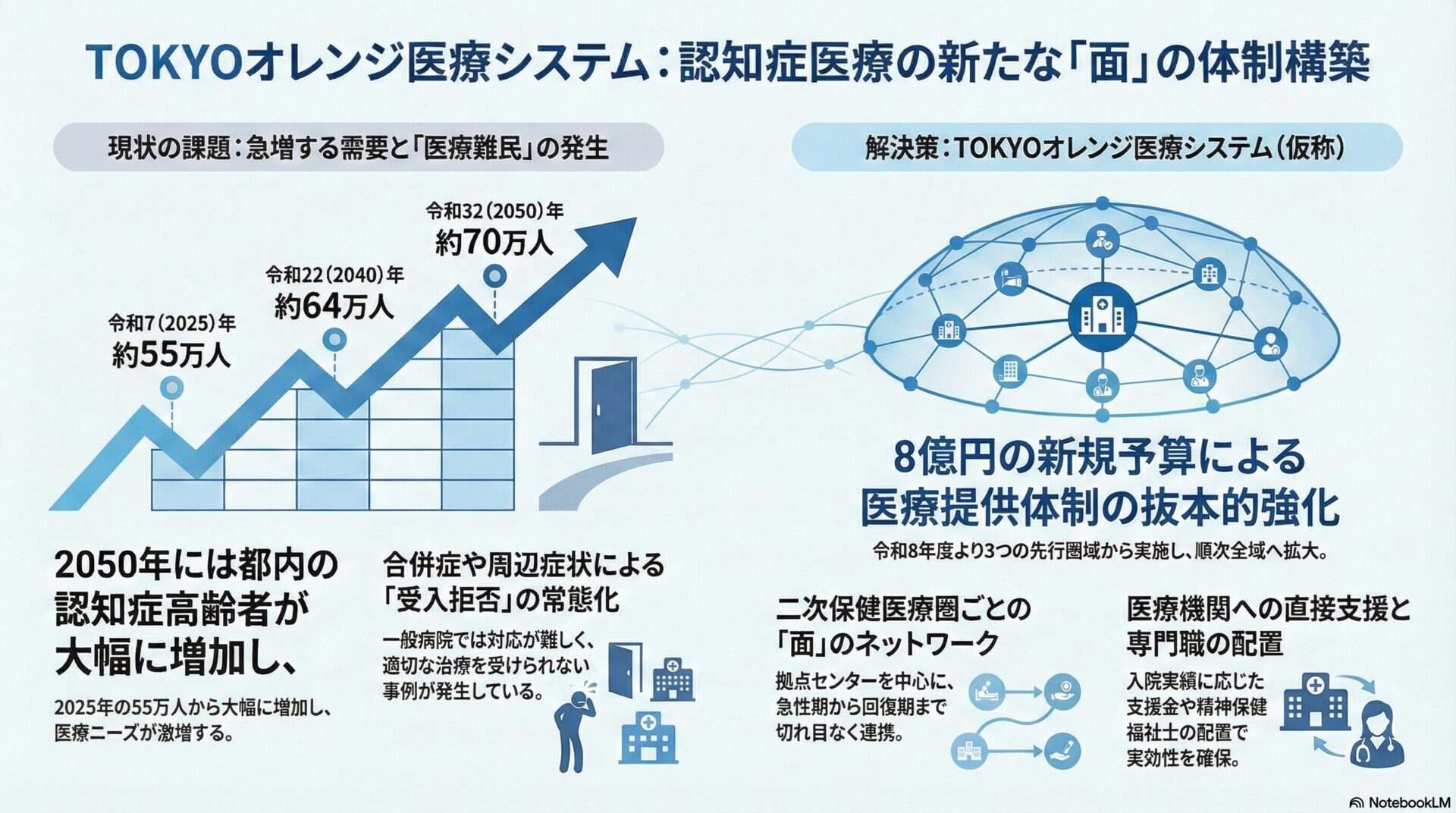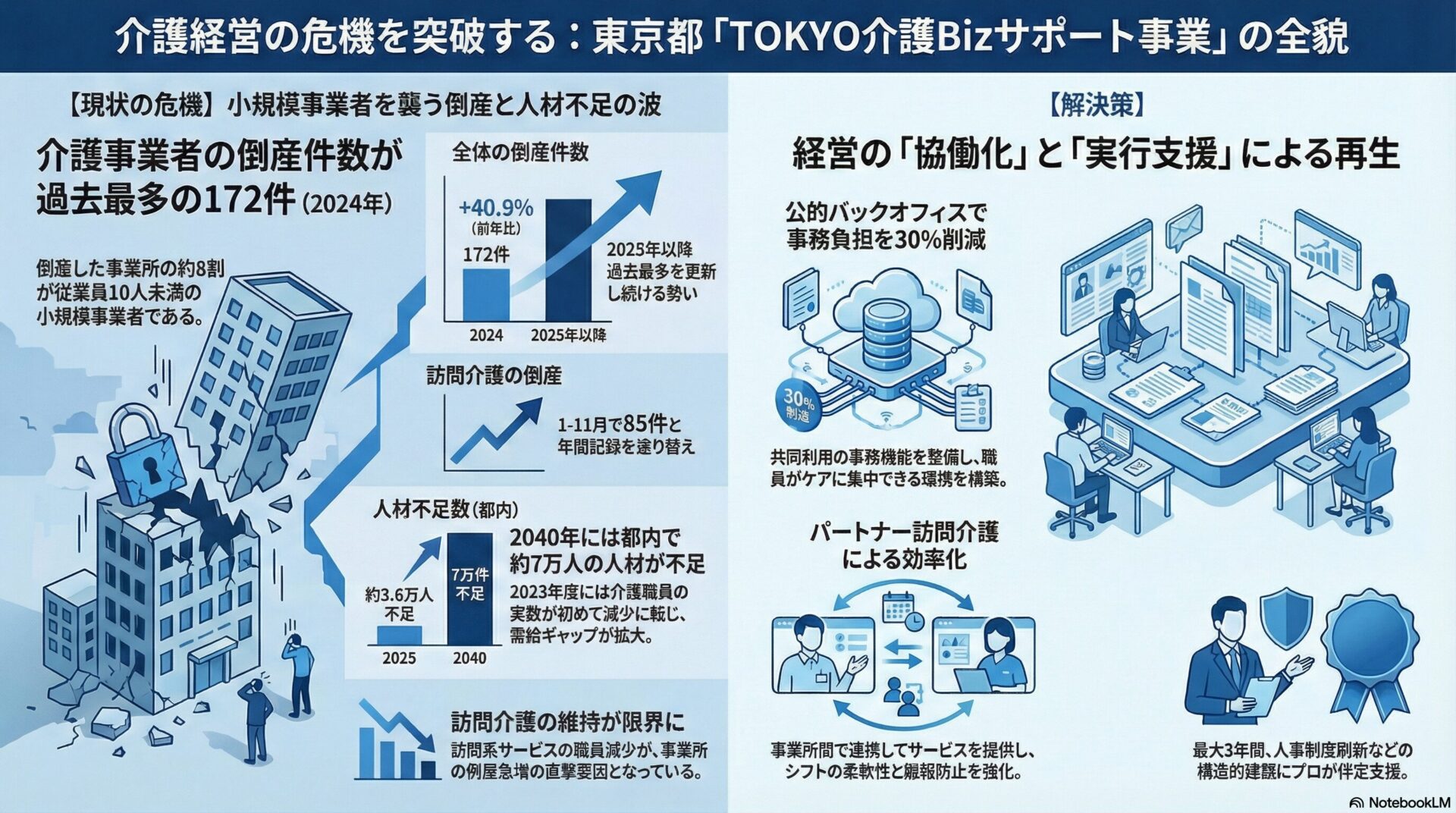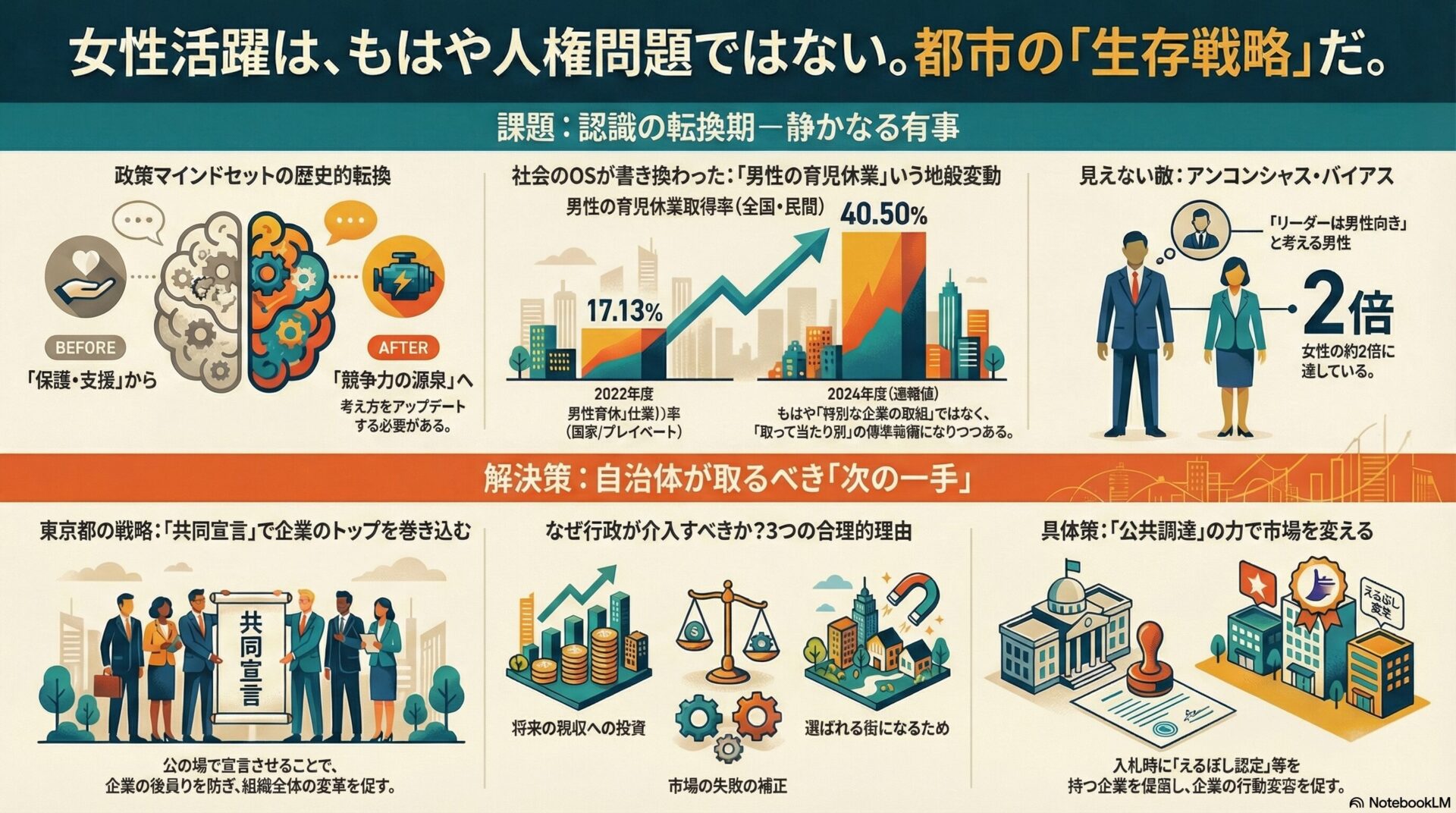東京都特別区の成り立ちと都区制度改革

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
概要
東京都の「特別区」は、地方自治法において「基礎的な地方公共団体」と明確に位置づけられています。しかし、その地位は一朝一夕に確立されたものではなく、「市」でも「区」でもない特殊な存在として、東京という大都市のあり方と共に揺れ動き、変遷を重ねてきた長い歴史があります。
本稿は、その複雑な歴史的経緯と、今日の制度を確立した「都区制度改革」の全容を、特別区職員の皆様の業務の礎となる知識として、詳細に解説するものです。
「東京市」の誕生と「東京都」への移行
(1889年~1947年)
今日の都区制度の原型は、戦前の「東京府」と「東京市」の二重行政構造とその解消の試みに遡ります。
東京府と東京市の「二重行政」時代
(1889年~1943年)
- 1889年(明治22年):
- 東京市の誕生市制町村制の施行により、東京府の管轄下にあった15区を区域として「東京市」が誕生しました。しかし、東京市は一般の市とは異なる特例(市制特例)により、市長は公選ではなく官選(内務大臣が推薦し天皇が任命)とされ、市役所も存在せず、その職務は東京府知事が兼任しました。
- 1898年(明治31年):
- 市制特例の廃止市制特例が廃止され、東京市は一般の市と同様に公選の市長と独自の市役所を持つことになり、ようやく法人格として独立します。
- 1932年(昭和7年):
- 35区への拡大(大東京市)周辺の5郡82町村を編入し、東京市は15区から「35区」へと拡大。人口500万人を超える世界有数の大都市「大東京市」が完成しました。
- 二重行政の弊害この結果、東京府の区域内に「東京市」という巨大な自治体が存在する「府市二重行政」の問題が深刻化します。道路、水道、都市計画など、広域的な行政ニーズに対し、府と市の権限が錯綜し、非効率が生じていました。
戦時体制下の「東京都制」施行
(1943年)
太平洋戦争の戦局が悪化する中、首都の行政を一元化し、戦争遂行体制(特に防空や食糧配給)を強化する必要に迫られました。
- 目的:
- 二重行政の解消と、首都行政の一元的・強力な執行体制の構築。
- 法律:
- 東京都制(1943年(昭和18年)7月1日施行)
- 内容:
- 東京府と東京市を廃止・統合し、「東京都」を設置。
- 東京都長官(官選)が、従来の府知事と市長の両方の権限を掌握。
- 旧東京市の35区は、法人格を失い、東京都の単なる「行政区」に格下げされました。
- 区長は公選ではなく、都長官が任命する官吏(役人)となりました。
この「東京都制」こそが、府と市を「統合」した直接の契機です。しかし、それは地方自治の発展ではなく、戦時下の中央集権的な国家統制の強化が目的でした。
戦後の再出発と自治権の「後退」
(1947年~1952年)
終戦を迎え、日本国憲法(地方自治の本旨)と地方自治法の制定により、東京の制度も民主化の波を受けます。
地方自治法の施行と「特別区」の誕生
(1947年)
1947年(昭和22年)5月3日、地方自治法が施行されます。
- 35区から23区へ:
- 戦災復興と行政基盤の強化のため、同年3月に35区は23区に再編されます(同年8月に板橋区から練馬区が分区し、現在の23区が確定)。
- 「特別区」の地位:
- 地方自治法において、都の区は「特別区」と名付けられました。
- 自治権の付与:
- この時点での特別区は、「市に関する規定が準用される」とされ、法人格を持つ「特別な地方公共団体」として位置づけられました。
- 区長公選制の導入:
- 最大の変更点は、区長が住民による直接選挙で選ばれる「区長公選制」が採用されたことです。
この時点では、特別区は一般の市とほぼ同等の自治権を持つ存在として再スタートを切りました。
シャウプ勧告と「内部的団体」への格下げ
(1952年)
この自治権は、わずか5年で大きく後退します。
- 背景:
- シャウプ勧告(1950年)GHQの要請によるシャウプ税制使節団は、「東京は一つの大都市として統一的に運営されるべき」であり、「23区がそれぞれ独立した市として振る舞うのは非効率」と勧告しました。
- 1952年(昭和27年)の地方自治法改正:
- この勧告を色濃く反映した法改正が実施されます。
- 地位の変更:
- 特別区は「市」に準ずる存在から、東京都の「内部的な団体」(都の内部組織)へと大幅に格下げされました。
- 区長公選制の廃止:
- 最大の自治権の後退として、区長公選制が廃止されました。区長は「区議会の同意を得て、都知事が選任する」方式に変更され、区長の任免権は事実上、都知事が握ることになりました。
- 権限の制限:
- 特別区の事務は法律で限定的に列挙され(制限列挙)、それ以外の多くの都市的事務(清掃、消防、水道など)は都の事務とされました。
- 地位の変更:
- この勧告を色濃く反映した法改正が実施されます。
この1952年改正により、戦後の「都(広域自治体)と区(基礎自治体)」の関係は、「都(大都市)と区(内部組織)」という、都が圧倒的に優位な関係へと変貌しました。
自治権拡充への道と「区長公選制」の復活
(1952年~1999年)
1952年以降、特別区は失われた自治権を取り戻すための長い運動の時代に入ります。
自治権拡充運動
(1960年代~)
人口が急増し、行政需要が多様化する中で、「内部的団体」という制約は区民サービス提供の足かせとなっていきました。各区(特に革新区長が誕生した区)は、都に対して事務の移管や財源の拡充を求める「自治権拡充運動」を粘り強く展開します。
決定的な転換点:
区長公選制の復活(1975年)
この運動の最大の成果が、1974年(昭和49年)の地方自治法改正(1975年4月施行)による「区長公選制の復活」です。
- 背景:
- 1952年以降の「知事選任・議会同意」方式は、区政の停滞や「区長不在」といった問題を各地で引き起こしました。
- 影響:
- 住民が直接、区のリーダーを選べるようになったことで、特別区は「住民の意思を直接反映する自治体」としての性格を劇的に取り戻しました。
- 事務の「市並み」化:
- 同時に、特別区の事務が「制限列挙」から、原則として「市並み」(市が処理する事務は原則として特別区も処理する)へと転換されました。
この1975年の改革は、特別区が「内部的団体」から脱却し、2000年の抜本改革へと向かうための決定的な布石となりました。
「基礎的な地方公共団体」への転換
(2000年)
1990年代、日本全体で「中央集権から地方分権へ」という大きな潮流が生まれます。1995年の「地方分権推進法」の制定は、全国一律の規制を見直す動きを加速させました。
この流れの中で、「都が区の事務や財源を強力にコントロールする」という都区制度は、地方分権の理念に逆行する旧態依然の制度として、抜本的な見直しが迫られました。
「基礎自治体」としての法的位置づけ
(2000年4月1日施行)
1999年(平成11年)の「地方分権一括法」による地方自治法の大改正(2000年4月1日施行)により、都区制度は歴史的な大転換を遂げました。
- 改正の核心:
- 地方自治法第281条において、特別区の法的地位が「都の内部的団体」から「基礎的な地方公共団体」へと明確に書き換えられました。
- 意義:
- これにより、特別区は法律上、一般の「市」と同格の基礎自治体として、自己決定権と自己責任に基づき、地域の行政を包括的に担う主体として再定義されました。
改革の具体的・詳細な内容
この「基礎自治体」への転換に伴い、都と区の役割分担、権限、財源のあり方が全面的に見直されました。
事務の大幅な移管(都から区へ)
- 原則:
- 「基礎自治体である特別区が処理すべき事務は、特別区が担う」という原則が確立されました。
- 象徴的な移管事務(清掃事業):
- 改革の最大の象徴が、それまで都が一元的に行っていた「清掃事業」(ごみの収集・運搬・処分)の特別区への移管です。これにより、各区が自らの責任と判断で、リサイクルの推進やごみ減量、収集体制の構築を行うようになりました。(※中間処理(焼却)は23区共同の「東京二十三区清掃一部事務組合」が担う)
- その他の移管:
- このほか、区立公園の設置管理、産業経済行政の一部、まちづくり関連事務(例:屋外広告物)など、多くの事務が都から区へ移管されました。*(補足:その後も段階的な移管が進み、2012年(平成24年)には児童相談所の設置・運営権限が移管可能となりました)
都区財政調整制度の再構築
最も複雑かつ重要な変更が「カネ」の流れの変更です。制度の名称(都区財政調整制度)は残りましたが、その性格が根本的に変わりました。
- 旧制度(~1999年度):
- 性格:
- 都から区への「垂直的な財政移転」。
- 仕組み:
- 都が23区内で固定資産税、法人住民税などの「市町村税」を一括して徴収し、そこから一定割合を「調整交付金」として各区に配分する仕組み。区の財源は、この都からの交付金に大きく依存していました。
- 性格:
- 新制度(2000年度~):
- 性格:
- 「23区間での水平的な財政調整」。
- 仕組み:
- 財源の明確化:
- 固定資産税、法人住民税、特別土地保有税の3税を「調整税源」と位置づけ。
- 都区の配分:
- 都と23区が、これらの税収を一定のルール(例:固定資産税は都45%:区55%)で分け合います。
- 水平調整:
- 区に配分された55%分を「共通のプール(財政調整財団)」に入れ、そこから各区の基準財政需要額(行政運営に必要な標準経費)と基準財政収入額(区税などの標準収入)の差額を埋める形で、各区に「特別区財政調整交付金」として再配分します。
- 財源の明確化:
- 意義:
- これは、都が一方的に交付額を決める「交付金」ではなく、「基礎自治体である23区が、互いの財政力格差を是正し合うための、法律に基づいた水平調整システム」へと変貌したことを意味します。これにより、区の財政運営の自律性と予見可能性が格段に高まりました。
- 性格:
都の権能制約の廃止(区の条例制定権の確立)
- 旧制度:
- 都は、区の事務に対して広範な「調整権」を持ち、区が条例を制定する際にも都の承認が必要な場合があるなど、強い関与・介入が可能でした。
- 新制度:
- これらの都による包括的な関与・介入権限は原則として廃止されました。特別区は、一般の市と同様に、法律の範囲内で自由に条例を制定できる「完全な条例制定権」を獲得しました。
東京都の役割の明確化
改革により、23区の区域内における都の役割は、以下のように明確化されました。
- 広域自治体(都道府県)としての事務
(警察、教育(高校以上)、広域的な道路・河川管理など) - 大都市として一体的に処理すべき事務
(消防、水道、下水道) - 都区財政調整制度の運営
まとめ:現在の特別区の姿
特別区の歴史は、「首都・東京」という巨大都市の行政を「誰が(都か、区か)」「どのように担うか」という、自治と効率の間の長い緊張関係の歴史でした。
- 1943年(東京都制):
- 「効率(戦争遂行)」を優先し、区の自治を奪い「行政区」に。
- 1952年(シャウプ勧告):
- 「大都市の一体性」を優先し、区を「内部的団体」に。
- 1975年(区長公選制復活):
- 「住民自治」の要求が実り、自治権回復の第一歩を踏み出す。
- 2000年(都区制度改革):
- 「地方分権」の潮流に乗り、区が「市」と同格の「基礎的な地方公共団体」としての地位を確立。
現在の特別区は、一般の市とは異なる独自の財政調整制度を持つ一方で、区民に最も身近な行政主体として、自らの条例と予算に基づき、自己決定・自己責任で地域経営を担う存在です。この「基礎自治体」としての重い責任こそが、特別区職員の皆様の業務の根幹にあると言えます。本稿が、日々の業務における制度理解の一助となれば幸いです。




-320x180.jpg)

-320x180.jpg)