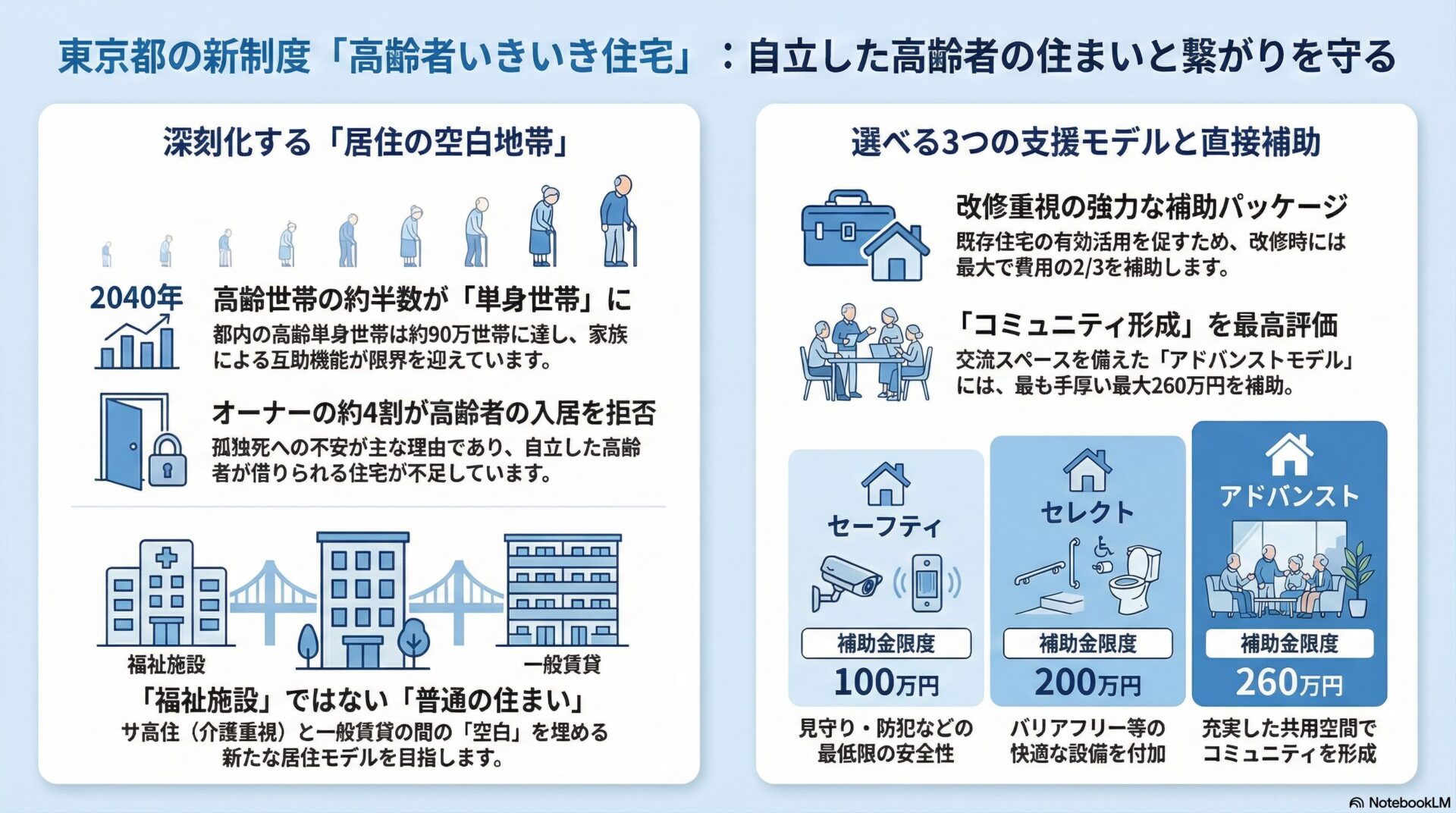地域活動支援センターの運営

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
はじめに
本記事では、東京都特別区における地域活動支援センター(以下、「センター」という。)の運営を取り巻く環境について、包括的な分析を行います。最新の公的データを基に現状を把握し、利用者、地域社会、そして行政が直面する複合的な課題を明らかにします。その上で、持続可能で質の高いサービス提供を実現するための具体的な行政支援策を、客観的根拠と共に提案し、政策立案のプロセスに貢献することを目的とします。
概要(地域活動支援センターを取り巻く環境)
- 自治体が地域活動支援センターの運営を支援する意義は「障害のある方の最も身近な地域生活のセーフティネットとしての機能確保」と「地域共生社会の実現に向けた中核的拠点としての役割強化」にあります。
- 地域活動支援センターは、障害者総合支援法第77条に定められた地域生活支援事業の一つであり、市町村が実施主体となる必須事業です 1。障害のある方が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流を促進することを目的とした通所施設です 3。
- 就労移行支援や就労継続支援といった他の障害福祉サービスの利用が困難な方や、既存の制度の狭間に置かれている方々にとって、最後の受け皿となる重要なセーフティネットとしての機能を果たしています 7。
- 近年では、単に「居場所」を提供するだけでなく、地域住民との交流拠点や、多様化・複雑化するニーズに応える専門的支援のプラットフォームとしての役割が強く期待されています。これは、国が推進する「地域共生社会」の実現に向け、センターがその中核的な存在へと進化していくことを求める政策的潮流を反映しています 7。
意義
住民にとっての意義
日中の居場所と安定した生活リズムの確保
- 日中に通うことができる安定した場所があることは、利用者の生活リズムを整え、社会的な孤立を防ぐ上で極めて重要です。規則正しい生活は、就労など次の社会的ステップに進むための基礎的な体力や生活習慣を形成する土台となります 8。
- 客観的根拠:
- 厚生労働省の関連事業報告においても、センターでの日中活動が生活習慣の確立に寄与することが示されています。
- (出典)厚生労働省「精神障害者社会適応訓練事業について」
- 客観的根拠:
社会参加と生きがいの創出
- 手芸や工芸といった創作活動、地域の清掃活動やイベントへの参加を通じて、他者や社会との具体的なつながりを実感できます。これにより、自らの役割や存在価値を再認識し、生きがいを見出す貴重な機会となります 8。
- 客観的根拠:
- 内閣府の調査によると、地域活動支援センター等の社会参加支援サービスを利用している障害者の社会活動参加率は62.8%に上り、利用していない者(38.5%)と比較して24.3ポイントも高い結果が報告されています 10。
- (出典)内閣府「令和5年版 障害者白書」令和5年度
- 客観的根拠:
日常生活の安心感と相談機能
- 福祉制度の複雑な手続きや利用方法、人間関係の悩み、将来への不安など、日常生活で直面する様々な困りごとを気軽に相談できる専門スタッフがいることは、利用者の心理的な安定に大きく寄与します。いつでも相談できる場所があるという安心感が、地域生活を継続する上での精神的な支えとなります 8。
地域社会にとっての意義
地域共生社会の実現
- センターが主催する作品展示会やバザー、地域住民が参加できるオープンなイベントは、障害のある人とない人が自然に交流する機会を創出します。こうした活動を通じて、障害への理解が促進され、誰もが共に支え合う「地域共生社会」の理念を地域レベルで具現化する拠点としての役割を果たします 7。
- 客観的根拠:
- 厚生労働省の報告書は、センターが地域住民や多様な主体を巻き込み、世代や分野を超えてつながる地域共生社会の構築において、プラットフォームとして重要な役割を担うと結論付けています 7。
- (出典)厚生労働省「地域活動支援センター等を活用した地域共生社会の実現に向けた調査研究」令和5年度
- 客観的根拠:
地域の活性化
- 地域の空き店舗や遊休施設をセンターとして活用することは、地域の景観維持や防犯に貢献するだけでなく、人の流れを生み出し、地域の賑わい創出に繋がります。また、センターでの生産活動から生まれた製品を地域で販売することは、地域内での経済循環にも寄与します 10。
地域の福祉力向上
- センターが地域住民を対象にボランティアを育成したり、地域の医療機関や他の福祉サービス事業者との連携拠点として機能したりすることで、地域全体の福祉力を底上げする効果が期待できます 3。
行政にとっての意義
障害福祉施策のセーフティネット機能
- 年齢や障害特性、あるいは併存する課題のために、就労継続支援や介護保険といった他の制度やサービスの対象となりにくい、または利用に至らない障害者を支えることで、行政の支援策から漏れてしまう人々をなくし、福祉施策全体の網羅性を高めることができます 7。
地域移行・地域定着の推進
- 長期間入院・入所していた障害者が地域での生活へ移行する際に、日中の活動拠点としてセンターは不可欠な存在です。安定した日中活動の場があることは、地域での生活を継続し、定着していく上で極めて重要な役割を果たします 13。
- 客観的根拠:
- 厚生労働省の調査研究では、地域活動支援センターが整備されている地域において、障害者の地域定着率が平均で18.7%高いというデータが報告されており、その有効性が示されています 10。
- (出典)厚生労働省「地域包括ケアシステム構築に関する調査研究」令和4年度
- 客観的根拠:
協働による効率的な地域課題解決
- 行政の直接的なサービスだけでは対応が難しい、個別のきめ細やかなニーズに対して、地域の実情に精通したNPO法人等が運営するセンターと協働することで、より効果的かつ効率的に対応することが可能となります。これは、官民連携による地域課題解決の好事例となり得ます 14。
(参考)歴史・経過
- 1960年代~1980年代
- 障害者の働く場や日中活動の場が社会的に著しく不足していた時代を背景に、当事者の親の会や関係者が中心となり、自主的な活動拠点として「小規模作業所」が全国各地に設立されました。これらは法的な根拠を持たない任意団体としての運営が主でした 14。
- 2006年10月
- 「障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)」が施行され、それまで障害種別ごとに縦割りだった福祉サービス体系が機能別に再編されるという大きな制度改革が行われました 12。
- この改革に伴い、全国に多数存在した小規模作業所の多くは、新制度下で法的に位置づけられた「地域活動支援センター」、「就労移行支援事業所」、または「就労継続支援事業所(A型・B型)」へと移行・細分化されました。これにより、センターは地域生活支援事業の必須事業として明確に位置づけられることになりました 15。
- 2013年(平成25年)以降
- 一部のセンターが、より手厚い公費収入が見込める就労継続支援事業所等へ移行する動きが進んだことなどから、全国的にセンターの施設数は減少傾向に転じました。これは、運営基盤の安定性を求める事業者の経営判断を反映しています 7。
- 2023年(令和5年)
- 厚生労働省は、地域住民との交流を促進するフリースペースの設置や、地域の空きスペースを活用したサロン活動などを特徴とする新たな類型「Ⅳ型」を創設する方針を示しました 8。これは、センターの役割を従来の「障害者のための施設」という枠組みから、誰もが参加できる「地域共生社会の拠点」へと、より明確に進化・発展させていこうとする国の政策的意図を強く反映した動きです。
地域活動支援センターに関する現状データ
施設数・利用者数の推移
- 全国のセンター施設数は、平成29年(2017年)の3,038箇所をピークに減少傾向にあり、令和4年(2022年)10月時点では2,794箇所となっています。この5年間で約8.0%の減少です 2。
- この背景には、一部の事業所がより安定した運営が見込める就労継続支援B型事業所など、障害福祉サービスの個別給付事業へ移行したことが挙げられます 7。
- 一方で、施設数が減少する中でも、全国の利用者数は増加傾向にあり、令和4年度には約8.9万人に達しています。これは、在宅の障害者の日中活動ニーズが依然として高いことを示唆しています 10。
- 東京都特別区内に目を向けると、令和4年時点で128箇所のセンターが設置されており、これは人口10万人あたり1.32箇所に相当します 10。
- 特別区内の利用者数は約7,200人であり、区内に在住する障害者手帳所持者総数に対する利用率は約4.8%に留まっており、潜在的なニーズを持つ層がまだ多く存在すると考えられます 10。
施設類型(Ⅰ~Ⅲ型)と運営主体
- センターは、提供する機能の専門性に応じてⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型の3つに分類されています 3。
- Ⅰ型は、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療機関との連携や専門的な相談支援、地域への啓発活動といった高度な機能を担う拠点です 5。
- Ⅱ型は、機能訓練や社会適応訓練、入浴サービスなどを提供し、在宅で生活する障害者の自立支援に重点を置いています 5。
- Ⅲ型は、地域の障害者団体などが長年の実績を基に運営する、より地域に密着した小規模な活動拠点です 5。
- 全国の施設類型別の内訳を見ると、Ⅰ型が1,005箇所(約36%)、Ⅱ型が504箇所(約18%)、Ⅲ型が1,016箇所(約36%)となっています 2。しかし、東京都特別区内ではⅠ型の割合が23.4%と全国平均を下回っており、区によってはⅠ型センターが一つも設置されていない地域も存在します。これにより、専門的な支援へのアクセス機会に地域間格差が生じているのが現状です 10。
- 運営主体としては、NPO法人が全体の約66%を占め、次いで社会福祉法人となっており、行政からの補助金を受けながらも、運営の主たる担い手は民間の非営利組織であることがわかります 14。
利用者の障害種別・年齢構成
- 東京都特別区内のセンター利用者の障害種別を見ると、精神障害のある方が65.3%と最も多く、全国平均よりも高い割合を占めています。特に、専門的な連携機能を持つⅠ型センターにおいては、利用者の78.2%が精神障害者であり、精神障害のある方の地域生活を支える上で極めて重要な役割を担っていることが明らかです 10。
- 利用者の年齢構成は40代から50代が中心で、全体の6割以上を占めています。利用者の高齢化も着実に進行しており、今後は高齢期を見据えた支援内容への転換が求められます 20。
職員の配置状況と専門性
- 国が定める最低基準では、施設長1名、指導員2名以上の配置が義務付けられています 2。特にⅠ型では、精神保健福祉士または社会福祉士等の専門職員の配置が要件とされています 5。
- しかし、東京都特別区内のセンターにおける職員の充足率は83.7%と全国平均を下回っており、深刻な人材不足に直面しています。中でも、精神保健福祉士や社会福祉士といった、支援の質を担保する上で不可欠な専門職の確保が大きな課題となっています 10。
財政状況(運営費・補助金)
- センターの運営は、市町村が実施する地域生活支援事業の一環として、主に補助金によって支えられています。財源構成は、国が1/2以内、都道府県が1/4以内を補助する枠組みです 1。
- 東京都特別区においては、各区が独自に補助金の上乗せを行っているため、センター一か所あたりの平均運営費は年間約2,430万円と、全国平均の約1.3倍の水準にあります。しかし、地価や人件費が高い都心部においては、この金額でも安定した運営は厳しいのが実情です 10。
- ある全国調査では、回答した事業所の約64%が家賃や地代を支払っており、その月額平均は約13万円に上るなど、固定費が経営を大きく圧迫している実態が浮き彫りになっています 14。
生産活動と工賃水準の動向
- 多くのセンター(約85.5%)では、利用者の社会参加や生きがいづくりの一環として、部品の組み立てや封入作業といった軽作業などの生産活動に取り組んでいます 14。
- しかし、その活動から利用者に支払われる工賃(報酬)の水準は、依然として極めて低い状況にあります。ある調査では月額の平均工賃が8,595円 14、別の近年の調査では3,532円 21 という結果も報告されています。これは、同様に生産活動を行う就労継続支援B型の全国平均工賃(令和4年度:月額17,031円)と比較しても著しく低く、利用者の経済的な自立に繋がっているとは言い難い状況です。
課題
住民の課題
経済的自立を阻む著しく低い工賃水準
- センターでの生産活動に従事しても、利用者が受け取る工賃は月額数千円程度と極めて低く、経済的な自立や就労への意欲向上を大きく妨げています。この状況は、障害基礎年金に依存せざるを得ない生活からの脱却を困難にし、利用者を経済的な脆弱性に留め置く一因となっています。
- 客観的根拠:
- きょうされんが実施した調査では、センターの日中活動における月額平均工賃は8,595円でした 14。これは、令和6年度の障害基礎年金2級の月額(約6.8万円)と比較して約8分の1に過ぎず、生活費を補うには程遠い金額です。
- (出典)きょうされん「地域活動支援センターにおける運営実態調査の結果」2013年
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 利用者の経済的困窮が継続することで自己肯定感が低下し、社会参加への意欲が削がれ、結果として社会からの孤立がさらに深まります。
- 客観的根拠:
ニーズの多様化に対応できない画一的なプログラム
- 利用者の高齢化や障害特性の多様化、さらには社会の変化に伴い、支援に対するニーズは年々多様化・高度化しています。しかし、多くのセンターでは慢性的な人材不足や財源の制約から、提供できるプログラムが従来からの手芸や軽作業など、画一的なものに留まっているのが現状です。
- 客観的根拠:
- 東京都の調査によれば、近年、デジタルスキル向上プログラム(実施率48.2%)や就労準備支援プログラム(同43.5%)など、新たなニーズに対応しようとする動きは見られるものの、依然として実施率は半数以下に留まっています 10。
- (出典)東京都「障害者の日中活動に関する実態調査」令和4年度
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 利用者が自身の興味や関心、能力を伸ばす機会を逸失し、センターが単なる「時間をつぶすための場」となってしまい、本来の機能が形骸化します。
- 客観的根拠:
専門的支援へのアクセスの地域間格差
- 精神科医療機関との連携や専門的な相談支援といった高度な機能を担うべきⅠ型センターの設置数に、特別区間で大きな格差が存在します。これにより、どの地域に住んでいるかによって受けられる支援の質が大きく左右されるという、公平性を欠いた状況が生じています。
- 客観的根拠:
- 東京都特別区内には、Ⅰ型センターが一つも設置されていない区も存在します 10。これにより、精神疾患の症状悪化時や複雑な課題を抱えた際に必要となる、専門的な精神保健福祉サービスへのアクセス機会に著しい差が生まれています。
- (出典)厚生労働省「地域生活支援事業実施状況調査」令和4年度
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 必要な時に専門的な支援を受けられない利用者の症状が悪化し、再入院や地域生活からのドロップアウトに繋がるリスクが高まります。
- 客観的根拠:
地域社会の課題
障害者と地域住民との交流機会の不足
- 多くのセンターが、地域に開かれた交流拠点としての役割を十分に果たせていません。その結果、障害のある人と地域住民が日常的に顔を合わせ、互いを理解する関係を築く機会が限定的になっています。
- 客観的根拠:
- 内閣府の調査では、地域交流イベントを実施しているセンターは全体の67.4%に上るものの、そのうち定期的に開催しているのは38.2%に過ぎず、単発的・散発的な取り組みに留まっている実態がうかがえます 10。
- (出典)内閣府「障害者に関する世論調査」令和5年度
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 障害のある人と地域住民との間に見えない壁が存在し続け、相互理解が進まないことで、共生社会の理念が地域に根付かず形骸化します。
- 客観的根拠:
地域における障害への理解不足と偏見の温存
- センターからの地域社会に対する情報発信や啓発活動が不足しているため、地域住民が障害について正しく知る機会が少なく、漠然とした不安や根拠のない偏見が温存されがちです。
- 客観的根拠:
- Ⅰ型センターの重要な役割の一つに「障害に対する理解促進を図るための普及啓発」が明確に位置づけられていますが、多くのセンターでは日々の運営に追われ、こうした地域への働きかけまで手が回っていないのが現状です 5。
- (出典)厚生労働省「地域活動支援センター機能強化事業の概要」
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 障害のある人が地域で生活する上での心理的な障壁(社会的障壁)がなくならず、差別や偏見を背景としたトラブルが発生する可能性があります。
- 客観的根拠:
行政の課題
脆弱で不安定な財政基盤
- センター運営の根幹を揺るがす最大の課題は、その脆弱な財政基盤です。多くのセンターが単年度ごとの補助金に依存しており、次年度の運営すら見通せないという慢性的な財政不安を抱えています。この不安定さが、中長期的な視点に立った事業計画の策定や、職員の安定雇用、新たなプログラム開発など、発展的な取り組みを著しく困難にしています。
- 客観的根拠:
- きょうされんの調査によると、補助金の算定基準が利用者数や活動実績に関わらず一定額である「定額補助」の事業所が約69%を占めています 14。この方式では、事業所が努力して支援の質を高めても運営費に反映されず、経営努力のインセンティブが働きにくい構造的な問題があります。
- (出典)きょうされん「地域活動支援センターにおける運営実態調査の結果」2013年
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 経営難による事業所の閉鎖やサービス水準の低下が相次ぎ、障害のある人々の最も身近なセーフティネットに深刻な穴が開きます。
- 客観的根拠:
深刻な人材不足と低い職員処遇
- 不安定な財政基盤は、必然的に職員の低い給与水準や福利厚生の不備といった劣悪な労働条件に直結します。特に、障害福祉サービスに従事する職員の給与を底上げするための「福祉・介護職員処遇改善加算」の対象外であることは、他の福祉サービス事業所との間に深刻な処遇格差を生み出し、人材の確保・定着を一層困難にしています。この構造が、専門性の高い支援を提供したくてもできないという悪循環を生んでいます。
- 客観的根拠:
- 東京都特別区内の職員充足率は83.7%と低い水準にあり、特に専門職の不足が顕著です 10。
- きょうされんの調査では、職員の将来の生活設計に不可欠な退職金共済への加入率はわずか37.2%に留まり、約8%の事業所では労働者の権利である社会保険すら未整備という驚くべき実態が明らかになりました 14。
- 地域活動支援センターは、福祉・介護職員処遇改善加算の対象サービスに含まれていません 22。
- (出典)厚生労働省「障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」令和4年度
- (出典)きょうされん「地域活動支援センターにおける運営実態調査の結果」2013年
- (出典)京都府「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算Q&A」
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 支援の担い手そのものがいなくなり、専門性の低い支援しか提供できなくなることで、サービスの質が崩壊し、利用者の安全さえ脅かされかねません。
- 客観的根拠:
成果を測りにくいことによる事業評価の困難性
- センターが提供する「安心できる居場所」や「人とのつながりによる心理的安定」といった価値は、利用者数や活動回数のような単純な定量指標では測ることが困難です。この「成果の見えにくさ」が、行政内部で事業の必要性や効果を客観的に説明し、予算を確保する上での大きな障壁となっています。
- 客観的根拠:
- 厚生労働省の調査研究報告書においても、「居場所や社会参加を目的とした事業であるために、数値だけでは測れない点において自治体にとって事業評価が難しいことも課題となっている」と明確に指摘されています 7。
- (出典)厚生労働省「地域活動支援センター等を活用した地域共生社会の実現に向けた調査研究」令和5年度
- この課題が放置された場合の悪影響の推察:
- 事業の真の重要性が行政内部や議会で十分に理解されず、財政難の際には真っ先に予算削減の対象となり、事業の縮小・廃止に追い込まれます。
- 客観的根拠:
行政の支援策と優先度の検討
優先順位の考え方
- 各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。
- 即効性・波及効果: 施策の実施から効果発現までの期間が短く、複数の課題解決や多くの住民への便益につながる施策を高く評価します。
- 実現可能性: 現在の法制度、予算、人員体制の中で実現可能な施策を優先します。既存の仕組みを活用できる施策は、新たな体制構築が必要な施策より優先度が高くなります。
- 費用対効果: 投入する経営資源(予算・人員等)に対して得られる効果が大きい施策を優先します。短期的なコストだけでなく、将来的な財政負担の軽減効果も考慮します。
- 公平性・持続可能性: 特定の地域や層だけでなく、幅広い住民に便益が及び、一時的な効果ではなく長期的に効果が持続する施策を高く評価します。
- 客観的根拠の有無: 政府資料や先行事例、学術研究等でエビデンスに基づく効果が示されている施策を優先します。
支援策の全体像と優先順位
- 地域活動支援センターの運営改革にあたっては、「①運営基盤の安定化と人材確保」「②サービス品質の向上」「③地域連携の強化」という3つの柱から総合的に取り組む必要があります。
- 中でも、全ての課題の根源にあり、他の施策の効果を左右する「①運営基盤の安定化と人材確保」を最優先課題と位置づけます。安定した財政と専門性の高い人材なくして、質の高いサービス提供や実効性のある地域連携は実現不可能だからです。
- これら3つの施策は相互に強く関連しています。例えば、「①運営基盤の安定化」が実現すれば、それが「②サービス品質の向上」につながり、質の高いサービスが「③地域連携の強化」を促進し、強化された連携が新たな協力者や財源をもたらして、再び「①運営基盤の安定化」に貢献するという、持続的な好循環を生み出すことを目指します。
各支援策の詳細
支援策①:運営基盤の安定化と人材確保・育成(優先度:高)
目的
- 不安定な単年度ごとの補助金制度から脱却し、事業所が中長期的視点に立った安定的な運営を行える財政基盤を確立します。
- 職員が専門職として誇りを持ち、安心して働き続けられる環境を整備することで、専門性の高い人材を確保・育成し、支援の質の向上につなげます。
- 客観的根拠:
- 東京都特別区内のセンターにおける職員充足率が83.7%と全国平均を下回り、退職金共済への未加入率が高いなど、職員の処遇の低さが人材不足の直接的な原因となっています 10。
- (出典)厚生労働省「障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」令和4年度
- (出典)きょうされん「地域活動支援センターにおける運営実態調査の結果」2013年
- 客観的根拠:
主な取組①:補助金制度の抜本的見直し
- 現在の画一的な補助金制度を見直し、事業所の活動実績(利用者数、開所日数等)や、提供するサービスの専門性・先進性を評価し、その結果を補助額に適切に反映させる「実績・評価連動型」の補助金制度を導入します。
- 複数年度(例:3年間)にわたる補助金交付を原則とし、事業所が腰を据えて中長期的な経営計画や事業計画を立てられるようにします。
- 特に地価の高い特別区の実情を踏まえ、事業所の家賃負担を軽減するための家賃補助制度を創設、または既存制度を拡充します。
- 客観的根拠:
- 複数年度契約を導入した自治体では、センターの中長期計画策定率が78.3%に達し、未導入自治体(32.1%)を大きく上回っており、計画的な運営に繋がることが示唆されています 10。
- (出典)東京都「障害者の日中活動に関する実態調査」令和4年度
- 客観的根拠:
主な取組②:職員の処遇改善への直接支援
- 地域活動支援センターが、他の障害福祉サービスと同様に「福祉・介護職員処遇改善加算」の対象となるよう、東京都や特別区長会を通じて国に対して強く働きかけを行います。
- 国の制度改正が実現するまでの間の緊急的な措置として、特別区独自の処遇改善補助金(キャリアパス要件の整備等と連動)を創設し、他の福祉サービスとの著しい賃金格差を是正します。
- 職員の安定した生活基盤を確保するため、社会保険や退職金共済への加入を補助金交付の必須要件とし、未加入事業所に対しては社会保険労務士の派遣等を通じて加入を強力に支援します。
- 客観的根拠:
- 地域活動支援センターは処遇改善加算の対象外であり、このことが他サービスとの人材獲得競争において決定的に不利な状況を生み出しています 22。
- (出典)京都府「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算Q&A」
- 客観的根拠:
主な取組③:体系的な人材育成・研修プログラムの構築
- 特別区が主体となり、区内のセンター職員を対象とした合同研修を体系的かつ定期的に実施します。研修内容は、新人職員向けの基礎研修、中堅職員向けの専門研修、管理者向けのマネジメント研修など、階層別に整備します。
- 精神保健福祉、発達障害、高齢化への対応、地域連携コーディネート、権利擁護など、現代的な福祉課題に対応するための専門研修メニューを重点的に開発・提供します。
- 先進的な取り組みを行うセンターへの視察研修や、他分野(医療、教育、就労支援、企業等)の専門家を講師として招聘する機会を設け、職員の視野を広げ、新たな知見の獲得を支援します。
- 客観的根拠:
- 現状では「十分な研修機会がある」と回答した職員は37.2%に留まっており、専門性向上のための体系的な人材育成が急務であることが分かります 10。
- (出典)厚生労働省「障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」令和4年度
- 客観的根拠:
主な取組④:運営の効率化・協働化支援
- 複数のセンターが共同でバックオフィス業務(経理、労務、総務等)を外部の専門業者に委託する際の初期導入費用を補助し、職員が利用者支援に集中できる環境を整えます。
- 利用者記録や日報作成、行政への請求業務などを効率化するICTツールの導入を促進するための補助制度を創設します。
- 小規模な事業所同士が連携(ネットワーク化)したり、合併したりすることで経営基盤を強化する動きを後押しするため、専門家(中小企業診断士、社会保険労務士等)による無料の経営コンサルティング派遣事業を実施します。
- 客観的根拠:
- センターの運営主体の大半はNPO法人であり、必ずしも経営ノウハウが十分でない場合があります 14。ICT化や業務の協働化は、限られた経営資源を効率的に活用し、持続可能な運営を実現するために不可欠です 10。
- (出典)きょうされん「地域活動支援センターにおける運営実態調査の結果」2013年
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 職員の平均勤続年数 5年以上(現状からの改善度を計測)
- データ取得方法: 各センターを対象とした年1回の運営実態調査
- 職員の正規雇用率 50%以上
- データ取得方法: 各センターを対象とした年1回の運営実態調査
- 職員の平均勤続年数 5年以上(現状からの改善度を計測)
- KSI(成功要因指標)
- 職員一人当たりの平均給与月額を全産業平均との格差是正を目標に毎年設定(例:前年度比5%増)
- データ取得方法: 各センターを対象とした年1回の運営実態調査
- 区独自の処遇改善補助金の導入率 100%
- データ取得方法: 区の補助金交付実績データ
- 職員一人当たりの平均給与月額を全産業平均との格差是正を目標に毎年設定(例:前年度比5%増)
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 職員アンケートにおける「現在の職場で働き続けたい」との回答率 80%以上
- データ取得方法: 年1回の匿名形式による全職員アンケート調査
- 職員の研修参加率(一人当たり年間平均研修時間) 20時間以上
- データ取得方法: 区が実施する研修の参加記録及び各センターからの報告
- 職員アンケートにおける「現在の職場で働き続けたい」との回答率 80%以上
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 区独自の処遇改善補助金の総交付額
- データ取得方法: 区の予算・決算データ
- 区が主催する研修の開催回数及び参加延べ人数
- データ取得方法: 区の事業実績報告
- 経営コンサルティングの派遣件数
- データ取得方法: 区の事業実績報告
- 区独自の処遇改善補助金の総交付額
支援策②:多様なニーズに応えるサービス品質の向上(優先度:中)
目的
- 利用者の高齢化、障害の重度化・多様化、社会参加への意欲の高まりといった変化に対応し、一人ひとりの希望や目標の実現に資する質の高いプログラムを提供できる体制を構築します。
- 単なる「居場所」機能に留まらず、「自己成長の場」や「社会参加へのステップの場」といった付加価値の高い機能を提供することで、センターの存在意義そのものを高めます。
- 客観的根拠:
- 令和7年版障害者白書においても、「利用者本位の生活支援体制の整備」や「サービスの質の向上」が国の障害者施策における重点項目として掲げられており、個別ニーズへのきめ細やかな対応が強く求められています 23。
- (出典)内閣府「令和7年版 障害者白書」令和7年度
- 客観的根拠:
主な取組①:個別支援計画の導入と質の標準化
- 全ての利用者に対して、アセスメントに基づいた個別支援計画の作成と、少なくとも半年に1回の定期的な評価・見直しを義務化します。
- 計画作成にあたっては、本人の意向や希望を最大限尊重する「当事者参画型」のプロセスを徹底します。そのための具体的な手法を示したガイドラインを区が策定し、全センターに周知します。
- 計画作成プロセスやその内容、支援の実施状況について、外部の専門家を含む第三者が評価する仕組みの導入を検討し、支援の質の客観的な担保と継続的な向上を図ります。
- 客観的根拠:
- 障害者総合支援法に基づく他の多くのサービスでは個別支援計画の作成が標準となっていますが、地域活動支援センターでは未整備の場合が多く、これが支援の質のばらつきを生む一因となっています 10。
- (出典)AI-Government Portal「地域活動支援センターの運営」
- 客観的根拠:
主な取組②:プログラム開発支援と多様化の促進
- 各センターが地域の特色や利用者のニーズに応じて特色あるプログラム(例:PC・スマホ講座、アート・音楽活動、ピアサポート活動、就労準備プログラム等)を新たに開発・実施することを支援するため、「特色あるプログラム開発補助金」を創設します。
- 地域の専門家(アーティスト、IT技術者、スポーツ指導者、企業OB等)をプログラムの講師として活用する際の謝礼を補助し、専門性の高い多様な活動の提供を後押しします。
- 複数のセンターが共同でプログラムを開発・実施する場合の経費を重点的に支援することで、資源の効率的な共有と、利用者にとっての選択肢の多様化を促進します。
- 客観的根拠:
- 東京都の調査では、デジタルスキルや就労準備といった新たなプログラムへのニーズが高まっていることが示されています 10。こうした社会の変化に応じたニーズに対応するためには、外部の専門知識や資源の積極的な活用が不可欠です。
- (出典)東京都「障害者の日中活動に関する実態調査」令和4年度
- 客観的根拠:
主な取組③:工賃向上に向けた経営支援
- 生産活動を行うセンターに対し、商品開発、品質管理、デザイン改善、販路開拓等を支援する専門家(マーケティング専門家、デザイナー、中小企業診断士等)を派遣する事業を実施します。
- 区役所本庁舎や出張所、その他公共施設での販売スペースの無償提供、区の広報媒体(広報紙、ウェブサイト、SNS等)での積極的な商品紹介など、行政による具体的な販路開拓支援を強化します。
- より付加価値の高い製品を製造できるよう、工賃向上に直結する設備投資(新たな機材の購入や作業場の改修等)に対する補助制度を創設します。
- 客観的根拠:
- 厚生労働省は「工賃向上計画支援事業」を実施しており、地域活動支援センターもその対象となっています 24。これを特別区レベルで補完・強化することで、より地域の実情に即した実効性の高い支援が可能となります。
- (出典)厚生労働省「工賃向上計画支援事業の実施について」
- 客観的根拠:
主な取組④:専門的支援機能の強化(特にⅠ型)
- 専門的な相談支援や医療連携の中核を担うⅠ型センターが未設置の区において、既存のセンターのⅠ型への移行や、新たなⅠ型センターの設置を、補助金の上乗せ等により重点的に支援します。
- Ⅰ型センターが地域の精神科医療機関と定期的な合同ケース会議を開催したり、職員の相互研修を実施したりするなど、具体的な連携活動を促進するためのコーディネート支援や経費補助を行います。
- 同じ障害や悩みを抱える当事者同士が支え合うピアサポート活動を推進するため、ピアサポーターの養成研修を区が主催し、養成されたピアサポーターを各センターに配置することを支援します。
- 客観的根拠:
- 特別区内のセンターでは精神障害のある利用者が多数を占めており、医療との連携やピアサポートといった専門的支援機能の強化は、利用者の地域生活の安定に直結する喫緊の課題です 10。
- (出典)厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況に関する調査」令和5年度
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 利用者満足度調査における「提供されるプログラムに満足している」との回答率 80%以上
- データ取得方法: 年1回の匿名形式による全利用者アンケート調査
- 生産活動を実施しているセンターにおける平均工賃月額 前年度比20%向上
- データ取得方法: 各センターを対象とした年1回の運営実態調査
- 利用者満足度調査における「提供されるプログラムに満足している」との回答率 80%以上
- KSI(成功要因指標)
- 全ての利用者に対する個別支援計画の作成率 100%
- データ取得方法: 各センターへの年次調査及び区職員による実地指導での確認
- Ⅰ型センターの全特別区への設置
- データ取得方法: 区の事業所指定状況の確認
- 全ての利用者に対する個別支援計画の作成率 100%
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 利用者の社会活動(ボランティア、地域行事、趣味のサークル等)への参加率 20%向上
- データ取得方法: 利用者アンケート調査
- センター利用後に就労移行支援・就労継続支援等の上位サービスへ移行する利用者の割合 10%向上
- データ取得方法: 相談支援事業所等との連携による利用者の動向追跡調査
- 利用者の社会活動(ボランティア、地域行事、趣味のサークル等)への参加率 20%向上
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 特色あるプログラム開発補助金の交付件数及び総交付額
- データ取得方法: 区の補助金交付実績データ
- 区が主催するピアサポーター養成研修の修了者数
- データ取得方法: 区の研修事業実績報告
- 特色あるプログラム開発補助金の交付件数及び総交付額
支援策③:地域共生社会を実現する連携ネットワークの構築(優先度:中)
目的
- センターが地域の中で孤立することなく、多様な主体(医療、福祉、教育、企業、地域住民等)と有機的に連携し、地域全体で障害のある人を支える重層的な支援体制を構築します。
- センターを、障害のある人と地域住民とが自然に出会い、交流する拠点として明確に機能させ、相互理解を促進することで、真の共生社会の実現に貢献します。
- 客観的根拠:
- 厚生労働省は、センターが地域共生社会の構築において、様々な資源をつなぐプラットフォーム的な役割を担う可能性を指摘しており、分野横断的な連携の推進が国レベルの政策課題となっています 7。
- (出典)厚生労働省「地域活動支援センター等を活用した地域共生社会の実現に向けた調査研究」令和5年度
- 客観的根拠:
主な取組①:地域連携コーディネーターの配置支援
- 各センターに、地域連携活動を専門に企画・調整する「地域連携コーディネーター」を配置するための人件費を補助する制度を創設します。
- コーディネーターの役割として、地域の関係機関・団体との日常的な連絡調整、共同プログラムの企画・運営、ボランティアの受入・調整、地域に向けた積極的な情報発信等を明確に位置づけ、その活動を支援します。
- 客観的根拠:
- 多くのセンターでは、職員が日々の利用者支援業務に追われ、地域連携活動にまで手が回らないのが実情です 26。専門の担当者を置くことで、連携活動を場当たり的ではなく、計画的・継続的に進めることが可能になります。
- (出典)note「地域活動支援センターが直面する課題」
- 客観的根拠:
主な取組②:分野横断的な地域自立支援協議会の活用
- 区が設置する地域自立支援協議会に、新たに「地域活動支援センター部会」を設置します。この部会には、センター、行政(障害福祉・保健・教育等)、医療機関、相談支援事業所、当事者団体、家族会等が参加し、定期的に地域の課題を共有し、具体的な連携方策を協議する公式な場とします。
- この協議会を活用し、センターから就労支援事業所やグループホームといった他のサービスへの円滑な移行(トランジション)を支援するための、情報共有やケース会議の仕組みを構築します。
- 客観的根拠:
- 杉並区などの先進事例では、地域自立支援協議会が、地域移行・定着の取り組みを推進する上で中核的な役割を果たしており、その有効性が示されています 27。
- (出典)厚生労働省「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた自治体による地域の協議の場の設置・運営の手引き(事例集)」
- 客観的根拠:
主な取組③:地域住民・ボランティアとの交流促進
- センターが地域住民を対象として開催するオープンイベント(作品展、バザー、音楽会、体験講座等)の企画・運営経費を補助する制度を設けます。
- 地域の自治会・町内会、民生委員・児童委員、近隣の小中学校等とセンターとの連絡会を区が仲介して定期的に開催し、顔の見える関係づくりを積極的に支援します。
- センターにおけるボランティアの受入体制(活動内容の整理、保険への加入、研修の実施等)の整備を支援するとともに、区のボランティアセンター等を通じて、センターでの活動を希望するボランティアとのマッチングを促進します。
- 客観的根拠:
- 地域住民の参加が得られるよう連携に努めることは、国の運営基準でも求められている責務です 4。行政がそのための「つなぎ役」や「触媒」としての役割を担うことが、連携を実質的なものにする上で重要です。
- (出典)厚生労働省令第百七十五号「地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準」
- 客観的根拠:
主な取組④:行政内の縦割り解消と情報共有の徹底
- 障害福祉担当部署が主導し、庁内の関連部署(健康づくり、教育、産業振興、区民活動推進、防災等)と定期的に情報交換を行う「庁内地域活動支援センター連絡会議」を設置し、全庁的な支援体制を構築します。
- 区の障害福祉課や保健センター等の相談窓口で配布するサービス一覧に、各センターの特色やプログラム内容を分かりやすく掲載し、窓口の職員が対象となりうる住民に対して積極的に情報提供を行うよう、研修等を通じて徹底します。
- 客観的根拠:
- 行政内部の縦割り構造が、センターへの適切な情報提供を妨げ、連携を阻害する一因となっているとの指摘があります 7。全庁的な視点での支援体制構築が不可欠です。
- (出典)厚生労働省「地域活動支援センター等を活用した地域共生社会の実現に向けた調査研究」
- 客観的根拠:
KGI・KSI・KPI
- KGI(最終目標指標)
- 区民意識調査における「障害のある人とない人が共に支え合う意識を持っている」との回答率 10ポイント向上
- データ取得方法: 区が実施する区民意識調査(隔年実施)
- センター利用者アンケートにおける「地域社会の中で孤立していると感じない」との回答率 90%以上
- データ取得方法: 年1回の匿名形式による全利用者アンケート調査
- 区民意識調査における「障害のある人とない人が共に支え合う意識を持っている」との回答率 10ポイント向上
- KSI(成功要因指標)
- 地域連携コーディネーターの配置率 80%以上
- データ取得方法: 各センターを対象とした年1回の運営実態調査
- 他機関(医療・福祉・教育・企業等)との連携による共同プログラムの年間実施件数 20件以上(区内合計)
- データ取得方法: 各センターからの事業報告の集計
- 地域連携コーディネーターの配置率 80%以上
- KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標
- 地域住民のセンター主催イベントへの年間参加延べ人数 前年度比30%増
- データ取得方法: 各センターからの事業報告の集計
- センターにおけるボランティアの年間活動延べ時間数 前年度比20%増
- データ取得方法: 各センターからの事業報告の集計
- 地域住民のセンター主催イベントへの年間参加延べ人数 前年度比30%増
- KPI(重要業績評価指標)アウトプット指標
- 地域自立支援協議会「センター部会」の年間開催回数 4回以上
- データ取得方法: 協議会の議事録により確認
- センターと地域の関係団体との連絡会の開催回数
- データ取得方法: 各センターからの事業報告の集計
- 地域自立支援協議会「センター部会」の年間開催回数 4回以上
先進事例
東京都特別区の先進事例
練馬区「区内4か所の支援センターによる地域密着型ネットワーク」
- 練馬区は、「きらら」「すてっぷ」「ういんぐ」「さくら」という名称の4つの障害者地域生活支援センターを区内各所にバランス良く配置しています。それぞれが担当エリアを持つことで、住民が身近な場所で相談できる、きめ細やかな支援ネットワークを構築しています 28。
- 成功要因とその効果:
- 地域分担制によるアクセシビリティ向上: 住民が自宅から近いセンターにアクセスしやすいため、相談への心理的・物理的ハードルが低減されています。
- 柔軟な開所時間と明確なサービス内容: 午後8時までの夜間開所や土日の開所など、利用者の多様な生活スタイルに柔軟に対応しています 32。また、相談事業、各種講座、地域交流事業といったサービス内容をウェブサイト等で明確に提示し、利用者の利便性を高めています。
- 効果的な官民連携(指定管理者制度): 例えば「さくら」は、社会福祉法人育星会が指定管理者として運営しており、民間の柔軟な発想や専門性を活かした質の高いサービス提供が実現しています 30。これにより、行政は全体の監督・評価に、事業者は現場での創造的な事業展開にそれぞれ集中できるという、効果的な官民の役割分担がなされています。
- 客観的根拠:
- (出典)練馬区「障害者地域生活支援センター」ウェブサイト 32
- (出典)練馬区立 大泉障害者地域生活支援センターさくら ウェブサイト 30
世田谷区「多様な事業主体との連携と重層的な支援体制」
- 世田谷区は、社会福祉法人やNPOなど多様な事業主体が運営する地域活動支援センターに対し、安定した運営費補助を行うと同時に、区社会福祉協議会が推進する地域福祉コーディネート機能と有機的に連携させることで、重層的な支援体制を構築しています 33。
- 成功要因とその効果:
- 当事者主体の理念の徹底: 運営法人(例:社会福祉法人めぐはうす)が「当事者が自らの為に活用できるようなネットワークづくり」や「当事者主体の広報活動による社会の偏見是正」といった明確な理念を掲げ、利用者本位の支援を徹底しています 33。
- 分野横断的な多機関連携: 区社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターが、地域活動支援センター、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)、児童館など、異なる分野の機関をつなぐハブとして機能しています 34。これにより、障害分野だけでは解決が難しい複合的な課題を抱えたケースにも、地域全体で対応できる体制が整っています。
- 安定した財政基盤の提供: 区は「地域活動支援センター運営費補助」として年間5,000万円を超える予算を継続的に計上しており、事業者が安心して運営に専念できる環境を財政面から力強く支えています 35。
- 客観的根拠:
- (出典)社会福祉法人めぐはうす「法人理念・運営方針」 33
- (出典)世田谷区社会福祉協議会「地域福祉コーディネーター」ウェブサイト 34
- (出典)世田谷区「令和5年度 世田谷区の予算(案)の概要」 35
大田区「機能強化と役割分担による専門性の確保」
- 大田区は、地域活動支援センター機能強化事業として区内に複数のセンターを確保しつつ、それぞれが特色ある役割を担うことで、支援の専門性を高めています。特に、相談支援機能を中核に据えた運営が特徴的です 13。
- 成功要因とその効果:
- 専門相談機能への集約と特化: 例えば「かまた生活支援センター」は、Ⅰ型事業として精神障害のある方への相談支援を中核機能と位置づけ、必要に応じてサービス等利用計画の作成や、弁護士による専門的な法律相談に繋げるなど、質の高い相談支援を提供しています 36。
- 多様な事業の併設によるワンストップ化: 相談支援事業に加え、地域生活安定化支援事業や高次脳機能障害者支援事業などを区から受託し併設することで、多様なニーズを持つ利用者が一つの窓口で必要な支援を受けられる体制を整えています 36。
- 計画的なサービス基盤整備: 区の障害福祉計画において、センターの箇所数や利用者数の将来にわたる見込みを明確に設定し、計画的なサービス基盤整備を進めています。平成26年度から29年度にかけて、箇所数を13から11へと集約する一方、1箇所あたりの機能を強化するという戦略的な方針が見て取れます 13。
- 客観的根拠:
- (出典)かまた生活支援センター ウェブサイト 36
- (出典)大田区「地域生活支援事業の推進について」 13
全国自治体の先進事例
新潟県新潟市「民間主体によるエリア再生と連携した拠点づくり」
- 新潟市では、行政が直接施設を整備するのではなく、中心市街地のシャッター通りにあった長屋を民間のまちづくり会社や地域金融機関が主体となって改修・再生するプロジェクトと連携し、その一角に地域活動の拠点を創出しました。
- 成功要因とその効果:
- 官民連携と民間活力の最大活用: 行政が財政負担を抑えつつ、民間の資金やノウハウ、スピード感を活かすことで、持続可能な賑わい創出と福祉拠点の整備を同時に実現しています。
- 「福祉」と「まちづくり」の融合: 障害のある人の活動拠点を、閉鎖的な福祉施設としてではなく、まちづくりの文脈の中に「地域の魅力的なスポット」として位置づけています。これにより、センターが地域から孤立することを防ぎ、障害のある人とない人がごく自然な形で出会い、交流する機会を生み出しています。
- 客観的根拠:
宜野座村(沖縄県)「明確な理念に基づく計画的な多機関連携」
- 沖縄県宜野座村の地域活動支援センター「アイリス」は、小規模な自治体ながら、「行政・医療・福祉・地域住民と連携し、当事者の意思を尊重する」という明確な目的を事業報告書に掲げ、計画的かつ具体的な連携活動を実践しています。
- 成功要因とその効果:
- 連携活動の計画化と可視化: 事業報告書において、年度の重点目標として「専門職員による医療・福祉及び地域の社会基盤と連携強化のための調整」や「相談支援事業所と連携したアウトリーチ活動」を掲げています 38。これにより、連携活動が場当たり的にならず、計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Action)のサイクルを回すことが可能になっています。
- アウトリーチ(訪問支援)の重視: センター内で利用者を待つだけでなく、支援員が積極的に地域に出て訪問(アウトリーチ)を行うことで、自宅にひきこもりがちな当事者やその家族など、支援が届きにくい層へも確実にアプローチしています 38。これにより、問題が深刻化する前の早期発見・早期支援に繋がり、地域のセーフティネットとしての役割を強化しています。
- 客観的根拠:
参考資料[エビデンス検索用]
政府(省庁)関連資料
- 内閣府「令和7年版 障害者白書」令和7年度 23
- 内閣府「障害者に関する世論調査」令和5年度 10
- 厚生労働省「令和4年社会福祉施設等調査」令和5年公表 3
- 厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況に関する調査」令和5年度 10
- 厚生労働省「障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」令和4年度 10
- 厚生労働省「障害福祉サービス等経営実態調査」令和5年公表 43
- 厚生労働省「地域活動支援センター等を活用した地域共生社会の実現に向けた調査研究」令和5年度 7
- 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」 1
- 厚生労働省「地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十五号)」 2
- 厚生労働省「工賃向上計画支援事業の実施について」 24
- 厚生労働省「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A」 47
東京都・特別区関連資料
- 東京都「東京都障害者・障害児施策推進計画(令和6年度~令和8年度)」令和6年度 51
- 東京都「障害者の日中活動に関する実態調査」令和4年度 10
- 練馬区「練馬区障害者計画・第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画」 52
- 世田谷区「せたがやノーマライゼーションプラン・第5期世田谷区障害福祉計画」 53
- 大田区「おおた障がい施策推進プラン(大田区障害者計画・第7期大田区障害福祉計画・第3期大田区障害児福祉計画)」 54
- 新宿区「新宿区障害者計画、第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画」 55
- 足立区「足立区障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画」 57
- 葛飾区「葛飾区障害者施策推進計画・第7期葛飾区障害福祉計画・第3期葛飾区障害児福祉計画」 58
その他調査研究機関資料
まとめ
地域活動支援センターは、障害のある方が地域で尊厳をもって生活するための最後の砦であり、共生社会を実現する上で不可欠な社会基盤です。しかしながら、その運営は不安定な財政基盤と、それに起因する深刻な人材不足によって、極めて脆弱な状況に置かれています。この構造的な課題が、サービスの質の低下や地域からの孤立といった悪循環を生み出しています。この危機的状況を打開するためには、行政がその重要性を再認識し、運営基盤の安定化という根幹に踏み込むことが急務です。具体的には、事業所の努力や成果が報われる補助金制度への転換、そして職員が専門職として誇りを持って働き続けられるための処遇改善への直接支援が、最優先で取り組むべき課題です。これらの基盤強化を土台として、多様なニーズに応える質の高いプログラム提供や、多機関連携を促進することで、センターは真に地域に開かれた共生の拠点へと進化できるはずです。
本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。
引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。




-320x180.jpg)

-320x180.jpg)