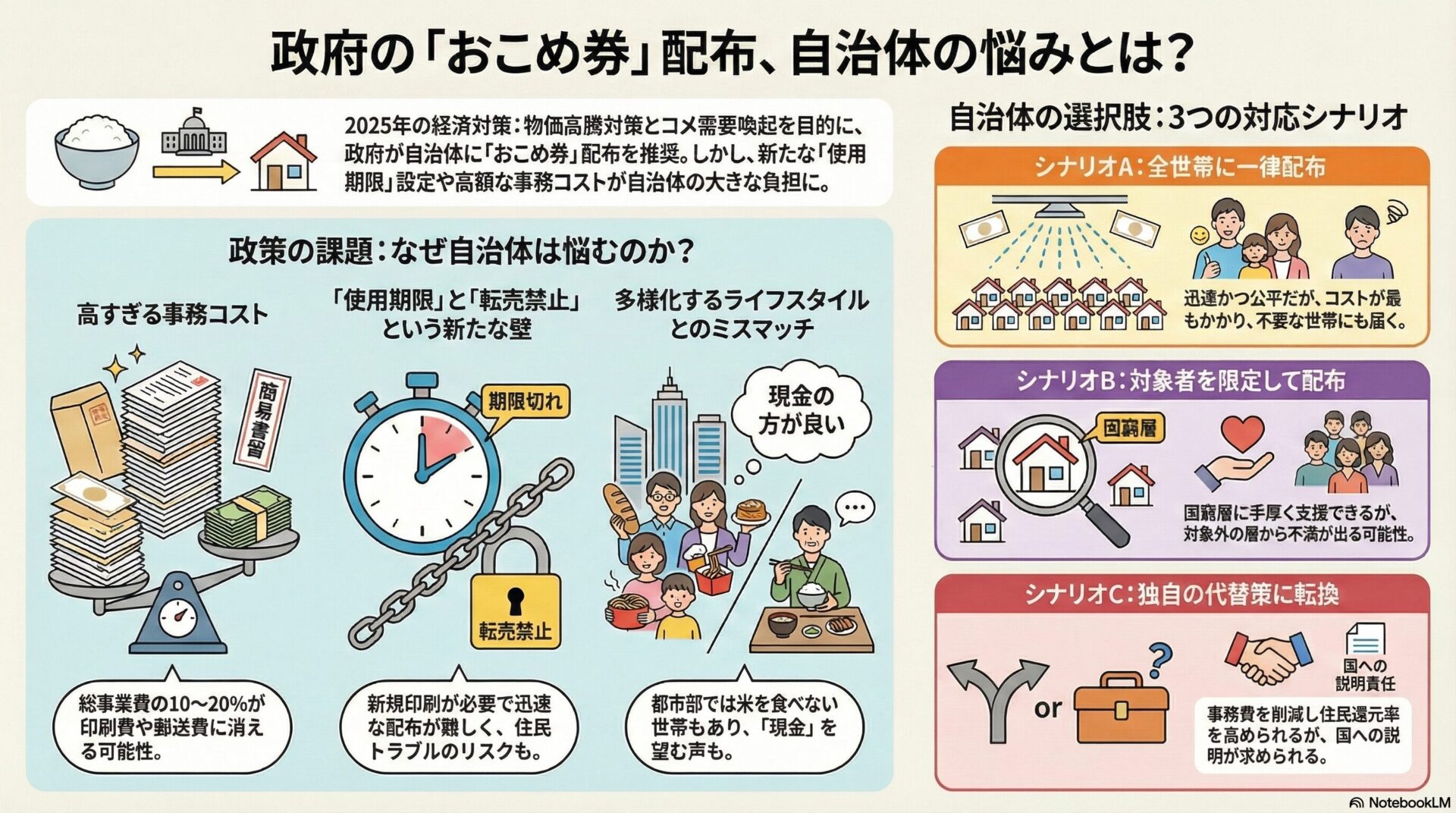【骨太の方針2025】行政分野別 分析レポート(防災政策)

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※2024年方針からの変更点には【新規】または【拡充】と付記しています。
(出典)内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2025」令和7年度
防災政策
概要
「骨太の方針2025」における防災政策は、令和6年能登半島地震という最新の教訓と、首都直下地震や南海トラフ巨大地震といった国難級災害の切迫性を真正面から受け止め、これまでの防災体制を根本から覆す歴史的な大転換を示すものです。その核心は、従来の各省庁縦割りの対応の限界を認め、【新規】内閣総理大臣直属の強力な司令塔として「防災庁」を創設し、「人命・人権最優先の防災立国」を実現するという国家の断固たる決意にあります。
本方針が示す防災政策は、大きく分けて4つの柱で構成されています。
第一に、前述の「防災庁」創設による防災体制の抜本的強化です。これにより、平時から発災時、復旧・復興に至るまで、切れ目なく、かつ強力に国の防災施策を主導する体制が構築されます。
第二に、能登半島地震の教訓を徹底的に反映した「災害対応能力のアップデート」です。特に、半島地域の地理的制約、インフラの脆弱性、そして復興途上の二重被災といった過酷な現実を踏まえ、初動対応の迅速化と被災者支援の質の向上に主眼が置かれています。
第三に、気候変動による災害の激甚化・頻発化を前提とした「国土強靭化の加速」です。「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」を継続・強化し、ハード・ソフト一体となった事前防災を強力に推進します。
第四に、先進技術を最大限に活用する「防災DXと防災技術の革新」です。AI、ドローン、衛星通信などを駆使し、情報収集・伝達の高度化、避難行動の最適化、そして災害対応の効率化を目指します。
これらの国家戦略の最前線で、住民の命と暮らしを守る最後の砦となるのが基礎自治体です。国の防災体制が大きく変わる中、自治体は受け身の対応から脱却し、より主体的かつ戦略的に地域防災力を向上させていくことが求められます。本レポートは、国の新たな方針を深く理解し、それを地域の実情に即した実効性のある計画やアクションへと落とし込むための羅針盤となるものです。
国の動向(2024年→2025年の変化)
2025年方針は、令和6年能登半島地震という極めて大きな災害の発生を受け、2024年方針から劇的とも言えるほど踏み込んだ内容へと進化しています。
- 「防災庁」創設の明確化と権限の具体化
2024年方針では「防災・危機管理の司令塔機能の強化を検討」という表現に留まっていましたが、2025年方針では【新規】「2026年度中に防災庁を設置する」と明確に時期を定めました。さらに、その位置づけを単なる調整機関ではなく、【新規】「内閣総理大臣を助ける専任の大臣を置き」「勧告権等の権限を有する」強力な司令塔と具体的に規定しました。これは、国の防災行政における歴史的な組織改革です。 - 能登半島地震の教訓の徹底的な反映
2025年方針には、能登半島地震で露呈した課題への対応策が随所に盛り込まれています。【新規】「復興の最中に奥能登豪雨によって二重の被災となった」という現実に言及し、複合災害への備えの重要性を強調。また、【新規】「半島」という地理的条件を明記し、道路寸断や孤立集落への対策、代替交通・輸送手段の確保の必要性を強く打ち出しています。 - 被災者支援における「質」の重視
避難所運営に関し、これまでの量的な確保から、【新規】「避難所環境の抜本的改善」「衛生の確保」「温かい食事、入浴設備」といった「質」の向上を強く求める記述に変化しています。特に、【新規】「洋式の快適トイレの推進」「トレーラーハウス等の活用」など、具体的な改善策が明記されたことは大きな進展です。 - 事前防災から「事前復興」へ
災害が起こる前から、復興まちづくりのプロセスや方針をあらかじめ準備しておく【新規】「事前防災・事前復興まちづくり」の推進が明記されました。これは、災害対応のフェーズをさらに前に進め、より迅速で質の高い復興を目指すという、新たな防災思想の導入を意味します。
【新規】防災体制の抜本的強化
自治体が取り組むべきアクション
- 「防災庁」との連携体制の構築
- 国の防災庁創設の動きと連動し、区の地域防災計画における国の役割と責任分担を再整理します。特に、防災庁が持つ勧告権がどのような場面で行使され、区としてどう対応すべきか、具体的なケースを想定したシミュレーションや図上訓練を実施します。
- 防災庁や都との連絡調整を担う専門職員(リエゾン)を明確に定め、平時から緊密な情報連携・関係構築を図ります。
- 地域防災計画の全面的な見直し
- 国の国土強靱化基本計画や新たな災害対策基本法等の改正に迅速に対応し、地域防災計画を毎年見直すことを常態化します。その際、能登半島地震の教訓、特に①インフラ寸断による孤立リスク、②高齢化率の高い地域での避難行動、③複合災害(地震+豪雨、地震+火災)のリスクなどを、区の地域特性に合わせて徹底的に反映させます。
- 防災専門人材の育成と確保
- 国の「気象防災アドバイザー」や「地域防災マネージャー」といった専門資格の取得を、防災担当職員だけでなく、一般職員や地域住民(自主防災組織リーダー等)に対しても奨励・支援します。
- 防災・危機管理分野における実務経験を持つ退職自衛官や警察官、消防官などを、専門監やアドバイザーとして積極的に任用する制度を検討・導入します。
災害対応能力のアップデート
自治体が取り組むべきアクション
- 避難所の「質」の抜本的向上
- 全ての指定避難所について、TKB(トイレ、キッチン、ベッド)の観点から総点検を実施します。特に、仮設トイレの洋式化率の目標設定、温かい食事を提供できる厨房設備の整備、段ボールベッド・パーティションの備蓄を計画的に進めます。
- 福祉避難所の指定を拡充するとともに、一般の避難所においても、要配慮者(高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人等)のための専用スペースや相談窓口を確保する運営マニュアルを策定・徹底します。
- 【新規】トレーラーハウスやコンテナハウスを、災害時の応急仮設住宅や避難所の補完施設として活用するための協定を、平時から民間事業者と締結します。
- 帰宅困難者・孤立地域対策の強化
- 首都直下地震に備え、一時滞在施設の確保目標を再検証するとともに、事業者に対する従業員の一斉帰宅抑制と施設内待機の徹底を、条例なども視野に、より実効性のある形で要請します。
- 木造住宅密集地域や、大規模な盛土造成地など、インフラ寸断により孤立する可能性のある地域を具体的に抽出し、地域内の備蓄(水、食料、医薬品)の強化や、アマチュア無線、衛星携帯電話といった多様な通信手段の確保を図ります。
- 多様な主体との連携による被災者支援
- 災害ケースマネジメント(被災者一人ひとりの状況に応じて、必要な支援を届ける仕組み)を円滑に実施するため、社会福祉協議会、NPO、ボランティア団体、専門家(弁護士、臨床心理士等)との連携による「被災者支援プラットフォーム」を平時から構築・運営します。
- 【新規】改正災害対策基本法も踏まえ、災害ボランティアの円滑な受け入れと活動支援、そして被災地での活動を専門的にコーディネートする「災害中間支援組織」の育成・連携を強化します。
国土強靭化の加速
自治体が取り組むべきアクション
- ハード・ソフト一体となった事前防災の推進
- インフラの耐震化(橋梁、上下水道管路等)、無電柱化、木造住宅密集地域の不燃化といったハード対策を着実に推進します。
- ハザードマップの全戸配布と、それを用いた地域ごとの防災ワークショップを徹底し、住民一人ひとりの「マイ・タイムライン」(個別避難計画)の作成を支援するなど、ソフト対策との一体的な推進を図ります。
- 【新規】「事前防災・事前復興まちづくり」の導入
- 災害リスクの高い地域について、被災後の復興まちづくり(例:高台移転、土地利用規制の導入、より安全な道路網の再編)のビジョンや手順を、平時から地域住民と議論し、あらかじめ合意形成しておく「事前復興計画」の策定に着手します。
- 重要インフラ・ライフラインの維持
- 電力・ガス・通信・上下水道といったライフライン事業者と連携し、重要インフラの強靭化計画を共有し、災害時の迅速な復旧に向けた連携訓練を定期的に実施します。
- 【新規】災害用井戸の活用や上下水道の分散型システムの導入など、大規模システムがダウンした場合の代替手段の確保を検討します。
防災DXと防災技術の革新
自治体が取り組むべきアクション
- 情報収集・伝達・共有の高度化
- ドローンやAIを活用した被害状況の迅速な把握、SNS等からの被災情報のリアルタイム収集・分析(デマ情報のフィルタリング含む)、Lアラート(災害情報共有システム)の活用による住民へのプッシュ型情報発信など、防災情報システムを高度化します。
- 避難行動支援の最適化
- AIを活用して、リアルタイムの災害状況と個人の状況(現在地、家族構成、避難に必要な時間など)に応じて、最適な避難経路やタイミングを提示するシステムの研究・導入を検討します。
- 避難行動要支援者の情報をデジタル化し、関係機関(消防、警察、民生委員等)が円滑に共有できる仕組みを構築します。
- 【新規】先端防災技術の積極的な導入
- 国の研究開発動向を注視し、災害救助ロボットや瓦礫の中を探査できるドローン、自動運転による物資輸送といった先端技術について、平時から民間企業や大学と連携し、地域での実証実験や導入可能性の検討を進めます。
まとめ
~行政職員に求められる「最悪を想定する想像力」と「主体的な行動力」~
「骨太の方針2025」が示す防災政策は、もはや「想定外」という言葉を許さない、極めて厳しい現実認識に基づいています。私たち行政職員に求められるのは、常に最悪の事態を想定する「危機管理の想像力」と、前例や所管の壁を越えて住民の命を守るために行動する「主体性」です。
防災は、防災担当部署だけの仕事ではありません。福祉、教育、都市計画、財政、広報など、全ての部局が自らの業務と防災を結びつけ、組織横断的に取り組む「総合防災行政」への転換が不可欠です。このレポートを基に、自部署の役割を再確認し、より実効性のある防災対策へと繋げていただくことを期待します。