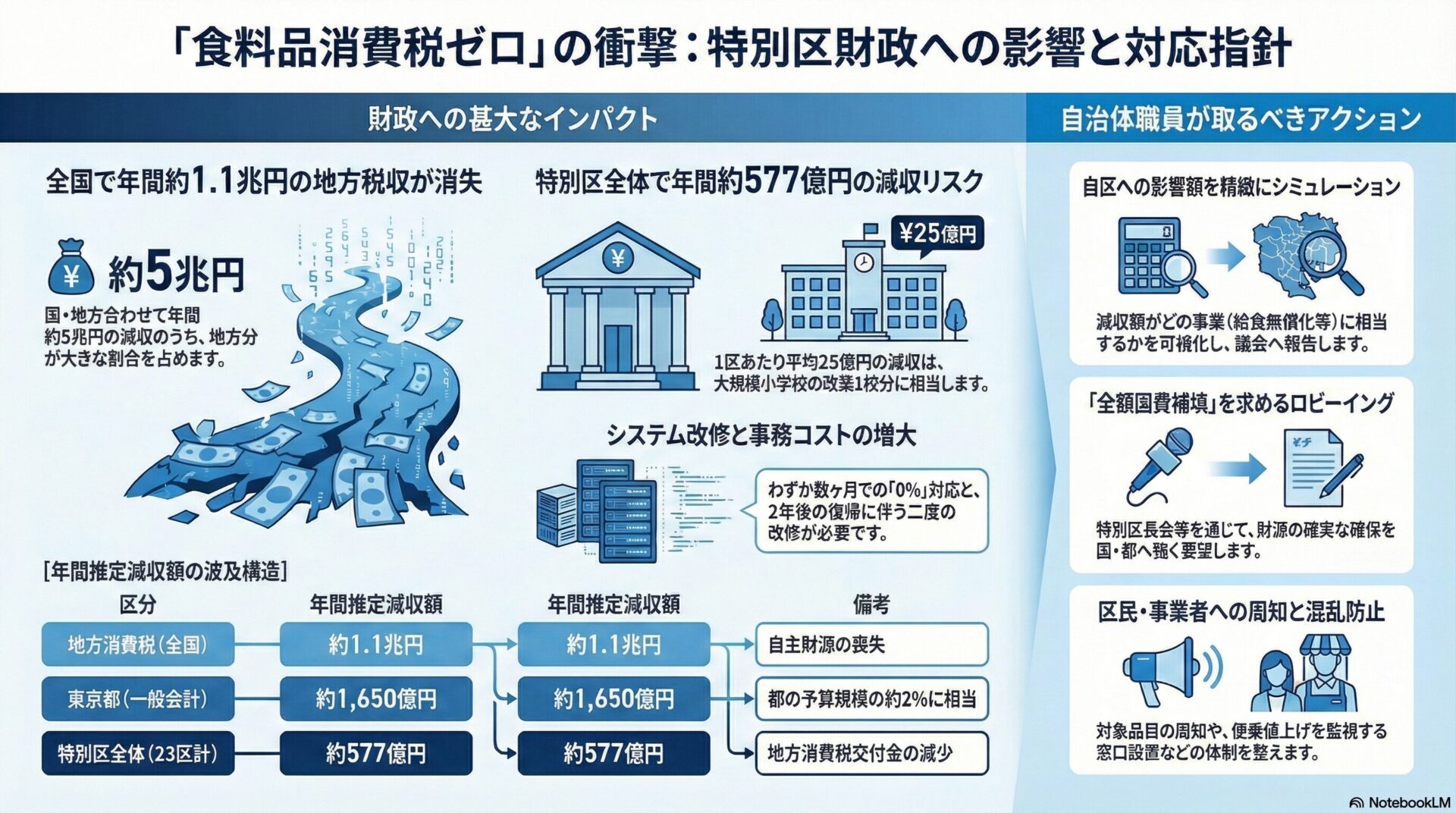【骨太の方針2025】行政分野別 分析レポート(子育て、子ども政策)

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※2024年方針からの変更点には【新規】または【拡充】と付記しています。
(出典)内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2025」令和7年度
子育て、子ども政策
概要
第一に、2025年方針における子育て・子ども政策は、「こども未来戦略」に基づき昨年策定された「加速化プラン」の着実な実行を最優先課題としています。2024年10月から始まる児童手当の抜本的拡充や、2026年度から本格実施される「こども誰でも通園制度」など、具体的な施策が目白押しであり、自治体にはこれらを遅滞なく、かつ円滑に実施するための極めて高度な実行能力と準備が求められます。これは、単なる事務作業ではなく、制度の趣旨を住民に丁寧に説明し、現場の混乱を最小限に抑え、誰もが必要な支援を受けられるよう配慮する、行政の総合力が問われる局面です。
第二に、経済的支援の強化と並行して、すべての子どもと家庭を孤立させないための「伴走型支援」と「質の高い保育・教育」が一層重視されています。特に、子育て世帯が直面する多様な課題に対応するため、【新規】「こども家庭センター」の機能強化が明記され、妊娠期から切れ目なく支援を提供する体制の構築が急がれます。また、保育の「量」の確保から「質」の向上へと政策の重心が移っており、保育士の配置基準改善や処遇改善を着実に進めることが、子どもの健やかな育ちを保障する上で不可欠とされています。
第三に、【新規】子どものウェルビーイング(Well-being)向上という視点が、政策の中心に明確に据えられました。いじめ、不登校、児童虐待、子どもの自殺といった深刻な問題に対し、これまで以上に踏み込んだ対策が求められています。特に、子どもの死因究明(CDR:Child Death Review)の推進や、若年妊婦や社会的養護経験者といった特に困難を抱える子ども・若者への支援強化が明記されたことは、すべての子どもの「命」と「権利」を守り抜くという国の強い決意の表れです。
第四に、これらの施策を安定的に支える財源として、2026年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されます。医療保険料に上乗せして徴収されるこの新たな負担について、国民の理解を得ることが極めて重要となります。自治体には、この支援金がどのように地域の子育て支援の充実に繋がるのかを、具体的かつ分かりやすく住民に「見える化」するという、重要な役割が課せられています。
国の動向(2024年→2025年の変化)
- 「加速化プラン」の実行フェーズへの完全移行
2024年方針が「加速化プラン」の策定段階であったのに対し、2025年方針は、その完全な実行フェーズに入ったことを明確に示しています。児童手当の拡充(所得制限撤廃、高校生まで延長、第3子以降3万円)や「こども誰でも通園制度」について、実施時期を明記の上で着実な施行を求めており、自治体にとっては待ったなしの状況です。 - 伴走型支援の拠点「こども家庭センター」への機能集約
2024年方針では個別の支援策が並列的に記述されていましたが、2025年方針では【新規】「こども家庭センター」が、妊娠期からの相談、母子保健、児童福祉を一体的に担う中核拠点として明確に位置づけられました。これは、縦割りになりがちだった支援体制を再編・統合し、利用者本位のワンストップサービスを実現しようとするものです。 - 子どもの権利擁護とウェルビーイングへの踏み込み
2025年方針では、【新規】こどもの死亡事例を多機関で検証し再発防止につなげるCDR(Child Death Review)の推進や、【新規】若年妊婦や社会的養護経験者への支援、【新規】こども性暴力防止法の施行準備など、特に脆弱な立場に置かれた子どもの権利を守るための具体的な記述が大幅に拡充されました。これは、単なる子育て支援から、「こどもまんなか社会」の理念を具現化する、より本質的な子ども政策へと深化していることを示しています。 - 財源論の具体化と「見える化」の要請
最大の懸案であった財源について、【新規】2026年度からの「子ども・子育て支援金制度」の創設が正式に明記されました。これに伴い、「制度の意義やその使途などの周知の準備を進める」とされ、自治体に対しても、支援金によるサービス拡充を住民に具体的に説明する「見える化」の努力が強く求められることになります。
加速化プランの着実な実行と制度の円滑な導入
自治体が取り組むべきアクション
- 【最重要】児童手当の抜本的拡充への万全な準備
- システム改修と周知徹底
2024年10月支給分(12月支払)からの制度変更に対応するため、情報システムの改修を確実に完了させることが絶対条件です。同時に、所得制限の撤廃により新たに対象となる世帯や、支給額が変更となる多子世帯に対し、申請手続きの要否や変更内容について、混乱が生じないよう多角的な周知(広報紙、ウェブサイト、SNS、学校を通じた通知等)を徹底します。 - 問い合わせ体制の構築
制度変更直後には、区役所の窓口や電話がパンク状態になることが予想されます。専門のコールセンターの設置や、ウェブサイトでのFAQ(よくある質問)の充実、チャットボットの導入など、問い合わせに迅速かつ正確に対応できる体制を構築します。
- システム改修と周知徹底
- 【最重要】「こども誰でも通園制度」の制度設計と実施体制の構築
- 地域の保育資源の総点検
制度の本格実施(2026年度)を見据え、区内の保育所等の空き定員の状況や、一時預かり事業の実施状況を正確に把握します。保育士の確保・育成計画とも連動させ、受け入れ可能なキャパシティを算出します。 - 利用しやすい制度設計
国のモデル事業の結果も参考に、利用時間の上限、利用料、予約方法、対象年齢など、地域のニーズに応じた、保護者が利用しやすく、かつ保育現場に過度な負担がかからない制度を設計します。 - 安全確保と質の担保
新たな子どもを受け入れるにあたり、事故防止や感染症対策のマニュアルを整備するとともに、保育の質が低下しないよう、保育士への研修や巡回指導の体制を整えます。
- 地域の保育資源の総点検
- 高等教育費の負担軽減策の周知
- 多子世帯や理工農系の学生を対象に拡充される授業料等減免と給付型奨学金について、対象となる可能性のある高校生やその保護者に対し、中学校・高校と連携して、制度内容や申請時期を早期から丁寧に周知します。経済的な理由で進学を諦めることがないよう、きめ細かな情報提供が重要です。
- 子育て世帯への住宅支援の強化
- 国の支援策と連携し、公営住宅への子育て世帯の優先入居枠を拡大するとともに、民間賃貸住宅に入居する子育て世帯への家賃補助制度の拡充や、多子世帯向けのより広い住宅への住み替え支援などを検討します。
すべての子どもと家庭を包摂する支援体制
自治体が取り組むべきアクション
- 【拡充】こども家庭センターの機能強化
- ワンストップ相談体制の確立
母子保健(保健師)と児童福祉(子ども家庭支援員、児童福祉司)の専門職が物理的に同じフロアで執務し、常に情報共有・連携できる体制を構築します。住民にとっては、「どこに相談すればよいか分からない」という不安を解消し、一つの窓口で必要な支援につながることができるメリットがあります。 - アウトリーチ(訪問型)支援の強化
支援が必要であるにもかかわらず、自ら相談に来られない家庭に対し、積極的に訪問して関わりを持つアウトリーチ支援チームを強化します。虐待のリスクを早期に発見し、深刻化する前に介入することが目的です。
- ワンストップ相談体制の確立
- 保育の「質」の向上
- 保育士の専門性向上と負担軽減
国の配置基準改善(4・5歳児:25対1)を着実に実施するとともに、ICTの導入(登降園管理、保護者連絡の電子化等)による保育士の事務負担の軽減を支援します。また、障害児保育や医療的ケア児に関する専門研修の機会を増やし、保育士の専門性向上を後押しします。 - 多様な保育サービスの提供
夜間保育、休日保育、病児・病後児保育、きょうだい児の一時預かりなど、保護者の就労形態や家庭状況の多様化に対応した柔軟な保育サービスの提供体制を拡充します。
- 保育士の専門性向上と負担軽減
- 【新規】特に困難を抱える子ども・若者への支援
- 若年妊婦・特定妊婦への包括的支援
予期せぬ妊娠などにより困難を抱える若年妊婦等に対し、居場所の提供、産前・産後ケア、住まいの確保、経済的支援、就労支援などを一人ひとりの状況に合わせて包括的に提供する支援拠点を整備します。 - 社会的養護経験者の自立支援
児童養護施設等を退所した若者が、地域で孤立することなく安定した生活を送れるよう、相談支援、住居確保支援、就労・就学支援を継続的に行う伴走型支援を強化します。
- 若年妊婦・特定妊婦への包括的支援
子どものウェルビーイング向上と権利擁護
自治体が取り組むべきアクション
- いじめ・不登校・自殺対策の強化
- 教育と福祉の連携強化
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー(SSW)の配置を拡充するとともに、こども家庭センターと教育委員会、学校が緊密に連携し、困難を抱える児童・生徒の情報を早期に共有し、一体的に支援する体制を構築します。 - 多様な学びの場の確保
学校に行きづらさを感じる子どもたちのために、教育支援センター(適応指導教室)の機能強化や、フリースクール、メタバース(仮想空間)を活用したオンライン上の居場所など、多様な学びの場と居場所を確保・支援します。
- 教育と福祉の連携強化
- 【新規】こどもの死因究明(CDR)の推進
- 多機関連携による検証体制の構築
国の動きと連動し、予防可能であった子どもの死亡(虐待、いじめ、事故等)をなくすため、医師、警察、行政(福祉、教育、保健)、消防等が連携して死亡事例を検証し、再発防止策を提言する地域CDRの体制を構築します。
- 多機関連携による検証体制の構築
- 【新規】こども性暴力防止法の施行準備
- 学校や保育所、学習塾、スポーツクラブなど、子どもと接する全ての事業者に対し、日本版DBS(性犯罪歴を有する者が特定の職業に就くことを制限する仕組み)の導入を見据え、従業員の性犯罪歴の確認の重要性について周知・啓発します。
まとめ
~行政職員に求められる「寄り添う視点」と「繋ぐ力」~
子育て・子ども政策の推進において、私たち行政職員に最も求められるのは、制度や法律の知識以上に、困難を抱える子どもや保護者の立場に立って物事を考える「寄り-添う視点」です。一人ひとりの家庭が抱える事情は千差万別であり、画一的な制度適用だけでは解決できない課題が山積しています。
そして、その課題を解決するために不可欠なのが、庁内の関係部署はもちろん、学校、保育園、医療機関、NPO、地域住民といった多様な主体をコーディネートし、支援の輪を築き上げる「繋ぐ力」です。一人の職員、一つの部署でできることには限界があります。地域社会全体で子どもたちの育ちを支えるという大きな目標に向かって、粘り強く連携のネットワークを構築していくこと。それこそが、「こどもまんなか社会」を実現するための、私たち行政職員が果たすべき最も重要な役割なのです。