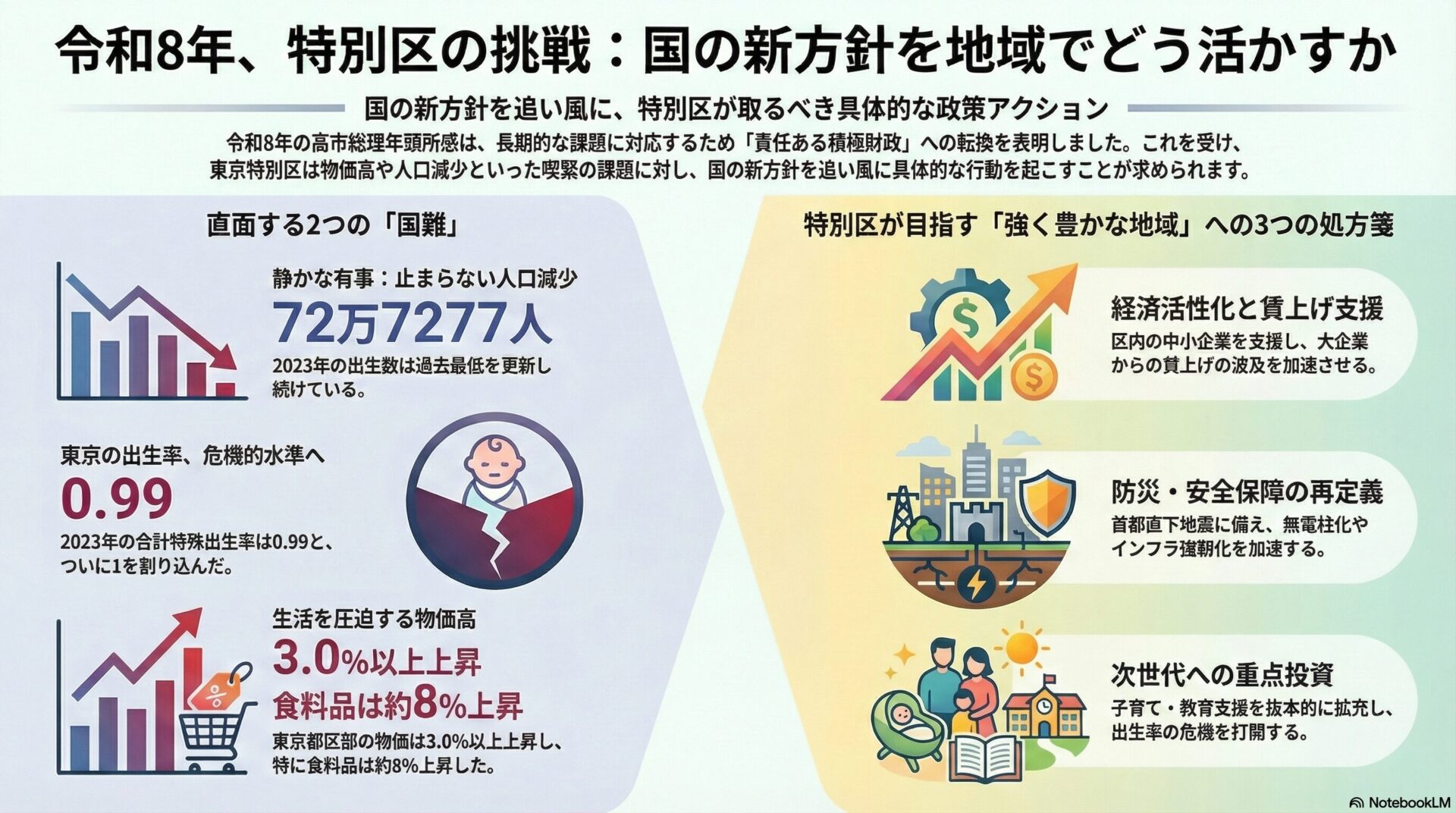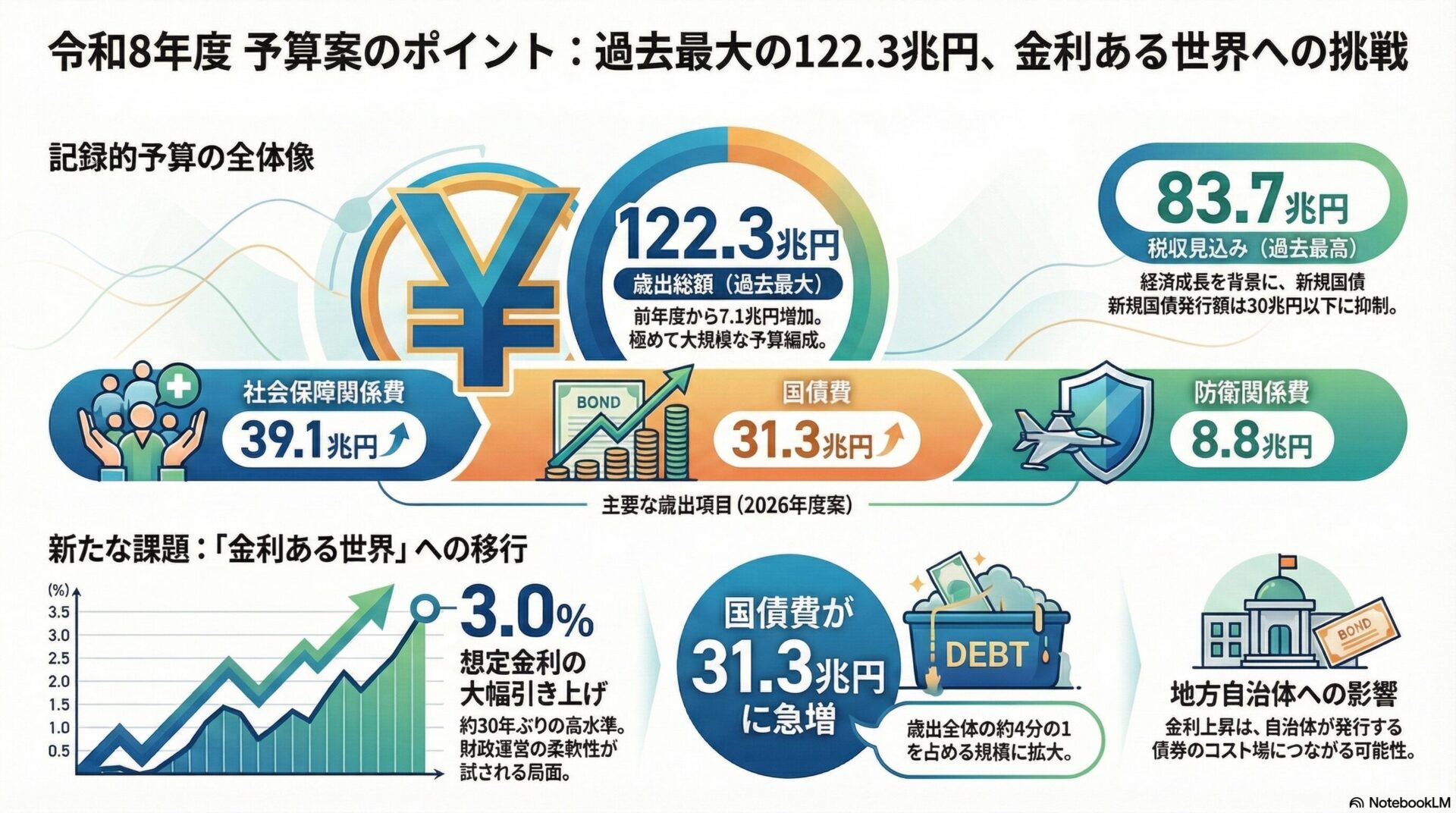【骨太の方針2025】行政分野別 分析レポート(スポーツ政策)

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
※2024年方針からの変更点には【新規】または【拡充】と付記しています。
(出典)内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2025」令和7年度
スポーツ政策
概要
第一に、2025年方針におけるスポーツ政策は、スポーツを単なる健康増進や競技力向上のための活動としてだけでなく、地域振興、経済成長、そしてウェルビーイング(Well-being)向上に貢献する極めて有効な「ソリューション(解決策)」として明確に位置づけています。【新規】武道・スポーツツーリズムや、スポーツコンプレックス(複合施設)を核としたまちづくりは、交流人口を拡大し、地域に新たな賑わいと経済効果をもたらす「稼ぐ力」としてのスポーツの可能性を示しています。自治体には、スポーツを文化振興や産業振興、都市計画といった他分野の政策と戦略的に連携させ、地域全体の価値を高める「総合プロデューサー」としての役割が求められます。
第二に、「する」スポーツの領域において、ライフステージを通じた多様なニーズへの対応が一層重視されています。大規模国際大会のレガシーを継承しつつも、より住民の日常生活に焦点を当て、子どもたちの運動機会の確保から、働き世代の健康増進、そして高齢者の介護予防まで、誰もが、いつでも、どこでも、気軽にスポーツに親しめる環境整備が急務とされています。特に、障害者スポーツ(パラスポーツ)の振興や、性別や年齢にかかわらず楽しめるスポーツプログラムの提供は、インクルーGシブな共生社会を実現するための重要な柱です。
第三に、スポーツ界が抱える構造的課題への改革が、政策の重要なテーマとなっています。【新規】大規模国際大会の開催支援と並行して、アスリートのインテグリティ確保(誠実性・健全性)や、スポーツ団体のガバナンス強化が明記されたことは、スポーツ界の透明性と公正性を高めようとする国の強い意志の表れです。自治体においても、地域のスポーツ団体への支援にあたり、適切な組織運営やコンプライアンス遵守を求めていく必要があります。
第四に、【新規】「eスポーツ」が、成長産業及び若者との新たな接点として初めて本格的に位置づけられました。eスポーツの活用は、若者の交流促進やデジタル人材の育成、さらには新たな産業創出に繋がる可能性を秘めています。これは、スポーツ政策が、従来のフィジカルな活動だけでなく、デジタル空間における新たな文化やコミュニティをもその対象として捉え始めたことを示しており、自治体にとっても新たな地域活性化の切り口となり得ます。
国の動向(2024年→2025年の変化)
- 「稼ぐ力」としてのスポーツ政策の強化
2024年方針では健康増進や地域コミュニティ活性化の文脈が強かったのに対し、2025年方針では【新規】武道・スポーツツーリズム、スポーツコンプレックス・ホスピタリティ、他産業との連携による事業創出といった、スポーツの産業化・経済効果を重視する記述が大幅に拡充されました。これは、スポーツをコストセンターからプロフィットセンターへと転換させようとする国の明確な戦略です。 - 【新規】eスポーツの政策への本格的な位置づけ
2024年方針にはなかった「eスポーツ」の活用が、2025年方針で初めて明記されました。DXの推進、海外展開、他産業との連携といった文脈で語られており、単なるゲームとしてではなく、地域振興や産業創出に資する新たな政策ツールとして国が認知したことを意味します。 - 大規模国際大会のレガシーとガバナンス強化
2025年世界陸上(東京)、デフリンピック(東京)、2026年アジア・アジアパラ競技大会(愛知・名古屋)、ワールドマスターズゲームズ2027関西といった具体的な大会名を挙げ、開催支援を明記するとともに、【新規】インテグリティ確保等の競技者の環境整備という文言が加わり、スポーツ界のガバナンス強化への要請が強まっています。 - 障害者スポーツ(パラスポーツ)との連携強化
2025年方針では、パラスポーツの振興について【新規】日本パラスポーツ協会や全日本ろうあ連盟、スペシャルオリンピックス日本等との連携を具体的に記述し、より多様な障害のある人々がスポーツに参加できる環境整備を目指す姿勢を鮮明にしました。
スポーツによる地域振興と経済活性化
自治体が取り組むべきアクション
- 【拡充】スポーツツーリズムの戦略的推進
- 「みる」ツーリズム
地域のプロスポーツチームと連携し、試合観戦と地域の観光(食事、宿泊、文化体験)を組み合わせた観戦ツアーを企画・PRします。また、大規模なスポーツ大会を誘致し、国内外からの観戦客を受け入れるための環境整備(多言語対応、交通アクセス改善)を進めます。 - 「する」ツーリズム
地域の豊かな自然環境(河川、公園、臨海部など)を活用し、マラソン、サイクリング、トライアスロンといった参加型のスポーツイベントを育成・誘致します。 - 【新規】「武道」ツーリズム
地域の武道場を活用し、海外からの愛好家を対象とした本格的な稽古体験プログラムや、初心者向けの文化体験プログラムを造成します。地域の歴史や精神性と結びつけることで、付加価値を高めることができます。
- 「みる」ツーリズム
- 【新規】スポーツコンプレックスを核としたまちづくり
- 老朽化した体育館や競技場を、単に建て替えるのではなく、複数のアリーナ、トレーニング施設、商業施設(レストラン、ショップ)、宿泊機能などを組み合わせた複合型・多機能型の「スポーツコンプレックス」として再整備する構想を検討します。
- 施設の設計段階から「ホスピタリティ」の視点を取り入れ、トップアスリートから地域住民、観戦客まで、誰もが快適に過ごせる空間を創出します。これにより、施設の収益性を高め、周辺地域への経済的な波及効果を生み出します。
- 【新規】eスポーツの活用による新たな賑わいの創出
- 地域の商業施設や公共施設を活用し、eスポーツの大会や体験会を企画・実施します。これにより、普段行政のイベントに参加しない若者層との新たな接点を創出し、地域の賑わいを創出します。
- 地域の専門学校やIT企業と連携し、eスポーツ関連のイベント運営や映像配信を担うデジタル人材の育成や、関連産業の創出を支援します。
ライフステージに応じたスポーツ機会の提供
自治体が取り組むべきアクション
- 子どもの運動機会の確保
- 外遊びの機会が減少している子どもたちのために、地域の公園でのプレーパーク(冒険遊び場)の開催や、学校の校庭・体育館の週末開放を拡充します。
- 多様なスポーツに触れる機会を提供するため、地域の総合型地域スポーツクラブと連携し、複数の種目を体験できる「スポーツ探検隊」のようなプログラムを実施します。
- 働き世代の健康増進
- 地域の企業と連携し、昼休みや就業後に気軽に参加できるスポーツプログラム(ヨガ、ランニング教室など)をオフィス街の公園や公共施設で実施します。
- スポーツジムやフィットネスクラブの利用料を補助する「スポーツ活動奨励制度」などを検討し、住民の自発的な健康づくりを後押しします。
- 高齢者の介護予防・健康寿命延伸
- 地域包括支援センターや老人クラブと連携し、高齢者が無理なく楽しめる体操教室やウォーキング、グラウンド・ゴルフといった「通いの場」を拡充します。
- 理学療法士などの専門職と連携し、個々の身体機能に応じた科学的根拠のある介護予防運動プログラムを導入します。
- 【拡充】障害者スポーツ(パラスポーツ)の振興
- 地域の体育施設において、障害のある人が優先的に利用できる時間帯を設定したり、車いすバスケットボールやボッチャなどのパラスポーツ用具の貸し出しを行ったりするなど、参加へのハードルを下げます。
- 地域の障害者団体や特別支援学校と連携し、パラスポーツの体験会を開催するとともに、指導者やボランティア(サポーター)の育成にも取り組みます。
まとめ
~行政職員に求められる「越境する力」と「巻き込む力」~
スポーツ政策を成功に導くために、私たち行政職員に求められるのは、スポーツ部局という枠組みの中に留まらず、観光、産業、まちづくり、福祉、教育といった他分野へ積極的に越境していく力です。スポーツが持つ多面的な価値を最大限に引き出すためには、分野横断的な視点での戦略的な政策連携が不可欠だからです。
そして、もう一つ重要なのが、地域の多様なプレイヤーを「巻き込む力」です。プロスポーツチーム、地域のスポーツ団体、民間企業、学校、そして熱意ある市民。これらの人々が持つ情熱やアイデア、資源を結びつけ、地域全体でスポーツを支え、楽しむという大きなムーブメントを創り出すこと。それこそが、スポーツを通じて地域を元気にし、住民の暮らしを豊かにするための、私たち行政職員が果たすべき役割なのです。