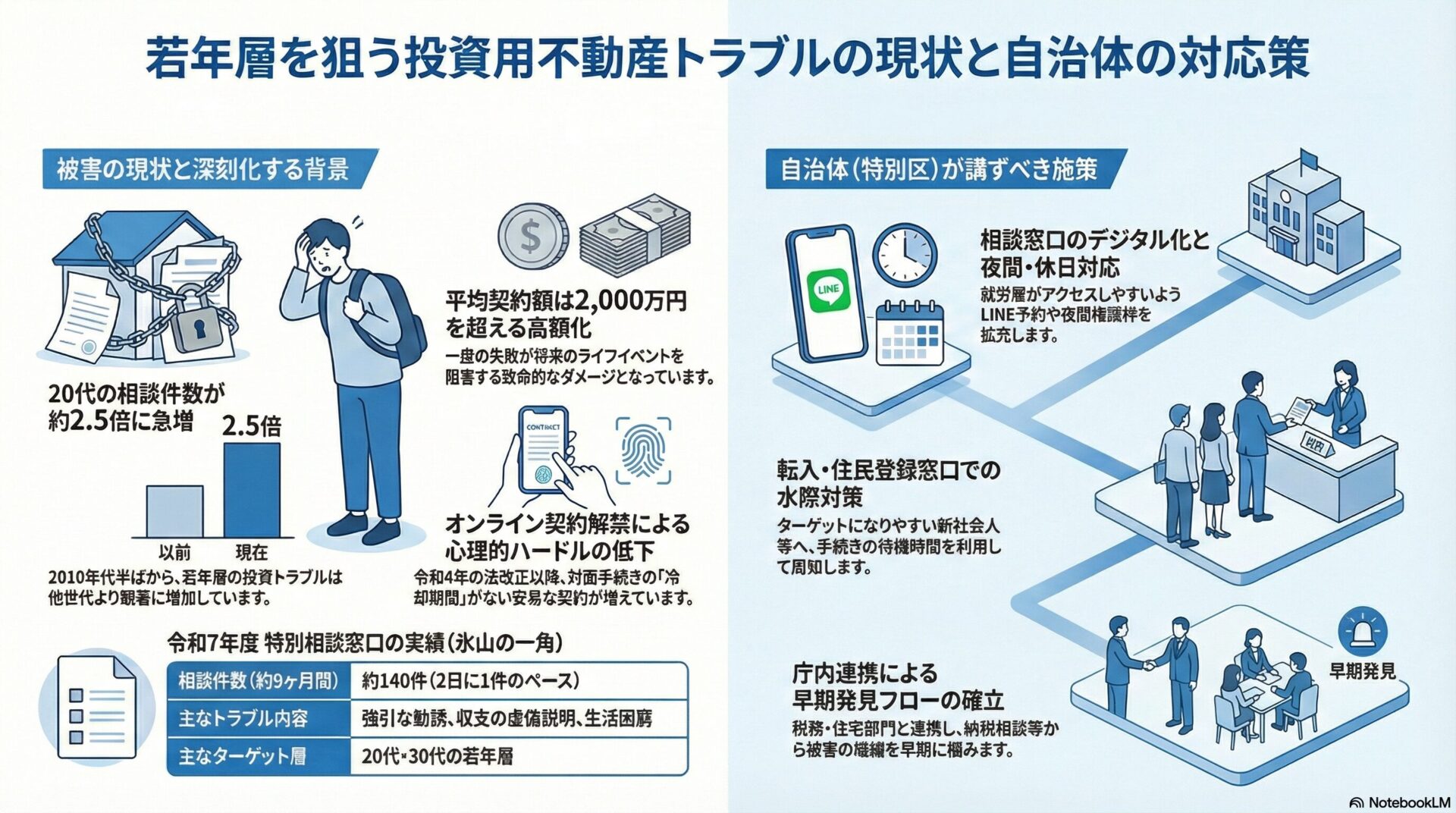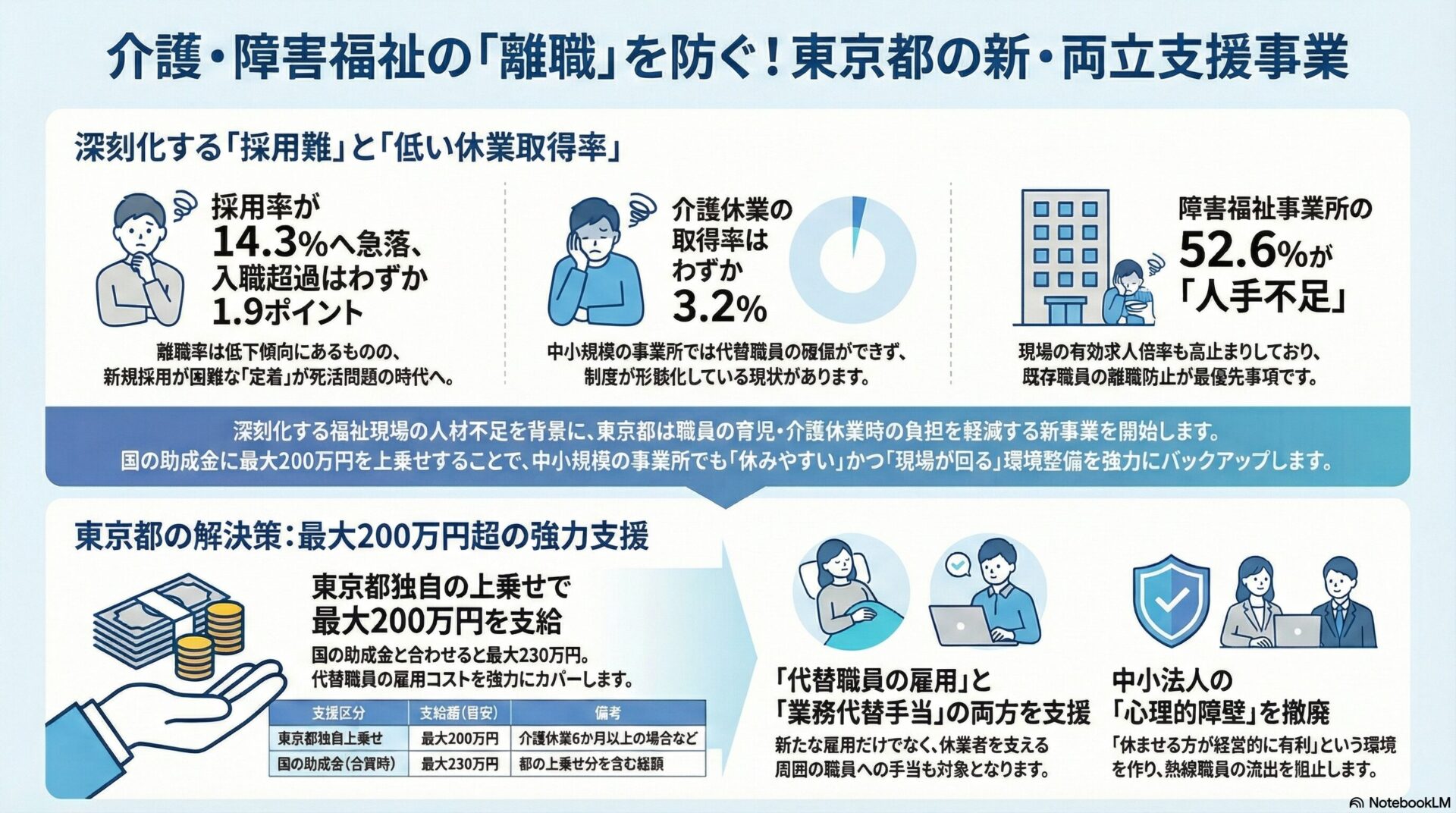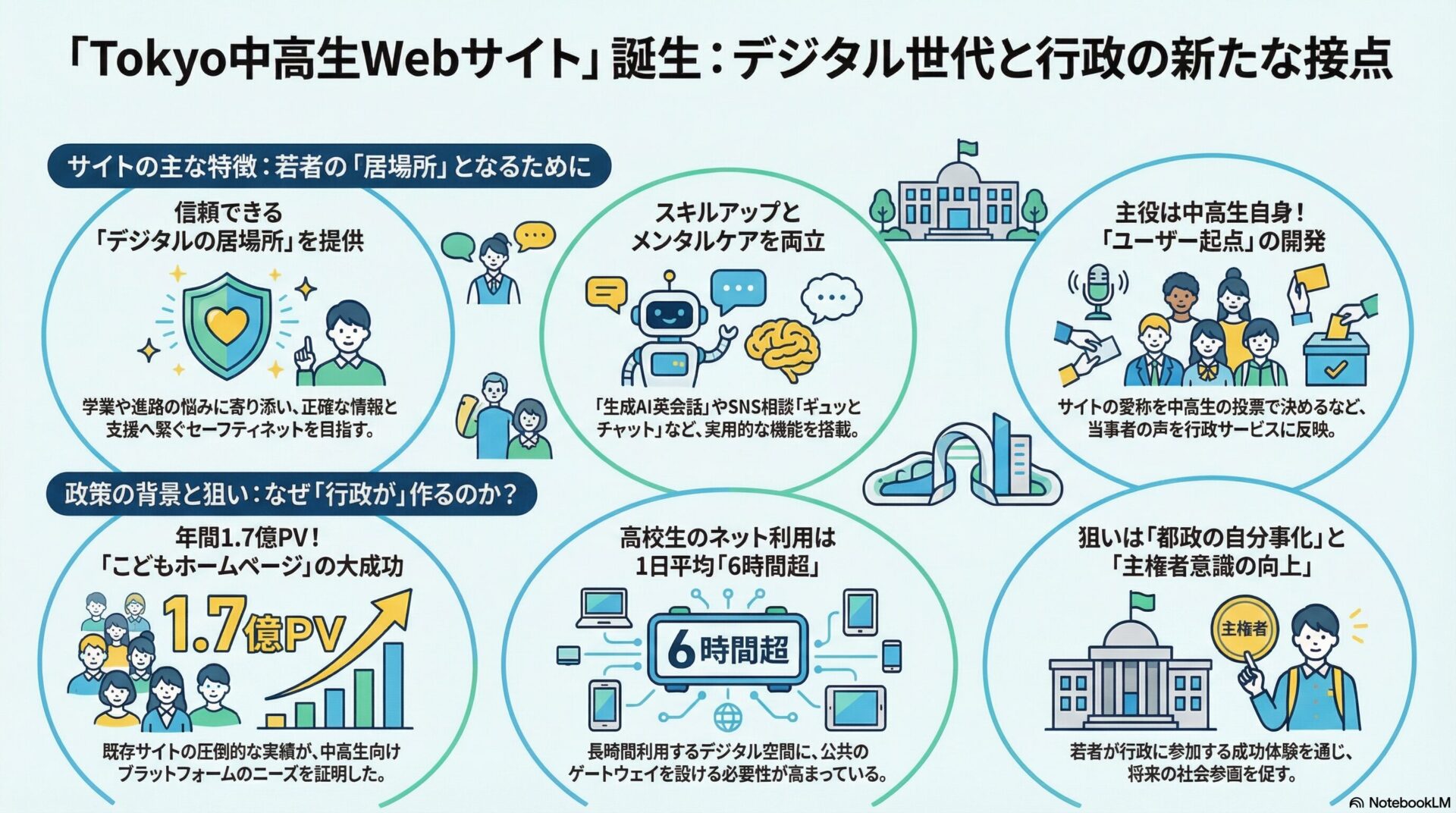【東京都】TOURISE AWARDS 2025「世界最高観光地」受賞

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
エグゼクティブサマリー:
新たな「観光立国」のフェーズへ
2025年11月、サウジアラビアのリヤドで開催された第1回「TOURISE AWARDS 2025」において、東京都は「総合第1位(Best Overall Destination)」、「食と料理部門(Best Food & Culinary Destination)」、「エンターテインメント部門(Best Entertainment Destination)」の3冠を達成するという快挙を成し遂げました。この事実は、単なる一過性の祝賀ニュースとして消費されるべきではありません。これは、東京都および特別区(23区)の観光行政において、これまでの政策の正当性が国際的に証明された瞬間であると同時に、これからの政策立案に対する極めて高度な要求、いわば「質的転換へのマンデート(命令)」が突きつけられたことを意味します。
本レポートは、特別区の自治体職員および政策立案担当者を対象に、この受賞の真の意味を解体し、今後の具体的な政策展開に資する詳細な分析を提供するものです。メディアの表面的な報道を超え、なぜサウジアラビア主導の賞が重要なのか、具体的にどの指標が評価されたのか、そして「世界一」の称号がもたらすオーバーツーリズムという副作用にどう対処すべきかについて、客観的根拠に基づき論じます。
特に注目すべきは、主催者であるサウジアラビアが国家戦略「ビジョン2030」の下、観光を石油に代わる次世代の基幹産業と位置づけ、世界の観光投資と政策決定の「コントロールルーム」になろうとしている点です。この文脈において、東京が初代王者として選ばれたことは、今後拡大が見込まれる中東・湾岸諸国(GCC)やグローバルサウスからの富裕層・高付加価値旅行者(High-Value Travelers)にとって、東京が「主要なデスティネーション」として認知されたことを示唆します。
一方で、足元のデータを見れば、訪日外国人旅行者数は2025年に4,020万人(推計)と過去最高を記録する見込みであり、特定地域における混雑やマナー違反といった「オーバーツーリズム」の問題は深刻化の一途をたどっています。東京都知事が受賞スピーチで触れたように、「持続可能な未来」への舵取りこそが、我々に課された喫緊の課題です。
本稿では、食、エンターテインメント、安全、持続可能性といった多角的な視点から、各区の先進事例(台東区のハラル対応、豊島区のアニメ戦略、中央区の築地再開発、渋谷区のナイトタイムエコノミー施策等)を詳細に分析し、特別区全体として取り組むべき「次なるステップ」を提言します。15,000語に及ぶ本詳細分析を通じ、読者がグローバルな視座とローカルな現場感覚を統合し、実効性のある政策を立案するための一助となることを企図します。
第1章
TOURISE 2025の地政学的背景と戦略的意義
サウジアラビア「ビジョン2030」とグローバル観光の覇権シフト
「TOURISE AWARDS」の重みを理解するためには、まず主催国であるサウジアラビア王国の意図を正確に把握する必要があります。これは単なる民間イベントではなく、国家の威信と未来を懸けた巨大な国家プロジェクトの一環であるからです。
サウジアラビアは現在、ムハンマド皇太子主導の下、石油依存型経済からの脱却を目指す国家改革計画「ビジョン2030」を推進しています。この計画の中で、観光産業は経済多角化の柱の一つとして位置づけられており、2030年までに年間訪問者数1億5,000万人、GDPにおける観光産業の貢献度を10%に引き上げるという野心的な目標(KPI)が設定されています。
サウジアラビアは、自国を単なる観光地として売り込むだけでなく、世界の観光産業における「意思決定の中心地」あるいは「コントロールルーム」としての地位を確立しようとしています。リヤドで開催された「TOURISE Summit」は、世界中の投資家、政策立案者、イノベーターを一堂に会させ、観光の未来を形成するためのプラットフォームとして設計されています。
この地政学的な文脈において、東京が「初代受賞都市」に選ばれたことは、極めて戦略的な意味を持ちます。
第一に、これは「欧米中心」であった従来の観光評価軸が、「中東・アジア・グローバルサウス」を含む多極的な評価軸へとシフトしていることの象徴です。従来の旅行雑誌やランキングは欧米の視点が強かったのですが、TOURISEはサウジアラビア観光省が支援し、グローバルな視点を取り入れています。
第二に、サウジアラビアを含む湾岸協力会議(GCC)諸国は、世界でも有数の「高消費額」を誇る旅行者層を抱えています。彼らが主催する賞でトップに立つことは、これら高付加価値層に対する最強のマーケティングとなり得ます。特別区の行政官は、従来の東アジアや欧米豪に偏ったインバウンド戦略に加え、中東市場という新たな、かつ極めて購買力の高いターゲット層への対応(ラグジュアリー、ハラル、プライバシー重視のサービス等)を本格的に検討すべき時期に来ています。
TOURISEプラットフォームの構造的特質:
「投資」と「政策」の融合
TOURISEプラットフォームの特徴は、単なる表彰制度にとどまらない点にあります。それは「観光、テクノロジー、投資、持続可能性のエコシステム全体を統合する」ことを目的としています。
具体的には、以下の要素が密接にリンクしています:
- 投資誘致機能:
- TOURISEは、観光地への投資を加速させるための「ディールフロー(投資案件の流れ)」を生み出すことを目指しています。東京がここで評価されたことは、東京の観光インフラ(ホテル、エンタメ施設等)に対する国際的な投資意欲を喚起する呼び水となる可能性があります。
- 技術革新のショーケース:
- AIやデータ活用による観光DX(デジタルトランスフォーメーション)が重視されており、サウジアラビア自身も電気飛行タクシー(eVTOL)の導入など、先端技術の実装に積極的です。東京が評価された背景にも、こうした「イノベーション」への親和性が挙げられます。
行政の視点からは、TOURISEが「政策対話の場」として機能している点に注目すべきです。世界中の観光大臣や元世界的組織のトップが審査員やアドバイザリーボードに名を連ねており、ここでの議論は世界の観光政策のトレンドセット(流行決定)機能を持ちます。したがって、TOURISEでの評価基準(アクセシビリティ、持続可能性、真正性など)は、今後の国際標準となる可能性が高く、特別区の観光基本計画においてもこれらの指標をベンチマークとすることが推奨されます。
受賞の背景:
なぜ今、中東主導の評価が東京にとって重要なのか
東京がパリやニューヨーク、ロンドンといった伝統的な観光都市を抑えて「総合優勝」を果たした背景には、現代の旅行者が求める価値観の変化があります。
TOURISEのファイナリスト選出においては、「真正性(Authenticity)」、「イノベーション(Innovation)」、「包摂性(Inclusion)」、「持続可能性(Sustainability)」、「安全性(Safety)」といった基準が重視されました。
東京は、世界最大級のメガシティでありながら、驚異的な治安の良さを維持し(Safety)、数百年前の寺社仏閣と最先端のテクノロジーやポップカルチャーが同居しています(Authenticity & Innovation)。この「ハイブリッドな魅力」こそが、グローバルな評価基準において東京を際立たせている要因です。
特に中東地域からの視点では、東京の「清潔さ」「安全性」「礼儀正しさ」は極めて高く評価されています。また、アニメやマンガといった日本のソフトパワーはサウジアラビアの若年層にも深く浸透しており、これらが複合的に作用して「東京」ブランドへの憧れを醸成しています。
特別区にとっての示唆は明確です。我々が「当たり前」と思っている「治安の良さ」や「新旧の混在」こそが、グローバルな競争力の源泉であるということです。都市開発において、古い街並み(下町や横丁)を一掃して均質なビル街にするのではなく、それらを「真正性」という価値ある資産として保全・活用する政策こそが、国際的な競争力を維持するために不可欠です。
第2章
「Best Overall Destination」受賞の深層分析
評価の決定打:
「江戸の伝統」と「破壊的イノベーション」の共存
小池百合子東京都知事は受賞後のコメントにおいて、東京が評価された理由を「何世紀にもわたる江戸の伝統とイノベーションが調和して融合している点」にあると述べています。また、TOURISEの審査員講評においても、東京の「独特のアイデンティティとキャラクター」が高く評価されています。
この「伝統と革新の融合」は、しばしば観光パンフレットの決まり文句として使われますが、TOURISEの文脈ではより具体的な「都市機能」として評価されています。
例えば、交通インフラにおけるICカードやMaaS(Mobility as a Service)の利便性と、皇居や浅草寺といった歴史的遺産の物理的な近接性です。旅行者は、世界最高水準の鉄道網を使って、数十分以内に「サイバーパンク的な渋谷」から「静寂な明治神宮」へと移動できます。このような「タイムトラベル的体験」を、ストレスなく(高い利便性と安全性で)提供できる都市は、世界的に見ても稀有です。
行政への示唆:
特別区のまちづくりにおいて、「機能性(イノベーション)」と「情緒(伝統)」を対立項としてではなく、補完項として扱う必要があります。例えば、歴史的な商店街にキャッシュレス決済や多言語デジタルサイネージを導入する支援策は、まさにこの「融合」を体現する施策であり、TOURISE的な評価軸に直結します。
競合都市(パリ、ニューヨーク)との比較優位性分析
TOURISE AWARDSのファイナリストには、パリ、ニューヨーク、京都といった強力な競合が並んでいました。これらの都市を抑えて東京が選ばれた要因を比較分析することで、東京の強みと今後の課題が浮き彫りになります。
表1:主要競合都市との観光指標比較(TOURISE評価基準に基づく定性分析)
| 評価項目 | 東京 (Tokyo) | パリ (Paris) | ニューヨーク (New York) | 東京の勝因・特徴 |
| 食・料理 | ◎ (Best Food受賞) | 〇 (Best Shopping受賞) | 〇 | ミシュラン星付きからB級グルメ、居酒屋まで、価格帯とジャンルの「層の厚さ」が圧倒的。 |
| 安全性 | ◎ | △ | △ | 深夜の独り歩きや公共交通機関の治安において、東京は圧倒的な優位性を持つ。 |
| 清潔さ | ◎ | △ | △ | 公共空間の清潔さは、旅行者の快適性(Convenience/Value)に直結する重要指標。 |
| エンタメ | ◎ (Best Entertainment受賞) | 〇 | 〇 | アニメ・マンガという独自の強力なIPに加え、テーマパークや没入型体験が評価された。 |
| ショッピング | 〇 | ◎ (Best Shopping受賞) | 〇 | パリは「クチュールの首都」としてショッピング部門を受賞。東京もデパート等の質は高いが、ブランド力でパリに譲る。 |
この比較から分かるように、東京の勝因は「総合力」にあります。特に「食」と「エンターテインメント」の質と量が、基盤となる「安全性」と「インフラ」の上に成り立っている点が強みです。一方で、ショッピング体験における「文化的な発見」や「ラグジュアリーの演出」においては、パリに学ぶべき点も多くあります。
「Tokyo Tokyo」ブランドの浸透とインフラの貢献
東京都が推進してきた観光ブランディング「Tokyo Tokyo Old meets New」は、今回の受賞コンセプトと完全に合致しています。筆文字(Old)とゴシック体(New)を組み合わせたロゴは、視覚的にも都市のアイデンティティを体現しており、国内外での認知拡大に寄与してきました。
また、インフラ面での貢献も見逃せません。東京メトロ等は、訪日外国人向けの企画乗車券「Tokyo Subway Ticket」のオンライン販売を強化し、QRコードによる発券システムを導入するなど、シームレスな移動体験を提供しています。こうした「ストレスフリーな移動環境」は、TOURISEの評価基準である「利便性(Convenience)」において高いスコアを獲得する要因となったと考えられます。
行政への示唆:
各区独自の観光プロモーションにおいても、「Tokyo Tokyo」ブランドとの整合性を意識し、相乗効果を狙うべきです。また、区内のコミュニティバスやレンタサイクル等の二次交通についても、主要交通機関との結節点強化やキャッシュレス対応を進め、「ラストワンマイル」の利便性を向上させることが、都市全体の評価を底上げします。
第3章
「食と料理部門(Gastronomy)」における勝利と課題
ミシュランを超えて:
「江戸前」のエコシステムとサプライチェーン
「食と料理部門」において、東京はロンドンや香港を抑えて受賞しました。その授賞理由として、「謙虚なカウンター(立ち食い等)から、革新的な懐石料理に至るまで、比類なき料理の深み」が挙げられています。これは、単に高級レストランが多いこと(ミシュランの星の数世界一)だけでなく、ストリートフードや居酒屋文化も含めた「食の裾野の広さ」が評価されたことを意味します。
この「深み」を支えているのが、江戸時代から続く「江戸前」の食文化と、それを支える高度なサプライチェーンです。豊洲市場(旧築地市場)に代表される鮮魚流通システムや、近郊農業からの新鮮な食材供給が、東京の食のクオリティを底支えしています。
行政への示唆:
「ガストロノミー・ツーリズム(食観光)」は、地域活性化の切り札となります。しかし、それは単にレストランを紹介することではありません。食材の産地、歴史的背景、職人の技術といった「ストーリー」を付加価値として提供することが重要です。各区は、区内の老舗店舗や伝統的な食文化(例:深川めし、もんじゃ焼き、そば、うなぎ等)を「文化遺産」として位置づけ、その保存と発信を支援すべきです。
築地再開発プロジェクト:
食文化とイノベーションの融合拠点
中央区における最大のトピックであり、東京の食の未来を左右するのが「築地市場跡地」の再開発プロジェクトです。
2024年4月に事業予定者が決定し、三井不動産を中心とする企業連合が、「食」と「スポーツ」、「ウェルネス」等を融合させた大規模な開発を行うことが発表されました。
プロジェクトの要点と観光的意義:
- デザインの継承:
- 新たに建設される約5万人収容のマルチスタジアムは、かつての築地市場の扇形の形状を継承し、「扇」をモチーフとした屋根デザインが採用される予定です。これは、場所の記憶(レガシー)を物理的なデザインに残す試みであり、観光客に対する「ストーリー性」の提供につながります。
- 食のイノベーション拠点:
- 商業施設エリアは、単なるショッピングモールではなく、食に関する「イノベーションハブ」としての機能を持つことが計画されています。これは、TOURISEが重視する「イノベーション」の要素を具現化するものであり、世界中のフードテック企業や料理人を惹きつける磁場となることが期待されます。
- 開業スケジュール:
- 一部施設の開業は2020年代後半(2028-2029年度頃)を目指しており、全体開業は2030年代前半となる見込みです。
中央区および周辺区への示唆:
この巨大プロジェクトは、周辺の築地場外市場や銀座エリア、浜離宮恩賜庭園、隅田川テラス等との回遊性を劇的に高める可能性があります。区としては、開発事業者と連携し、場外市場の賑わいや「カオスな魅力」を維持しつつ、新しい施設との相乗効果を生み出す動線計画やエリアマネジメントが求められます。また、水上交通(舟運)のハブとしての機能強化も期待されており、舟運を活用した広域観光ルートの構築も視野に入れるべきです。
台東区・港区の事例に見る「食の多様性(ダイバーシティ)」戦略
TOURISEの重要な評価軸である「包摂性(Inclusion)」において、食の分野で最も重要な課題が「食のバリアフリー(ハラル、ヴィーガン、アレルギー対応等)」です。東京が今後、中東や欧米からの多様な旅行者を受け入れるためには、この分野での対応強化が不可欠です。
先進事例の分析:
- 台東区(浅草・上野)の取り組み:
- 台東区は、「ムスリムフレンドリーマップ」や「ヴィーガンマップ」の作成において、都内でも先駆的な役割を果たしています。具体的には、「Tokyo Dietary Diversity Map」を発行し、ハラル認証店だけでなく、ヴィーガン対応店の情報を網羅し、ピクトグラムを用いて視覚的に分かりやすく情報提供を行っています。また、ハラルラーメン店やウズベキスタン料理店など、具体的な店舗情報を行政が発信することで、ムスリム旅行者に安心感を与えています。これは、区内にモスク(アサクサ・モスク等)が存在し、ムスリム旅行者のニーズが顕在化していたことへの迅速な対応であったといえます。
- 港区の取り組み:
- 港区には多くの大使館が立地しており、外国人居住者比率も約7.9%と高い水準にあります。そのため、区内のレストランやホテルにおける多言語対応や食の多様性対応は比較的進んでいます。また、国際化推進プランにおいて、多文化共生の視点から外国人住民と地域コミュニティの連携を重視しています。
全区的な展開への提言:
台東区や港区の事例は、他の区にとっても再現可能なモデルです。
- 情報の一元化:
- 区内の「食のバリアフリー」対応店を調査し、デジタルマップ化する。
- 認証取得支援:
- ハラル認証やヴィーガン認証の取得にはコストと手間がかかるため、区として講習会の開催や認証取得費用の助成を行う。
- ピクトグラムの普及:
- 厳格な認証取得が難しい小規模店舗に対しては、「ポークフリー」「アルコールフリー」等の食材ピクトグラムの掲示を推奨し、情報開示による選択肢の提供(情報バリアフリー)を進める。
第4章
「エンターテインメント部門」の勝因とナイトタイムエコノミー
豊島区・池袋の「国際アート・カルチャー都市」戦略とコンテンツツーリズム
「エンターテインメント部門」での受賞は、東京がソウルやメキシコシティを抑えた結果です。この勝利の背景には、東京ディズニーランド(厳密には千葉県だが東京圏の資産)やチームラボのような没入型施設に加え、アニメ・マンガという世界最強のコンテンツIPの存在があります。
豊島区のケーススタディ:
豊島区(池袋)は、かつての「消滅可能性都市」という汚名を返上すべく、「国際アート・カルチャー都市」構想を掲げ、徹底した文化政策と都市再生を進めてきました。
- アニメ東京ステーション(Anime Tokyo Station):
- 2023年10月に池袋にオープンしたこの施設は、アニメの制作資料(セル画等)の展示や企画展を行う拠点であり、世界中のアニメファンにとっての聖地となっています。
- 乙女ロードとアニメイト:
- 池袋は「乙女ロード」に代表される女性向けアニメ文化の集積地であり、世界最大級のアニメショップ「アニメイト池袋本店」は、単なる物販店を超えた観光名所となっています。
- マンホールツーリズム:
- 区内のマンホールをアニメキャラクターのデザインにするなど、回遊性を高める細やかな仕掛けも行っています。
行政への示唆:
豊島区の成功は、「強みの明確化」と「官民連携」の賜物です。区がアニメを「文化」として正式に位置づけ、ハード(施設)とソフト(イベント・マンホール等)の両面で支援することで、民間活力を最大限に引き出しました。他の区においても、自区の持つ文化的資産(例:杉並区のアニメスタジオ、練馬区の漫画家ゆかりの地、世田谷区の特撮文化等)を再定義し、観光資源として磨き上げる余地があるます。
渋谷区・新宿区におけるナイトライフの可能性と「安全性」のパラドックス
東京のナイトタイムエコノミー(夜間の経済活動)は、エンターテインメントの重要な柱であると同時に、行政にとって最も管理が難しい領域でもあります。
渋谷区の取り組み:
渋谷区は、若者文化とナイトライフの中心地ですが、ハロウィン時の騒動や路上飲酒などの課題に直面してきました。これに対し、渋谷区観光協会は「Shibuya Nightlife Guide」という情報デスクを設置し、多言語対応のスタッフが外国人観光客に対し、安全なクラブやバー、イベント情報を案内する取り組みを行っています。
また、「Shibuya Night Map」を作成し、お酒を飲まない人向けの「ノンアルコール」の楽しみ方や、食事中心のナイトライフ(Shibuya Dish Award受賞店など)も紹介することで、ナイトライフの多様化と健全化を図っています。これは、単なる規制(路上飲酒禁止)だけでなく、適切な誘導(コンシェルジュ機能)を組み合わせたスマートな対応策といえます。
新宿区(歌舞伎町)の課題:
歌舞伎町は世界的に有名な歓楽街ですが、ぼったくり(Tout)や客引きの問題が依然として深刻です。外国人観光客向けのガイド記事では、「客引きには絶対についていかない」「料金システムを事前に確認する」といった自衛策が強調されています。
また、近年は「トー横キッズ」と呼ばれる若者の滞留問題など、社会福祉的な課題も観光地のイメージに影を落としています。
ナイトタイムエコノミーの経済効果:
ナイトタイムエコノミーは、飲食、交通、エンタメなど多岐にわたる産業に波及効果をもたらします。英国の事例ではGDPの4%以上を占めるとの試算もあり、東京においても公共交通機関の終電延長や深夜バスの拡充などが議論されてきましたが、採算性や人手不足の壁があり実現には至っていません。
行政への示唆:
区レベルでできる現実的な施策は、渋谷区のような「情報の適正化」と「エリアマネジメント」です。
- ナイト・メイヤー(夜の市長)的機能:
- 行政、警察、商店街、住民の調整役を設置し、夜間のルール作りと活性化を両立させる。
- 安心・安全情報の多言語発信:
- ぼったくり被害防止のための啓発動画やデジタルサイネージの設置、パトロールの強化。
- 「夜の文化」の創出:
- ナイトクラブだけでなく、美術館や博物館の夜間開館(ナイトミュージアム)や、夜間のライトアップイベント等を支援し、夜遊びの選択肢を「飲酒」以外にも広げる。
コンテンツ産業の集積と「コト消費」への転換
エンターテインメント部門での勝利は、モノ消費(ショッピング)からコト消費(体験)へのシフトを象徴しています。
アニメ、ゲーム、音楽、食体験など、東京には「ここでしかできない体験」が無数にあります。TOURISEの評価基準である「真正性」は、まさにこの独自の体験価値に向けられています。
行政は、ハコモノ(施設)を作ることよりも、こうしたソフトコンテンツを生み出すクリエイターや事業者が活動しやすい環境(スタートアップ支援、規制緩和、表現の場の提供)を整備することに注力すべきです。
第5章
オーバーツーリズムと持続可能性への挑戦
観光公害の現状データと住民感情の悪化
「世界一の観光都市」という栄誉の裏で、東京は深刻な「オーバーツーリズム(観光公害)」の危機に直面しています。
2025年の訪日外国人旅行者数は過去最高を更新するペースで推移しており、特に東京、京都、大阪の「ゴールデンルート」への集中が著しい状況です。
具体的な弊害:
- 混雑:
- 居住区や通勤経路での混雑に対し、約6割の住民がネガティブな影響を感じているという調査結果があります。
- マナー違反:
- ゴミのポイ捨て、私有地への立ち入り、写真撮影に伴う交通妨害などが頻発しています。
- ジェントリフィケーション:
- 観光客向けの店舗や宿泊施設が増加し、住民向けの商店が減少したり、家賃が高騰したりする現象も懸念されます。
出国税引き上げと「入場料」議論:
需要管理の財政的メカニズム
増え続ける観光客によるインフラ負荷に対応するため、国および東京都レベルで新たな財源確保と需要抑制策が検討されています。
出国税(国際観光旅客税)の引き上げ:
政府・与党は、現行1人あたり1,000円の出国税を、3,000円程度に引き上げる案を検討しています。さらに、ビジネスクラス以上の利用者には5,000円といった傾斜配分も議論されています。この増収分は、オーバーツーリズム対策(混雑緩和、マナー啓発、地方分散等)に充てられる予定です。
二重価格(Dual Pricing)と入場料:
外国人観光客に対してより高い料金を設定する「二重価格」や、これまで無料だった観光資源への「入場料」導入も議論の遡上に載っています。これは、需要を価格メカニズムでコントロールすると同時に、維持管理費用を受益者に負担させるという考え方です。
特別区への示唆:
現在、東京都内の宿泊税は都と区で調整されていますが、オーバーツーリズム対策の財源として、区独自の「法定外目的税」の導入や、宿泊税の拡充・配分見直しを検討する余地があります。確保した財源は、清掃活動の強化、多言語案内板の整備、観光公害対策の専任スタッフ雇用などに充当すべきです。
「ゴールデンルート」からの脱却と地方・周辺区への分散戦略
国の方針として、観光客を東京・京都・大阪から地方へ分散させることが掲げられているが、東京都市圏内部においても「都心部(特別区)」から「周辺部(多摩地域・島嶼部)」や「住宅地エリア」への分散が必要です。
「Undiscovered Tokyo(知られざる東京)」のプロモーション:
浅草や渋谷といった過密エリアではなく、まだ知られていない魅力を持つエリア(例:荒川区の路面電車、江東区の水辺、世田谷区のサブカルチャー等)への誘導を図ります。
小池知事は受賞スピーチで、東京の島嶼部(伊豆諸島・小笠原諸島)の魅力についても言及し、分散への意欲を示しています。
行政の役割:
各区は、隣接する区や多摩地域と連携し、広域的な観光ルートを開発するべきです。単独の区だけでは滞在時間が短くても、広域連携によって「半日コース」「1日コース」を組成できれば、観光客の滞在を分散・長期化させることができます。
第6章
特別区職員に向けた政策提言とロードマップ
以上の分析を踏まえ、特別区の行政官が取り組むべき具体的な政策の方向性を提言します。
「量」から「質」へ:
高付加価値旅行者(HVT)の誘致戦略
TOURISEの受賞は、東京が「安くて美味しい街」から「世界最高水準の体験ができる街」へと脱皮するチャンスです。
KPI(重要業績評価指標)を「観光客数」から「観光消費額」および「住民満足度」へと転換すべきです。
- 具体的施策:
- ラグジュアリーホテル開発に伴う周辺環境の整備(電線地中化、歩道の拡幅、街路樹の整備)。
- HVTはホテルの中だけでなく、街全体の質を評価します。
- 高単価な体験コンテンツの開発支援(例:寺社での早朝貸切座禅、伝統工芸作家によるプライベートワークショップ、市場での特別見学ツアー)。
- これらは混雑を避けつつ、高い収益をもたらします。
- ラグジュアリーホテル開発に伴う周辺環境の整備(電線地中化、歩道の拡幅、街路樹の整備)。
自治体間連携による「広域観光圏」の形成
観光客にとって「区境」は存在しません。行政区分に縛られない連携が必要です。
- 具体的施策:
- 下町連携:
- 台東区、墨田区、荒川区、葛飾区などが連携し、歴史と職人文化をテーマにした広域ルートを形成する。
- ベイエリア連携:
- 港区、中央区、江東区が連携し、水上交通(舟運)を活用した移動ネットワークと、夜景・食を組み合わせたナイトタイム観光を推進する。
- データ共有:
- 観光客の動態データや混雑状況を区間で共有し、特定の場所に人が集中しないよう相互に送客し合う仕組みを作る。
- 下町連携:
観光DXとデータ駆動型「マナー啓発」の社会実装
「マナーを守ってください」という看板を立てるだけでは、問題は解決しません。テクノロジーを活用したスマートな管理が求められます。
- 具体的施策:
- 混雑の可視化:
- 主要観光スポットの混雑状況をリアルタイムでWebやアプリで配信し、空いている時間帯への来訪を促す(ナッジ理論の応用)。
- デジタルサイネージとAI:
- 街頭のサイネージで、現在の混雑状況やマナー情報を多言語で表示する。AIカメラを活用し、異常な混雑やトラブルの予兆を検知するシステムの実証実験を行う。
- キャラクターの活用:
- アニメやマンガのキャラクターを活用し、威圧的でない形でルールやマナーを伝える動画やポスターを作成する。これは「エンタメ部門」受賞都市ならではのアプローチです。
- 混雑の可視化:
結論:持続可能な都市観光の実現に向けて
「TOURISE AWARDS 2025」における「世界最高観光地」の受賞は、東京にとってゴールではなく、新たなスタートラインです。
世界は東京に、単に楽しい旅行先であること以上のものを求めています。それは、伝統を守りながら革新を続け、数千万人の訪問者を受け入れながらも、住民の生活の質と治安を維持するという、極めて高度な「都市経営」のモデルです。
特別区の職員に求められるのは、グローバルな視点(TOURISEのような国際的評価軸や中東市場の動向)を持ちつつ、ローカルな現場(区民生活、商店街、個別の観光スポット)における課題を解決する「グローカル」な政策立案能力です。
もはや「観光振興」と「生活環境保全」は対立する概念ではありません。持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)こそが、地域の経済を回し、文化を継承し、都市のブランド価値を高める唯一の道です。
今回分析した食の多様性、ナイトタイムエコノミーの適正化、分散戦略、高付加価値化といった施策を、各区の実情に合わせてカスタマイズし、迅速に実行に移すことが求められています。
東京が真の意味で「世界一」の都市であり続けるために、行政のプロフェッショナルとしての知恵と行動力が今、試されています。




-320x180.jpg)

-320x180.jpg)