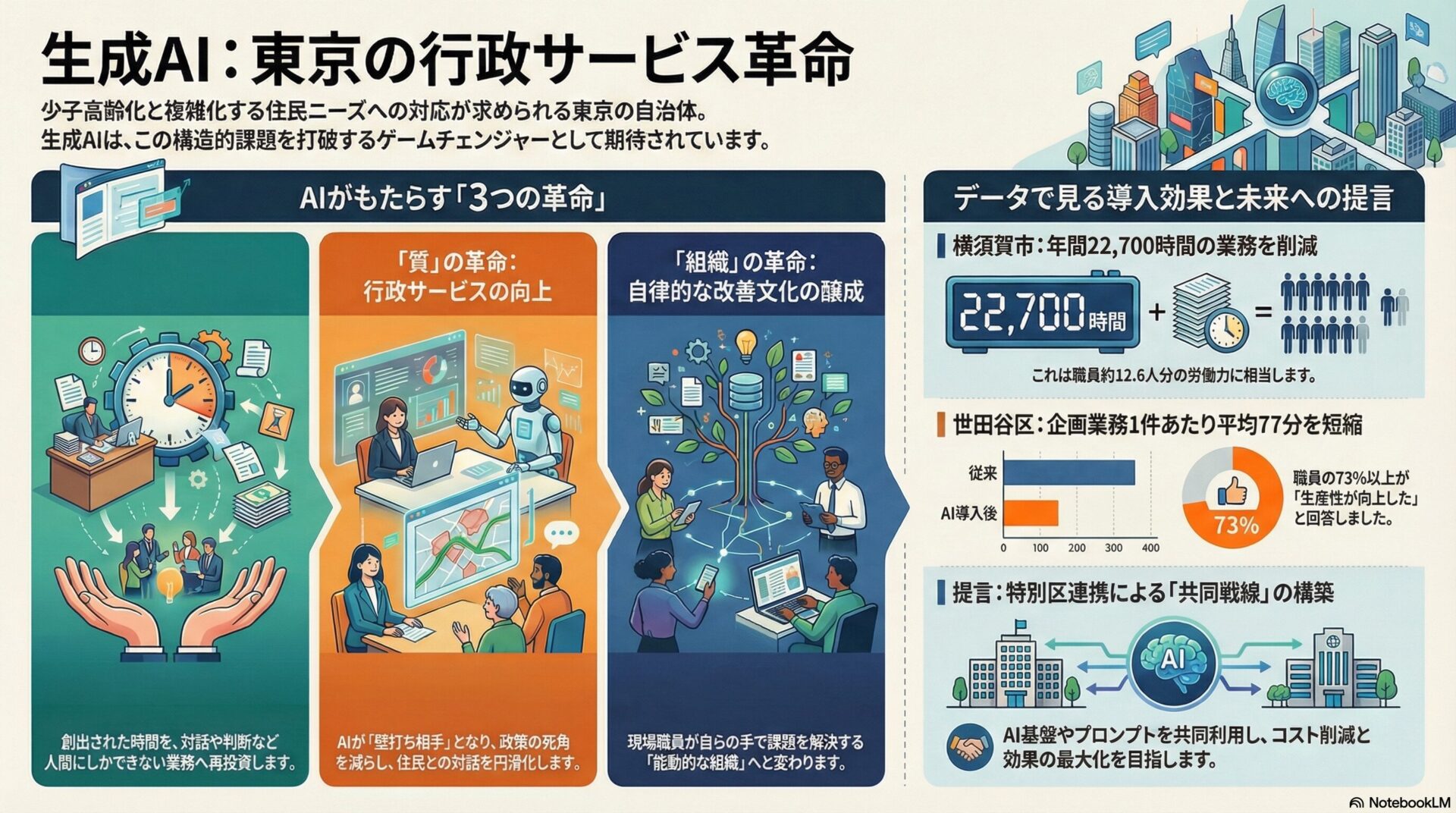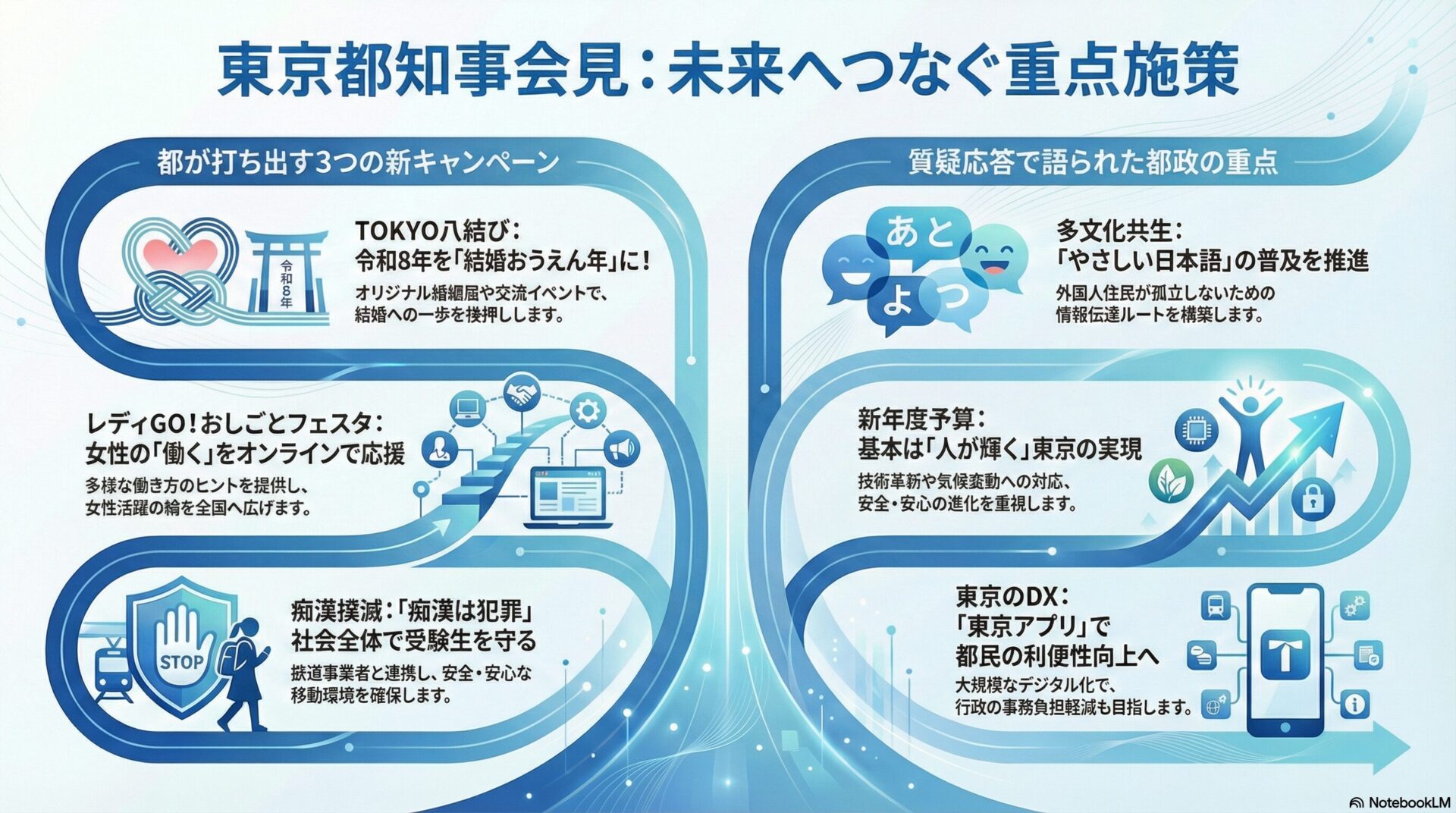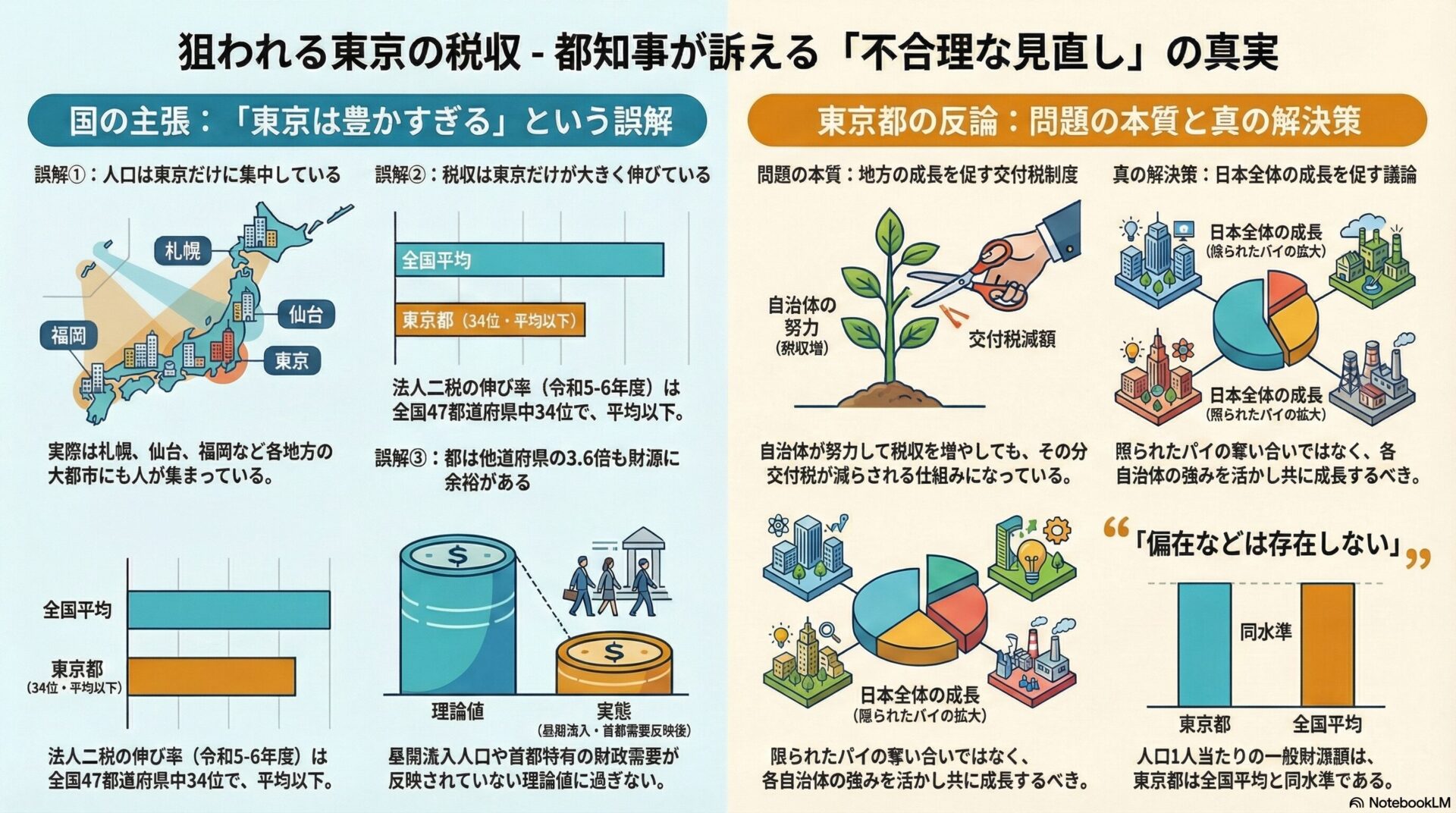【東京都】東京2025デフリンピックの戦略的活用と共生社会実現

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
政策立案の新たな地平として
本レポートの目的と位置づけ
本ドキュメントは、東京都特別区(23区)の自治体職員、特に政策企画、福祉、スポーツ振興、およびまちづくりを担当する実務者に向けて作成された、包括的な政策提言レポートです。2025年に開催される「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025(以下、東京2025デフリンピック)」および、その関連イベントである「スポーツFUN PARK」を題材に、単なる国際スポーツ大会の運営支援にとどまらない、都市機能のアップデートと社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)を実現するための論理的基盤と具体的施策を提示します。
昨今、自治体行政には「エビデンスに基づく政策立案(EBPM)」と同時に、多様化する住民ニーズに対応した「ナラティブ(物語性)のある政策展開」が求められています。デフリンピックは、1924年のパリ大会から続く100年の歴史の中で、初めて日本で開催される記念碑的な大会です。この歴史的文脈と、現在進行形で進む「手話言語条例」の制定やデジタル技術の進展を掛け合わせることで、行政は「障害者支援」という狭義の福祉施策を超え、「ユニバーサルコミュニケーション社会の構築」という広義の都市戦略を描くことが可能となります。
対象読者へのメッセージ
日々の業務において、皆様は予算の制約、縦割り行政の弊害、そして多様化する区民の声に直面していることでしょう。本レポートでは、東京2025デフリンピックを「外圧」や「単なるイベント」として処理するのではなく、既存の行政課題(例:高齢化に伴う難聴者対策、地域コミュニティの希薄化、多文化共生)を一挙に解決へ導くための「レバレッジ(てこ)」として活用する視座を提供します。提示するデータや他区の先行事例は、そのまま議会答弁や企画書の根拠資料として活用いただけるよう、出典を明記し、客観性を担保しました。
歴史的・社会的背景:
100年の軌跡と「言語」としての手話
政策の「意義」を深く理解するためには、その歴史的背景と当事者が置かれてきた社会的状況を把握する必要があります。これは、施策の「魂」を決定づける重要な要素です。
デフリンピック100年の歴史と東京開催の重み
デフリンピック(Deaflympics)は、国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)が主催する、聴覚障害者のための国際的な総合スポーツ競技大会です。特筆すべきは、その歴史の長さです。パラリンピックの起源とされるストーク・マンデビル競技大会が1948年に始まったのに対し、デフリンピックの第1回大会(当時は「国際沈黙競技大会」と呼ばれた)は、1924年にパリで開催されています。
東京2025デフリンピックは、この第1回大会から数えてちょうど100周年にあたる、第25回の記念大会です。1世紀にわたるろう者スポーツの歴史において、日本での開催は初であり、アジア太平洋地域においても、ニュージーランド(1989年)、オーストラリア(2005年)、台湾(2009年)に次ぐ4回目の開催となります。
招致活動は2018年頃から全日本ろうあ連盟を中心に本格化し、2022年9月のウィーンにおけるICSD総会で、他都市の立候補がない中で東京の開催が決定しました。この経緯は、一見すると競合がいなかったための消極的な決定に見えるかもしれませんが、実際には「100周年を祝うにふさわしい都市」として東京が選ばれたという文脈があり、行政としてはこの「記念碑的価値」を最大限に強調すべきです。
「手真似」から「言語」へ:
法的地位の変遷
デフリンピックを語る上で欠かせないのが、日本国内における手話の地位向上の歴史です。かつて日本では、手話は「手真似(てまね)」と呼ばれ、「猿真似(さるまね)」という蔑称に由来する言葉で侮蔑される時代がありました。ろう学校においてすら、手話の使用が禁じられ、口話法(相手の口の形を読み取り、発声する教育法)が強制された歴史的事実があります。
しかし、当事者団体の長年の運動により、状況は劇的に変化しました。全国すべての地方議会(1,741自治体)において「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書が採択され、手話が日本語と同等の「言語」であるという認識が広まりつつあります。現在、東京都内の多くの自治体でも手話言語条例が制定されていますが、この背景には「奪われた言語を取り戻す」という人権回復の歴史があることを、行政職員は深く認識しておく必要があります。東京2025デフリンピックは、この「手話=言語」という社会的合意を、祝祭的なイベントを通じて確固たるものにする「儀式」としての機能も有しているのです。
政策の枠組み:
「Vision 2025」と行政のアクションプラン
東京都および関係団体は、2025年に開催される世界陸上とデフリンピックの両大会を見据え、「Vision 2025」および「TOKYO FORWARD 2025」というコンセプトを掲げています。ここでは、その詳細を紐解き、各区が参照すべき具体的なアクションプランを分析します。
TOKYO FORWARD 2025の基本理念
東京都スポーツ推進総合計画等において示されている「TOKYO FORWARD 2025」は、2020年東京大会のレガシーを継承しつつ、さらに発展させることを主眼としています。そのビジョンは「誰もが輝くインクルーシブな都市・東京(Tokyo, an inclusive city where everyone can shine)」の実現です。
特にデフリンピックにおいては、以下の3つのミッションが掲げられています。
- デフスポーツの輝きと価値を通じて、人々と社会をつなぐ(Connect people and society)
- 東京2025デフリンピックを世界と未来への架け橋とする(Bridge to the world and the future)
- 「誰もが個性を活かし、力を発揮できる」共生社会を実現する(Realise an inclusive society)
10のアクションプランと具体的施策
東京都は、このビジョンを達成するために10の具体的なアクション(取組)を提示しています。特別区の職員は、自区の施策をこれらのアクションに紐づけることで、都の補助金獲得や広域連携をスムーズに進めることができます。
| 分野 | アクションNo. | アクション名称 | 自治体における具体的施策の可能性 |
| ユニバーサル・コミュニケーション | Action 1 | 重要な情報を、伝わる言葉で | 公共施設サインの多言語化・「やさしい日本語」化、ピクトグラムの刷新。 |
| Action 2 | デジタルで切り拓く東京の未来 | 窓口への音声認識・字幕表示システムの導入、都立・区立公園への音声案内アプリの実装。 | |
| 魅力の発信 | Action 3 | 文化・芸術を肌で感じる | ろう者の芸術家による文化イベントの開催、手話狂言や視覚的演劇の招聘。 |
| Action 4 | 東京の魅力を世界へ | バリアフリー観光ルートの策定、デフ対応可能な宿泊施設の支援。 | |
| 次世代育成 | Action 5 | 子供たちに夢と希望を(2025 for kids) | 小中学校でのデフアスリートによる出前授業、競技観戦プログラムの実施。 |
| Action 6 | 子供たちと一緒に創る(2025 with kids) | メダルや記念品の制作プロセスへの参画、応援フラッグの作成ワークショップ。 | |
| サステナビリティ | Action 7 | 環境をみんなで守る | 大会運営におけるプラスチック削減、環境配慮型素材の活用。 |
| Action 8 | 共に未来を創る | 障害の有無にかかわらず参加できる地域清掃活動等の実施。 | |
| 協働・参画 | Action 9 | みんなで創り上げる(Make it together 2025) | 手話ボランティアの育成、クラウドファンディングによる市民参加の促進。 |
| Action 10 | 知る、楽しむ、応援する! | パブリックビューイングの開催、SNSを活用した応援キャンペーン。 |
特にAction 2「デジタルで切り拓く東京の未来」は重要です。都営地下鉄におけるドア開閉表示灯の整備や、都立施設へのヒアリングループ(磁気誘導ループ)等の導入が進められていますが、特別区においても区役所本庁舎や区民センターにおける同様の設備投資は、デフリンピックを契機とした「正当な予算要求」として成立します。
地域別詳細分析:
特別区(23区)における取組と条例の現状
デフリンピックの会場は東京都内に分散しており、各区がそれぞれの地理的条件や資源を活かした取組を行っています。ここでは、会場を有する区(ホスト区)と、そうでない区も含めた条例制定状況を詳細に分析します。
競技会場を有する区の動向
① 世田谷区:聖地「駒沢」を有するメインステージ
世田谷区には、1964年東京オリンピックのレガシーであり、今回のデフリンピックでも主要会場となる「駒沢オリンピック公園」が所在します。
- 開催競技:
- 陸上、ハンドボール(一部)、レスリング等。
- 特徴的取組:
- 2025年11月の大会本番に先駆け、「スポーツFUN PARK」などの大規模イベントを開催。区民が日常的にスポーツに親しむ環境(ジョギングコース、ドッグラン等)と、国際大会の非日常を融合させています。
- 政策示唆:
- 大規模公園を有する自治体は、単なる「場所貸し」にならぬよう、周辺商店街への回遊策や、区民優先の観戦枠確保などを交渉すべきです。
② 渋谷区:文化発信拠点としての「目に見える応援」
渋谷区は、東京体育館(卓球会場)を有し、その発信力を活かした独自の取組を展開しています。
- 開催競技:
- 卓球(東京体育館)。
- 特徴的取組:
- 「デフリンピック応援 in SHIBUYA」と題し、キャラバンカーの誘致や、区長自らが参加する手話応援(サインエール)イベントを実施。また、「渋谷おもてなしサポーター」制度を設け、ソフト面での受け入れ態勢を強化しています。
- 政策示唆:
- 渋谷区のアプローチは「ブランディング」に重きを置いています。若者文化やファッションとデフスポーツを融合させ、「クールなイベント」として認知させる戦略は、若年層への啓発において極めて有効です。
③ 中野区:新体育館を活用した次世代育成
中野区は、2020年にオープンした「中野区立総合体育館(キリンレモンスポーツセンター)」をテコンドー会場として提供しています。
- 開催競技:
- テコンドー。
- 特徴的取組:
- 小学生を対象としたテコンドー体験・観戦イベントを企画し、事前申し込み不要で参加できるオープンな環境を整備。また、技術ミーティングや計量会場としても詳細なスケジュールが組まれており、運営面での貢献度が高いです。
- 政策示唆:
- 新しい公共施設のお披露目と、マイナースポーツ(テコンドー)の普及、そして障害理解教育をセットにした「一石三鳥」の施策展開です。
④ 大田区:地域資源とマスコットの連携
大田区は、「大田区総合体育館」をバスケットボール会場として提供しています。
- 開催競技:
- バスケットボール。
- 特徴的取組:
- 東京都が主導する「東京2025デフリンピック応援隊」に、区の公式キャラクター(はねぴょん等)を参加させ、親しみやすさを演出しています。
- 政策示唆:
- 「バスケの街」としての地域アイデンティティとデフバスケットボールをリンクさせることで、既存のバスケファンをデフスポーツの観客として取り込む戦略が有効です。
23区における手話言語条例の制定状況と政策意図の分析
条例の名称は、その自治体が「手話」をどう捉えているかという政策的意思の表れです。都内各区の条例は大きく2つのパターンに分類されます。
| 分類 | 条例の特徴 | 該当区(例) | 政策的含意 |
| A. 手話言語条例(単独型) | 手話の独自性、歴史的背景、文化的価値を強調する。 | 江戸川、荒川、板橋、中野、品川、杉並、世田谷、文京 | 手話を「日本語とは異なる一つの言語」として尊重する姿勢が鮮明。ろう者コミュニティとの連携が強く、文化施策としての側面が強い。 |
| B. 包括型(手話+意思疎通) | 手話に加え、要約筆記、点字、触手話など、多様なコミュニケーション手段を包括的に扱う。 | 豊島、足立、墨田、葛飾、港、江東、台東、北、新宿、大田、渋谷、練馬、中央 | 障害種別を限定せず、「情報バリアフリー」全体を推進する実務的なアプローチ。デジタル技術(ICT)活用との親和性が高い。 |
【分析と提言】
貴区がAタイプであれば、デフリンピックを「言語・文化の祭典」として位置づけ、手話劇や映画祭などの文化プログラムを強化すべきです。一方、Bタイプであれば、聴覚障害だけでなく、視覚障害や知的障害も含めた「ユニバーサルコミュニケーション環境の整備(窓口DXなど)」へ予算を重点配分するロジックが組み立てやすいと言えます。新宿区のように、多国籍な住民構成を持つ区では、外国人住民とのコミュニケーション支援も含めた「多文化×多言語(手話含む)×デジタル」の施策展開が望まれます。
イベント・ケーススタディ:
「スポーツFUN PARK」の戦略的活用
デフリンピック本大会の成功は、プレイベントによる機運醸成にかかっています。その中核となるのが「スポーツFUN PARK」です。
スポーツFUN PARKの概要と機能
「スポーツFUN PARK」は、デフリンピック期間中(2025年11月)、駒沢オリンピック公園に設置される一大スポーツ体験拠点です。
- コンテンツ:
- デフスポーツ体験:
- ハンドボール等の競技体験を通じて、音のない世界でのプレーを体感する。
- インクルーシブ・アクティビティ:
- カヤック、トランポリン、フライングディスクなど、障害の有無にかかわらず楽しめる種目を用意。
- 連携イベント:
- 「スポーツフェスタ2025 in 駒沢オリンピック公園」や「TOKYOエシカルマルシェ」と同時開催し、スポーツに関心の薄い層(買い物客、家族連れ)も取り込みます。
- デフスポーツ体験:
駒沢オリンピック公園という「磁場」
駒沢オリンピック公園は、1964年東京大会の第2会場として整備され、その後も都民のスポーツ拠点として機能してきた「聖地」です。
- 多機能性:
- 陸上競技場、体育館だけでなく、ドッグランやサイクリングコース、子供向けの公園(ぶた公園等)があり、多様な世代が日常的に利用しています。
- 防災機能:
- 災害時の避難場所としての機能も有しており、イベントを通じて防災意識の啓発(例:聴覚障害者への災害時情報伝達訓練)を行うことも可能です。
【提言】
各区は、自区内で完結するイベントだけでなく、この「スポーツFUN PARK」へのバスツアー企画や、区民枠の確保などを通じて、広域的な連携を図るべきです。また、マルシェへの区内福祉作業所の出店支援などは、障害者の工賃向上に直結する具体的施策となります。
データに基づく現状分析と課題
政策の説得力を高めるためには、客観的な数値データが不可欠です。ここでは、障害者スポーツを取り巻く厳しい現状と、予算の規模感を共有します。
障害者スポーツ実施率の「30%の壁」
スポーツ庁および東京都の調査によると、障害者のスポーツ実施率は健常者に比べて著しく低い状況です。
| 項目 | 成人一般(全国) | 障害者(東京) | 乖離(ギャップ) |
| 週1回以上のスポーツ実施率 | 52.3% | 30.9% | ▲21.4pt |
【阻害要因の分析】
調査結果によれば、スポーツを行わない理由として「健康上の理由」以外に、以下の社会的要因が挙げられています。
- 場所がない:
- 障害者が利用しやすい設備(バリアフリートイレ、更衣室)や、心理的に利用しやすい雰囲気の欠如。
- 仲間・指導者がいない:
- 「一人ではできない」「専門的な指導者が地域にいない」。
- 情報が届かない:
- どこでどんな教室が開催されているか、自分にできるスポーツは何かという情報へのアクセス障壁。
この「21.4ポイントのギャップ」を埋めることこそが、行政の責務です。デフリンピックは、特に「聴覚障害者が参加できるスポーツ環境」を可視化し、情報のバリアを破壊する契機となります。
身体障害者手帳所持者の推移と「見えない障害」
東京都統計年鑑によると、身体障害者手帳所持者数は約2万人前後で推移していますが(※注:特定の区またはカテゴリの数値の可能性があるため、全体の傾向として捉える)、重要なのはその内訳の変化です。
- 内部障害の増加:
- 心臓機能障害などの内部障害は増加傾向にあります。
- 高齢化:
- 手帳所持者の大部分(98.2%)が18歳以上であり、加齢による中途障害が増えています。
聴覚障害は外見から判別しにくく、また高齢化に伴う難聴(老人性難聴)は、手帳を取得しない軽度・中等度難聴者を含めると潜在的な数は膨大です。デフリンピックにおける「音声情報の文字化」等の技術は、これらすべての層に恩恵をもたらすユニバーサルデザインであることを強調し、予算獲得のロジックとすべきです。
予算規模と投資効果
東京都の予算案において、国際スポーツ大会等の開催経費として約227億円が計上されています。また、区市町村への支援として、スポーツ施設の改修や気運醸成事業への補助メニュー(数億円規模)が用意されています。
- 区市町村支援:
- 7億4,800万円(施設整備・気運醸成)
- パラスポーツ振興:
- 19億8,776万円
これらは「使い切るべき予算」です。特に、デフリンピック関連の啓発事業は、比較的採択されやすい傾向にあるため、各区の企画課は積極的に申請を行うべきです。
具体的政策提言:
特別区が今すぐ着手すべき4つの柱
以上の分析を踏まえ、各区が実行すべき具体的な政策を4つの柱に整理して提言します。
① ハード整備から「デジタル・バリアフリー」への転換(DX推進課・施設管理課向け)
物理的な段差解消(スロープ設置等)は一定程度進んでいます。次は「情報の段差解消」です。
- 窓口のDX:
- タブレット端末を活用した遠隔手話通訳サービスの導入。UDトーク等の音声認識アプリの公用端末への標準インストール。
- デジタルサイネージの活用:
- 区立施設や駅前のサイネージにおいて、緊急情報が文字と手話動画で表示されるシステムの構築。
- 根拠:
- 「Vision 2025」Action 1, 2 および 各区の手話言語・意思疎通条例。
② 「教育」を通じた次世代の心のバリアフリー化(教育委員会・学校向け)
子供たちの柔軟な感性に働きかける施策は、将来的な社会的コストを低減させる投資です。
- デフアスリート派遣:
- 中野区や渋谷区の事例を参考に、地域の小中学校へ選手を派遣し、交流授業を行う。
- 手話歌・サインエールの普及:
- 運動会や学芸会で手話を取り入れた演目を実施する。
- 根拠:
- 「Vision 2025」Action 5, 6、学習指導要領における特別活動・道徳の充実。
③ 地域経済と連動した「おもてなし」体制の構築(産業振興課・観光課向け)
デフリンピックは経済活動の機会でもあります。
- 商店街のバリアフリー化:
- 指差し会話シート(コミュニケーションボード)を区が作成し、商店街加盟店に配布する。筆談具の設置を助成する。
- ユニバーサルツーリズム:
- 区内の観光名所をろう者が案内するツアーの造成支援。
- 根拠:
- 「Vision 2025」Action 4。
④ 庁内横断プロジェクトチーム(PT)の結成(企画政策課向け)
縦割りの弊害を打破するため、期間限定のPTを結成する。
- メンバー構成:
- 障害福祉課(当事者支援)、スポーツ振興課(イベント)、教育委員会(学校連携)、情報政策課(DX)、産業振興課(地域連携)。
- ミッション:
- デフリンピックを契機とした「区内情報バリアフリー化計画」の策定と実行。新宿区のように、地域振興部と福祉部が連携窓口を持つ体制が望ましいです。
結論:2025年以降の東京を見据えて
東京2025デフリンピックは、12日間のスポーツイベントとして終わらせてはなりません。それは、「音声に頼らない社会インフラ」の実証実験の場であり、超高齢社会を迎える東京が持続可能な都市であるための**「生存戦略」**そのものです。
期待されるレガシー
- 社会的レガシー:
- 手話が当たり前に通じる社会、情報の保障が権利として確立された社会。
- 物理的レガシー:
- デジタル技術によって聴覚障害者と健常者がスムーズに対話できる窓口環境。
- 人的レガシー:
- ボランティア経験を通じて、障害当事者と自然に接することができるようになった区民たち。
職員へのエール
特別区職員の皆様におかれては、前例踏襲の壁を乗り越え、この「100年に一度」の機会を最大限に活用していただきたいと思います。予算要求のロジックは、本レポートに示した通り、「条例遵守」「都の方針との整合性」「客観的データに基づく課題解決」で強固に構築できます。
まずは、駒沢公園で開催されるプレイベントや、近隣のデフスポーツ大会に足を運び、音のない世界で繰り広げられる熱狂を肌で感じてほしい。その体験こそが、皆様の政策立案に魂を吹き込む最強の原動力となるはずです。