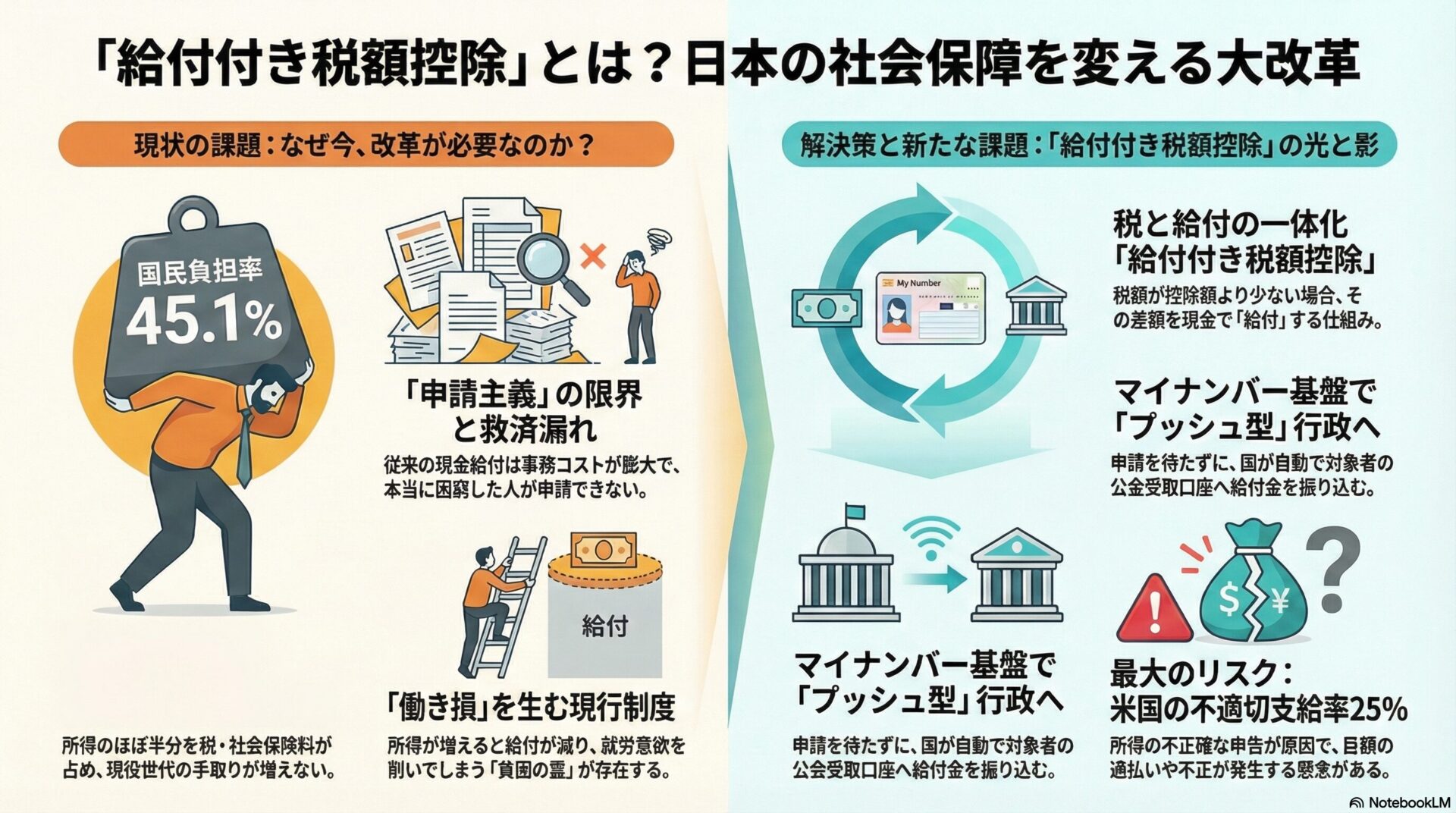【令和8年度政府予算概算要求】行政分野別 分析レポート(総務省)

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
令和7年8月に公表された「概算要求」について、「前年度(令和7年度)からの変化(新規・拡充など)」「政策立案への示唆」を試行的に追加しました。
(出典)総務省「概算要求(令和7年8月29日)」令和7年度
総務省 令和8年度概算要求の概要
第1 一般会計
- 令和8年度要求額
- 19兆884億円+事項要求
- 令和7年度予算額
- 19兆3,861億円
- 比較増減額
- ▲ 2,977億円
| 区分 | 令和8年度 要求額A | 令和7年度 予算額 B | 比較増減額 (A-B) C | 増減率 (C/B)% |
| 地方交付税等財源繰入れ | 186,096+事項要求 | 188,728 | ▲ 2,633 | 1.4 |
| 歳出 | ||||
| 一般 | 4,788+事項要求 | 5,133 | ▲ 345 | ▲ 6.7 |
| 恩給費 | 441 | 551 | 110 | 20.0 |
| 政策的経費 | 4,032+事項要求 | 4,582 | 549 | 12.0 |
| 重要政策の推進のための要望 | 315 | 315 | 皆増 | |
| 総務省所管合計 | 190,884+事項要求 | 193,861 | 2,977 | 1.5 |
注記事項
※計数はそれぞれ四捨五入しているため、積上げと合計、増減額及び増減率が一致しない場合がある。
第2 東日本大震災復興特別会計 ※総務省関係分
- 令和8年度要求額
- 2億円+事項要求
- 令和7年度予算額
- 667億円
- 比較増減額
- ▲ 665億円
| 区分 | 令和8年度 要求額 A | 令和7年度 予算額 B | 比較増減額 (A-B) C | 増減率 (C/B)% |
| 総務省所管計上額 (地方交付税) | 事項要求 | 659 | ||
| 復興庁所管計上額 | 2 | 9 | ▲ 7 | ▲ 72.7 |
| 総務省関係費合計 | 2+事項要求 | 667 | ▲ 665 | ▲ 99.6 |
注記事項
※計数はそれぞれ四捨五入しているため、積上げと合計、増減額及び増減率が一致しない場合がある。
重点事項
I 活力ある地域社会の実現と健全で持続可能な地方行財政基盤の確立 18兆6,481.2億円+事項要求
- 地域の担い手支援や関係人口の拡大等を通じた地域活性化 28.1億円+事項要求
- AI社会を支えるデジタルインフラの整備等 625.0億円+事項要求
- 地域DXの推進 866.9億円+事項要求
- 持続可能な地方行財政基盤の確立 2.3億円
- 地方の一般財源総額の確保と財政健全化等 18兆6,095.8億円+事項要求
II 信頼できる情報通信環境の整備
- デジタル空間の健全性の確保等 80.5億円
- サイバーセキュリティ対策の強力な推進 54.7億円+事項要求
III 防災・減災、国土強靱化の推進による安全・安心なくらしの実現
- 林野火災や大規模災害に備えるための消防防災力・地域防災力の充実強化 114.0億円+事項要求
- 通信・放送インフラの強靱化 70.9億円
IV 国際競争力の強化・経済安全保障の確保
- デジタルインフラの中核となる技術・システムの国際競争力の強化、経済安全保障の確保等 576.3億円+事項要求
- 国内外におけるAIガバナンスの実現 4.7億円
- 放送・配信コンテンツの製作力強化・海外展開推進 16.3億円
V 国の土台となる社会基盤の確保
- 郵便局のユニバーサルサービスの充実と公共サービスの拡大 0.4億円
- 郵便局の活用による地域社会の持続可能性の確保 1.7億円
- 行政運営の改善を通じた行政の質の向上 3.0億円
- EBPMの推進及び基盤となる統計の整備 288.5億円
- 主権者教育の推進・政治資金の透明性の向上等 2.3億円
- 恩給の適切な支給 446.7億円
- その他の主要事項(政党交付金) 315.4億円
令和8年度総務省所管予算概算要求における主な事業
I 活力ある地域社会の実現と健全で持続可能な地方行財政基盤の確立
地域の担い手支援や関係人口の拡大等を通じた地域活性化
- 【新規】ふるさと住民登録制度の創設 事項要求
- 地方創生2.0の実現に向けて、関係人口の量的拡大・質的向上を図るため、様々な形で地域に継続的に関わる方がアプリで簡単・簡便に登録でき、担い手活動等を通じて地域との関わりを深めるプラットフォームとなるシステムの構築や周知・広報等を実施 (プラットフォームとなるシステムについては、デジタル庁一括計上予算で要求予定) 1111
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 人口減少が続く地方において、定住・移住だけでなく、多様な形で地域に関わる「関係人口」を地域活性化の重要な担い手と位置づけ、その関与を促進・可視化するため。
- 行政側の意図
- デジタルなプラットフォームを通じて関係人口との接点を継続的に確保し、地域の担い手としての活動を促すことで、将来的な移住や地域課題解決への協力を引き出す狙いがある。
- 期待される効果
- 関係人口の増加による地域経済の活性化や、新たな地域づくりのアイデア・人材の獲得が期待される。
- 特別区への示唆
- 特別区においても、区外へ転出した元住民や区内に勤務する人々を「関係区民」と捉え、地域の祭りやボランティア活動への参加を促す仕組みは、コミュニティ活性化に有効である。
AI社会を支えるデジタルインフラの整備等
- 【拡充】データセンター、海底ケーブル/5G、光ファイバ等の通信インフラ整備 77.6億円+事項要求 (R7当初:39.9億円、R6補正:145.3億円)
- データセンターの地方分散、国際海底ケーブルの多ルート化に向けた支援(ワット・ビット連携)や、5G、光ファイバ等の情報通信インフラの整備を推進 2
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 東京圏に集中するデータセンターの災害リスクを低減し、国内のどこにいても安定したデジタルサービスを利用できる環境を構築するため、国土全体の強靭性を高める必要があるから。
- 行政側の意図
- デジタルインフラを地方に分散させることで、首都直下地震等の大規模災害時におけるデータ滅失や通信途絶のリスクを軽減し、国の経済安全保障を確保する意図がある。
- 期待される効果
- 通信インフラの信頼性向上や、地方におけるデジタル関連産業の誘致・雇用創出が期待される。
- 特別区への示唆
- 区の基幹システムや区民の重要データを扱う際は、地方に分散立地されたデータセンターの活用を検討するなど、業務継続計画(BCP)におけるリスク分散の観点がより重要になる。
地域DXの推進
- 【拡充】マイナンバーカードを円滑に取得、更新できる環境整備 823.9億円 (R7当初:203.5億円、R6補正:1,061.5億円)
- マイナンバーカードや電子証明書の更新需要の増加への対応や出張申請受付等の推進など、カードの取得を希望する国民に対する円滑な取得環境・交付体制を整備
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- デジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの普及と利活用を一層推進するため、国民がストレスなくカードを取得・更新できる体制を、行政サービスの最前線である自治体で構築する必要がある。
- 行政側の意図
- カードの交付体制を強化することで、今後の運転免許証との一体化など、さらなる機能拡充に備えるとともに、オンラインでの行政手続利用率の向上を加速させる狙いがある。
- 期待される効果
- 区民の利便性向上に加え、窓口業務の効率化や行政手続のオンライン化が進むことが期待される。
- 特別区への示唆
- 今後本格化するカード更新需要に対し、臨時窓口の開設や出張申請サポートの拡充は必須。区民への丁寧な周知と、円滑な交付体制の構築・人員確保が急務となる。
- 【拡充】自治体情報システムの標準化 3.1億円+事項要求 (R7当初:2.1億円、R6補正:194.8億円)
- 自治体情報システムに係る標準準拠システムへの移行に必要となる経費(現行システムの分析、データ移行等)を地方自治体に補助するため、デジタル基盤改革支援基金を拡充
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 各自治体が個別にシステムを開発・運用する非効率を解消し、国全体の行政コスト削減と住民サービスの迅速な提供を実現するため、システムの標準化・共通化が不可欠であるから。
- 行政側の意図
- システム移行に伴う自治体の財政的・技術的負担を軽減し、国が定めた期限内での円滑な移行を確実に実行させる意図がある。これにより、国主導の制度改正にも迅速に対応できる体制を整える。
- 期待される効果
- 自治体のシステム運用コスト削減、迅速な法改正への対応、職員の業務負担軽減などが期待される。
- 特別区への示唆
- 標準化は、単なるシステム更新ではなく、業務プロセス全体を見直す好機。移行を機に、部署間のデータ連携のあり方や、より効率的な業務フローの構築を検討すべきである。
- 【拡充】AI等のデジタル技術と通信インフラを用いた地域の社会課題解決の推進 21.1億円 (R7当初:2.3億円、R6補正:74.0億円)
- AI等のデジタル技術と通信インフラを活用した地域課題解決策の創出・実装を支援
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 人口減少や高齢化といった地域社会が抱える複雑な課題に対し、従来の手法だけでは対応が困難であり、AI等の先端技術を活用した新たな解決モデルを創出・普及させる必要があるため。
- 行政側の意図
- 先進的なモデル事業を支援し、成功事例を創出することで、他地域への横展開を促す狙いがある。これにより、国全体の課題解決能力の底上げとデジタル実装の加速を目指す。
- 期待される効果
- 行政サービスの効率化、新たな住民サービスの創出、地域課題解決の精度向上が期待される。
- 特別区への示唆
- 交通、防災、福祉など、特別区が抱える多様な都市課題の解決にAIを活用するチャンス。国の支援制度を活用し、民間企業と連携した実証実験などを積極的に企画・検討すべきである。
地方の一般財源総額の確保と財政健全化等
- 地方の一般財源総額の確保 18兆6,095.8億円+事項要求 (R7当初:18兆8,728.4億円)
- 地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2025年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保(経済・物価動向等を適切に反映)
- [地方交付税(地方団体交付ベース) 19兆3,367億円(R7当初:18兆9,574億円)]
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 物価高騰や社会保障費の増大など、地方自治体を取り巻く財政環境が厳しさを増す中で、行政サービスを安定的に提供できるよう、国が財源を保障する必要があるため。
- 行政側の意図
- 地方財政の安定性を確保することで、自治体が中長期的な視点に立った政策を展開できる環境を整える意図がある。国の重要政策を地方で着実に実施させるための基盤でもある。
- 期待される効果
- 各自治体における安定した財政運営と、住民への継続的な行政サービスの提供が可能となる。
- 特別区への示唆
- 地方交付税に頼らない特別区においても、国の財政動向は重要。特に物価高騰等を反映した財源確保の動きは、次年度の予算編成における人件費や物件費の積算の参考となる。
II 信頼できる情報通信環境の整備
デジタル空間の健全性の確保等
- 【拡充】インターネット上の偽・誤情報、違法・有害情報対策等の推進 29.2億円 (R7当初:8.5億円、R6補正:29.2億円)
- インターネット上の偽・誤情報等の流通・拡散に対応するため、対策技術の開発・実証・社会実装及び意識啓発を推進
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 偽・誤情報が社会的な混乱や人権侵害を引き起こすリスクが増大しており、民主主義の健全な運営を維持するためにも、国として対策を講じる必要性が高まっているから。
- 行政側の意図
- 技術開発とリテラシー向上の両面から対策を進めることで、表現の自由を確保しつつ、偽・誤情報の流通による社会的な弊害を抑制し、健全なデジタル空間を確保することを目指す。
- 期待される効果
- 国民が情報を見極める能力の向上や、偽情報の拡散を抑制する技術の社会実装が進む。
- 特別区への示唆
- 災害時におけるデマの拡散防止や、区政に関する誤った情報への迅速な対応が重要。区民向けのリテラシー向上講座の開催や、公式サイト・SNSでの正確な情報発信を強化すべきである。
サイバーセキュリティ対策の強力な推進
- 【拡充】行政機関や重要インフラ事業者等を対象とした高度セキュリティ人材の育成 17.5億円 (R7当初:12.5億円)
- 行政機関や重要インフラ事業者等を対象とした実践的サイバー防御演習を行うとともに、新たに被害の未然防止に関する演習基盤を構築 9999
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- サイバー攻撃の巧妙化・高度化に伴い、行政や社会インフラが停止するリスクが増大している。有事の際に適切に対応できる専門人材の育成は、国の安全保障上、喫緊の課題であるため。
- 行政側の意図
- 実践的な演習を通じて、インシデント発生時の対応能力を向上させるとともに、攻撃を未然に防ぐプロアクティブな防御体制の構築を担う人材を組織的に育成する狙いがある。
- 期待される効果
- 行政機関や重要インフラのサイバー攻撃への耐性向上、インシデント発生時の迅速な復旧が期待される。
- 特別区への示唆
- 特別区においても、職員を国の研修へ積極的に派遣するとともに、区独自のサイバーセキュリティ演習を定期的に実施し、組織全体の対応能力を維持・向上させることが不可欠である。
III 防災・減災、国土強靱化の推進による安全・安心なくらしの実現
林野火災や大規模災害に備えるための消防防災力・地域防災力の充実強化
- 【新規】林野火災や大規模災害に備えるための消防防災力の充実強化 4.4億円+事項要求
- 広域的な消防防災体制の充実強化を図り、林野火災や大規模災害に備えるため、令和7年に発生した大規模な林野火災等を踏まえた緊急消防援助隊の新たな車両・資機材等の整備等を実施
政策立案への示唆
- この取組を行行政が行う理由
- 近年の気候変動の影響により、林野火災が大規模化・長期化する傾向にある。既存の消防力だけでは対応が困難な事態に備え、国のレベルで広域応援体制を強化する必要があるため。
- 行政側の意図
- 特定の災害に特化した最新の資機材を緊急消防援助隊に配備することで、国全体の特殊災害への対応能力を向上させ、被害の極小化を図ることを意図している。
- 期待される効果
- 林野火災等の特殊災害発生時における迅速な消火活動と、延焼被害の抑制が期待される。
- 特別区への示唆
- 特別区では林野火災のリスクは低いが、大規模市街地火災やNBC災害など、特殊な資機材を要する災害は起こりうる。国の動向を踏まえ、東京消防庁との連携や必要な資機材の整備計画を確認することが重要。
- 【拡充】消防防災分野の新技術・DX推進 5.0億円+事項要求 (R7当初:6.5億円、R6補正:22.2億円)
- 南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの大規模地震を想定した災害対応力の強化、風水害等をはじめとする災害の激甚化・頻発化、社会経済活動など消防を取りまく環境の変化への対応を図るため、消防分野において新たな研究開発・実用化や現場導入を推進
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 災害の激甚化や複雑化に対し、消防隊員の安全を確保しつつ、より効果的・効率的な災害対応を行うため、ドローンやAIなどの新技術の導入とデジタル化(DX)の推進が不可欠だから。
- 行政側の意図
- 研究開発から現場への導入までを一体的に支援することで、革新的な消防防災技術の社会実装を加速させ、将来起こりうる大規模災害に備える消防力の質的向上を目指している。
- 期待される効果
- 災害情報の迅速な収集・分析、救助活動の効率化、隊員の二次災害防止などが期待される。
- 特別区への示唆
- 国の研究開発の動向を注視し、開発された新技術をいち早く現場に導入するための検討(予算確保、職員研修等)を進めるべき。特に、人口密集地での活用が期待される技術は要注目。
通信・放送インフラの強靱化
- 【拡充】通信ネットワークの強靱化 35.1億円 (R7当初:25.9億円、R6補正:21.2億円)
- 蓄電池、発電機等を活用した災害時における携帯電話基地局の強靭化を推進
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 災害時において、住民の安否確認や避難情報の伝達に不可欠な通信手段を確保するため。特に、能登半島地震の教訓から、電源喪失による基地局の機能停止を防ぐ必要性が高まった。
- 行政側の意図
- 通信事業者によるインフラ強靭化の取組を国が財政的に支援することで、全国の基地局の耐災害性向上を加速させ、災害時における通信の途絶リスクを最小限に抑える狙いがある。
- 期待される効果
- 大規模停電が発生した際の携帯電話の通信可能エリア維持と、通信サービスの早期復旧が期待される。
- 特別区への示唆
- 区内に立地する携帯電話基地局の耐災害性について、通信事業者と情報を共有し、把握しておくことが重要。また、避難所等における非常用電源の確保・強化を再点検すべきである。
- 【拡充】放送ネットワークの強靱化 35.7億円 (R7当初:29.0億円、R6補正:22.0億円)
- 放送ネットワークの耐災害性の強化や災害からの早期復旧の支援・視聴環境の整備等を実施
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- テレビやラジオは、特に高齢者などデジタルに不慣れな層にとって、災害時に命を守るための重要な情報源であり、その伝達手段を確実に維持・確保する必要があるため。
- 行政側の意図
- 放送事業者の中継局等のインフラ強靭化を支援することで、災害時でも放送が途絶することなく、地域住民に正確な災害情報が継続的に提供される体制を全国的に構築することを目指す。
- 期待される効果
- 災害時における情報伝達の安定化と、住民の迅速な避難行動への貢献が期待される。
- 特別区への示唆
- コミュニティFMなど、地域に密着した放送手段の耐災害性強化も重要。国の支援策も視野に入れつつ、地域放送事業者と連携した防災情報伝達体制の強化を検討すべきである。
IV 国際競争力の強化・経済安全保障の確保
デジタルインフラの中核となる技術・システムの国際競争力の強化、経済安全保障の確保等
「DX・イノベーション加速化プラン2030」の着実な実施
- 【拡充】オール光ネットワーク技術等の次世代情報通信基盤の研究開発・国際標準化・社会実装・海外展開の加速等 185.3億円 (R7当初:184.3億円、R6補正:495.0億円)
- オール光ネットワーク※1を中核とする次世代情報通信基盤、AI、量子暗号通信※2の早期実現に向けた研究開発・国際標準化を支援
- ※1 光の特性を最大限に活用した、低遅延・高信頼・低消費電力のネットワーク
- ※2 盗聴を確実に検知できる、量子コンピュータ時代でも安全な暗号方式 16
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 今後の社会経済活動を支える次世代情報通信基盤(Beyond 5G/6G)の分野で、日本が国際的な主導権を確保するため。技術開発から国際標準化、海外展開までを一体的に推進する必要がある。
- 行政側の意図
- 国の経済安全保障を強化するとともに、新たな成長産業を創出する狙いがある。特に、低消費電力化は、脱炭素社会の実現にも貢献する重要な要素と位置づけている。
- 期待される効果
- 日本の技術的優位性の確立、新たな国際市場の獲得、国内の通信環境の高度化が期待される。
- 特別区への示唆
- 将来のスマートシティ化を見据え、次世代通信基盤がもたらす新たなサービス(自動運転、遠隔医療等)を区政にどう取り込むか、長期的な視点での検討を開始すべき時期にある。
- 【拡充】デジタルインフラの海外展開支援 30.2億円 (R7当初:13.2億円、R6補正:63.0億円)
- 経済安全保障の確保に資するデジタルインフラの海外展開について、調査・実証事業等を実施
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 日本の質の高いデジタルインフラ技術をパッケージで海外に展開し、相手国の社会課題解決に貢献するとともに、日本の経済成長につなげるため。経済安全保障の観点からも重要である。
- 行政側の意図
- 政府がトップセールスや調査・実証事業を支援することで、民間企業だけでは乗り越えにくい海外展開のリスクを低減し、日本企業の国際競争力を後押しする意図がある。
- 期待される効果
- インフラ関連産業の海外受注拡大と、友好国との経済関係強化が期待される。
- 特別区への示唆
- 直接的な関わりは少ないが、区内企業の海外展開支援策の一環として、こうした国の動きを情報提供することは有益。また、海外都市との交流事業において、テーマとして活用できる可能性がある。
- 【新規】低軌道衛星コンステレーションを活用した衛星通信の自律性向上 事項要求
- 海外勢に依存している低軌道衛星コンステレーション※3による通信サービスについて、我が国の自律性向上のため、インフラ整備を支援
- ※3 Satellite Constellation(直訳:衛星一群)。低軌道に打ち上げた多数の非静止衛星を連携させたシステム
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 災害時の通信確保や、山間部・離島など地上網の整備が困難な地域の通信手段として期待される衛星通信サービスを、海外事業者に依存する現状は経済安全保障上のリスクであるため。
- 行政側の意図
- 国内の技術・インフラ整備を支援することで、衛星通信分野における日本の自律性を高め、いかなる状況下でも国民生活や経済活動に必要な通信を確保できる体制を構築する狙いがある。
- 期待される効果
- 災害に強い通信網の構築、国内宇宙産業の活性化、通信サービスの選択肢拡大が期待される。
- 特別区への示唆
- 大規模災害による地上通信網の途絶に備え、衛星通信サービスを区役所や避難所のバックアップ回線として導入することを検討すべき。国の技術開発動向を注視する必要がある。
放送・配信コンテンツの製作力強化・海外展開推進
- 【拡充】放送・配信コンテンツの製作力強化・海外展開推進 16.3億円 (R7当初:2.9億円、R6補正:22.7億円)
- 放送・配信コンテンツの企画開発・製作・権利処理・流通フェーズ等の課題改善に向けた取組をパッケージとして実施
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 日本の魅力的な文化や価値観を発信する上で重要な役割を担う放送コンテンツの国際競争力を高め、クールジャパン戦略の中核として、国のブランドイメージ向上と経済効果を狙うため。
- 行政側の意図
- コンテンツ製作の各段階(企画、製作、権利処理、流通)における課題を一体的に支援することで、製作から海外展開までの好循環を生み出し、産業全体の成長を促進する意図がある。
- 期待される効果
- 高品質なコンテンツの増加、海外での日本コンテンツの視聴機会拡大、関連産業の活性化が期待される。
- 特別区への示唆
- 区の魅力を発信するシティプロモーションにおいて、動画コンテンツの活用は有効。国の支援策の動向は、映像制作会社等との連携や、より質の高いプロモーション動画を企画する上で参考になる。
V 国の土台となる社会基盤の確保
郵便局の活用による地域社会の持続可能性の確保
- 【拡充】郵便局の「コミュニティ・ハブ」としての活用推進 1.7億円 (R7当初:1.5億円)
- 地域に残り続ける郵便局を「コミュニティ・ハブ」として活用するため、複数郵便局を対象とした広域型を重点化して各種サービスの実証を実施
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 人口減少地域において、行政窓口や民間サービスが縮小する中、全国に遍在する郵便局ネットワークを行政サービスや生活支援の拠点として活用し、住民の利便性を維持するため。
- 行政側の意図
- 郵便局が持つ拠点性や住民からの信頼性を活かし、行政サービスの補完や新たな地域サービスの創出拠点としての可能性を探る。これにより、持続可能な地域社会の実現を目指す。
- 期待される効果
- 住民の利便性向上、行政コストの効率化、郵便局ネットワークの維持・活用が期待される。
- 特別区への示唆
- 高齢化が進む地域において、身近な郵便局で一部の行政手続や相談が可能になれば、住民の利便性は大きく向上する。区内の郵便局と連携したモデル事業の検討は価値がある。
EBPMの推進及び基盤となる統計の整備
- 【拡充】令和8年経済センサス-活動調査など社会・経済実態の把握に資する統計調査等の実施 282.5億円 (R7当初:823.3億円、R6補正:296.6億円)
- 「令和8年経済センサス-活動調査※4」等の5年に一度行うこととされている周期統計調査の実施等
- ※4 我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得るための調査
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 客観的な証拠に基づく政策立案(EBPM)を推進するためには、その基礎となる正確で信頼性の高い統計データが不可欠。特に経済センサスは、日本の経済構造を網羅的に把握する最重要の調査である。
- 行政側の意図
- 全ての事業所・企業の活動実態を詳細に把握することで、国や地方自治体が、より実態に即した効果的な産業振興策や地域経済政策を立案・評価できるデータ基盤を提供する狙いがある。
- 期待される効果
- 政策の精度向上、行政の透明性確保、国民や事業者への説明責任の向上が期待される。
- 特別区への示唆
- 経済センサスの結果は、区内の産業構造や経済動向を把握するための貴重なデータソース。調査結果を詳細に分析し、区の産業振興計画や商店街支援策などの見直しに活用すべきである。
まとめ
【総括】令和8年度概算要求のポイントと特別区への示唆
令和8年度の総務省概算要求は、近年の大規模災害や社会情勢の変化を強く意識し、「強靭化」と「新たな連携」を二つの大きな柱として推進する姿勢が明確に示されています。特に、能登半島地震の教訓を踏まえた防災対策の抜本的な強化と、デジタル技術を駆使した地域課題解決への投資が際立っています。これは、日本の行政が直面するリスクへの対応力向上と、持続可能な社会基盤の構築を急ぐ国の強い意志の表れです。
特別区の職員にとっては、これらの国の大きな潮流を的確に捉え、自身の業務や政策にどう結びつけるかが、次年度の事業計画を策定する上で極めて重要になります。以下に、主要なポイントと特別区への具体的な示唆をまとめます。
1. デジタルと防災における「国土強靭化」の加速
今回の概算要求で最も象徴的なのは、デジタルインフラと防災体制の強靭化に向けた大幅な予算拡充です。
- 国の動向:
能登半島地震で露呈した通信インフラの脆弱性への反省から、携帯電話基地局の電源強化や衛星通信の活用といった「通信の途絶を防ぐ」ための予算が重点的に配分されています。また、東京圏に一極集中するデータセンターを地方へ分散させることで、首都直下地震等の大規模災害に備える「デジタル版国土強靭化」も本格化しています。サイバーセキュリティ分野においても、実践的な演習基盤を新たに構築するなど、人材育成がさらに強化されています。 - 特別区への示唆:
これらの動きは、特別区に対して自らの業務継続計画(BCP)の再点検を強く促すものです。区の基幹システムや区民の重要データを、地方に新設されるデータセンターへバックアップする等のリスク分散策は、今後必須の検討事項となります。また、災害時における情報伝達手段として、地上通信網が途絶する事態を想定し、衛星通信を活用した連絡体制の構築や、地域FM局との連携強化など、通信手段の多重化を具体的に進める必要があります。
2. AI活用と「関係人口」に着目した地域づくりの新展開
人口減少社会への対応として、AI等の先端技術活用と、地域との新たな関わり方を模索する動きが鮮明になっています。
- 国の動向:
AI等のデジタル技術を活用した地域課題解決への支援が大幅に拡充され、国が成功事例の創出と横展開を後押しする姿勢が明確です。また、新たに「ふるさと住民登録制度」が創設されることは注目に値します。これは、移住・定住だけでなく、地域に多様な形で関わる「関係人口」を正式なパートナーとして位置づけ、その力を地域活性化に活かそうという、新しい地域づくりの哲学を示すものです。 - 特別区への示唆:
「関係人口」の考え方は、地方だけの課題ではありません。特別区においても、区外へ転出した元住民や、区内に通勤・通学する人々を「関係区民」と捉え、地域のイベントや防災訓練、オンラインコミュニティへの参加を促す施策は、新たな地域活力の創出につながります。国のAI関連の支援制度は、福祉、交通、ごみ問題といった都市部特有の課題解決にも応用可能です。これらの制度を積極的に活用し、民間企業と連携した実証実験などを企画することで、より質の高い区民サービスの実現が期待できます。
今回の概算要求は、特別区がこれまで以上に「災害への備え」と「デジタル技術による変革」を自区の政策の中心に据えるべきであることを示唆しています。国の大きな政策の潮流を追い風とし、より安全で持続可能なまちづくりを主導していくことが、これからの特別区の職員に求められています。