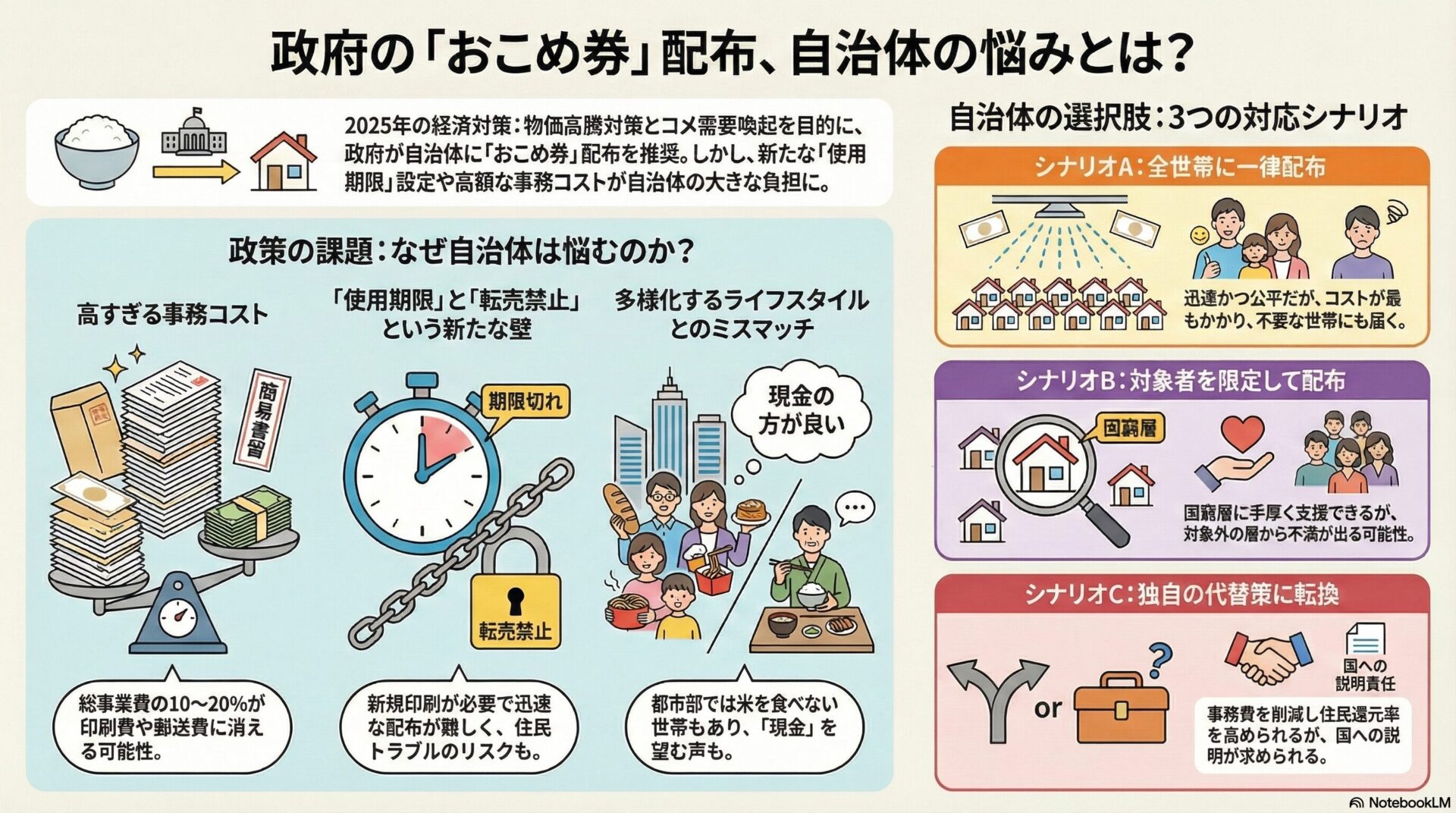【令和8年度政府予算概算要求】行政分野別 分析レポート(デジタル庁)

はじめに
※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。
※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。
※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。
※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。
令和7年8月に公表された「概算要求」について、「前年度(令和7年度)からの変化(新規・拡充など)」「政策立案への示唆」を試行的に追加しました。
(出典)デジタル庁「概算要求(令和7年8月29日)」令和7年度
デジタル庁 令和8年度概算要求の概要
未来を担うこどもたちのための保育の質の向上等
保育の質の向上等
子どものための教育・保育給付交付金 [1兆8,380億円+事項要求]
- 事業の目的
- 子ども・子育て支援法に基づき、市町村が支給する施設型給付費等の支給に要する費用の一部を負担することにより、子どもが健やかに成長するように支援することを目的とする。
- 事業の概要
- 教育・保育給付認定を受けた小学校就学前の子どもが、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業等)を利用する際に施設型給付費等を支給する市町村に対し、支給に必要な費用の一部を負担するため交付金を交付する。
- 【主な事項要求】
- 社会保障の充実
- 令和8年度に実施する「量的拡充」及び「質の向上」に必要な経費について確保する(消費税引上げ以外の財源も含む)。
- 新しい経済政策パッケージの実施
- 「新しい経済政策パッケージ」に基づく幼児教育・保育の無償化等については、予算編成過程において検討する。 等
- 社会保障の充実
- 併せて「こども未来戦略」に基づき、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善を進める。
- 実施主体等
- 【実施主体】 市町村
- 【負担割合】
- 施設型給付(私立):国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4
- 地域型保育給付(公私共通):国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4
- ※公立の施設型給付については、地方交付税により措置
- ※0~2歳児相当分については、事業主拠出金の充当割合を控除した後の負担割合
- ※1号給付に係る国・地方の負担については、経過措置あり 【拡充】 7年度の1兆8,002億円から増額されており、保育現場の処遇改善や質の向上への取り組みが継続・強化されています。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 子育て世帯の経済的負担を社会全体で支え、全ての子供に質の高い教育・保育の機会を保障するため、地方自治体の財政を国が支援する必要があるから。
- 行政側の意図
- 幼児教育・保育の安定的な提供体制を全国で維持し、待機児童問題の解消や保育の質の向上、保育士の処遇改善を財政面から後押しする狙いがある。
- 期待される効果
- 子育て世帯の負担軽減と、保育サービスの安定供給・質の向上が期待される。
- 特別区への示唆
- 国・都からの安定財源を前提に、保育ニーズの多様化に対応した施設整備や、保育士の確保・定着に向けた独自の処遇改善上乗せ策などを検討すべき。
【新規】乳児等のための支援給付交付金(こども誰でも通園制度) [事項要求]
- 事業の目的
- 子ども・子育て支援法に基づき、市町村が支給する乳児等のための支援給付の支給に要する費用を負担することにより、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする。
- 事業の概要
- 【対象児童】 保育所、認定こども園、地域型保育施設、企業主導型保育施設に在籍していない生後6か月から満3歳未満のこども
- 【実施事業所】 保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター 等において設備運営基準を満した事業所
- 【実施方法】 一般型又は余裕活用型
- 【単 価】 内閣府令で定める予定の月の利用可能時間を上限とした上で、こども一人1時間当たりの単価を設定。(予算編成過程において検討)加えて、障害児、要支援家庭のこども、医療的ケア児を受け入れる場合の加算の他、必要な加算についても検討する。
- 実施主体等
- 【実施主体】 市町村
- 【負担割合】 支援納付金:1/2 国:1/4 都道府県:1/8 市町村:1/8 【新規】 7年度にはなかった「こども誰でも通園制度」の本格実施に向けた給付金であり、8年度から新たに追加されました。自治体においても制度開始に向けた準備が必要です。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 従来の保育制度ではカバーしきれない、在宅で子育てをする家庭の孤立化防止やリフレッシュニーズに応えるため、新たな支援の枠組みが必要だから。
- 行政側の意図
- 専業主婦(夫)家庭や短時間就労家庭など、全ての家庭に保育サービスへのアクセスを提供し、子育て支援の公平性を確保し、こどもの育ちを社会全体で支える狙い。
- 期待される効果
- 親の育児負担軽減とこどもの発達支援、潜在的な虐待リスクの早期発見が期待される。
- 特別区への示唆
- 都市部の多様な保育ニーズに対応するため、既存の保育施設に加え、地域の子育て支援拠点など多様な事業者の参入を促し、柔軟な受け入れ体制を構築することが重要。
【拡充】【一部推進枠】子ども・子育て支援全国総合システム等情報公表事業 [10億円]
- 事業の目的
- 子ども・子育て支援法第58条の規定に基づく特定教育・保育施設等の情報公表及び幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設等の情報公表について、全国の施設・事業情報をインターネット上で直接検索・閲覧できる環境を構築し、安定した運用を行うことを目的とする。
- 令和8年度においては、「こども誰でも通園制度」・「小規模保育(3歳~5歳)」を施設種別に追加、見える化の報告様式や登録機能の改善(施設から改善要望等のあった事項等)、他システム(保育業務施設管理プラットフォーム等)との連携改善、認可外保育施設等の登録過程改善及び第三者評価等の公表項目の改善のための改修を行う。
- 実施主体等
- 【実施主体】 独立行政法人福祉医療機構 【拡充】 7年度の2億円から大幅に増額されています。「こども誰でも通園制度」の開始に伴うシステム改修が主な要因であり、情報公表の範囲が拡大されます。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 保護者が保育サービスを選択する際に必要な情報を公平かつ網羅的に提供し、ミスマッチを防ぐとともに、事業者の透明性を確保する必要があるため。
- 行政側の意図
- 「こども誰でも通園制度」の開始に伴い、対象施設の情報も公表することで、利用者の利便性を高め、新制度の円滑な利用を促進する狙いがある。
- 期待される効果
- 保護者の施設選択の利便性向上と、保育サービスの質の見える化が期待される。
- 特別区への示唆
- 国が整備するシステムと連携しつつ、区独自の詳細情報(空き状況、特色ある取り組み等)を発信するプラットフォームを整備・充実させることが望ましい。
【新規】ミドルリーダーの活躍による保育の質向上推進事業 [1億円]
- 事業の目的
- 各園における保育の質向上を図っていくためには、園内研修や公開保育等の取組など、保育所・認定こども園等の保育者が保育実践を互いに見合い学び合う取組を推進することが重要である。また、地域に開かれた保育を進め、互いの保育実践を見合い意見交換等を進めたり、有識者等からの助言等を受けたりする中で、自園や保育者自身の保育の良さや課題を見直し改善していく機運の醸成を図っていくことが求められる。このため、自園や他園の園内研修・公開保育などの企画・実施を行うことができるドルリーダーの育成、園・保育士同士の学び合いを中心とした協働的な取組を推進し、各園ひいては地域全体の保育の質向上を図る。
- 事業の概要
- 自治体において、地域で中核となって保育所や認定こども園等における保育の質向上に取り組むことが期待されるミドルリーダーを募り、参加するミドルリーダー同士の学び合いによる資質向上や、当該ミドルリーダーが勤務する園はもとより、自園以外の保育所や認定こども園等における保育の質向上に向けた取組の支援、それらの勤務園でのフィードバック等の取組に要する費用の一部を支援する。
- (支援経費の例)
- ミドルリーダーに対する研修の実施経費
- ミドルリーダーが保育現場を不在にすることに伴う雇上げ費用
- ミドルリーダーによる他園への園内研修や公開保育等の支援に関する費用
- 外部有識者の協力を得た園内研修・公開保育等の実施費用 等
- 実施主体等
- 【実施主体】 都道府県又は市町村
- 【補助基準額】 1自治体当たり500万円
- 【補助割合】 国:1/2、都道府県・市町村:1/2 【新規】 7年度には見られなかった事業で、保育現場の中核を担うミドルリーダー層の育成に特化した支援策として8年度に新設されました。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 個々の保育施設の努力だけでは限界がある保育の質の向上を、地域全体で体系的に推進するため、施設間連携の中核となる人材を育成する必要があるから。
- 行政側の意図
- 各園に保育の質の向上を担うリーダーを配置し、園内研修の活性化や園同士の連携を促すことで、ボトムアップでの質向上サイクルを生み出す狙いがある。
- 期待される効果
- 地域全体の保育の質の平準化と向上が期待される。
- 特別区への示唆
- 区内の保育施設間の連携を促進するハブとして本事業を活用し、ミドルリーダーのネットワークを構築し、先進的な保育実践の共有や合同研修を企画することが有効。
【拡充】地域における保育の質の向上の体制整備調査研究 [0.6億円]
<子ども・子育て支援推進調査研究・普及促進事業>
- 事業の目的
- 地域の実情を踏まえつつ、自治体が中核となり、地域全体で保育の質の確保・向上を推進する体制整備のモデル開発を行い、地域ぐるみで質の高い保育を保育所等が行うことができる体制の構築を推進する。
- 事業の概要
- 都道府県等から3年程度モデル地域を継続的に指定し、地域単位で、保育内容に関する課題の把握、地域における保育実践・改善に関する指導助言、研修等の企画立案等を担う中核的機能を構築し、域内の保育所等の保育の質の確保・向上のための取組を進めつつ、持続的に地域全体で保育の質を確保・向上させるための仕組みのモデル開発を行う。
- (中核的機能の例)
- 保育指導職の配置
- 幼児教育センターや大学等との連携等による保育の質の確保・向上のための地域のネットワークの形成
- (想定される取組の例)
- 地域の課題を踏まえた独自の研修の実施
- 公開保育による交流の機会の創出
- 公立園の拠点化
- 法人をまたぐ施設間の職員の交流等
- 実施主体等
- 【実施主体】
- ①都道府県、指定都市・中核市、10万人程度以上の市町村(計6箇所程度 ※令和7年度に指定を受けているものを優先する)
- ②上記以外の市町村(計4箇所程度)【拡充】
- 【委託基準額】
- ①都道府県等1か所当たり800万円程度、②市町村1か所当たり400万円程度 【拡充】 7年度の0.5億円から増額され、対象となる市町村の範囲が拡大(②の追加)されており、より多くの自治体が活用できる可能性があります。
- 【実施主体】
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 保育の質は地域全体の課題であるとの認識のもと、自治体が司令塔となり、大学等の外部機関とも連携して、質の向上を推進する体制のモデルを構築するため。
- 行政側の意図
- 自治体主導で地域全体の保育の質を向上させる仕組みを確立し、その成功モデルを全国に展開することで、国全体の保育水準を引き上げることを目指している。
- 期待される効果
- 持続可能な保育の質の向上サイクルの構築と、地域格差の是正が期待される。
- 特別区への示唆
- 大学や専門機関が多いという地域特性を活かし、連携体制のモデル地域となることを目指せる。公立保育園を地域全体の質向上の拠点として位置づけることも有効。
【新規】保育所等における第三者評価改善モデル事業 [0.2億円]
- 事業の目的
- 保育所や認定こども園等においては、保育の質の向上を図っていく上で、自己評価の取組に加え、より多様な視点を取り入れる観点から、第三者評価を活用することが重要。第三者評価の結果を保護者や地域と共有することは、協働体制の構築にも資する。
- 一方、第三者評価については、必ずしも保育そのものの改善に十分に踏み込めていないといった指摘もある。
- こうしたことを踏まえ、第三者評価の改善を図り、それを活用した各保育所や認定こども園等の保育の質の向上の取組を推進する。
- 事業の概要
- 都道府県等から3年程度モデル地域を継続的に指定し、国内の質評価スケール等(※)を活用した第三者評価の実施、当該評価を活用した保育実践の見直し・改善、保育士等や評価者の育成等について、モデル開発を行う。
- ※国立教育政策研究所幼児教育研究センターが開発した「幼児教育における保育実践の質評価スケール案」等
- 【主な調査研究の観点(例)】
- 実施体制、評価機関の認証
- 実施園へのフィードバック、保育の改善
- 自己評価との関連付け
- 評価の公表
- 監査との役割分担
- 評価者の育成
- 【対象施設】
- 保育所、認定こども園、地域型保育事業 等
- 実施主体等
- 【実施主体】 都道府県・市町村
- 【委託基準額】 都道府県等1か所当たり 500万円程度 【新規】 7年度にはなかった事業で、第三者評価の質の改善と活用促進に焦点を当てたモデル事業として新たに開始されます。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 現行の第三者評価が形式的なものに留まっているとの課題認識から、より保育現場の質の改善に実質的に寄与する評価制度へと転換を図る必要があるため。
- 行政側の意図
- 評価結果が具体的な保育実践の改善に繋がるような、新たな評価手法や評価者の育成方法のモデルを開発し、その成果を全国に普及させたい考えがある。
- 期待される効果
- 第三者評価制度の実効性向上と、評価を通じた保育の質の向上が期待される。
- 特別区への示唆
- 監査や指導との連携・役割分担を明確にした上で、評価結果を施設への支援策に繋げる独自の仕組みを検討し、モデル事業として国に提案することも考えられる。
【拡充】【推進枠】「はじめの100か月の育ちビジョン」を踏まえた取組の推進 [2.0億円]
(令和7年度当初予算:0.4億円+令和6年度補正予算額:1.4億円)
- 事業の目的
- 令和5年12月、全てのこどもの誕生前から幼児期までの「はじめの100か月」(妊娠期から小1まで)から生涯にわたるウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に幸せな状態)の向上に向けて、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの100か月の育ちビジョン)」が閣議決定された。
- 本ビジョンを社会全体の全ての人に共有し、本ビジョンを踏まえた取組を推進するため、「1.『はじめの100か月の育ちビジョン』の普及啓発」「2.『はじめの100か月の育ちビジョン』地域コーディネーターの養成」「3.『はじめの100か月』の育ちの科学的知見に関する調査研究」を3年間で集中的に実施。
- これらの実施と3つの施策の相互の有機的な連携により、「はじめの100か月の育ちビジョン」を非常に大切だと思う人の割合を増加させることを目指し、全てのこどもの「はじめの100か月」の育ちを社会全体で支援・応援することで、本ビジョンの実現を図る。
- 事業の概要
- 1.「はじめの100か月の育ちビジョン」の普及啓発
- ① 「はじめの100か月の育ちビジョン」の効果的な広報
- 本ビジョンの社会的な認知度の向上とビジョンを踏まえた行動の促進を図るため、「はじめの100か月」をテーマとしたイベントの開催や外部メディアとのタイアップなど、様々な効果的な広報を実施。
- ② 「はじめの100か月の育ちビジョン」の効果的な普及啓発のための効果検証・マーケティング調査
- 社会全体の全ての人と本ビジョンを共有するため、これまでの普及啓発の効果検証を行うとともに、「はじめの100か月」のこどもと関わる機会が少ないターゲット層に乳幼児の育ちや子育てに関心を持ってもらうための効果的な情報発信についてマーケティング調査を実施し、今後の広報戦略を策定する。
- ① 「はじめの100か月の育ちビジョン」の効果的な広報
- 2.「はじめの100か月の育ちビジョン」地域コーディネーターの養成
- 本ビジョンを踏まえて、「はじめの100か月」の育ちを支える環境や社会の厚みを増すことを目指し、乳幼児やその保護者・養育者と地域の人々をつなぐ活動を行う地域コーディネーターを全国的に養成するため、各地域におけるモデル事例を創出。
- 多様なモデル事例を創出するため、実施主体を12団体(前年度10団体)に拡充
- 地方キャラバン(対面・オンライン)の開催によるモデル事例の全国展開、子育て関係団体のネットワーク強化
- これまでに蓄積した知見を「活動の手引き」にまとめ、全国どこでも「はじめの100か月」のコーディネーター活動を実施できるようノウハウを提供
- 3.「はじめの100か月」の育ちの科学的知見に関する調査研究
- 諸外国の「はじめの100か月」のこどもの育ちに関する政府方針や、裏付けとなった科学的知見・同方針に基づく施策等を調査するとともに、大学等と連携したシンポジウムを開催することで、「はじめの100か月」のこどもの育ちに関する最新の科学的知見の収集・分析を行う。
- これにより、我が国で「はじめの100か月」のこどもの育ちを支えるために拡充すべき取組の検証や、これまでの施策の効果検証に繋げる。
- 1.「はじめの100か月の育ちビジョン」の普及啓発
- 実施主体等
- 【実施主体】 民間企業・民間団体等
- 【委託先】 1.民間企業等 2.統括事業者+自治体・民間団体等12か所程度(465万円/1件) 3.大学・民間企業等 【拡充】 7年度の0.4億円から大幅に増額され、普及啓発やコーディネーター養成の取り組みがさらに強化されます。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- こどもの育ちの重要性に関する国民全体の理解を深め、社会全体で子育てを応援する気運を醸成するため、国が主導して理念の普及啓発を行う必要があるから。
- 行政側の意図
- 科学的知見に基づいた育ちのビジョンを社会の共通認識とすることで、子育てに困難を抱える家庭への支援や、地域における見守りの目を増やすことを目指す。
- 期待される効果
- 社会全体の子育てに対する関心の向上と、地域における子育て支援活動の活性化。
- 特別区への示唆
- 区の広報媒体やイベントを通じてビジョンの普及に努めるとともに、養成される地域コーディネーターと連携し、区の実情に合った支援活動を展開することが期待される。
【新規】【推進枠】保育所等虐待防止対策支援事業 [555億円の内数]
<保育対策総合支援事業費補助金>
- 事業の目的
- 保育所等における虐待等の不適切事案が相次いでいることを踏まえ、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号。以下「改正法」という。)において、新たに保育所等における虐待に係る通報義務等の仕組みを創設した。
- 本事業は、改正法を踏まえ、保育所等における虐待を未然に防止するとともに、虐待対応に係る自治体の体制を強化することを目的とする。
- 事業の概要
- (1)専門人材の活用
- 都道府県や市町村における虐待対応において、専門的知見に基づき自治体の判断をサポートする専門人材や、こどもの心のケアを行う専門人材、保育所等における虐待防止に係る指導等を行う専門人材、関係機関へのつなぎ支援等を行うための専門人材の派遣を支援する。
- (2)虐待対応実務者会議の設置
- 都道府県の指導監督部局や市町村の虐待対応部局の実務者等で構成される会議(虐待対応実務者会議)を開催し、虐待の発生・増減要因の精査・分析、虐待等の判断や指導等の対応方針の検討、連絡・対応体制の構築等の連携強化の取組を支援する。
- (3)自治体職員等の対応力強化研修
- 都道府県職員や市町村職員等を対象とした、効果的な取組事例の紹介等による横展開により対応力の強化を図るための研修の実施を支援する。
- (4)保育士等への研修等
- 保育士等に対する虐待の未然防止に関する研修や、施設長など保育所等内において指導的立場にある者等を対象とした、職員のストレス及びハラスメント対策やこどもの人権擁護の視点に立った保育の実践方法の修得等に関する研修の実施を支援する。
- (1)専門人材の活用
- 実施主体等
- 【実施主体】 都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市
- 【補助率】 国1/2、都道府県等1/2 【新規】 改正児童福祉法を踏まえ、保育所等における虐待防止対策を強化するため、8年度に新設された事業です。自治体における専門人材の活用や研修体制の構築が求められます。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 保育所等での不適切事案の発生を受け、法改正による通報義務化と併せて、自治体の対応体制を強化し、こどもの安全を確保する責務があるため。
- 行政側の意図
- 専門人材の派遣や研修を通じて、自治体職員の対応能力の向上を図り、虐待の未然防止と発生時の迅速かつ適切な対応を可能にすることを目指している。
- 期待される効果
- 虐待の未然防止、早期発見・早期対応、および保育現場全体の健全化が期待される。
- 特別区への示唆
- 国の支援を活用し、虐待対応の専門人材を確保・育成するとともに、区内の全保育施設を対象とした虐待防止研修の実施計画を策定することが急務となる。
【見直し】保育士・保育所支援センター設置運営事業 [555億円の内数]
<保育対策総合支援事業費補助金>
- 事業の目的
- 各地域における保育人材確保の実効性を高めるため、各保育士・保育所支援センター(以下、「センター」という。)において、地域の実情に応じた支援目標や確実な根拠に基づくKPI(重要業績評価指標) を設定し、取組の事業効果を評価し、見直し・改善・支援内容の充実を図り、センターを基軸として地域の保育人材の確保のために総合的に取り組む費用の一部を補助する。
- 事業の概要
- センターにおいて、次の業務を行う拠点としての機能を担う体制を整備し、関係機関と連携しながら、総合的に取り組む。
- 保育に関する業務への関心を高めるための広報
- 保育に関する業務に従事することを希望する保育士に対し、職業紹介、保育に関する最新の知識及び技能に関する研修の実施その他の保育に関する業務に円滑に従事することができるようにするための支援
- 保育所の設置者に対する、保育士が就業を継続することができるような就労環境を整備するために必要な助言その他の援助
- 上記のほか、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するために必要な業務
- 実施主体等
- 【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市
- 【補助率】 国:1/2、都道府県・指定都市・中核市:1/2
- 【補助基準額】
- 基本分:上記業務で必須とする取組に対し補助基準額を設定
- ※ 実際の配置職員の人数に応じた基準額の上限を設定
- 加算分:基本分の業務に加え、取組をさらに実施し強化する場合は、取組に必要な人員を配置した場合に加算
- (取組例)
- 中高生を対象とした保育体験
- 学生、潜在保育士を対象とした職場体験
- 保育所等に対する(新卒)採用セミナー
- 求職セミナー
- 復職前研修
- 保育士・保育所等に対する巡回支援(*)
- 保育士交流会
- 保育士を目指す者と現役保育士との座談会
- (*) 社会保険労務士等の専門職が対応する場合の加算を検討。
- ※ 実績による上乗せ:令和8年度の事業を開始する際、KPIを設定し、令和8年度末のKPIの達成に応じて、補助基準額の引き上げを検討
- KPIとして想定される例
- アウトプットKPI(就職説明会・研修の開催回数、相談対応件数等)
- アウトカムKPI(センターへの新規登録者数、就職マッチング件数等) 【拡充】 7年度の事業内容から見直され、KPI設定と達成度に応じた補助基準額の引き上げという成果連動の仕組みが導入される点が大きな変更点です。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 保育人材の不足は待機児童問題に直結し、子育て支援の根幹を揺るがすため、行政が主導して地域レベルでの総合的な人材確保策を講じる必要があるから。
- 行政側の意図
- KPIの導入により、各センターの取り組みの成果を「見える化」し、より効果的な人材確保策へのインセンティブを与え、事業効果の最大化を図る狙い。
- 期待される効果
- 根拠に基づく事業改善が進み、地域の実情に応じた効果的な保育士確保が期待される。
- 特別区への示唆
- 就職マッチング件数などのアウトカムKPIを設定し、達成に向けた具体的な戦略を立てる必要がある。社会保険労務士等の専門家との連携も有効となる。
【拡充】認可外保育施設改修費等支援事業 [555億円の内数]
<保育対策総合支援事業費補助金>
- 事業の目的
- 認可外保育施設の質の確保・向上を図るため、認可外保育施設の指導監督基準を満していない施設に対して、指導監督基準又は保育所等の設備に関する基準を満たすための改修及び移転等に要する経費を補助することにより、こどもを安心して育てることができる体制整備を行う。
- 事業の概要
- 認可外保育施設に対して、指導監督基準又は認可保育所等の設備の基準を満たすために必要な改修費や移転費等の費用を補助する。
- 対象事業者は、以下の要件を満たすものとする。
- ① 指導監督基準を満たすための改修等(令和6年度末までの時限措置を令和11年度末まで延長)【拡充】
- 都道府県と市区町村との連名により、以下(1)、(2)の内容を盛り込んだ「認可外保育施設指導監督基準適合化支援計画」を作成した施設であること。
- ② 保育所等の設備に関する基準を満たすための改修等
- (1)職員配置は指導監督基準を満たしていること(有資格者の配置1/3以上)。
- (2)設備基準については、改修費等の支援を受けることにより認可基準を満たすこと。
- (3)「認可化移行計画」を策定し、段階的に認可施設・事業への移行を目指すこと。
- 実施主体等
- 【実施主体】 都道府県、市町村
- 【補助率】 国:1/2、都道府県・市町村:1/4、事業者:1/4
- 【補助単価】 ①指導監督基準を満たすための改修等 改修費等:1か所当たり19,776千円 移転費:1か所当たり1,484千円
- ②保育所等の基準を満たすための改修等 改修費等:1か所当たり39,553千円 移転費:1か所当たり6,181千円 【拡充】 指導監督基準を満たすための改修等に関する時限措置が、7年度時点の計画(令和6年度末まで)から令和11年度末まで延長されています。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 認可外保育施設も重要な保育の受け皿であり、全てのこどもの安全を確保するため、指導監督基準を満たすよう施設改修等を支援する必要があるため。
- 行政側の意図
- 時限措置の延長により、より多くの認可外施設に基準適合への移行期間を与え、質の向上と認可施設への移行を段階的に促していく狙いがある。
- 期待される効果
- 認可外保育施設の安全性の向上と、保育の受け皿全体の質の底上げが期待される。
- 特別区への示唆
- 区内の認可外施設の実態を把握し、指導監督基準適合化支援計画の策定を積極的に働きかけるとともに、認可化移行を目指す施設への相談支援体制を強化すべき。
【見直し】【一部推進枠】保育士修学資金貸付等事業 [555億円の内数]
<保育対策総合支援事業費補助金>
- 事業の目的
- 保育人材確保事業を着実に実施するため、都道府県・指定都市で実施している保育士修学資金貸付等事業の貸付原資等の充実や新規に貸付事業を実施する自治体への支援を行う。
- 事業の概要
- 1.保育士修学資金貸付(個人向け)
- 保育士養成施設に通う学生に対し、修学資金の一部を貸付け、卒業後、5年間の実務従事により返還を免除。※令和8年度募集より、実務従事期間を8年間に変更【見直し】
- 2.保育補助者雇上支援(事業者向け)
- 保育補助者の雇い上げに必要な費用を貸付け、保育士の負担を軽減。
- 3.未就学児をもつ保育士の保育所復帰支援(個人向け)
- 未就学児の保育料の一部を貸付け、再就職を促進。
- 4.潜在保育士の再就職支援(個人向け)
- 就職準備金を貸付け、潜在保育士の掘り起こしを促進。
- 5.未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援(個人向け)
- ファミリー・サポート・センター事業等の利用料金の一部を支援。
- 1.保育士修学資金貸付(個人向け)
- 実施主体等
- 【実施主体】 都道府県・指定都市
- 【補助割合】 国:9/10、都道府県・指定都市:1/10 【拡充】 7年度の制度から見直され、保育士修学資金貸付の返還免除要件である実務従事期間が5年から8年に変更される予定です。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 保育士資格の取得や、潜在保育士の復職にかかる経済的負担を軽減することは、保育人材を安定的に確保するための有効な手段であるため。
- 行政側の意図
- 返還免除要件の実務従事期間を延長することで、貸付制度利用者の長期的な現場定着を促し、人材確保の効果を持続させる狙いがある。
- 期待される効果
- 新規保育士の確保と、潜在保育士の現場復帰促進、保育士の離職防止が期待される。
- 特別区への示唆
- 都が実施する貸付事業について区の広報で周知徹底を図るとともに、区独自の家賃補助など、貸付制度と組み合わせた総合的な保育士確保策を検討することが有効。
【拡充】保育人材等就職・交流支援事業
<保育対策総合支援事業費補助金>
- 事業の目的
- 保育人材を確保するため、新規資格取得者の確保や就業継続支援、離職者の再就職支援、さらに、保育士の技能の向上に向けた取組など、保育士・保育所支援センタ―等の関係機関と連携の上、市町村等が主体となって実施する取組に要する費用の一部を補助することにより、こどもを安心して育てることができる環境を整備する。
- 事業の概要
- 1 保育人材等就職支援事業
- 2 保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等支援事業
- 実施主体等
- 【実施主体】 1 保育人材等就職支援事業:市町村、(9)のみ都道府県も含む 2 保育士キャリアアップ人材交流等支援事業:市町村
- 【補助割合】 1 保育人材等就職支援事業:国:1/2、都道府県・市町村:1/2 2 保育士キャリアアップ人材交流等支援事業:国:3/4、市町村:1/4 【拡充】 7年度から継続している事業ですが、8年度概算要求においても保育人材確保のための重要な施策として位置づけられています。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 保育人材の確保には、就職支援だけでなく、就業後のキャリアアップや交流を通じた定着支援も不可欠であり、市町村レベルでのきめ細かな取り組みが必要なため。
- 行政側の意図
- 市町村が主体となり、地域の実情に応じた多様な人材確保・定着策を展開することを財政的に支援し、地域主導での保育人材確保を促進する狙いがある。
- 期待される効果
- 地域の保育現場のニーズに合った人材の確保と、保育士のキャリア形成支援による定着率向上が期待される。
- 特別区への示唆
- 区内保育施設間の人材交流や合同研修会を企画・実施するなど、保育士が孤立せず、キャリアアップを目指せる環境整備に本事業を活用すべきである。
こどもの可能性を引き出す安全・安心な居場所の確保
【新規】【推進枠】こどもの居場所づくり支援体制強化事業 [4億円]
<こども政策推進事業費補助金>
事業の目的
- こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支援体制の構築等に必要な実態調査・把握や広報啓発活動の支援を行うとともに、NPO法人等が創意工夫して行う居場所づくりのモデル事業を継続して実施する。
- 本事業により、こどもの居場所づくりを促進するために有効と考えられる、「こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業」の実施率の向上につなげる。
- なお本事業は、「こどもの居場所づくりに関する指針」に基づく取組に対して、3年間(令和6年度~令和8年度)で集中して支援を行い推進するものである。
事業の概要
- (1) 実態調査・把握支援
- (2) 広報啓発活動支援
- (3) NPO等と連携したこどもの居場所づくり支援(モデル事業)
実施主体等
- (1) 実態調査・把握支援
- 【実施主体】 都道府県、市区町村 【補助率】 国 1/2、都道府県・市区町村 1/2
- (2) 広報啓発活動支援
- 【実施主体】 都道府県、市区町村 【補助率】 国 1/2、都道府県・市区町村 1/2
- (3) NPO等と連携したこどもの居場所づくり支援(モデル事業)
- 【実施主体】 都道府県、市区町村、民間団体(全国展開しているオンラインの居場所に限る) 【補助率】 国 10/10 【新規】 7年度にはなかった事業で、自治体の居場所づくりに関する実態調査や広報活動を直接支援するメニューが新設されています。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 効果的なこどもの居場所づくりを進めるには、まず地域にどのようなニーズや資源があるかを把握する必要があり、その初期段階の取り組みを自治体が行えるよう支援するため。
- 行政側の意図
- 実態調査や広報といったソフト面の支援を強化することで、自治体が計画的に居場所づくりに取り組むことを促し、コーディネーター配置等の本格的な事業に繋げる狙い。
- 期待される効果
- 根拠に基づいた居場所づくり計画の策定と、住民やNPO等の参画促進が期待される。
- 特別区への示唆
- 本事業を活用して区内のこどものニーズを詳細に調査し、その結果を基に居場所マップを作成・配布するなど、情報提供の強化から着手することが有効。
こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業 [7億円]
<こども政策推進事業費補助金>
事業の目的
- こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支援体制の構築等に必要な「こどもの居場所づくりコーディネーター」の配置等の支援を行う。「こどもの居場所づくりコーディネーター」は、地域の既存資源の把握やネットワーキング、利用ニーズの実態把握や、新たに居場所づくりをする人の支援、継続していくためのサポート等の役割を担い、地域全体でこどもの居場所づくりの推進に取り組む。
事業の概要
- 地域のニーズを把握し、資源の発掘・活用、その地域で居場所を求めるこどもを居場所につなげる等、地域の居場所全体をコーディネートしたり、安定的で質の高い居場所の運営において必要となる、運営資金のやりくりや人材の活用・育成等の組織経営をサポートする人材の配置に対して財政支援を行う。
- また、地方自治体と連携して実施される居場所づくりの取組に対し、その立ち上げ資金を補助する。
実施主体等
- 【実施主体】 都道府県、市区町村
- 【補助率】 国1/2、都道府県・市区町村 1/2 【拡充】 7年度の9億円から予算額は変動していますが、こどもの居場所づくりの中核を担う事業として継続されています。上記の新規事業との連携が重要となります。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 地域に点在するこどもの居場所や支援者を繋ぎ、ネットワーク化することで、地域全体として切れ目のない支援体制を構築するため、専門の調整役が必要だから。
- 行政側の意図
- コーディネーターを配置することで、新規の居場所づくりを支援するとともに、既存の居場所の運営基盤を強化し、持続可能な活動となるよう後押しする狙いがある。
- 期待される効果
- こどもと支援のマッチング精度向上と、地域における居場所づくりの活性化が期待される。
- 特別区への示唆
- 多様なNPOや民間事業者が活動する区の特性を活かし、コーディネーターを核とした官民連携のプラットフォームを構築し、情報共有や連携強化を図るべき。
子育て短期支援事業
<子ども・子育て支援交付金>令和8年度概算要求額 2,061億円の内数+事項要求
事業の目的
- 保護者の疾病その他の理由により家庭においてこどもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらのこども及びその家庭の福祉の向上を図る。
事業の概要
- (1)短期入所生活援助(ショートステイ)事業
- (2)夜間養護等(トワイライトステイ)事業
実施主体等
- 【実施主体】 市町村(特別区を含む)
- 【補助率】 国1/3、都道府県1/3、市町村1/3 【拡充】 7年度から継続される基幹事業ですが、後述の機能強化モデル事業と連携し、受け皿の確保や多様なニーズへの対応がより一層求められます。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 保護者の病気や育児疲れなど、一時的に家庭での養育が困難になる事態はどの家庭にも起こりうるため、セーフティネットとして公的な預かりの場を確保する必要がある。
- 行政側の意図
- レスパイトケア(一時休息)の機会を提供することで、保護者の心身の負担を軽減し、結果として児童虐待のリスクを低減させることを目指している。
- 期待される効果
- 子育て家庭の孤立化防止と、育児困難に陥る前の早期の支援介入が期待される。
- 特別区への示唆
- 利用の心理的ハードルを下げるための周知広報を強化するとともに、障害児や医療的ケア児など、特に支援が必要なこどもの受け入れ体制を強化することが課題となる。
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
<子ども・子育て支援交付金>令和8年度概算要求額 2,061億円の内数+事項要求
事業の目的
- 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、調整等を行う。
事業の概要
- ○主な実施要件
- ○相互援助活動の例
- ○実施市町村 (令和6年度)1,009市町村、(令和5年度)996市町村
実施主体等
- 【実施主体】 市町村(特別区を含む)
- 【補助率】 国:1/3、都道府県:1/3、市町村:1/3 【拡充】 7年度から継続。地域の子育て相互援助活動の中核として、引き続き安定的な運営が期待されます。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 保育施設では対応しきれない早朝・夜間の預かりや送迎など、多様化・個別化する保育ニーズに、住民の相互扶助によって応える仕組みを構築・支援するため。
- 行政側の意図
- 地域住民が子育ての担い手として活躍する場を提供することで、地域の子育て力を向上させ、住民同士の繋がりを再生することを目指している。
- 期待される効果
- 多様な保育ニーズへの対応と、地域における子育て支援ネットワークの強化が期待される。
- 特別区への示唆
- マンション居住者の増加など地域コミュニティが希薄化しがちな都市部において、本事業は特に重要。支援会員(提供会員)を増やすための広報や研修を強化すべき。
【新規】【推進枠】子育て短期支援事業機能強化モデル事業(仮称) [0.5億円]
<こども政策推進事業費補助金>
事業の目的
- 子育て短期支援事業については新たな施設や里親等での受皿の確保、多様な児童が利用できるような受け皿の拡充が求められている。これらの取組を推進するため、設定したテーマに対する事業を実践し、アウトプット評価の実施を行い、取組事例として横展開を行うことで、子育て短期支援事業の機能強化を図る。
事業の概要
- (1)事業内容
- (2)実施方法
実施主体等
- 【実施主体】 都道府県・市町村
- 【補助率】 都道府県実施の場合:国2/3、都道府県1/3
- 市町村実施の場合: 国2/3、都道府県1/6、市町村1/6 【新規】 7年度にはなく、既存の子育て短期支援事業の機能強化(受け皿確保や多様な児童への対応)を目的としたモデル事業として8年度に新設されました。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 既存の児童養護施設だけでは、増大・多様化するショートステイのニーズに対応しきれないため、新たな受け皿の開拓や機能強化に向けたモデルを開発する必要がある。
- 行政側の意図
- 里親や他の福祉施設など、多様な資源を活用した受け皿確保のモデルケースを創出し、その成功事例を全国に広げることで、事業全体のキャパシティを拡大したい考え。
- 期待される効果
- 多様なニーズに対応できる柔軟な受け皿の確保と、事業の利用しやすさ向上が期待される。
- 特別区への示唆
- 区内のNPOや民間事業者と連携し、独自の受け皿モデルを構築して国に提案することが考えられる。特に夜間や緊急時の対応強化が都市部では求められる。
【新規】【推進枠】児童館等を活用した地域課題解決モデル事業(仮称) [1億円]
<こども政策推進事業費補助金>
事業の目的
- 児童館については、すべてのこどもを対象とする児童福祉施設として多様な役割を発揮しているところであり、国では「児童館ガイドライン」においてその機能等を整理している。
- 地域におけるこどもの諸課題に対応するべく、今後の児童館の活動を開発し、普及することを目的にモデル事業を実施する。
事業の概要
- (1)事業内容
- (2)実施方法
実施主体等
- 【実施主体】 都道府県、市町村
- 【補助率】 10/10
- 【補助額】 (1自治体当たり) 5,000千円 【新規】 7年度には見られなかった事業で、児童館の持つポテンシャルを活かして地域の課題解決に取り組むモデル事業として8年度に新設されました。補助率が10/10であり、自治体の積極的な活用が期待されます。
政策立案への示唆
- この取組を行政が行う理由
- 地域に根差した児童福祉施設である児童館が、従来の遊び場の提供機能に留まらず、地域の多様なこどもや家庭の課題解決拠点となる新たな役割を担うため。
- 行政側の意図
- 児童館をプラットフォームとして、ヤングケアラー支援や不登校支援、多文化共生など、地域の個別課題に応じた先進的な取り組みを創出し、そのモデルを普及させたい。
- 期待される効果
- 児童館の機能強化と、地域におけるこどもの複合的な課題に対する包括的支援の実現。
- 特別区への示唆
- 補助率10/10という有利な条件を最大限活用し、区が抱える優先課題(例:外国籍のこどもの支援)に特化したモデル事業を企画・実施すべき。
まとめ
【総括】令和8年度デジタル庁概算要求のポイントと特別区への示唆
令和8年度のデジタル庁概算要求のうち、こども家庭庁関連の保育施策は、「こども未来戦略」に基づき、保育の「量の拡充」から「質の向上」へと明確に軸足を移しつつ、全ての家庭を支えるユニバーサルな支援制度を創設するという強い意志が示されています。特に、「こども誰でも通園制度」の創設と、保育士の専門性向上に向けた多角的な新規事業が大きな柱となっています。
特別区においては、これらの新制度の円滑な導入に向けた体制整備が急務となると同時に、保育人材の確保・定着という根源的な課題に対し、KPI(重要業績評価指標)を意識した成果志向の取組へと転換していくことが求められます。
1. 全ての家庭を支える「こども誰でも通園制度」の創設
最大の目玉は、親の就労要件を問わず、生後6か月から3歳未満のこどもが月一定時間まで保育所等を利用できる「こども誰でも通園制度」の本格実施です。これは、従来の保育制度の枠組みを大きく超え、在宅で子育てをする家庭の孤立防止や育児負担の軽減を目指す、新たなセーフティネットの構築を意味します。国の情報公表システムも本制度に対応するため、大幅な改修が予定されています。
- 特別区への示唆
- 新制度の実施主体として、区内の潜在的な利用ニーズを的確に把握し、既存の保育所や幼稚園、地域の子育て支援拠点など、多様な受け皿を確保するための事業者との調整が急務です。利用者の利便性を高めるため、区独自のオンライン予約システムの導入なども検討すべきでしょう。
2. 保育の「質」向上への体系的アプローチ
保育士の処遇改善を継続する一方、令和8年度は保育の質そのものを高めるための新規事業が体系的に盛り込まれています。各園のリーダーを育てる「ミドルリーダー活躍推進事業」、評価の実効性を高める「第三者評価改善モデル事業」、そして自治体が主体となって地域全体の質向上を目指す「体制整備調査研究」など、多層的なアプローチで保育の専門性向上を図る姿勢が鮮明です。
- 特別区への示唆
- これらの新規事業を積極的に活用し、区内の保育施設間の連携を促進するハブとしての役割を担うべきです。例えば、ミドルリーダーのネットワークを構築し、先進的な保育実践の共有や合同研修を企画することで、区全体の保育の質を底上げすることが可能です。
3. 成果志向(KPI)を導入した保育人材確保策
保育人材の確保は依然として最重要課題であり、各種支援事業が継続・拡充されています。特に「保育士・保育所支援センター」の運営事業では、新たにKPI(重要業績評価指標)の達成度に応じて補助額が変動する成果連動の仕組みが導入される見込みです。これにより、自治体にはより効果的な人材確保策の立案と実行が求められます。
- 特別区への示唆
- 「就職マッチング件数」などの具体的なアウトカムKPIを設定し、その達成に向けた戦略的な事業展開が不可欠となります。社会保険労務士等の専門家と連携した職場環境改善支援など、踏み込んだ取組が有効です。
4. こどもの安全確保と多様な居場所づくり
保育所等における虐待防止対策として、専門人材の活用や自治体職員向けの研修を支援する事業が新設されました。また、児童館の新たな可能性を引き出す「地域課題解決モデル事業」や、ショートステイの受け皿を拡充するモデル事業など、地域の多様な資源を活用してこどもの安全な居場所を確保する取組も強化されています。
- 特別区への示唆
- 虐待防止対策では、国の支援を活用し、区内の全保育施設を対象とした研修計画の策定が急務です。また、補助率10/10の児童館モデル事業などを活用し、ヤングケアラー支援や不登校支援といった、各区が抱える喫緊の課題解決に繋げることが期待されます。